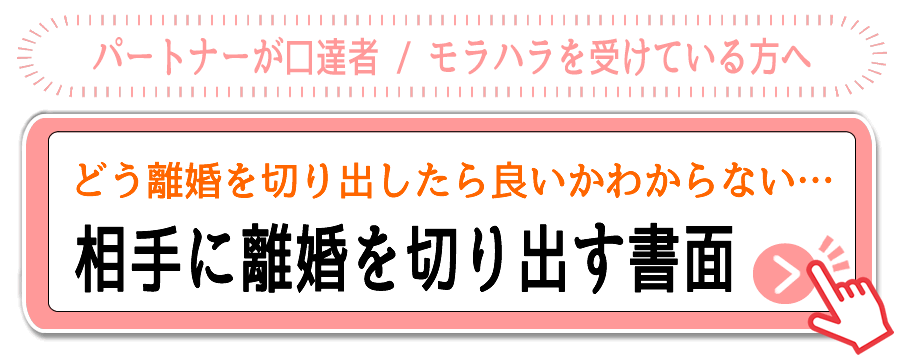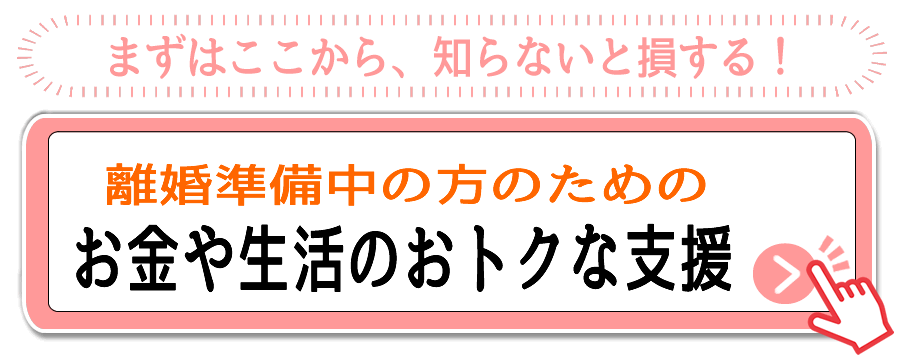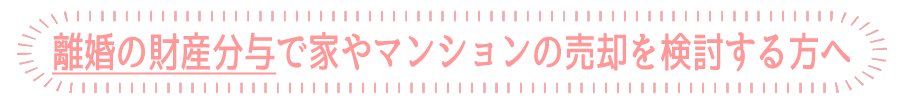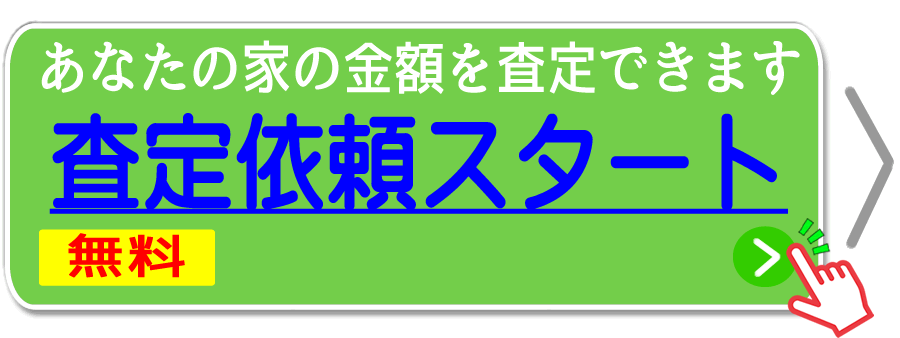PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
離婚協議書の書き方ガイド|後悔しないために決めておきたいことと作成のポイント
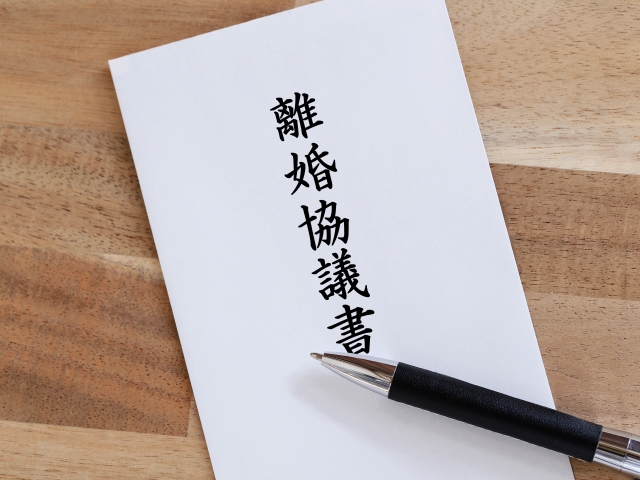
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 離婚で不動産を売る|住宅ローン・名義・財産分与の不動産売却ガイド
- 浮気調査を探偵に依頼する前に知っておきたい全知識|費用・手口・選び方・注意点を徹底解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
離婚協議書とは?なぜ必要なのか

口約束では不十分?書面化する意味
離婚の話し合いは、多くの場合、夫婦間の「口頭のやりとり」で進められます。
ですが、言った・言わないのトラブルを避けるためには、きちんと書面に残すことが大切です。
とくに金銭や子どものことが絡む内容は、記憶や解釈の違いで、離婚後に深刻な争いへ発展することがあります。
たとえば、
- 養育費の支払いが途中で止まった
- 「財産はもらえるはずだったのに」と主張される
- 面会交流のルールで揉める
こうしたケースでも、離婚協議書に明文化された内容が証拠になります。
後悔しないためにも、最低限の取り決めは書き残しておきましょう。
法的効力のある・なしで何が違う?
離婚協議書には「単なる書面」と「法的効力をもつ書面」の2種類があります。
ふたりで書いた協議書には法的拘束力がなく、約束を破られても、すぐに強制執行(差し押さえなど)できません。
一方、公正証書にした協議書であれば、養育費や慰謝料が未払いになったときに、裁判を経ずに給与差し押さえを行うことも可能です。
公正証書との違いと使い分け
「離婚協議書」と「公正証書」は混同されがちですが、正確には次のような違いがあります。
| 種類 | 作成方法 | 効力 |
|---|---|---|
| 離婚協議書(私文書) | 夫婦が自分で作成 | 証拠にはなるが、強制執行力なし |
| 離婚に関する公正証書 | 公証役場で作成 | 裁判を経ずに強制執行可能 |
すべてを公正証書にする必要はありませんが、金銭的な取り決めがある場合は、公正証書化を強くおすすめします。
離婚協議書を作るべき人とは

離婚後のトラブルを避けたいすべての人へ
「協議書なんて、仲良く別れるなら必要ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
ですが、たとえ話し合いがスムーズに終わっても、生活が変わることで関係性も変わるのが離婚後です。
時間が経つにつれ、
- 支払う余裕がなくなる
- 気持ちが冷めて連絡が取れなくなる
- 新しいパートナーが影響してくる
といった要因で、当初の合意が守られないリスクは十分にあります。
将来の自分と子どもを守るために、「記録としての離婚協議書」は欠かせません。
子どもがいる夫婦は特に要注意
親権や養育費、面会交流など、子どもに関する取り決めは感情論になりやすく、最も争点になりやすい部分です。
とくに養育費は「払う」「払わない」で揉めることも多く、書面化していなかったせいで泣き寝入りしたケースも少なくありません。
また、面会交流については、
- 「月に1回、週末に会う」
- 「子どもの希望を尊重する」
など、具体的に決めておかないと、実現しないまま関係が断絶することもあります。
財産・ローン・借金が絡む場合も必須
離婚の際には、共有財産だけでなく、住宅ローンや借金、連帯保証人の問題なども出てきます。
たとえば、
- 名義は相手だけど支払いは自分
- 契約は共同名義
- 車のローンが途中
などのケースでは、誰が何を引き継ぐのかを明記しないと、支払い義務だけが残る危険性があります。
また、後から相手に借金があることを知るといったこともあるため、「財産と負債の開示」「精算の取り決め」も忘れず盛り込みましょう。
離婚協議書に記載すべき基本項目

離婚協議書には、単に「離婚に合意しました」と書くだけでは不十分です。
離婚後の生活で発生するであろう問題に備え、あらかじめ取り決めておくべき項目が多数あります。
ここでは、最低限記載しておくべき5つの主要項目を解説します。
1. 離婚の合意
協議書の冒頭には、両者が協議のうえ離婚することに合意した旨を記載します。
例:
「夫○○○○と妻○○○○は、協議のうえ、令和○年○月○日をもって離婚することに合意した。」
この一文があることで、合意離婚の成立と日付の確認が明確になります。
2. 親権・養育費・面会交流
未成年の子どもがいる場合、必ず取り決めておきたい項目です。
- 親権者の指定:法律上どちらが親権を持つかを明記
- 養育費の金額・支払い方法・支払期限:例)毎月○万円を○日までに振込
- 面会交流の頻度や方法:例)月1回○曜日に実施、宿泊の可否など
特に養育費は、口約束では支払いが滞るリスクが高く、具体的な条件を書面化することが重要です。
3. 財産分与・住宅・ローン
共有財産については、どの財産をどちらが取得するかを明記しておきます。
- 現金・預金・株式などの金融資産
- 自動車や家具などの動産
- 持ち家(住宅)の名義・売却・住み続ける人など
- 住宅ローンの債務者・連帯保証人の整理
「〇〇のマンションについては妻が引き取り、ローン支払いは夫が続ける」など、不動産の扱いと支払い責任は明確にしておくべきです。
4. 年金分割
専業主婦(夫)であった場合、離婚後の年金に差が出ることがあります。
年金分割制度を利用する場合は、「合意分割すること」「割合」「手続きはいつ誰が行うか」を記載します。
例:
「厚生年金の標準報酬の50%を限度として、年金分割請求を行うことに合意する。」
5. 慰謝料・その他特記事項
不貞行為やDVなど、慰謝料の支払いがある場合は、その金額や支払い期日を具体的に記載します。
また、引っ越しや氏の変更、連絡手段などの取り決めがあれば、特記事項として加えます。
離婚協議書の書き方と注意点

離婚協議書は、正式な契約書と同様に作成します。
誤解や無効化を防ぐためには、構成と表現に注意が必要です。
基本構成と例文
離婚協議書の基本的な流れは、以下のようになります:
- 表題「離婚協議書」
- 作成年月日
- 当事者の氏名・住所・生年月日
- 各取り決め事項(前章で述べた項目)
- 作成部数と保管方法
- 署名・押印
例文(冒頭部分):
離婚協議書
夫 ○○○○(以下「甲」という)と妻 ○○○○(以下「乙」という)は、協議のうえ、離婚に関し以下のとおり合意し、本書を作成した。
このように、契約書の形式に則って記載することが基本です。
曖昧な表現はNG|トラブルになりやすい言い回しとは
離婚協議書では、「なるべく払う」「できる限り面会させる」といった曖昧な表現は避けるべきです。
NG例:
- 養育費は可能な限り支払う
- 面会は双方が希望する場合に応じて行う
OK例:
- 養育費として毎月3万円を、毎月末日までに乙の指定口座へ振り込む
- 面会交流は毎月第2土曜日の午後1時から5時まで、甲の自宅にて行う
子ども関連の取り決めの書き方
子どもに関しては、「子の福祉を最優先とする」視点が求められます。
- 親権者と監護者を分ける場合は、両者の役割を明記する
- 面会交流については、子どもの年齢・希望も考慮する
- 養育費は「大学卒業まで」「20歳まで」など、支払いの終了時期も明確に記載する
お金の支払い条件の書き方
金額だけでなく、支払方法・支払期限・遅延時の対応まで書くことで、実効性が高まります。
例:
「甲は乙に対し、養育費として毎月3万円を、毎月25日までに乙名義の口座に振り込む。
振込手数料は甲の負担とし、3日以上遅延した場合は年10%の遅延損害金を加算する。」
第三者(証人)を入れるべきか
法的には証人の署名・押印は必須ではありません。
ですが、公平性や信頼性を高めたい場合は、第三者を立てておくと安心です。
証人候補
- 互いの親族(中立な立場であることが望ましい)
- 弁護士や行政書士などの専門家
- 親しい友人など
離婚協議書を公正証書にするには

離婚協議書は夫婦だけで作成する「私文書」でも問題ありませんが、養育費・慰謝料・財産分与など“お金”が絡む場合は、公正証書にすることで初めて実効性が生まれます。
ここでは、公正証書化するメリットや流れ、必要書類、費用の目安を整理します。
公正証書にするメリットと効力
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する「公的な文書」です。
最大の特徴は、強制執行力を持たせられる点です。
未払いが生じたときに、裁判をせずに給与差し押さえを申し立てられるため、支払いトラブルのリスクを大幅に軽減できます。
【主なメリット】
- 養育費の未払いが起きた場合、すぐに強制執行できる
- 文書としての信頼性・証拠力が高い
- 紛失した場合も公証役場で正本・謄本を再発行可能
- 中立の立場で公証人が内容を確認するため安心感がある
「離婚後が不安」「約束が守られないのではないか」と感じているなら、公正証書化することで精神的な負担が大きく軽減されます。
公正証書作成の流れ
公正証書は、次のような流れで作成します。
1. 事前準備:離婚協議書の原案を作る
まず夫婦の間で話し合い、
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 面会交流
などの内容をまとめた文案を用意します。
この段階は私文書の離婚協議書と同じで、まずは内容を言語化するところから始まります。
2. 公証役場に連絡し、予約を取る
公正証書を作成するには、公証役場に事前予約が必要です。
公証人が文案を確認し、問題がないか精査するため、メールやFAXで原案を送るよう求められます。
3. 公証人による内容チェック
公証人は、文案が法律に反していないか、表現に不備がないか確認します。
修正が必要な場合、公証人から指摘が入るため、安心して文書の精度を高められます。
4. 当日、双方が公証役場へ行き、署名・押印
当日は、本人確認書類を持参して、公証役場で正式に署名・押印します。
※事情がある場合は代理人を立てることも可能です。
5. 正本・謄本の受け取り
公正証書が完成したら、夫婦それぞれが保管する正本・謄本を受け取ります。
紛失しても再発行できる点は公正証書の大きな安心材料です。
公正証書化に必要な書類
一般的には以下の資料が必要です:
- 当事者双方の本人確認書類
- 離婚協議書の文案
- 戸籍謄本(必要に応じて)
- 住民票(必要に応じて)
- 子どもの情報(氏名・生年月日)
- 養育費の算定根拠や財産資料(ある場合)
公証役場によって必要書類は前後しますので、事前に確認しておくと安心です。
費用の目安
公正証書の費用は、取り決める金額によって変動します。
一般的な相場は以下の通りです。
| 内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| 基本手数料 | 数千円〜数万円 |
| 養育費総額が大きい場合 | 数万円〜10万円台後半 |
| 代理人を立てる場合 | さらに別途費用 |
「高いのでは…?」と心配になる方もいますが、離婚後に支払いトラブルで何年も苦しむことを考えると、公正証書化の価値は大きいと言えます。
ひとりで作成できる?専門家に依頼するべき?

離婚協議書は、自分たちだけで作ることも、専門家に依頼することもできます。
どちらが良いかは、状況や不安の大きさによって変わってきます。
自作のメリット・デメリット
【メリット】
- 費用がかからない
- 自分たちのペースで話し合える
- 心情や事情に合わせて柔軟に書ける
【デメリット】
- 法律的に不適切な表現・抜け漏れが起きやすい
- 相手に押し切られ、不利な内容になりがち
- 公正証書化を見据えた書き方が難しい
特に、“相手が強くて話し合いが進めづらい”“言い返せない”という状況では、自作は不利になりやすい傾向があります。
弁護士・行政書士に依頼する場合のポイント
専門家に依頼する大きなメリットは、法律的な抜けや表現の曖昧さを防げる点です。
依頼を検討すべきケース
- 相手の不倫が絡んでいる
- DVなどで直接話し合いが難しい
- 住宅ローンや高額な資産がある
- 養育費や財産分与で意見が対立している
- 公正証書前提で文案を整えたい
行政書士は書類作成の専門家のため、協議書の整備が得意です。
弁護士は「交渉・代理」もできるため、トラブルが大きい場合に向いています。
費用相場と選び方
費用相場は次の通りです:
| 専門家 | 費用相場 |
|---|---|
| 行政書士 | 3万円〜10万円程度 |
| 弁護士(文案作成のみ) | 5万円〜20万円程度 |
| 弁護士(交渉を含む) | 20万円〜数十万円 |
選ぶ際は、
- 離婚案件の経験が豊富か
- 養育費・財産分与の取り扱い実績があるか
- 公正証書の作成経験があるか
を確認しておくと安心です。
「不安だから相談したいだけ」という方へ
専門家に依頼しなくても、一度だけ相談するという使い方もあります。
- 「この内容で大丈夫?抜けはない?」
- 「こういう書き方で問題は?」
- 「この条件は不利にならない?」
といった確認をするだけでも、精神的な安心感が得られ、後悔を減らせるでしょう。
離婚協議書を作る前に確認したい心の準備

離婚協議書の作成は、法律的な手続きというよりも、心の整理や覚悟の確認とも言えます。
「まだ離婚を決意しきれていない」「揉めたくないけど不安」という方にとっても、離婚協議書を作るという行為そのものが、今後の不安を和らげる準備になることがあります。
書面にするのが「怖い」と感じる方へ
協議書の作成をためらう理由のひとつに、「本当に離婚するんだ」という現実を突きつけられる気がして怖い、という声があります。
けれど、協議書は「離婚をすすめるための道具」ではなく、「自分と家族を守るための安全装置」です。
「まだ話し合いの途中だけど、気持ちの整理のために作ってみたい」
「離婚するか迷っているけれど、情報として知っておきたい」
そんな段階でも、作ってはいけないというルールはありません。
相手と冷静に話すための心構え
離婚協議書の作成には、相手との冷静なやりとりが欠かせません。
ときには感情が揺れ動き、会話が中断してしまうこともあるでしょう。
そのときは無理に進めるのではなく、いったん持ち帰る・第三者を入れる・時間をおくなどの工夫をしてみてください。
話し合いに向かうときは、次のような意識があると進めやすくなります:
- 相手を責めず、事実に集中する
- 感情的になりそうなら書面やメールで伝える
- 譲れないこと・妥協できることを事前に整理する
「まだ離婚するか迷っている」人でも作ってよい?
はい、問題ありません。
むしろ離婚に踏み切る前の段階で、「仮の協議書」「覚書」という形で条件を整理してみることは、感情に流されない判断材料になります。
たとえば、
- 養育費はどのくらい必要になるのか
- 財産はどのように分けるべきか
- 住まいはどうするか
そうした現実を紙の上で可視化することで、「離婚後の生活」の具体像が見えてきます。
その結果、「やっぱり離婚を回避しよう」と考え直すこともあります。
離婚協議書は、離婚を急がせるための道具ではなく、“冷静になるため”のツールとして活用することもできます。
よくある質問(FAQ)

Q. 離婚協議書がなくても離婚はできますか?
はい、可能です。
法律上は、離婚届を提出するだけで離婚は成立します。
ただし、口約束だけの離婚は、後から金銭や子どものことで揉めるリスクが非常に高いため、離婚協議書の作成が推奨されます。
Q. 離婚協議書の内容はあとから変更できますか?
基本的には、双方の合意があれば内容を変更・再作成することは可能です。
ただし、公正証書にした場合は、変更にも公証役場での手続きが必要になることがあります。
Q. 協議書に書いたのに相手が約束を守らない場合は?
私文書の離婚協議書では、すぐに法的強制力はありません。
一方、公正証書で「強制執行認諾条項」がある場合、裁判を経ずに給与差し押さえなどの手続きを取ることが可能です。
そのため、金銭に関する約束がある場合は、公正証書化しておくのが確実です。
Q. 離婚協議書を作るベストなタイミングはいつですか?
離婚届を出す前に作成するのが理想です。
なぜなら、一度離婚が成立してしまうと、相手と連絡が取れなくなる・協議を拒否されるといった問題が起きやすくなるからです。
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 浮気調査を探偵に依頼する前に知っておきたい全知識|費用・手口・選び方・注意点を徹底解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚協議書の書き方ガイド|後悔しないために決めておきたいことと作成のポイント
全国の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方
▼地域ごとの離婚の手続きと離婚届の書き方と出し方の情報はこちらから