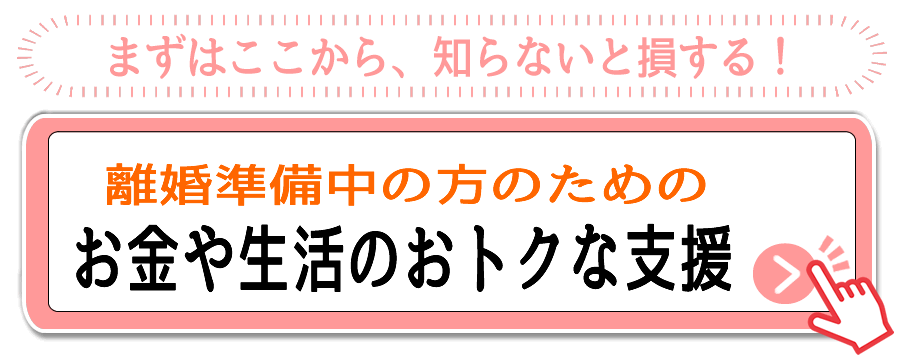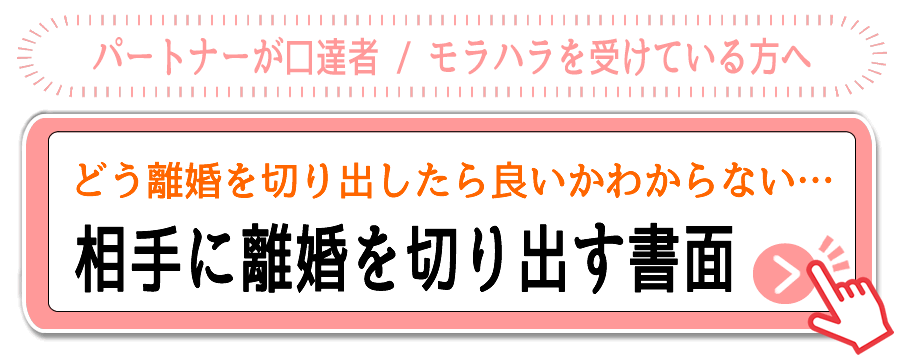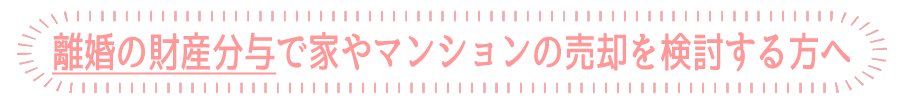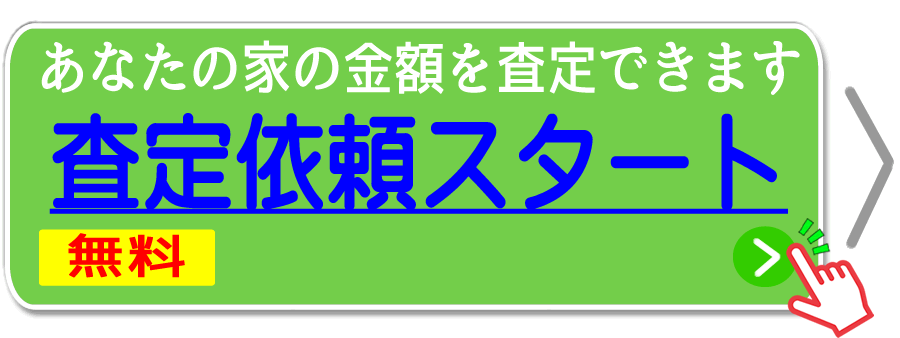子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント

- 離婚協議書の書き方ガイド
- いきなりホームレス?別れた旦那が家の住宅ローンを滞納するとどうなる?
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚で不動産を売る|住宅ローン・名義・財産分与の不動産売却ガイド
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
離婚を考えたとき、まず考えるべき「子どものこと」

子どもへの影響を最小限にするために
離婚を決断するとき、最も心を悩ませるのが「子どもにどんな影響があるのか」という問題です。
たとえ夫婦関係が破綻していたとしても、親であることには変わりありません。
子どもの心を守りながら、生活を安定させていくにはどうすればいいのか、それが多くの親にとっての共通の不安です。
とくに幼い子どもにとっては、離婚という出来事は日常が大きく揺らぐ出来事になります。
住む場所が変わる、名字が変わる、片親と離れて暮らすという現実は、想像以上に大きなストレスです。
だからこそ、離婚の決断は大人同士の問題としてだけでなく、「子どもの人生にも関わる選択」であることを忘れてはなりません。
「夫婦の問題」と「親の責任」は分けて考える
夫婦関係における不満やトラブルが重なっていくと、感情が先立ち、相手を責めたり子どもを巻き込んだ言動をしてしまうこともあります。
しかし、夫婦でなくなっても「親」としての役割は続きます。
離婚後も、子どもの健やかな成長のためには両親の協力が欠かせません。
「もう顔も見たくない」と感じていても、子どもにとっては、父親も母親もかけがえのない存在です。
相手の人格や過去の言動に対して不満があったとしても、子どもの前では親としての立場を尊重し合うことが大切です。
これは簡単なことではありませんが、長い目で見れば子どもの安心感や自尊心を守ることにつながります。
話し合いが難しい場合は第三者の介入も視野に
実際には、「相手と冷静に話し合うなんて無理」「感情的になってまともに協議できない」という方も多いでしょう。
そうしたときは、家庭裁判所の調停や、専門家によるカウンセリング・家族支援機関のサポートを活用するのも一つの方法です。
第三者が介在することで、感情をぶつけ合うのではなく、子どもにとって最善の方法を模索するための冷静な対話が可能になります。
夫婦間で意見が合わなくても、「子どものために」という共通の目的があれば、解決の糸口は見えてくるはずです。
親権とは何か?単独親権と共同親権の基本を理解する

そもそも親権とは?身上監護権と財産管理権の違い
「親権」という言葉は耳にしたことがあっても、その中身については意外と知られていません。
親権には、大きく分けて以下の2つの役割があります。
- 身上監護権(しんじょうかんごけん):子どもの身の回りの世話・しつけ・進学や居住地の決定など、日常生活を管理・監督する権利
- 財産管理権:子どもの名義で得た財産を管理したり、契約や財産処分を代理するなど、経済面を守る権利
つまり、親権とは単なる「子どもと一緒に住む権利」ではありません。
法的・経済的に子どもを守る責任を負う立場でもあるのです。
離婚時の親権は「単独親権」が原則だった
これまでの日本では、離婚をすると、父母のどちらか一方しか親権を持てない「単独親権」制度が原則でした。
離婚届を提出する際には、どちらが親権を持つかを明記しなければなりません。
この制度の背景には、「親権を明確にして子どもの生活環境を安定させる」という目的があります。
しかし一方で、親権を得られなかった側の親が、子どもの教育や健康、進路に関してまったく意見を持てないという問題も指摘されてきました。
たとえば、父親が親権者となった場合、母親は子どもの通学先の決定や手術の同意、財産管理に一切関与できません。
これは子どもの福祉よりも形式的な制度を優先しているのではないかという声につながり、長年にわたって議論されてきました。
共同親権はどう変わる?2026年の法改正予定と影響
現在、親権は「単独親権」が原則とされていますが、2026年4月に施行予定の民法改正により、共同親権制度が離婚後にも認められるようになります。
この改正は、国際的な潮流や、別居親との断絶による子どもの心理的負担への懸念を背景としたものです。
これまでは、たとえ双方が共同で子育てしたいと希望しても、法的にはどちらか一方にしか親権が認められず、もう一方の親は「法的には親権がない人」になっていました。
これにより、面会交流や学校への連絡、医療同意などで多くの制約が生じていました。
新制度では、離婚後であっても、父母双方が子の利益を最優先して協力できると判断された場合に限り、共同親権が認められることになります。
ただし、自動的に共同親権になるわけではなく、合意が得られない場合は家庭裁判所が判断することになります。
また、DVや虐待などの恐れがあるケースでは、安全確保の観点から共同親権を認めない方針が示されています。
親の権利ではなく、あくまで子どもの利益を守るための制度であることが強調されています。
子どもの親権をめぐる選択と現実

父母どちらが親権を持つべきかの判断基準
親権を決める際、最も重要なのは「子どもの福祉にとって、どちらがより良い環境を提供できるか」という視点です。
これは収入や住環境だけでなく、育児の実績、子どもとの関係性、今後の養育計画など多角的に見て判断されます。
たとえば、これまで主に育児を担っていた親の方が、子どもの生活リズムや性格を把握しており、安定した環境を継続できると見なされることが多いです。
とはいえ、一方的に「母親だから親権が取れる」「父親は取れない」という単純な構図ではありません。
とくに近年では、父親の育児参加も当たり前になりつつあり、家庭裁判所でも性別に偏らない判断が求められるようになっています。
親権をめぐって揉めた場合はどうなるか
夫婦の間で親権の合意ができない場合、調停や審判に進むことになります。
家庭裁判所では、さまざまな事情を聞き取り、子どもの利益を最優先にして親権者を決定します。
この過程では、双方の育児状況や生活基盤、子どもへの関わり方、教育や医療への配慮などが検討されます。
調停では合意形成が重視されますが、合意が困難な場合は裁判所の審判により決定が下されます。
注意したいのは、調停や裁判は精神的にも時間的にも負担が大きいという点です。
できる限り協議での解決を目指すことが、子どもにとっても親にとっても望ましい道と言えるでしょう。
家庭裁判所が重視する視点と子どもの意思の扱い
家庭裁判所が親権者を決める際に最も重視するのは、「子どもが安定した生活を送れるかどうか」です。
そのために見るポイントは次のようなものです:
- 現在どちらの親と生活しているか(継続性の原則)
- 保育園・学校などとの関係
- 兄弟姉妹との分離の有無
- 親の生活状況・精神的安定性
- 子どもの意思(とくに15歳以上)
15歳以上の子どもについては、家庭裁判所が意思確認を行うことが法的に定められており、その意見は強く反映されます。
一方で、小さな子どもの意思は間接的に確認されることが多く、「親の主張が子どもの希望」とされてしまうこともあるため、注意が必要です。
監護権と親権を分けて考えることも可能

親権を持たなくても子どもと暮らすことはできる?
離婚をする際、親権を持つのは通常ひとりだけ――これが現在の原則です。
しかし実は、「親権を持たない方の親」が子どもと一緒に暮らすことも可能です。
そのカギになるのが、「監護権」という概念です。
親権の中でも特に「子どもを育てていく日常的な役割」を担うのが監護権(かんごけん)です。
たとえば、学校への送り迎えや病院への付き添い、食事・入浴・学習の管理などがこれに該当します。
財産管理などの法的手続きを含む「親権」全体とは異なり、監護権は「日々の子育て」に関する部分に特化しているのです。
つまり、親権者は別の親であっても、自分が監護者になれば子どもと一緒に暮らせるという選択肢があるということです。
監護権と親権の分離とは?実際の事例も
親権と監護権を分けることは法的に可能ですが、現実にはそこまで多くない選択肢です。
なぜなら、日常の監護と法的な判断を別の親が担うという体制は、連携が取れなければトラブルのもとになりやすいためです。
たとえば、監護権は母親に、親権は父親にあるとします。
この場合、進学や転居といった重大な決定を母親がしたくても、父親の許可が必要になります。
日々の育児を担っている人が意思決定できないというのは、双方にとっても子どもにとっても不自由が生じかねません。
一方で、子どもを育てる能力はあるが、法的手続きを苦手とする親に監護権を、財産管理や手続きを得意とする親に親権を持たせるなど、両親の特性に応じた役割分担がうまく機能する例もあります。
父母の合意が前提だが、現実には難しい場合も
監護権と親権を分けるには、基本的に夫婦間の合意が必要です。
調停や裁判でも、このような分離を望む声がある場合には検討されますが、家庭裁判所としては、原則として親権と監護権は一体で判断する傾向が強いです。
理由はシンプルで、子どもにとって一貫した養育環境が望ましいからです。
双方が冷静に協力し合える関係性にある場合を除き、分離はリスクを伴います。
だからこそ、「制度として可能」であっても「現実的に有効か」は慎重な判断が求められます。
離婚後の子どもの暮らしと養育費のこと

離婚後の親子関係はどう変わる?
離婚をしても、親子の縁は切れません。
ただし、日常のふれあいや生活を共にする時間は確実に変わるでしょう。
これは、親だけでなく、子どもにとっても大きな変化です。
特に、別居する親との関係をどう保つかは、子どもの心に大きく影響します。
面会交流(面接交渉権)という制度があり、定期的に会う取り決めをすることで、関係を継続することができます。
月1〜2回の訪問や宿泊、ビデオ通話の活用など、子どもの年齢や生活リズムに合わせて柔軟に設計することが重要です。
また、面会の頻度や方法については、親の感情ではなく子どもの気持ちを尊重する視点を持つことが大切です。
親権がなくても面会交流や養育費の義務はある
しばしば誤解されがちですが、親権がない=育児に関われない、というわけではありません
面会交流や養育費の支払いは、親権とは別の問題です。 法律上、どちらが親権者であっても、もう一方の親には「扶養義務」や「子との交流の権利・責任」があります。 つまり、親権がなくても「親である責任」は継続するのです。 面会交流や養育費の取り決めは、口頭ではなく書面(公正証書や調停調書)にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことにつながります。 離婚後の生活に不安を感じる方も多いかと思います。 とくに子どもを一人で育てることになると、経済面・精神面で大きなプレッシャーがかかります。 そうした方のために、行政や自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。 たとえば: これらの制度は、申請しなければ利用できないものが多いため、早めに市区町村の窓口や専門相談機関に問い合わせることが大切です。 現在の日本の法律では、離婚後の親権は父母のいずれか一方のみが持つ「単独親権」が原則です。 しかし、2026年4月に施行される改正民法では、一定の条件下で「共同親権」も選べるようになります。 これまでの制度では、父母が離婚に際して合意をしても、共同親権を選ぶことはできませんでした。 しかし改正後は、父母双方の合意がある場合に限り、共同親権を選択することが可能になります。 さらに注目すべき点は、合意が得られない場合でも、家庭裁判所が「子の利益に資する」と判断すれば、例外的に共同親権を認めることがあるという制度設計です。 この改正法の施行予定日は2026年4月1日です。 対象となるのは、その施行日以降に離婚する父母、または家庭裁判所に親権の変更を申し立てたケースです。 既に離婚している家庭に対しては、自動的に共同親権が適用されることはありません。 希望する場合は、裁判所に申し立てを行い、認められる必要があります。 経過措置においては、「過去の離婚」であっても親のいずれかが申し出た場合に限り、制度変更の恩恵を受けられる可能性があります。 しかし、一度確定した親権の変更にはハードルがあるため、慎重な判断が求められます。 共同親権制度の導入に関しては、多くの賛否両論が巻き起こっています。 このように、共同親権は「万能な制度」ではなく、「慎重に運用されるべき選択肢の一つ」として導入されることが重要です。 共同親権が認められると、子どもは両親と引き続き関われるという点で、大きなメリットがあります。 進学・病気・習い事・転居など、人生の節目で両親が関わってくれることで、安心感と安定した愛情を受け取ることができます。 一方で、両親の関係が悪化したままであれば、対立が続き、子どもが板挟みにされるというリスクもあります。 とくに意見の食い違いが激しいと、教育方針や生活方針が揺れ動き、子どもが混乱する原因にもなりかねません。 つまり、共同親権が適しているかどうかは、親の関係性や協力体制が築けるかに大きく左右されるのです。 離婚は感情的になりやすい出来事です。 裏切られた、傷つけられた、失望した――そうした想いがあっても当然です。 しかし、その怒りを子どもにぶつけたり、子どもを味方につけようとするのは避けるべきです。 親として最も大切なのは、「今の自分の気持ち」ではなく「子どもにとって何が良いか」を基準に考えることです。 たとえ自分が親権を持てなくても、子どもが安心して生活できる環境を選ぶことが、長期的には親子の信頼につながります。 離婚や親権の問題は、ひとりで抱え込むには大きすぎる悩みです。 とくに「相手が話し合いに応じてくれない」「子どもの気持ちがわからない」といったときには、専門の第三者に相談することが有効です。 活用できる支援先の例: 適切なサポートを受けることで、自分の視野が広がり、子どもにとって最良の選択を冷静に判断する余裕が生まれることもあります。 以下は、親権や監護について判断に迷ったときに、自分に問いかけてみてほしいチェックリストです: こうした問いを通して、自分が何を大切にしたいのか、どんな親でありたいのかを再確認することができるはずです。 はい、親権がなくても「面会交流権」は原則として認められています。 これは親のための権利というより、子どもが親と関係を保つ権利として位置づけられています。 面会の頻度や方法(訪問・電話・ビデオ通話など)は、父母の協議または家庭裁判所の調停で決定します。 親権を持たない側の親でも、子どもと信頼関係を築いていくことは十分に可能です。 子どもが15歳以上であれば、家庭裁判所が直接意思を確認することが法で定められています。 15歳未満の場合でも、発達状況に応じて間接的な意見聴取が行われることもあります。 ただし、子どもの意思があっても、それがそのまま親権や監護権の決定に直結するわけではありません。 あくまで総合的な判断材料の一つとして扱われます。 養育費の支払いが滞った場合は、公正証書や調停調書があれば強制執行が可能です。 裁判所を通じて給与の差し押さえなどが行われることもあります。 また、養育費保証制度や支援団体による立て替えなどを利用できるケースもあるため、早めに市町村などへ相談するのが安心です。 2026年4月以降に施行される改正法では、過去に離婚した親も共同親権への変更を申し立てることが可能になる予定です。 ただし、変更には家庭裁判所の判断が必要であり、単に申し出れば認められるというわけではありません。 DVや虐待の履歴、親子関係の状況などを総合的に判断されます。 離婚は親にとっても大きな決断ですが、子どもにとっては人生を左右する大きな転機です。 その中で最も大切なのは、親のエゴや感情を抑えて「子どもの幸せを第一に考えること」。 制度は変わりつつあります。 共同親権や面会交流、支援制度など、選択肢は増えてきました。 だからこそ、親が自分の気持ちと向き合い、柔軟に、誠実に、子どもと向き合っていく姿勢が求められます。 このページが、迷いながらも「自分にできる最善」を探している親御さんの一助になれば幸いです。 困ったときは、どうかひとりで抱え込まず、周囲の支援や制度を活用してください。 子どもの未来を守れるのは、いまを生きる親のあなたです。 ▼地域ごとの離婚の手続きと離婚届の書き方と出し方の情報はこちらから子どもの安心と安定のためのサポート制度も
新しい制度「共同親権」は何がどう変わるのか
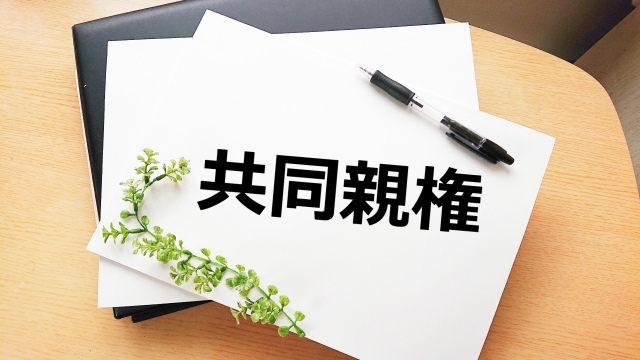
これまでとの違い:合意なくして親権共有が可能に?
実施時期と経過措置:2026年4月以降の対応
共同親権に対する賛否と課題
賛成の声
反対の声・懸念
子どもにとってのメリット・デメリット
どうすれば子どもにとって最善の選択ができるか

感情ではなく「子どもの利益」を基準に
信頼できる支援機関や相談窓口を活用する
迷ったときに読むべきチェックリスト
子どもがいる離婚でよくある質問(FAQ)

親権を持てなくても子どもと会える?
子どもの意思はどこまで尊重される?
養育費の支払いが滞ったらどうする?
共同親権の導入で過去の離婚も変更できる?
まとめ|子どもの未来を守るために、いま親ができること

全国の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方