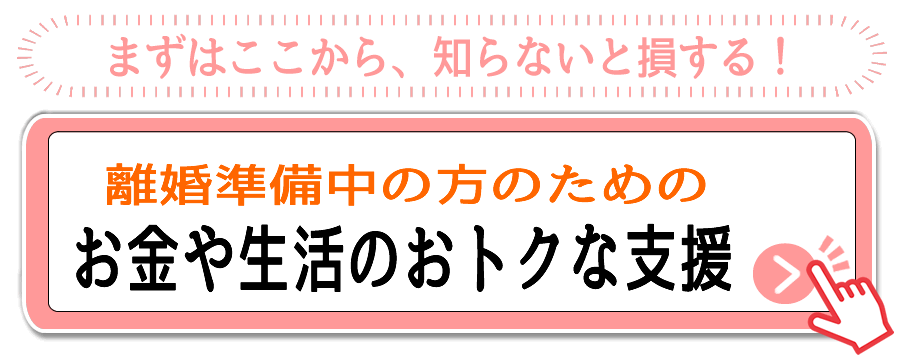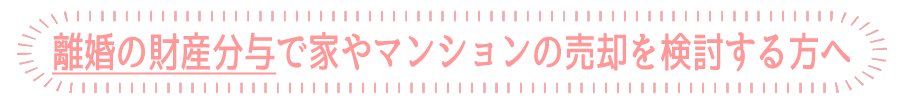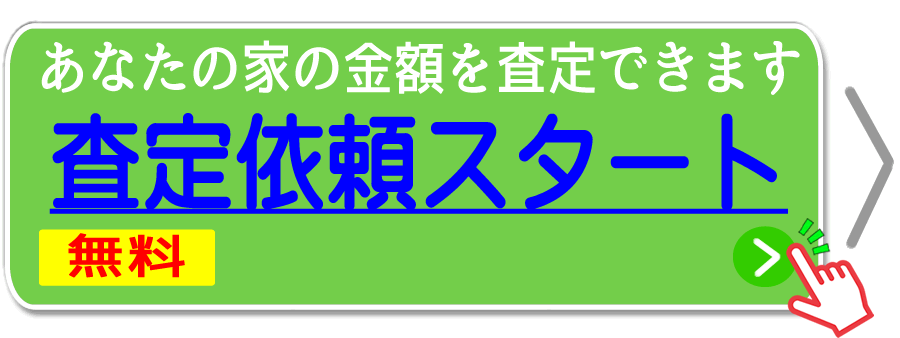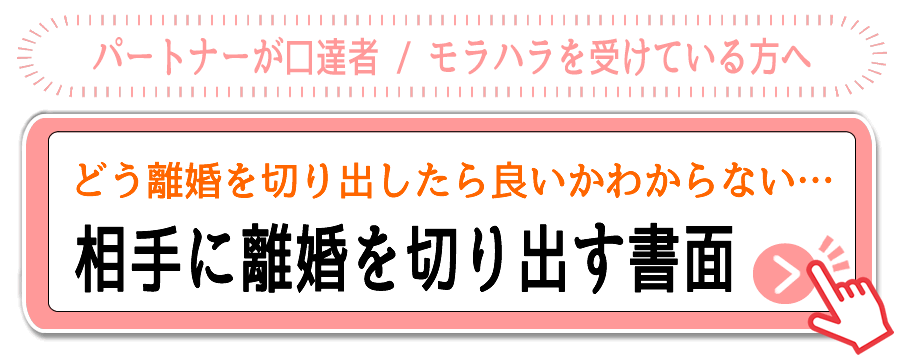離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説

- 離婚の財産分与とは?対象になるもの・ならないもの
- 離婚で問題になりやすい「持ち家」とは
- 共有名義の持ち家はどう分ける?トラブル回避のポイント
- 名義が相手のままの家に住み続けるリスクとは?
- 家を売却して分ける方法がもっとも安全?
- 財産分与の合意内容は「公正証書」などで残しておく
- 離婚協議書の書き方ガイド
- いきなりホームレス?別れた旦那が家の住宅ローンを滞納するとどうなる?
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
離婚の財産分与とは?対象になるもの・ならないもの

離婚を考え始めたとき、まず最初に悩むことの一つが「お金と財産をどう分けるか」ではないでしょうか。
なかでも持ち家や預金、ローンなどの資産と負債の取り扱いは、人生に大きく関わる問題です。
そもそも、離婚時に行う「財産分与」とは、夫婦で築いた財産を公平に分けるための制度です。
民法768条で定められており、協議離婚・調停離婚・裁判離婚いずれの場合も対象になります。
財産分与の基本ルールとは
財産分与では、基本的に「婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産」を半分ずつに分けるのが原則です。
夫の名義・妻の名義という形式は関係なく、「実質的に夫婦で築いたかどうか」が判断の基準となります。
専業主婦(主夫)で収入がなかった方も、「家事労働という形で家庭に貢献していた」と評価され、 貢献度に応じた財産分与を請求する権利があります。
婚姻期間中に築いた財産が対象になる
具体的には、次のようなものが財産分与の対象になります。
- 夫婦名義や一方の名義の預貯金
- 住宅・土地などの不動産
- 車や家財道具などの動産
- 生命保険の解約返戻金
- 株式や投資信託などの金融商品
たとえ名義が一方にしかなかったとしても、婚姻中に築いたものなら「共有財産」とみなされるケースが多いのです。
対象外になるもの(相続・贈与・結婚前の財産)
一方、以下のような財産は原則として財産分与の対象にはなりません。
- 婚姻前から持っていた個人資産
- 親などからの相続で得た財産
- 個人名義で贈与された財産
たとえば、結婚前に購入した持ち家は、たとえその後2人で住んでいたとしても「特有財産」とされる可能性があります。
ただし、婚姻中にリフォーム費用を共有財産から支払った場合などには、一部が分与の対象になるケースもあります。
判断が難しいときは、法律や不動産に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
離婚で問題になりやすい「持ち家」とは

離婚時の財産分与で、最も揉めやすく、また慎重な判断が求められるのが「持ち家(住宅不動産)」です。
現金や預金と違い、不動産は簡単に半分に分けることができません。
名義の問題、住宅ローンの残債、住み続けたいという希望…複数の要素が絡み合うため、感情と損得の両面で非常に複雑な問題になりがちです。
「名義」と「ローン残債」が絡むため複雑になりやすい
たとえば、次のようなケースを想像してみてください。
- 住宅の名義は夫、ローンも夫が支払っている
- 妻は子どもと一緒に今の家に住み続けたいと考えている
この場合、妻が家に住み続けたとしても、名義もローンも夫のままである限り、リスクは常に残ります。
夫がローン返済を滞らせた場合、たとえ妻と子どもが住んでいても、最悪、家が競売にかけられてしまうという事態もありえるのです。
住宅ローンの支払い名義・登記名義を再確認
財産分与を考える際は、まず以下の2点を必ず確認しましょう。
- 登記簿上の名義人は誰か(共有名義か単独名義か)
- 住宅ローンの契約者は誰か(連帯債務・連帯保証を含む)
たとえば、「夫婦共有名義」で「住宅ローンは夫のみ」という組み合わせも少なくありません。
このような場合、たとえ持ち分が2分の1ずつであっても、ローンの支払い責任は一方に偏っているという不均衡が生じています。
こうした事情を無視して単純に「半分ずつ分けましょう」と進めてしまうと、
後々トラブルになることもあるため、慎重な確認と交渉が必要です。
持ち家が財産分与の争点になる理由
不動産は高額な資産であるため、分与割合の中でも大きな比重を占めます。
しかし、それ以上に厄介なのが、「お金で解決しにくい感情」が絡む点です。
- 「自分がローンを払っていたのに家を取られたくない」
- 「子どもと一緒に暮らし続けたいから手放したくない」
- 「思い出があるから売るのがつらい」
こうした気持ちは、誰しもが持つ自然な感情です。
しかし、現実的なリスクや将来の影響を冷静に見つめることも大切です。
とくに「相手名義の家に住み続ける」「ローンを払ってもらう前提で生活を組み立てる」といった選択は、 相手の動向に依存するリスクが非常に高くなります。
共有名義の持ち家はどう分ける?トラブル回避のポイント

離婚後、夫婦で共有していた持ち家をどう扱うかは、とてもデリケートな問題です。
とくに「共有名義」になっている場合、法律上の権利関係が複雑で、感情的なもつれを生みやすい状況になります。
名義の割合がそのまま分与割合ではない
まず押さえておきたいのは、「登記上の名義が50%ずつでも、実際の財産分与は50:50とは限らない」という点です。
たとえば、名義は夫婦2分の1ずつでも、実質的な住宅ローンは夫のみが支払っていた――というケースもあります。
このような場合、貢献度や支払い状況をもとに調整されることが多く、
必ずしも「登記通りに半分ずつ」にはならない可能性があります。
住宅ローンの支払い状況と寄与度の影響
住宅ローンの返済は、財産形成における大きな寄与として評価されます。
したがって、どちらがどのくらい支払っていたかが分与割合に影響します。
一方で、家事や育児を担っていた側の貢献も無視はできません。
裁判所では「家事労働の寄与も含めた公平な分与」が原則とされているため、金銭的貢献だけではなく生活全体のバランスを見て判断されるのです。
共有名義を解消する3つの選択肢
共有名義の不動産を離婚後もそのままにしておくと、将来的なトラブルの火種になります。
できる限り名義を整理・解消しておくことが望ましいです。
主な選択肢は以下の3つです。
1. 売却して現金で分ける
もっともリスクが少なく、トラブルが起こりにくい方法です。
不動産を売却し、売却益からローンを精算したうえで、残った金額を分け合う形です。
売却時の不動産評価や手続きがやや煩雑にはなりますが、今後の関係を断ち切りやすいという大きなメリットがあります。
2. 一方が持ち家を引き取り、相手に代償金を支払う
どちらかが引き続き住みたい場合や、売却したくない事情がある場合には、
持ち分を相手から買い取り、「代償金」を支払って所有権を一本化する方法があります。
ただし、まとまった現金が必要となるため、住宅ローンの借り換えや資金調達が必要になるケースもあります。
3. 共有のまま維持(ただしリスクが大きい)
一時的に共有名義を維持するという選択もありますが、これは極力避けるべきです。
将来の再婚や相続、ローン滞納といった事態が起きた際、深刻なトラブルを招く可能性が高いためです。
どうしてもすぐに名義を整理できない場合は、契約書を作成するなどしてリスクを最小限に抑える工夫が必要です。
名義が相手のままの家に住み続けるリスクとは?

離婚後、子どものために慣れ親しんだ家に住み続けたい。
そう考える方は少なくありません。
しかし、その家が相手名義のままである場合、大きなリスクを抱えることになります。
住宅ローンが相手名義のまま=返済トラブルのリスク
離婚後も元配偶者がローンの契約者である場合、たとえ自分や子どもがその家に住んでいたとしても、返済義務は相手側にあります。
そして、もし元配偶者がローンを滞納した場合、金融機関は「住んでいる人」ではなく、「契約者」に対して督促や差し押さえを行います。
結果的に、住人であるあなたや子どもが立ち退きを迫られる可能性もゼロではありません。
相手が亡くなると相続が発生し、名義人が変わる可能性
もう一つのリスクは、相手の死亡によって名義が変わってしまうことです。
たとえば、離婚後に元配偶者が亡くなった場合、その家の所有権は相手の子どもや親族に相続されます。
すると、突然「全く別の人の持ち家に住んでいる」状態になり、立ち退きや名義トラブルが起きるリスクが一気に高まります。
こうした事態は、自分がその家でどれだけ長く暮らしていたとしても避けられないものです。
相手が売却や担保設定してしまうリスク
相手名義のままである以上、その人には「売却」や「担保に入れる」自由が残っています。
つまり、住んでいる側の合意がなくても、勝手に第三者に売却されたり、借金の担保にされてしまう可能性があるのです。
このようなリスクを回避するためにも、「住み続けたい」という気持ちがあるなら、名義の変更・ローンの引き継ぎ・共有解消などの具体的な対策が不可欠です。
住み続けるなら「名義変更」や「売却」を検討すべき理由
離婚後も住み続けたいと考えている場合は、次のような対応を検討するのが望ましいです。
- 相手の持ち分を買い取り、単独名義にする
- 住宅ローンを借り換えて、自分名義にする
- いったん売却し、別の住宅に住み替える
これらはいずれもハードルが低いわけではありませんが、長期的な安心と安全を手に入れるためには不可欠なステップです。
家を売却して分ける方法がもっとも安全?

離婚にともなう持ち家の財産分与において、もっともリスクが少なく、明確に分けられる手段が「売却」です。
感情的には「手放したくない」と感じるかもしれませんが、将来のトラブルを防ぐという点で、売却は非常に有効な選択肢です。
売却して現金化すれば分配しやすい
不動産は現物のままでは分けにくい資産ですが、売却して現金化すれば、明確に分割が可能になります。
たとえば、家を3000万円で売却し、ローン残債が1000万円であれば、差額の2000万円が夫婦の共有財産として分与対象になります。
この場合、1000万円ずつを取得する、あるいは話し合いで比率を調整することも可能です。
売却益を平等に分けることができれば、後々の感情的なしこりも残りにくくなります。
売却益が出る場合・ローン残債がある場合の対応
持ち家を売却する際は、以下の2パターンがあり、それぞれ対応が異なります。
1. 売却益が出るケース
住宅の市場価値がローン残債を上回っている場合、売却益が発生します。
この利益を夫婦で分けることができ、トラブルの少ない財産分与が実現しやすくなります。
2. ローン残債のほうが大きいケース(オーバーローン)
不動産価格よりもローン残債のほうが多い「オーバーローン」の場合は、
売却しても借金が残ってしまうため、持ち出しでの清算が必要になります。
たとえば、売却価格が2500万円、ローン残債が3000万円であれば、残りの500万円は自己負担しなければなりません。
このようなケースでは、代償金や精算方法をしっかり協議しておくことが重要です。
任意売却やリースバックという選択肢
オーバーローンや支払い困難な状況にある場合、任意売却(金融機関の同意を得ての売却)という手段もあります。
これは競売を避けつつ、より高値で売却できる可能性がある方法です。
また、一部のケースでは「リースバック」(自宅を売却し、売却先と賃貸契約を結んで住み続ける)という方法もあります。
ただし、家賃負担や契約条件に注意が必要で、慎重な判断が求められます。
売却が成立するまでのタイミングと注意点
家の売却は一朝一夕にできるものではありません。
販売活動 → 買主の決定 → 契約 → 引き渡しという流れがあり、完了までに数ヶ月かかることも珍しくありません。
離婚のタイミングと売却時期をどう合わせるか、また仮住まいの確保など、スケジュール管理も重要な要素になります。
また、離婚前に売却してしまうと、売却益に対する税務処理(譲渡所得税)の特例が使えなくなるケースもあるため、税金面での確認も欠かせません。
住宅ローンの名義変更・借り換えはできる?

離婚後に家を残したい場合、「住宅ローンの名義変更ができればいいのに」と考える方も多いでしょう。
しかし、住宅ローンの名義変更は簡単にはできないのが現実です。
銀行は「返済能力」を見て判断する
住宅ローンの契約者を変更するには、金融機関の審査を通過しなければなりません。
つまり、「これから支払っていく人が、安定した収入を持ち、返済能力があるか」が厳しくチェックされます。
離婚により世帯収入が減少する場合、単独名義に変更するのは難しいケースがほとんどです。
特に専業主婦(主夫)だった方や、パート勤務など年収が限られている方は、審査が通らない可能性が高いのです。
単独名義への変更が難しい場合の代替案
もし金融機関が名義変更を認めない場合には、以下のような代替策があります。
- 住宅ローンの借り換えを行い、新たに単独名義で契約する
- 一時的に売却して、現金で分与・新居を取得する
- リースバックやサブリースを利用し、資産化して住み替え費用に充てる
どの方法も一長一短があり、今後のライフプランと家計の安定性をふまえて判断する必要があります。
金融機関との交渉に同意が必要な理由
ローン名義が夫婦共有や、どちらか一方であっても、勝手に名義変更はできません。
必ず金融機関の許可が必要であり、場合によっては連帯保証人や担保条件の変更も求められることがあります。
この交渉は非常に煩雑で、個人での手続きが難しい場合は、住宅ローンに詳しい司法書士やファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの手です。
財産分与で損をしないために知っておくべきポイント

離婚時の財産分与では、感情が先走ってしまい、本来受け取れるはずの財産を放棄してしまうケースも少なくありません。
しかし、冷静に判断し、正しい手続きを踏めば、自分にとって不利な結果を回避することが可能です。
ここでは、財産分与で損をしないために意識すべき重要なポイントをご紹介します。
不動産の評価額を正確に知る
持ち家の財産分与で最も重要なのは、現在の市場価値を正確に把握することです。
固定資産税評価額や購入時の価格ではなく、「売却できるとしたらいくらになるか」が基準になります。
不動産会社に査定を依頼することで、現時点での売却見込み額が把握できます。
できれば複数の業者に依頼して、相場感をつかむのが理想です。
また、マンションなどは築年数や立地、管理状況によって評価が大きく異なるため、安易に自己判断せず、専門的な評価を受けることをおすすめします。
登記簿とローン契約書は必ず確認
不動産に関しては、「登記簿」と「住宅ローン契約書」が非常に重要な書類です。
- 登記簿:誰が名義人か、共有割合はどうかがわかる
- ローン契約書:契約者や連帯保証人の有無、返済条件が確認できる
これらの内容に誤認や思い込みがあると、分与の交渉や手続きに支障が出るため、事前に必ず確認しておきましょう。
第三者の専門家(弁護士・不動産業者)に相談を
「どこまでが共有財産なのか」「どう分けるべきか」「名義をどう整理するか」といった問題は、法的にも非常に複雑です。
感情的なやりとりだけで解決しようとすると、不公平な結果になったり、後々揉めごとになる可能性もあります。
弁護士に相談して、協議書の内容を詰める、不動産会社に売却の手続きを依頼するといった形で、冷静で中立的な立場の専門家をうまく活用しましょう。
財産分与の合意内容は「公正証書」などで残しておく

離婚に際して決めた財産分与の内容は、口約束のままでは危険です。
あとになって「そんな話はしていない」「そんな約束はしていない」と主張されても、証拠がなければ対処できません。
そこで、財産分与の合意内容は文書として残しておくことが非常に大切です。
口約束だけでは後々トラブルになる可能性
特に金銭の支払いを分割で受け取る場合や、住宅ローンの返済を相手に任せる場合などは、途中で支払いが止まるリスクもあります。
また、再婚や転職などで相手の状況が変われば、「もう払えない」「知らない」と言われる可能性も。
こうしたトラブルを防ぐためには、法的効力のある書面にしておくことが不可欠です。
合意書、公正証書、調停調書の違いと活用
文書で合意内容を残すには、以下の方法があります。
- 合意書(私的契約書):当事者同士の署名・押印が必要
- 公正証書:公証役場で作成し、強制執行力を持つ
- 調停調書:家庭裁判所で調停の結果として作成される
特に分割払いがある場合や将来的なトラブル回避を重視する場合には、公正証書や調停調書の作成を検討するとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 離婚後も共有名義のまま家に住み続けることはできますか?
A. 物理的には可能ですが、名義を整理しないままでは大きなリスクが残ります。
元配偶者が亡くなったり、家を担保に借金をした場合、住み続ける権利が失われる可能性もあるため、名義の整理や売却を検討すべきです。
Q. 財産分与に住宅ローンの残りは含まれますか?
A. はい、住宅ローンも分与対象の不動産に紐づいているため、負債として考慮されます。
売却で清算する、または一方が引き継ぐなどの方法がありますが、金融機関の同意が必要なケースもあるため注意が必要です。
Q. 相手が名義を変更してくれない場合はどうなりますか?
A. 協議で合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
ただし、住宅ローンが絡む場合は金融機関の判断も関わってくるため、法的なサポートを受けながら慎重に進めることが大切です。
まとめ・離婚による財産分与では持ち家の扱いに注意

離婚による財産分与のなかでも、「持ち家の扱い」は特に慎重に検討すべき重要なテーマです。
名義、ローン、住み続ける意思、子どもの生活環境…。
あらゆる要素が複雑に絡み合い、感情だけで判断するのは危険です。
とくに注意すべきは、次のようなケースです。
- 相手名義の家に住み続ける
- 住宅ローンは相手が払い続けるという約束
- 名義の整理をせず、共有のまま放置する
これらはいずれも、将来的に大きなトラブルにつながる可能性をはらんでいます。
もっとも安全な選択肢は、売却して現金で分けることです。
売却が難しい場合でも、名義変更やローン借り換えの検討、代償金の支払いなど、明確に財産を整理しておくことが、後の安心につながります。
財産分与は、離婚後の生活を支える土台です。
感情を整理し、必要であれば専門家のサポートを受けながら、納得のいく分け方を選んでいきましょう。
それが、新しい一歩を踏み出すあなた自身のためにも、子どもたちのためにも大切な決断になるはずです。
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚協議書の書き方ガイド|後悔しないために決めておきたいことと作成のポイント
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
全国の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方
▼地域ごとの離婚の手続きと離婚届の書き方と出し方の情報はこちらから