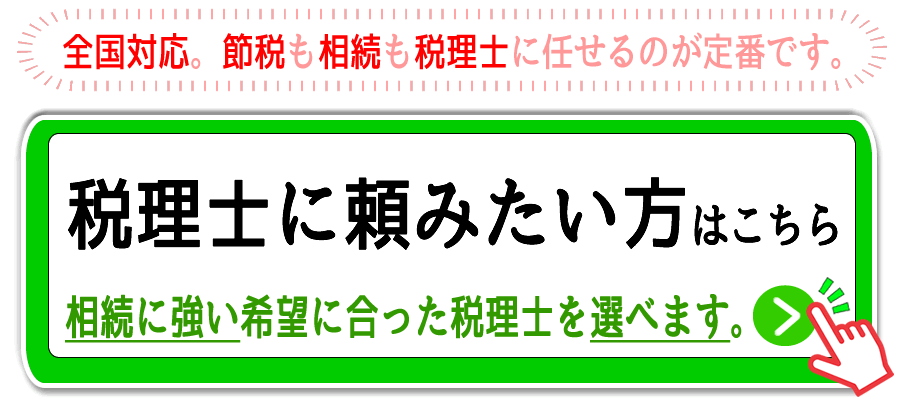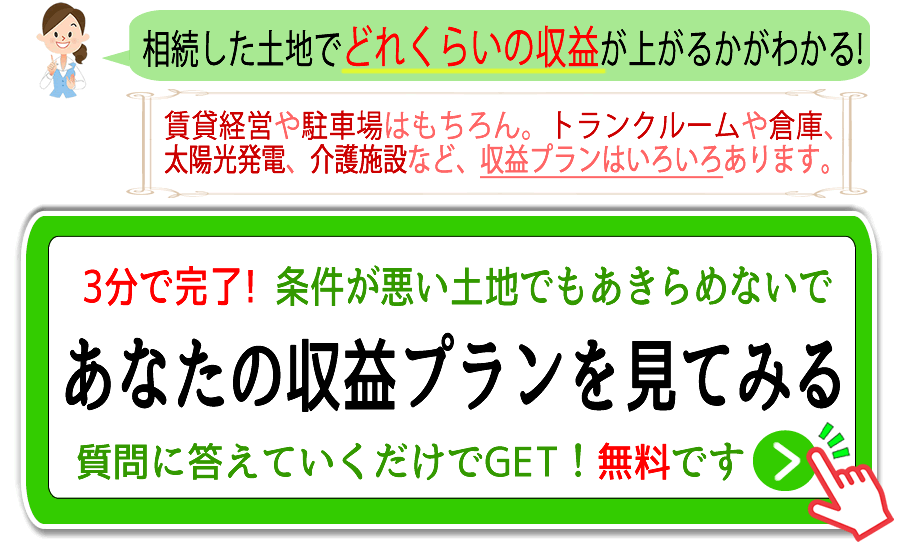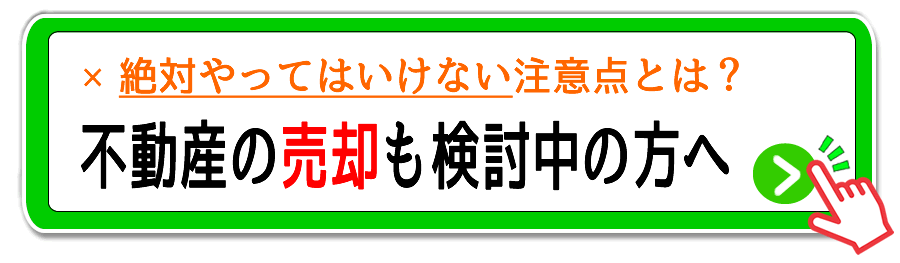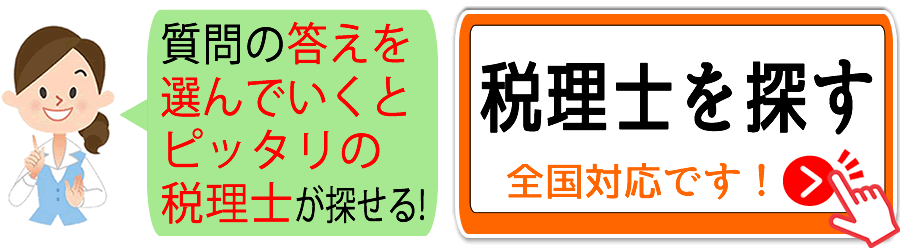PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説

- 相続した不動産がいくらで売れるか無料で査定できます
- 相続した不動産を売却すると税金がかかる?
- 譲渡所得税の仕組みを理解する
- 売却時にかかる税金の種類と税率
- 相続した不動産を売却するときの特例と控除
- 3年以内に売る vs 5年超えてから売る、どちらが有利?
- 売却時の「必要経費」として認められるもの
- 注意すべき税務申告と手続き
- 相続不動産の売却で税金を最小限に抑えるには?
- まとめ|相続した不動産の売却は、税務知識で差がつく
- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
相続した不動産を売却すると税金がかかる?

相続=譲渡ではない。売却時に課税される理由とは?
不動産を相続したと聞くと、「財産をもらっただけで税金がかかるのでは?」と不安になる方も多いかもしれません。
しかし、相続によって不動産を取得しただけでは、原則として税金(譲渡所得税)はかかりません。
一方で、その不動産を売却すると話は変わります。
売却によって利益が生じると、譲渡所得税(所得税+住民税)が課されるのです。
譲渡所得とは?相続と売却の税務の違い
「譲渡所得」とは、土地や建物などの資産を売却したことで得られる利益のことです。
たとえば、相続で取得した土地を2,000万円で売却し、取得費や必要経費を差し引いて1,000万円の利益が出た場合、この1,000万円が譲渡所得となります。
一方で、「相続税」は遺産の受け取りに対して課される税金であり、「譲渡所得税」とはまったく異なる性質の税金です。
つまり、相続したあとに不動産を売却すると、別の税金が新たに発生するという仕組みです。
相続しただけでは非課税、売却時に「譲渡所得税」がかかる
繰り返しになりますが、相続そのものには譲渡所得税は発生しません。
発生するのは、「売却したとき」、つまり財産を手放した瞬間です。
ここで重要なのは、相続した不動産の「取得価格」が不明であることが多いという点です。
被相続人が何十年も前に購入している場合、正確な購入金額や経費がわからないケースもあり、税額に大きな差が出るリスクがあります。
譲渡所得税の仕組みを理解する

譲渡所得=売却額-取得費-必要経費
譲渡所得の基本的な計算式は以下の通りです:
つまり、不動産をいくらで売ったかから、それを取得するためにかかった費用(取得費)や売却時にかかった費用(仲介手数料など)を差し引いた金額が、課税対象となる利益(譲渡所得)になります。
相続不動産の場合の取得費の考え方(被相続人の取得時点)
相続で取得した不動産の場合、「取得費」は自分ではなく被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した際の金額を引き継ぐというルールになっています。
たとえば、被相続人が昭和50年に500万円で土地を購入していた場合、その500万円が取得費となります。
もしこの土地を2,500万円で売却すれば、取得費500万円+譲渡費用(仮に200万円)を差し引いた1,800万円が譲渡所得となります。
このように、被相続人の購入時の金額や資料が残っているかどうかが、税額を大きく左右する要素となるのです。
取得費不明な場合は「概算取得費5%」が適用されるリスク
取得費がまったく不明な場合は、税法上の救済措置として、売却価格の5%を「概算取得費」とみなす制度があります。
つまり、2,000万円で売却しても、取得費が100万円とみなされ、残りの1,900万円に対して課税されることになります。
この「5%ルール」は、取得費の証拠書類が何もない場合の最終手段ですが、実際の取得費よりも著しく低くなるケースが多く、結果として税額が大きくなるため注意が必要です。
売却時にかかる税金の種類と税率

譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別所得税)
不動産の売却で利益が出ると、以下の3種類の税金が課されます:
- 所得税(国税)
- 住民税(地方税)
- 復興特別所得税(所得税×2.1%)
これらをまとめて「譲渡所得税」と呼ぶことがあります。
課税される税率は、所有期間によって大きく変わるため、次項で詳しく解説します。
短期譲渡・長期譲渡で税率が変わる
不動産を売却した場合、その所有期間に応じて「短期譲渡所得」または「長期譲渡所得」に区分され、課税される税率が異なります。
- 短期譲渡(5年以下):約39%(所得税30%+住民税9%)
- 長期譲渡(5年超):約20%(所得税15%+住民税5%)
さらに、所得税部分に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。
所有期間5年以内と5年超の違いに注意
ここで注意すべきは、「所有期間5年超」とは、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかという点です。
たとえば、
2019年3月に相続し、
2024年3月に売却した場合でも、
2024年1月1日時点でまだ4年と10か月のため、
→ 短期譲渡扱いになります。
つまり、5年と1日経っていても、その年の1月1日時点で5年を超えていなければ「短期」扱いになる点に注意が必要です。
相続した不動産を売却するときの特例と控除

相続空き家の3000万円特別控除とは?
相続した不動産を売却する際、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
これが、いわゆる「相続空き家の3000万円特別控除」です。
この特例は、被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家を、相続人が売却した場合に使える制度で、譲渡所得が3,000万円以内であれば課税されない非常に大きなメリットがあります。
適用条件(相続人居住歴なし・耐震改修or取壊し等)
この特例はすべての空き家に適用されるわけではなく、以下のような条件を満たす必要があります:
- 被相続人が「昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て」に住んでいたこと
- 相続人がその家を「居住用として利用していないこと」
- 耐震改修をして売却するか、取壊して更地として売却すること
- 相続開始後に「相続人が貸付・事業・他人居住に供していないこと」
また、不動産の売却価格が1億円以下であることも条件のひとつです。
細かい要件がありますが、該当すれば非常に有利な制度です。
売却期限は「相続発生から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」
この3000万円控除には明確な期限があります。
それが、
「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却契約を結ぶ」こと。
たとえば、2021年3月に被相続人が亡くなった場合、「2024年12月31日」までに売却しなければ、この特例は使えません。
売却契約日が基準になるため、引き渡し日や登記日ではないことにも注意が必要です。
3年以内に売る vs 5年超えてから売る、どちらが有利?
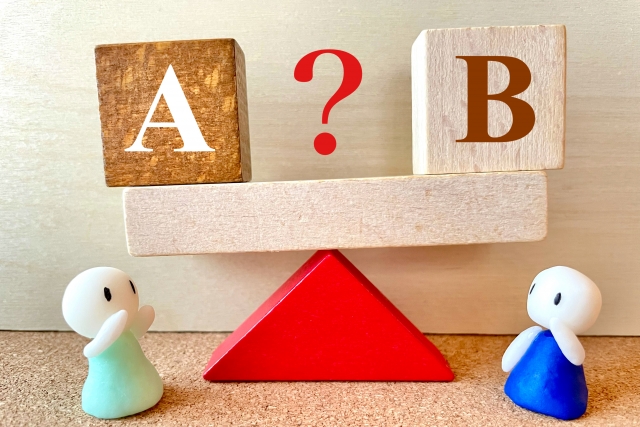
3000万円控除を活かすには「3年以内の売却」が基本
先述の特例を適用するには、「相続開始から3年経過年末まで」という期限があるため、3年以内に売却することが最重要となります。
控除額が3,000万円に達すれば、譲渡所得がゼロになり、税金もゼロになる可能性があるため、早期売却のほうが節税効果が高いケースも少なくありません。
一方で「5年超所有で長期譲渡になると税率が下がる」
一方で、相続によって取得した不動産を5年超保有してから売却すれば、譲渡所得が長期譲渡扱いとなり、税率が20%台前半に抑えられます(短期譲渡なら約39%)。
ただし、相続の場合の所有期間の起算点は「被相続人が取得した日」からカウントされるため、すでに5年以上所有していた不動産を相続した場合、長期譲渡となるケースも多いのです。
節税効果を比較し、どちらが得かケース別で検討を
- 控除(3000万円特例)を使えるか?
- 取得費の有無(概算取得費になるか)
- 不動産の売却価格と譲渡所得額
- 所有期間(長期譲渡の適用可否)
これらの要素を踏まえ、「控除を使ってすぐ売る」か「5年超えて税率を下げてから売る」かを慎重に比較しましょう。
具体的な判断が難しい場合は、相続税や不動産に詳しい税理士への相談をおすすめします。
売却時の「必要経費」として認められるもの

リフォーム費用・測量費・仲介手数料など
譲渡所得の計算で「必要経費」に含められる代表的なものには以下があります:
- 不動産会社に支払った仲介手数料
- 売却時に行った建物の解体費用
- 売却に伴う測量費・境界確定費
- 登記事項証明書などの取得手数料
- 改修工事費用(ただし「売却のための工事」と明確な場合のみ)
これらを譲渡費用として計上することで、譲渡所得を圧縮し、結果として納税額を減らせます。
相続登記費用や取得時の登録免許税は含められる?
一方で、相続時に支払った以下のような費用は、原則として「譲渡に直接関係ない」とされるため、必要経費としては認められないケースが多いです。
- 相続登記の登録免許税
- 相続に伴う司法書士報酬
- 相続税の納税
ただし、評価や税務処理の根拠資料と見なされるケースもあるため、グレーゾーンの費用については事前に税理士に確認することをおすすめします。
経費にできるもの・できないものの線引きに注意
売却に必要な経費かどうかは、「売却のために直接支出した費用であるかどうか」が判断基準になります。
たとえば、
- 解体して更地で売却するための費用 → OK
- 売却とは関係のないリフォーム → NG
- 相続手続きに関する費用 → 基本NG
経費として計上できるかどうかで、数十万円〜数百万円の節税効果が変わることもあります。
必ず明細や領収書を保管し、あとで説明できるようにしておくことが重要です。
注意すべき税務申告と手続き

譲渡所得の申告は「売却した翌年の確定申告」で行う
相続した不動産を売却した場合、その利益(譲渡所得)については、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
たとえサラリーマンで普段は確定申告が不要な方でも、不動産の売却益がある場合は必ず申告が必要です。
確定申告では以下の書類などが必要となります:
- 売買契約書の写し(売却時・取得時)
- 仲介手数料や登記費用などの領収書
- 相続登記に関する書類
- 住民票・登記事項証明書など不動産に関する資料
- 特例(3000万円控除など)を使う場合は別途添付書類
特例適用には書類添付が必須。申告ミスで控除無効になる例も
たとえば、相続空き家の3000万円特別控除を使うには、
- 被相続人の死亡日が確認できる戸籍の写し
- 相続登記の完了を証明する登記事項証明書
- 耐震改修を行った証明書または取壊し後の売却である証拠
- 譲渡所得の特別控除に関する明細書
など、多数の添付書類が必要です。
これらが不備だったり、条件を満たしていない場合は、控除が適用されず、数百万円単位で課税されるリスクもあります。
制度を使う際には、税理士に相談して確認しながら申告するのが安心です。
申告を忘れるとペナルティや追徴課税のリスクも
譲渡所得の申告を怠ると、
- 無申告加算税(5〜20%)
- 延滞税
- 場合によっては重加算税(35〜40%)
などの追徴課税が発生するおそれがあります。
とくに、税務署からの指摘で初めて発覚した場合は、悪質と判断されやすく、ペナルティも重くなりがちです。
売却益が出た年は、必ず忘れずに確定申告を行いましょう。
相続不動産の売却で税金を最小限に抑えるには?

早期売却と特例活用のバランスが鍵
節税の観点からは、3年以内の売却で3000万円控除を適用するのが有利なケースが多く見られます。
空き家であれば維持費や固定資産税もかかるため、早めに売却したほうが総合的なコスト削減にもつながります。
ただし、不動産市況や買い手の動向にも左右されるため、焦って安く売り急ぐことは避けるべきです。
必要経費の領収書・証拠は必ず保管
リフォームや解体費用、仲介手数料など、譲渡費用として計上可能な経費は、領収書や明細が残っていなければ認められません。
売却の準備段階から、次のような資料は必ず保管しておきましょう。
- 解体・測量・登記などの請求書・領収書
- 不動産会社との媒介契約書
- 買取業者との交渉記録や査定書
申告時に整理しておくと、税理士による計算もスムーズになります。
不動産会社任せにせず、税理士への相談も視野に
売却は不動産会社に任せることが多いですが、税金に関しては不動産業者は専門外です。
とくに、
- 節税を見据えた売却タイミング
- 特例や控除の適用判断
- 取得費や経費の精査
などは、税理士の助言を受けることで結果が大きく変わることがあります。
不動産を売却する前、または売却と同時に、税理士への相談も並行して進めることが理想です。
まとめ|相続した不動産の売却は、税務知識で差がつく

「いつ売るか」で税負担が大きく変わる
相続した不動産の売却では、売る時期によって適用できる控除や税率が大きく変動します。
3年以内の売却で控除を使うのか、それとも長期譲渡に切り替えるのか、その判断が税額に直結します。
特例を逃さないためにはスケジュール管理が重要
特例には厳密な期限が設けられています。
売却契約日をベースにして控除可否が決まるため、売るか迷っている間に期限が過ぎてしまうことも。
相続が発生した時点から、スケジュール管理を意識しておきましょう。
不安な場合は税理士・司法書士・不動産業者に相談を
不動産の売却には、税金・登記・売却実務と、多方面の専門知識が必要です。
自分ひとりで判断せず、それぞれの分野のプロと連携することで、失敗や無駄な納税を防ぐことができます。
特に税制は年々変わるため、直近の制度に精通した税理士への相談は、安心と節税のために非常に有効です。
よくある質問(FAQ)
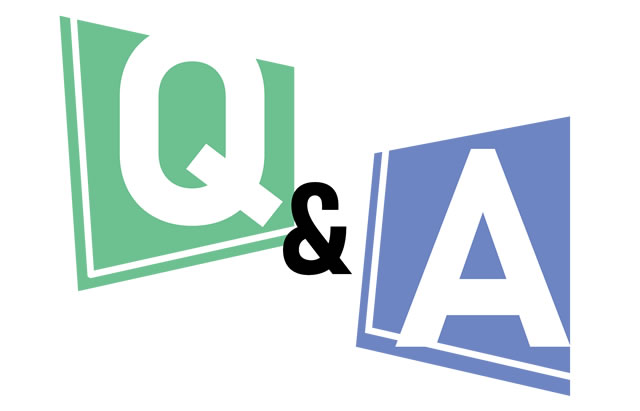
Q. 相続した不動産を売却すると、どんな税金がかかるのですか?
A. 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)がかかります。
相続そのものには課税されませんが、売却によって利益が出た場合、その利益に対して課税されます。
Q. 相続した不動産でも3000万円の控除は使えますか?
A. 一定条件を満たせば「相続空き家の3000万円控除」が使えます。
ただし、被相続人が一人で住んでいた家であることや、売却期限など複数の要件があります。
Q. 売却は早いほうが得ですか?それとも5年待ったほうが節税になりますか?
A. ケースによりますが、3000万円控除を使えるなら早期売却が有利なことが多いです。
ただし、長期譲渡(5年超)になると税率が下がるため、売却時期の判断は税理士に相談するのが確実です。
Q. 譲渡所得の計算で必要経費になるものは何ですか?
A. 仲介手数料、測量費、建物解体費用などが必要経費に該当します。
相続登記の費用や司法書士報酬などは原則として対象外ですが、個別判断が必要なものもあります。
- 相続した不動産がいくらで売れるか無料で査定できます
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
全国の相続の手続き完全ガイド|まず何をすればいい?期限・流れ・必要書類を徹底解説
▼地域ごとの相続の手続きの情報はこちらから