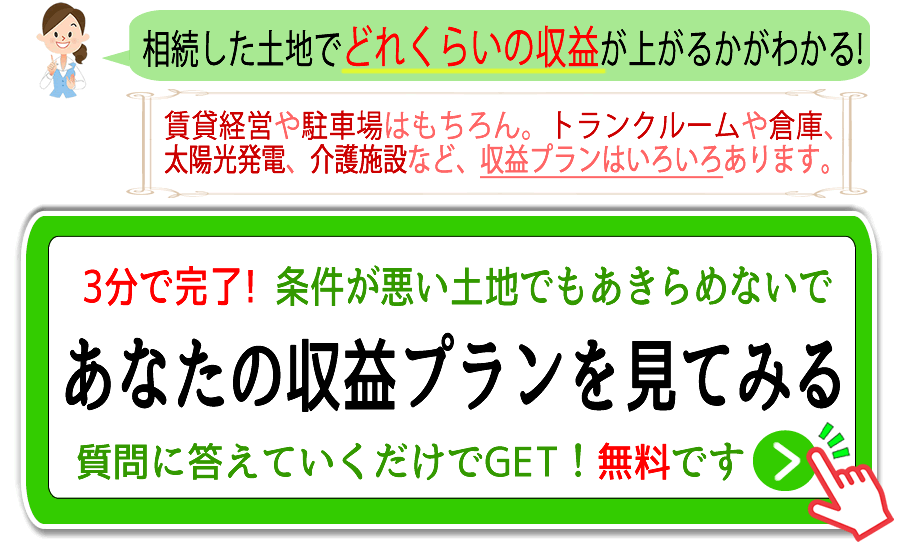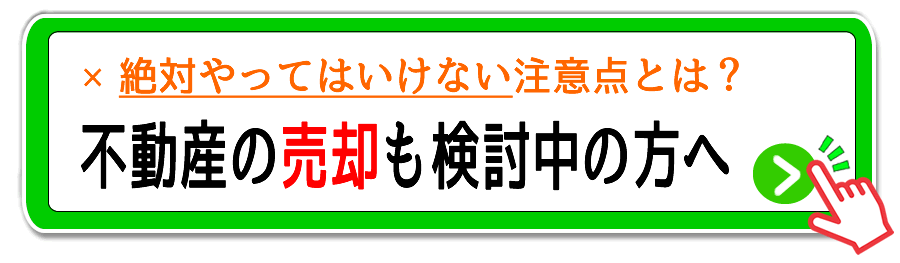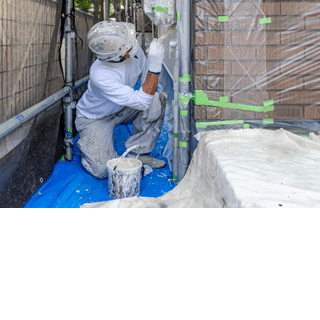PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて

- 相続した不動産がいくらで売れるか無料で査定できます
- 相続した不動産は売却できる?まず押さえるべき基本知識
- 不動産売却前に必要な手続き|相続登記と名義変更
- 相続不動産を売るときの税金とは?知っておくべきポイント
- 空き家を放置するとどうなる?早めの売却が有利な理由
- 実家を兄弟で相続した場合の売却のコツと注意点
- 不動産会社に相談するタイミングと選び方
- まとめ|相続不動産を売却するなら「早めに動く」が鉄則
相続した不動産は売却できる?まず押さえるべき基本知識

突然の相続で実家や土地を受け継ぐことになった場合、最初に頭をよぎるのは「この不動産、どうすればいいのか?」という悩みです。特に遠方に住んでいたり、住む予定のない空き家であったりする場合には、売却という選択肢が現実的になることが多いです。しかし、相続で得た不動産を売るためには、いくつかの法律的・手続き的なステップを踏む必要があることを知っておく必要があります。
まず、原則として相続開始直後に不動産をすぐに売ることはできません。不動産を売却するには「所有権」が自分の名義になっている必要があるため、相続登記と呼ばれる名義変更の手続きを先に行う必要があります。これにより、法的にその不動産の所有者として認められ、ようやく売却の手続きを進めることが可能になります。
また、相続人が1人だけであれば比較的スムーズですが、兄弟や親族など複数人が相続人となっている場合は注意が必要です。その不動産は、相続人全員の「共有財産」という状態になりますので、売却には全員の合意と署名が必要です。協議の末、誰か1人が引き継ぐ、または売却して現金を分配するなどの方向性を決めなければなりません。話し合いが難航するケースもあるため、早期に遺産分割協議書を作成しておくことがトラブル防止につながります。
さらに、2024年4月からは法律が改正され、相続登記が義務化されました。相続が発生してから3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあるため、放置せず早めの対応が求められます。この背景には、空き家の増加や所有者不明土地問題の深刻化があり、国としても相続後の不動産管理を「個人の責任」として明確にした形です。
相続不動産を売却することは、感情的にも法的にも複雑さを伴う行為です。しかし、流れを理解してしまえば、ひとつずつ確実に進めていくことが可能です。まずは、名義がどうなっているか、相続人は誰か、そして現状の資産価値はどの程度かを把握することから始めてみましょう。
不動産売却前に必要な手続き|相続登記と名義変更

相続した不動産を売却するには、まず「相続登記(名義変更)」を完了させることが必須です。登記とは、法務局に不動産の所有者としての権利を記録することであり、この手続きが完了していない限り、正式に売却することはできません。逆に言えば、名義が自分に変わって初めて、不動産の「売主」としての権限が発生するのです。
相続登記に必要な書類は複数あり、基本的には以下のようなものが必要になります:被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書(共有財産の場合)、固定資産評価証明書、そして登記申請書です。これらの書類を揃えて法務局に提出し、登録免許税という税金(不動産評価額の0.4%)を支払って初めて登記が完了します。
注意したいのは、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートした点です。これにより、不動産を相続した場合は、原則として3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性もあるため、「今は使っていないから」「売るかどうかまだ決めていないから」と放置していると大きなリスクになります。
また、登記をせずに不動産を売ることは、基本的にできません。登記されていない状態では、売買契約を締結することは可能でも、引き渡しや所有権移転登記ができず、買主からの信頼も失うことになります。例外的に「相続人全員の同意書」などがあれば買付け交渉は可能な場合もありますが、トラブルのもとになるため推奨されません。
また、共有状態の相続不動産では、「誰がどの割合で所有しているか」を明確にし、遺産分割協議書で合意を取った上で登記することが求められます。このとき、相続人全員が署名・押印し、実印の印鑑証明書を添える必要があり、意外と手間と時間がかかります。司法書士に依頼することでスムーズに進められますが、費用相場は5万〜10万円ほどです。
このように、相続不動産の売却には「名義変更」が大前提であり、法的な整備がなされて初めて次のステップに進むことができます。少し煩雑に思えるかもしれませんが、早めに動くことで税金や法的リスクを回避できるため、なるべく先送りにせず、計画的に準備を進めていくことが大切です。
相続不動産を売るときの税金とは?知っておくべきポイント

相続した不動産を売却する際、多くの方が不安に感じるのが「税金はいくらかかるのか?」という点です。「相続税を払ったのに、さらに税金がかかるの?」と疑問に思う方もいますが、実は相続と売却では別々の税金が課されるため、注意が必要です。ここでは、相続不動産売却に関係する税金の種類と、賢く節税するためのポイントをご紹介します。
まず押さえておきたいのは、不動産を売却して利益が出た場合、その利益には「譲渡所得税」がかかるということです。たとえば、相続した実家を2,000万円で売却し、その土地と建物の取得費や売却経費などを差し引いた結果、利益が出た場合は、その利益部分に課税されます。これがいわゆる「譲渡所得税」で、所得税と住民税を合わせて約20%(長期譲渡)が課税されるのが一般的です。
ただし、ここで活用したいのが「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」という制度です。これは、一定の条件を満たせば、売却益から最大3,000万円までを控除できる制度で、特に実家を売却する際に強い効果を発揮します。具体的には、被相続人が住んでいた家屋を相続し、相続から3年以内に売却する場合などに適用されます。これにより、多くのケースで課税対象がゼロになる可能性もあるため、必ず確認しておきたい制度です。
一方で、相続税と売却時の税金はまったく別の税目です。すでに相続税を納めたからといって、売却益に対する税金が免除されるわけではありません。逆に、相続税を支払っていない場合でも、売却時に譲渡所得税が発生することはありますので、混同しないよう注意が必要です。
また、相続した不動産を売却した際に損失が出た場合は、「譲渡損失の繰越控除」などの制度を活用できるケースもあります。たとえば、新たに購入した住宅との損益通算を行ったり、3年間の繰り越し控除を活用することで、今後の税負担を軽減できる可能性があります。
税金の取り扱いは非常に複雑であり、相続の状況や不動産の評価額、売却価格によって大きく異なるため、できれば税理士や不動産会社のサポートを受けながら進めるのが安心です。後から「こんなに税金がかかるなんて知らなかった…」と後悔しないためにも、早い段階で税制の確認と試算をしておくことを強くおすすめします。
空き家を放置するとどうなる?早めの売却が有利な理由

相続した実家や土地が空き家のままになっているというケースは、年々増加しています。しかし、空き家をそのまま放置することには、多くのリスクとデメリットが伴います。「いつか使うかもしれない」「思い出があって手放せない」といった理由から手を付けずにいると、気づかぬうちに大きな負担を抱えることになりかねません。ここでは、空き家を放置することによる具体的なリスクと、なぜ早めの売却が有利なのかをご紹介します。
まず最大のリスクは、固定資産税などの維持コストが継続的にかかることです。誰も住んでいなくても、土地や建物の所有者には税金が課され、年に数万〜十数万円におよぶ支払いが発生します。さらに、建物が老朽化すると「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇が打ち切られることがあります。これにより、税額が一気に6倍近くに跳ね上がるケースもあります。
また、空き家は防犯や衛生の面でも地域に悪影響を及ぼします。雑草の繁茂やゴミの不法投棄、動物のすみかになることもあり、近隣住民とのトラブルにつながることも少なくありません。万が一、台風や地震で倒壊し、他人の敷地に被害を与えた場合、所有者としての責任を問われる可能性もあるのです。
さらに、建物の劣化が進むと、売却自体が難しくなってしまうこともあります。築年数が古くなるほど需要は下がり、解体が必要になると、その費用も自己負担となるため、「使わないけど売れない」「売りたくても売れない」状態に陥るリスクが高まります。これは相続人にとっても大きな負債となりかねません。
その一方で、早めに売却を検討すれば、建物の価値がまだ残っているうちに売ることができるだけでなく、税金・維持管理・心理的負担といった「目に見えないコスト」を早期に解消できます。特に相続から3年以内に売却すれば、「3,000万円特別控除」などの税制優遇が受けられる可能性もあるため、経済的にも非常に有利です。
このように、空き家は放っておくほどに「資産」から「負債」へと変わっていく性質を持っています。「まだ使う予定はない」「誰も住む人がいない」と判断できるなら、なるべく早い段階で売却や活用の方針を決めることが、今後のトラブル回避と資産の最適化につながるでしょう。
実家を兄弟で相続した場合の売却のコツと注意点
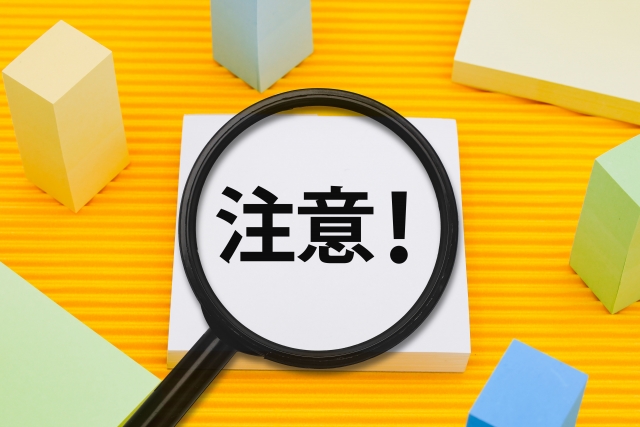
実家などの不動産を兄弟姉妹で共同相続するケースは非常に多く見られます。しかし、不動産は現金のように簡単に分けることができないため、相続人同士の意見の食い違いや感情のもつれがトラブルに発展しやすいのが現実です。だからこそ、「誰が所有するか」「売るのか、残すのか」を明確に決める協議と、合意形成のプロセスが非常に重要です。
共同相続が発生した場合、法的には相続人全員がその不動産の「共有者」となります。たとえば3人兄弟で相続した場合、それぞれ1/3ずつの所有権を持つことになります。この状態では、売却するには全員の同意と署名・押印が必須です。1人でも反対すれば売却は進まず、「放置されたまま誰も使わない空き家」となってしまうこともあります。
そこで必要になるのが「遺産分割協議書」の作成です。これは、相続人全員で話し合って「誰がどの財産を引き継ぐか」を合意するための正式な書面で、実印・印鑑証明付きで作成することで、登記や売却手続きにも使用できます。協議書によって不動産を1人の名義に集約すれば、その後の売却手続きがスムーズになります。
ただし、実際の協議では「売却して現金化したい」「残して思い出を守りたい」「将来子どもに使わせたい」など、各相続人の思惑が一致しないことも珍しくありません。そうした場合は、感情論に走らず、冷静な視点で財産の評価と活用法を検討することが大切です。専門家(司法書士、税理士、不動産会社)を交えた第三者の立場からアドバイスを受けることで、公平で納得感のある解決が可能になります。
また、話し合いがどうしてもまとまらない場合には、「共有物分割請求訴訟」という法的手段に頼ることもできますが、時間も費用もかかるため、できるだけ協議段階での合意を目指すことが現実的です。感情的な争いに発展する前に、第三者による不動産査定などを利用して「見える化」することも有効です。
兄弟間の信頼関係を損なわずに売却を成功させるには、お互いの立場や状況を理解し合いながら、法的根拠に基づいた協議を進めることが不可欠です。相続不動産の売却は、単なる資産処分ではなく、家族のこれからの関係性にも関わる大切な節目なのです。
不動産会社に相談するタイミングと選び方

相続した不動産を「売却しよう」と決めたとき、次に重要となるのが「どのタイミングで、どの不動産会社に相談するか」という点です。相続登記や遺産分割協議といった法的手続きも大切ですが、実際の売却活動をスムーズに進めるには、信頼できる不動産会社との連携が不可欠です。タイミングと選び方を誤ると、売却が長引いたり、思うような価格で売れない可能性もあります。
まず相談のタイミングですが、相続登記が完了していなくても相談自体は可能です。むしろ、早い段階で査定を依頼し、どれくらいで売れそうか目安を把握しておくことで、相続人間の協議や資金計画にも役立ちます。特に、相続から3年以内に売却すれば適用できる「3,000万円特別控除」など、期限付きの税優遇制度を逃さないためにも、早期相談は大きなメリットです。
不動産会社の選び方としては、「地域に強い会社」と「実績のある大手」のどちらが自分に合っているかを見極めることがカギとなります。たとえば、地方の空き家などは地域密着型の業者の方が地元の買主を持っているケースも多く、地価や需要に詳しい担当者の存在が強みになります。一方で、都市部や高額物件であれば、広告展開やネット集客に強い大手仲介会社が有利になることもあります。
また、複数の不動産会社に査定を依頼して比較することも非常に重要です。一括査定サイトを活用すれば、複数社から同時に価格の提案を受けられるため、相場観の把握や担当者の対応力を見比べることができます。ただし、高額な査定額だけを基準にせず、説明の根拠があるか、売却プランが現実的か、信頼できる対応かといった視点でも見極めましょう。
さらに、相続に関する専門知識を持つ不動産会社を選ぶことも、スムーズな売却には欠かせません。相続登記や税務処理に慣れている会社であれば、司法書士や税理士との連携もスムーズで、「売却+法的整理」をワンストップで対応してもらえるケースもあります。相談時には、過去の相続不動産売却実績を確認するのも有効です。
このように、相続不動産の売却は「誰と組むか」で結果が大きく変わります。焦って選ぶのではなく、複数社の対応を比較した上で、自分の事情や不動産の特徴に合ったパートナーを選ぶことが、納得のいく売却への近道です。
まとめ|相続不動産を売却するなら「早めに動く」が鉄則

相続で不動産を受け継ぐというのは、人生の中でもそう多くはない重要な局面です。大切な家族の思い出が詰まった家だからこそ、「そのまま残しておくか」「売却して資産に変えるか」という判断には、悩みや葛藤がつきものです。しかし、空き家を放置してしまうことで税金や維持費が膨らんだり、トラブルが発生したりするケースも決して少なくありません。
ここまでご紹介してきたように、相続不動産の売却には、相続登記や名義変更といった法的な手続きをはじめ、共有者との合意形成・税金対策・不動産会社選びなど、さまざまな検討事項があります。それだけに、「何から始めたらいいかわからない」と不安を抱えたまま、手つかずで放置してしまうことが最大のリスクとなるのです。
特に、2024年の相続登記義務化によって、3年以内の登記申請が求められるようになった今、「いつかやる」ではなく「今すぐ動く」ことが重要になっています。早めに準備を始めることで、売却までのプロセスを計画的に進められ、税制優遇(3,000万円特別控除など)を逃さず活用することも可能になります。
また、信頼できる不動産会社に早めに相談することで、必要な書類の準備や相場の把握、売却時期の見極めなど、専門的な視点からアドバイスを受けられます。一人で悩み続けるよりも、まずは相談することが、結果としてもっともスムーズな解決策となることが多いのです。
相続不動産の売却は、「資産をどう活かすか」というライフプランにも深く関わります。ご自身やご家族の未来にとって最適な選択をするためにも、正しい情報を得て、専門家と一緒に一歩踏み出すことをおすすめします。
今このページを読んでくださっているあなたには、すでに「考える準備」が整っています。まずは無料の一括査定や初回相談など、できるところから始めてみてはいかがでしょうか?将来の不安を「今」取り除くための行動が、きっと大きな安心につながります。
- 離婚で不動産を売る|住宅ローン・名義・財産分与の不動産売却ガイド
- 放置している空き家、ずっとこのままで大丈夫?──管理できない不安に今こそ向き合う
- 住宅ローンが払えない…家を売るしかない?滞納リスクと解決策を徹底解説
- 住み替え・買い替えで家を売るときの完全ガイド|後悔しない売却タイミングと手続きのポイント
- リバースモーゲージとは?リースバックとの違いとおすすめの選び方を解説
- リースバックとは?仕組み・メリット・注意点を徹底解説|住み慣れた家を手放さずに資金確保
- 土地を活用するよりも売却したほうが良いケースとは?
全国の相続や離婚で家やマンションや土地を納得価格で売却できる不動産屋探し
▼地域ごとの家やマンションや土地を納得価格で売却できる不動産屋の情報はこちらから