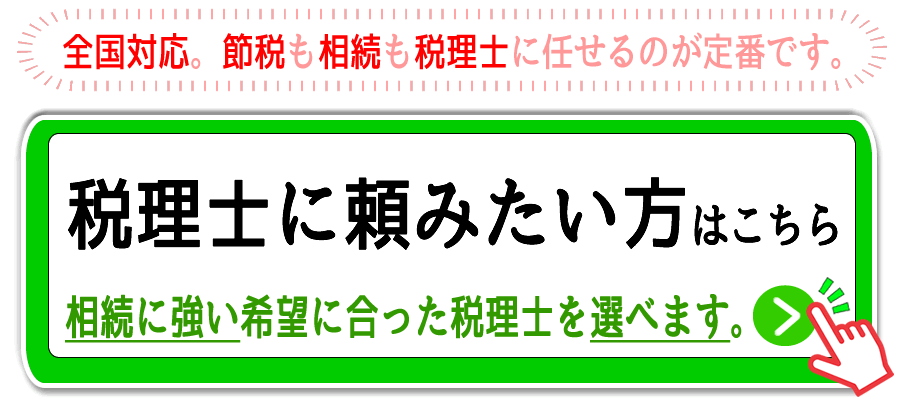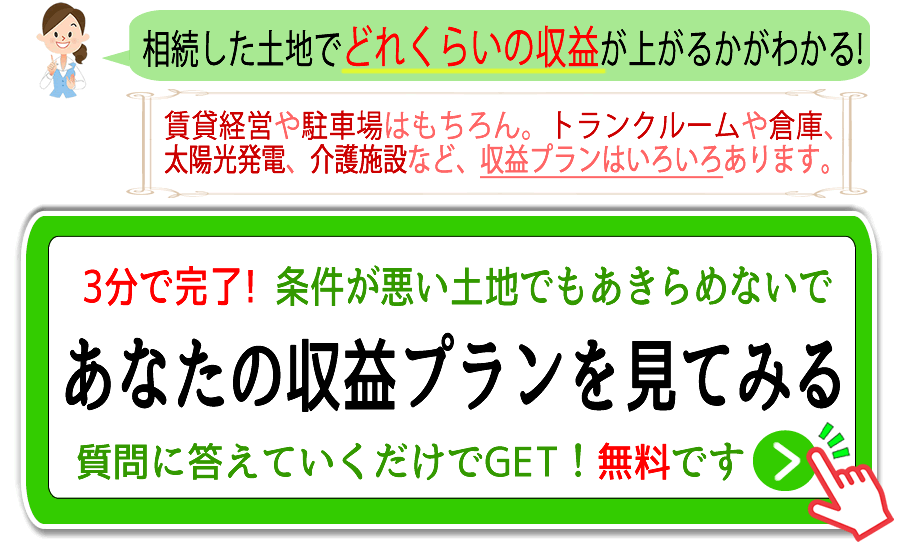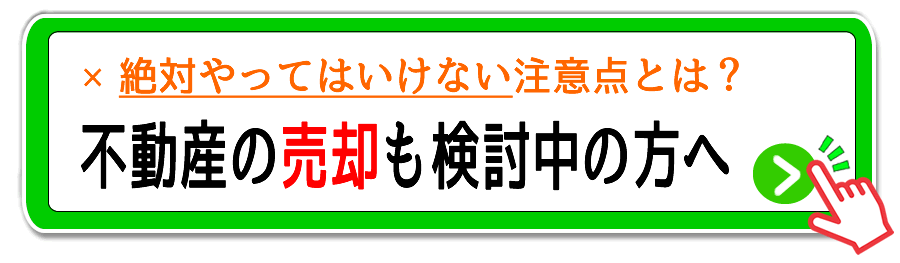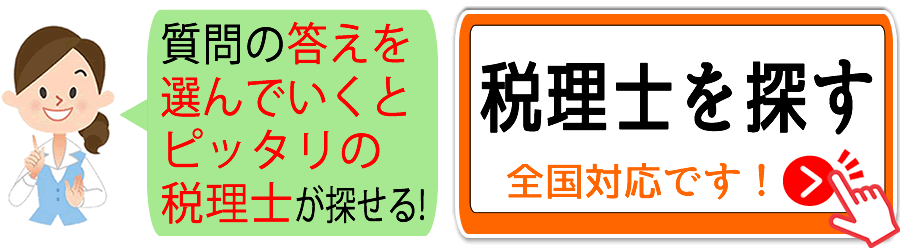PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説

- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
相続で「弁護士か税理士か」で迷うのはなぜ?

相続は法律と税金の交差点にある
誰かが亡くなったあとに訪れる「相続」は、単なる遺産の受け渡しではありません。
財産の分配、相続人間の調整、相続税の申告や納付など、さまざまな手続きが複雑に絡み合うため、専門家の力を借りる場面が少なくありません。
このとき、多くの方が最初に感じる疑問が「弁護士に相談すべきか?税理士で大丈夫なのか?」というものです。
特に、相続は一生のうちに何度も経験するものではなく、ほとんどの方にとって初めての出来事。
誰に、どのタイミングで相談すべきかがわからず、迷ってしまうのも当然です。
「弁護士に相談すべき?」と思う場面とは
たとえば、遺産の分け方でもめている、誰かが遺留分を主張している、あるいは遺言書の内容に異論が出ている――そんなときには、「弁護士が必要なのでは?」と考える方が多いでしょう。
弁護士には「代理権」があり、調停や訴訟の場で当事者の代わりに主張・交渉ができる強力な立場です。
「税理士に依頼すべき?」と思う場面とは
一方で、「相続税がかかりそうだ」「不動産の評価や税金の計算が不安」「税務署から指摘されないようにしたい」といった税務面の不安がある場合は、「税理士に相談しよう」という判断になります。
申告期限もあるため、実務的な対応が求められるのです。
弁護士と税理士、それぞれの役割と専門分野

弁護士の主な役割は「争いごとの代理と調整」
弁護士は、法律に関する幅広い知識を持ち、相続人同士のトラブルや感情的な対立など、「争いごと」への対応を主な役割とします。
たとえば、
- 遺言書の内容に疑問がある
- 相続人の一部が連絡に応じない
- 相続分に納得せず、交渉がこじれている
といったケースでは、弁護士が代理人となって調停や裁判に出席し、法的に問題を解決していきます。
感情のもつれを調整する立場でもあり、争族(争う相続)を避けるうえで重要な存在です。
税理士の主な役割は「相続税の計算と申告」
税理士は、税金の専門家として、相続税や贈与税の申告・節税・資産評価などを担当します。
法律上の代理行為や紛争の解決は行えませんが、金銭的な影響が大きい「税務面」の手続きを正確かつ合法的に進める力があります。
特に相続税申告は、被相続人の財産内容(不動産・預貯金・株式・事業資産など)によって大きく変わります。
評価の仕方ひとつで税額が何百万円も変わることもあり、専門知識と経験が求められます。
どちらも国家資格だが、活動領域は異なる
弁護士も税理士も国家資格ですが、扱える業務内容と対応範囲には明確な違いがあります。
たとえば、弁護士は税務申告を行いませんし、税理士は調停や裁判に立ち会えません。
- 弁護士:調停・訴訟・代理交渉・遺産分割協議の代理
- 税理士:相続税の試算・税務調査対応・節税提案・申告書の作成
と、それぞれ専門分野がはっきりしているため、相続の内容に応じて誰に依頼すべきかを見極めることが大切です。
税理士の役割は「生前対策〜申告・二次相続の見通し」まで広がるが、訴訟・調停には対応不可
相続に関する税理士のサポート範囲は、被相続人の生前から始まっています。
- 生前贈与や不動産活用による相続税対策
- 家族信託の税務判断
- 相続開始後の財産評価・申告
- 配偶者や子への二次相続のシミュレーション
このように税理士は、相続の全体像を見据えた中長期的な視点でサポートできます。
ただし、相続人間でトラブルが生じた場合の仲裁や代理交渉はできないため、その際は弁護士の力が必要になります。
弁護士が必要になる相続のケース

相続人同士で揉めている・争いが起きそう
相続の現場では、「話し合いでは解決できない」状態になることも少なくありません。
たとえば、兄弟姉妹で相続割合をめぐって対立している、長男だけが財産を多く相続しようとしている、などのケースです。
こうしたトラブルが顕在化している場合は、弁護士に依頼して第三者を介入させることが、状況を悪化させないためにも有効です。
法的な観点から適切な分配方法や対話の場を整える役割を担います。
遺言書の有効性が争われている
「父が晩年に書いた遺言書は有効なのか?」「内容が偏っていて納得できない」など、遺言書に対して疑念や反発がある場合も、弁護士の出番です。
特に、
- 公正証書ではなく自筆の遺言書
- 認知症の可能性がある時期の作成
- 特定の相続人だけに偏った内容
といった状況では、遺言無効確認訴訟などの法的手続きが視野に入ります。
これは税理士では扱えない領域です。
遺留分侵害の主張が出ている
遺言書がある場合でも、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分があります。
この権利を侵害された相続人が主張を始めた場合には、法的な交渉や請求が必要となるため、弁護士が代理人として立ち会う必要があります。
特に遺留分の請求は期限(1年以内)があるため、迅速な対応が求められる分野でもあります。
調停・訴訟への発展が視野にある
「話し合いが完全に決裂している」「裁判所の力を借りるしかない」といった状況になれば、家庭裁判所での調停や審判・訴訟が必要になります。
この段階で頼れるのは弁護士だけです。
税理士は調停や訴訟の代理を行うことができないため、法廷に立つ必要が出てきた時点で、弁護士への依頼が不可欠です。
「感情のもつれ」の仲裁が必要なケースも
相続は「感情の問題」が複雑に絡む場面でもあります。
「昔の恨み」「介護の負担の差」「疎遠だった兄弟への不信感」など、法的根拠だけでは整理できない葛藤が積み重なっていることも少なくありません。
このような場合でも、弁護士は法律家として冷静に、かつ第三者の視点で介入することで、話し合いを前進させる役割を果たします。
税理士のみで対応可能な相続とは

相続人間で話し合いがまとまっている
反対に、相続人全員の意思が揃っていて、分割内容に合意がある場合は、弁護士の出番は基本的にありません。
このような円満相続のケースでは、税理士だけで手続きを進めることが可能です。
特に遺言書があり、その内容に従って全員が納得している場合には、トラブルもなくスムーズに進みます。
相続税の申告が必要なケース
相続財産が一定額(基礎控除額)を超える場合、相続税の申告が必要になります。
これは税務署への申告であり、専門的な計算・評価・書類作成が必要な領域です。
ここで活躍するのが税理士です。
申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」と定められており、期限内に正確に対応できるかが極めて重要になります。
遺産の内容や分割方法に明確な合意がある
現金・預貯金・不動産などの遺産について、「これは兄に、不動産は妹に」といった形で話し合いが円満にまとまっている場合、税理士のサポートだけで問題なく進められます。
ただし、不動産評価や譲渡リスク、二次相続などの視点は重要なため、税理士による戦略的な助言は不可欠です。
不動産や預貯金の評価・申告・節税対策がメイン
相続財産には土地・建物・預貯金・株式などが含まれますが、特に不動産が絡む場合は評価額によって税額が大きく変わります。
税理士はこのような資産の評価を、
- 路線価評価
- 小規模宅地等の特例
- 相続時精算課税制度の適用判断
など、豊富な知識と経験に基づいて節税効果を最大化する提案を行えます。
税理士だけに依頼しても問題ないケースと注意点

争いがなければ弁護士なしで進められる
相続人間の信頼関係があり、遺産分割について合意が得られているのであれば、税理士だけで十分なケースは数多くあります。
実際、遺産が数千万円〜1億円規模の家庭でも、トラブルがなければ税理士のみで完結することは珍しくありません。
税務署対応や相続税対策も税理士が中心
税務署から問い合わせがあった場合の対応や、申告書類の整備、納税資金の準備支援、土地活用による節税提案など、税理士は相続税務のプロフェッショナルとして心強い存在です。
ただし、途中で「争い」が生じたら弁護士との連携が必要
最初は円満に進んでいた相続でも、途中で意見の対立が起きたり、相続人の一人が反発を始めることもあります。
こうした「相続トラブルの兆し」が見えた段階で、速やかに弁護士へ相談することが重要です。
税理士と弁護士が連携して対応することで、税務面と法律面の両方を漏れなくカバーすることができます。
弁護士と税理士、両方に依頼すべきケースとは?

相続税申告+遺産分割協議でトラブルがある場合
相続税の申告が必要な一方で、遺産分割について意見が対立している、あるいはすでに揉め始めている場合には、税理士と弁護士の両方に依頼するのが最善です。
税務と法律の両面から対応することで、
- 適正な財産評価・申告
- 納税計画と資金確保
- 遺留分や不公平な分配に対する法的対処
といった複雑な相続問題を総合的に整理することが可能になります。
「税務」と「法律」が複雑に絡み合っている相続
たとえば、以下のようなケースは「税と法」の両側面が交差するため、両方の専門家が必要です。
- 財産に未登記の不動産や借地権が含まれている
- 名義変更に法的トラブルがある
- 節税対策に遺産分割の工夫が必要
- 海外資産が含まれる
このような場合、税理士だけでは対処できない部分があり、弁護士との協業が円滑な相続の鍵になります。
複数の専門家が連携して対応すればリスクも最小限に
相続は「法律・税務・登記・感情」が複雑に絡むテーマです。
だからこそ、一人の専門家にすべてを委ねるのではなく、役割ごとに適切な専門家に任せるという意識が重要です。
特に相続税の申告期限(10ヶ月)が迫っている中でトラブルが発生すると、申告と争いの両方を同時に進行する必要が生じます。
こうした事態に備えて、早い段階で弁護士と税理士の両方にアプローチしておくと、後の混乱を防げます。
ワンストップ対応可能な事務所もある
近年では、弁護士と税理士が連携している事務所や、グループ内で両方の資格者が在籍している専門家チームも増えています。
こうした事務所では、相続全体を一つの窓口で相談できるため、手続きの負担も軽減され、時間的ロスも少なく済みます。
相続の依頼先を決める際の判断ポイント

「争いがあるか」「税申告が必要か」で判断する
最初に考えるべきは、
- 相続人同士でもめそうか?
- 相続税の申告が必要か?
という2点です。
争いがあれば弁護士、税金の処理があれば税理士というように、目的に応じて適切な専門家を選ぶことで、時間も費用も無駄になりません。
費用感で選ばないほうがいい理由
「弁護士は高い」「税理士のほうが安そう」といった理由で依頼先を選ぶと、本来の目的が達成できずに結局やり直しになることもあります。
たとえば、争いがあるのに税理士にだけ依頼してしまうと、話し合いが進まず、結局弁護士にも追加で依頼することになり、かえって費用も時間もかかってしまいます。
最初に相談すべきは税理士?弁護士?
争いがなければ、税理士に最初に相談するのが一般的です。
税理士は相続全体の流れに精通しており、「今は争いがないが、将来的に起こりそうかどうか」まで含めて判断できます。
もし税理士が「このケースは弁護士に相談したほうがよい」と感じれば、信頼できる弁護士を紹介してもらえる場合も多いため、まずは税理士を起点に考えるのもひとつの手です。
迷ったら「相続税の有無」から考える
相続税の基礎控除(「3000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える財産があるかどうかは、税理士に相談すべきかどうかの大きな判断基準になります。
控除以下なら税申告の義務はありませんが、評価や特例の活用で課税対象から外せることもあり、判断を税理士に仰ぐメリットは大きいといえます。
まとめ|相続で迷ったらどちらに相談すべきか

争いがなければ税理士からスタートが基本
遺産の分割に対立がなく、申告や手続きに不安がある場合には、税理士のサポートだけで十分です。
財産評価・申告・節税アドバイスまで一貫して任せられるため、スムーズに相続を完了できます。
争いの火種があるなら弁護士の関与を視野に
一方、相続人同士の関係がぎくしゃくしていたり、「納得できない」という声が出ている場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
感情的な対立が深まる前に法的な整理をしておくことで、トラブルの拡大を防げます。
税理士と弁護士、それぞれの専門性を正しく使い分ける
相続の専門家を選ぶ際は、誰かひとりに丸投げするのではなく、必要に応じて役割を分担することが理想です。
税金は税理士、法律は弁護士、登記は司法書士といった具合に、プロフェッショナルを正しく活用することが、円満な相続への近道です。
よくある質問(FAQ)
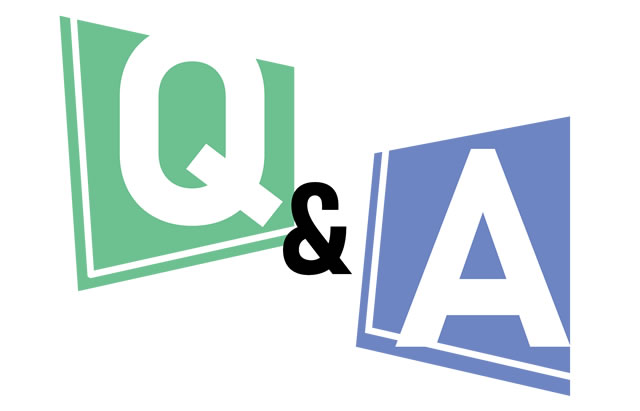
Q. 相続は税理士だけで対応できますか?
A. 相続人同士で争いがなければ、税理士だけで対応可能なケースが多くあります。
相続税の申告や財産評価、節税のアドバイスなど、税務面の手続きは税理士が担います。
ただし、相続人間でトラブルが起きた場合には、弁護士への依頼が必要になります。
Q. 相続で弁護士に相談すべきか迷っています
A. 相続人間の話し合いが難航している、あるいは感情的な対立がある場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
法的な代理交渉や調停、遺留分請求などは税理士では対応できないため、トラブルを避けるためにも弁護士の力が必要です。
Q. 弁護士と税理士の両方に依頼すると費用が高くなりませんか?
A. 確かに両方に依頼することで費用はかかりますが、役割が明確に分かれており、結果として手続きがスムーズに進みやすくなります。
ワンストップ対応の事務所もあり、費用面の調整がしやすいケースもあります。
Q. まずは税理士に相談してもいいのでしょうか?
A. 争いがなければ、まず税理士に相談するのが一般的です。
税理士は相続の全体像を把握し、必要に応じて弁護士への橋渡しをしてくれる場合もあります。
相続税が発生するかどうかの確認にも有効です。
Q. 税理士がいれば調停や訴訟も一緒に対応してくれますか?
A. 税理士は調停や訴訟などの法的手続きには関与できません。
争いが法的手段に発展する可能性がある場合は、必ず弁護士への依頼が必要になります。
早めに専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。
- 相続した不動産がいくらで売れるか無料で査定できます
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
全国の相続の手続き完全ガイド|まず何をすればいい?期限・流れ・必要書類を徹底解説
▼地域ごとの相続の手続きの情報はこちらから