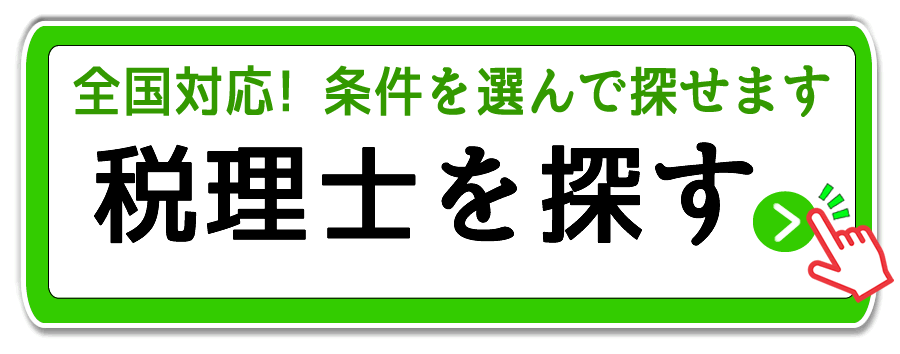大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント

- なぜ大家さんに税理士が必要なのか?
- 賃貸経営に関わる税金の種類と注意点
- 税理士ができる大家さん向けの節税対策
- 青色申告は大家さんにも有効か?
- 賃貸経営に強い税理士を選ぶポイント
- こんなときは相談を!大家さんの税務相談事例
- 税理士費用はどれくらい?賃貸経営ならではの契約形態
- まとめ|税理士をパートナーにして賃貸経営を安定化しよう
- よくあるQ&A(FAQ)
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
なぜ大家さんに税理士が必要なのか?

「税理士」と聞くと、法人や個人事業主のための存在という印象を持つ方も多いかもしれません。
しかし、賃貸経営を行う「大家さん」にとっても、税理士は重要なパートナーとなり得ます。
まず、賃貸経営による収入は「不動産所得」として申告されますが、一定の規模を超えると「事業的規模」と見なされ、必要な帳簿や申告手続きが一段と複雑化します。
物件の棟数や部屋数、収支の規模が大きくなるほど、減価償却や按分計算、税務調整といった専門的処理が必要となり、自力での対応には限界があります。
また、賃貸経営に特有の税務処理には、以下のような難しさがあります。
- 建物・設備・附帯工事の減価償却資産の区分と耐用年数の判断
- 家賃滞納や修繕費の税務上の処理方法
- 共用部と専有部における水道光熱費の按分計算
- 親族間での名義や収益分配の複雑性
これらの要素を踏まえると、賃貸物件を保有・運営することは、もはや「不動産投資ビジネス」に近い性質を持つといえるでしょう。
さらに、物件を相続したケースや複数物件を所有している場合、税務申告だけでなく相続対策・資産管理の観点でも税理士の存在が不可欠となります。
賃貸経営に関わる税金の種類と注意点

大家さんとして賃貸経営を行う際には、複数の税金が関係してきます。
以下では、賃貸経営で特に注意すべき税目とその特徴について解説します。
所得税・住民税
賃貸経営による家賃収入は、経費を差し引いた「不動産所得」として課税対象になります。
経費には、管理費・修繕費・固定資産税・減価償却費・火災保険料などが含まれます。
注意すべきは、「現金収入と実際の課税所得は必ずしも一致しない」という点です。
たとえば減価償却費は現金支出を伴いませんが、経費として控除できます。
また、所得税は累進課税であるため、収入が高くなるほど税率も高くなります。
特に本業の給与所得がある方は、家賃収入の合算により税率が大幅に上がるケースもあります。
固定資産税・都市計画税
不動産を所有している限り、毎年必ず課税されるのが固定資産税と都市計画税です。
これは収入の有無に関係なく発生します。
- 固定資産税評価額に応じて決定
- 土地と建物それぞれに課税される
- 都市計画区域内では都市計画税も併せて課税される
支払いは年4回に分割されることが多く、資金繰りの計画が立てづらいと感じる大家さんも少なくありません。
消費税が発生する特殊ケース
原則として、住宅の賃貸収入には消費税はかかりません(非課税取引)。
しかし、以下のような例外があります。
- 駐車場だけを貸している場合(課税対象)
- 貸会議室や店舗用スペースの賃貸(課税対象)
- 住宅付き事務所など、事業用途の割合が高い場合(一部課税)
これらの場合、消費税の申告義務や、課税事業者になる選択を迫られることがあります。
場合によっては消費税の納税義務が数百万円に達するケースもあるため、初期段階から税理士に相談するべきです。
税理士ができる大家さん向けの節税対策

税理士が大家さんに提供できるサポートの中でも、特に重要なのが「節税」です。
ただし、闇雲に経費を増やせば良いというわけではありません。
税法上、正しく処理しなければ節税どころか追徴課税のリスクにもつながります。
減価償却資産の管理と節税インパクト
建物本体・給排水設備・エアコン・外構工事など、賃貸経営では多くの支出が「減価償却資産」に該当します。
これらは購入費を一括で経費にできず、耐用年数に応じて分割して経費化する必要があります。
税理士に依頼することで、
- どの支出が減価償却資産に該当するのか
- 耐用年数や償却方法の適切な選定
- 物件売却時の帳簿残高調整
など、長期的なキャッシュフローと税額のバランスを取る支援が得られます。
修繕費 vs 資本的支出の仕訳判断
建物に手を加えたとき、その費用が「修繕費(経費)」として即時損金処理できるか、「資本的支出(資産計上)」として減価償却するかで、税負担は大きく異なります。
例えば…
- 屋根の塗装 → 修繕費になりやすい
- 屋根の葺き替え(全面改修) → 資本的支出に分類される可能性大
この判断は専門的でグレーゾーンも多く、税理士の見解が重要な防波堤になります。
空室リスクや未収家賃と損金処理
空室期間中の経費や、未回収家賃の処理についても判断が分かれます。
税務署に否認されると、過年度の修正申告・追徴課税のリスクが発生します。
税理士は、
- 空室時でも必要経費になる支出の範囲
- 貸倒損失の要件と時期の見極め
- 保証会社利用時の処理
など、正しい会計処理と証拠資料の整備をサポートしてくれます。
建物や設備の取り壊し・売却時の対応
老朽化による取り壊しや、資産入れ替え時の売却には特有の税務処理が必要です。
- 固定資産除却損
- 売却損益と譲渡所得
- 繰延資産や未償却残高の扱い
これらは複雑で、誤処理すれば後から大きな損失につながるため、事前に税理士の意見を仰ぐことが必須です。
青色申告は大家さんにも有効か?

青色申告は事業所得を対象とする制度ですが、一定の要件を満たした「不動産所得」でも適用可能です。
賃貸経営においても、節税面・経営管理面で大きなメリットがある制度です。
事業的規模(5棟10室基準)の判断とは
青色申告の最大の恩恵である「65万円の特別控除」を受けるには、賃貸経営が「事業的規模」と認定される必要があります。
判断の基準として代表的なのが「5棟10室基準」です。
- 一戸建ての貸付が5棟以上
- アパートやマンションの貸付が10室以上
いずれかを満たすと「事業的規模」と判断される可能性が高くなり、帳簿付けや確定申告の手間は増えるものの、大幅な節税が可能になります。
65万円控除と帳簿作成の義務
「事業的規模」と認定された場合、複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が義務付けられます。
記帳には会計ソフトを使う方法もありますが、実際には以下のような壁が生じやすいのが現実です。
- 減価償却の計算方法が分からない
- 修繕費と資本的支出の区分が曖昧
- 家賃滞納や敷金精算の扱いが複雑
このような実務上の課題をカバーする意味でも、税理士のサポートを受けて申告体制を整えることが合理的です。
賃貸経営に強い税理士を選ぶポイント

すべての税理士が不動産に詳しいわけではありません。
賃貸経営に強い税理士を選ぶことが、経営効率・節税・リスク対策すべてにおいて重要です。
不動産所得に特化した経験があるか
まず確認すべきは、実際に不動産オーナーの顧客を多数抱えているかどうかです。
不動産所得には以下のような業種特有の処理が多いため、経験の蓄積が欠かせません。
- 減価償却と建物・設備の区分
- 修繕費の取り扱い
- 名義が異なる場合の按分と申告方法
ヒアリング時には、過去の不動産案件の事例や解決方法などを具体的に聞いてみるとよいでしょう。
修繕費・減価償却・共有名義の実務に強いか
特に「法的な所有者と実質的な管理者が異なるケース」では、税務処理の判断に高度な知見が求められます。
たとえば、親が所有し子が運用しているケースなどは、誤った処理をすると贈与税のリスクも発生します。
これらに対し、「実務ベースでの着地点」を見極められる税理士かどうかが選定のカギとなります。
税務調査対応の実績やアドバイス力
大家業も、家賃収入が安定しているほど税務調査の対象となる可能性が高まります。
調査対応に慣れている税理士であれば、普段から指摘されにくい申告体制を整えてくれるという安心感があります。
こんなときは相談を!大家さんの税務相談事例

税理士への相談は「確定申告直前だけ」という印象を持つ方も多いですが、実は“事前に相談することで防げるトラブル”が多いのが賃貸経営の特徴です。
相続で引き継いだ賃貸物件の初年度申告
相続した物件の家賃収入や減価償却の扱い、名義の変更と申告タイミングには注意が必要です。
登記と実態のズレがある場合、税務署の指摘を受ける可能性があります。
建替え・解体による除却損の計上
古くなった物件を取り壊した際、建物の未償却残高を「除却損」として損金処理することができます。
ただし、「実際の取り壊し時期」や「用途変更の有無」によって判断が分かれるため、税理士の判断が必要不可欠です。
サブリース契約の収支処理
サブリース契約では、オーナーが受け取るのは家賃ではなく“転貸料”です。
そのため、経費の計上方法や損益通算の可否など、特有の論点があります。
税理士費用はどれくらい?賃貸経営ならではの契約形態

税理士報酬は案件の内容や依頼範囲によって異なりますが、賃貸経営者の場合は「スポット契約」が基本となるケースが多いです。
確定申告のみのスポット契約
- 報酬相場:5万円〜15万円前後/年
- 業務内容:帳簿確認、減価償却計算、申告書作成など
- 年1回のやり取りのみで済むため、費用は抑えやすい
物件数が増えると顧問契約が必要になることも
- 複数物件、法人所有、複雑な相続案件などの場合は、月額顧問契約(1〜3万円程度)が必要になることも
- 税理士が定期的に帳簿を確認し、年度途中でも相談できるメリットあり
費用よりも「リスク回避効果」に注目
「安いからお願いする」よりも、不適切な申告をしてしまった際の追徴リスクや将来の損失の方がよほど大きなコストになり得ます。
単なる“節税屋”ではなく、経営リスクを抑える視点を持つ税理士を選ぶことが大切です。
まとめ|税理士をパートナーにして賃貸経営を安定化しよう

賃貸経営は、単なる副業や資産運用を超えた“中小ビジネス”の一形態です。
収入が安定する一方で、税務上のリスクや手続きの複雑さも伴います。
税理士を上手に活用することで、
- 節税効果を最大化しながら
- 税務調査リスクを最小限に抑え
- 将来の相続や事業承継にも備える
といった、長期的な視点での経営が可能になります。
信頼できる税理士を見つけ、パートナーとしての関係性を築くことで、あなたの賃貸経営はより盤石なものとなるでしょう。
よくあるQ&A(FAQ)
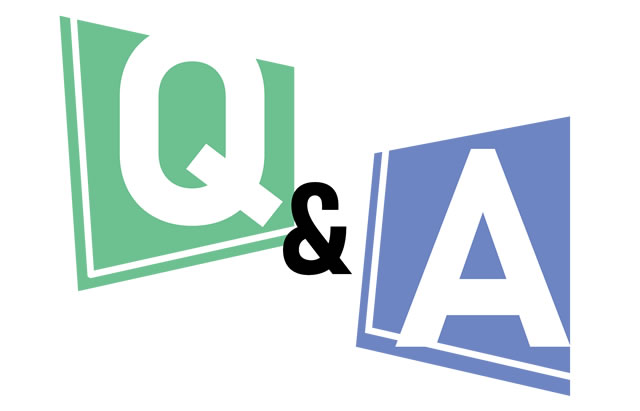
Q. 賃貸経営で消費税は関係ありますか?
A. 住宅の家賃収入は非課税ですが、駐車場や貸店舗などは課税対象になることがあります。
課税売上が一定額を超えると消費税の申告義務が発生するため、契約内容と収入形態に応じて注意が必要です。
Q. 家族に給与を出すことで節税できますか?
A. 家族への給与は、青色申告で事業的規模が認められた場合に限り、適切に届出をすれば経費として認められます。
金額や業務内容について税務署からの指摘を受けないよう、税理士と相談して調整することが重要です。
Q. 修繕費と資本的支出の違いを教えてください
A. 修繕費は現状回復のための支出で、全額をその年の経費にできます。
一方、資本的支出は建物の価値を高めたり、耐用年数を延ばす工事などで、減価償却によって複数年にわたって経費計上します。
税務上の判断が分かれるケースも多いため、専門家の判断が重要です。
Q. 確定申告は毎年税理士に依頼すべきですか?
A. 物件数が少なく収支が単純な場合は自身で申告することも可能ですが、減価償却・修繕費の処理・青色申告の適用など複雑な処理が増えると税理士のサポートが有効です。
ミスによる追徴を防ぐためにも、税理士に任せる大家さんは増えています。
Q. 相続した賃貸物件の減価償却はどうなりますか?
A. 相続した物件は、相続時の評価額や用途によって減価償却の計算が変わります。
また、過去の修繕履歴や相続前の帳簿が引き継げないケースもあり、税務処理には慎重な判断が必要です。
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
全国の税理士を探す
▼地域ごとの税理士の情報はこちらから