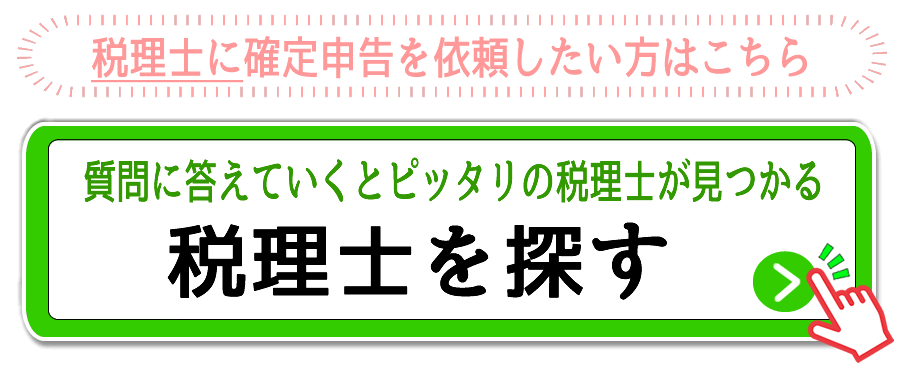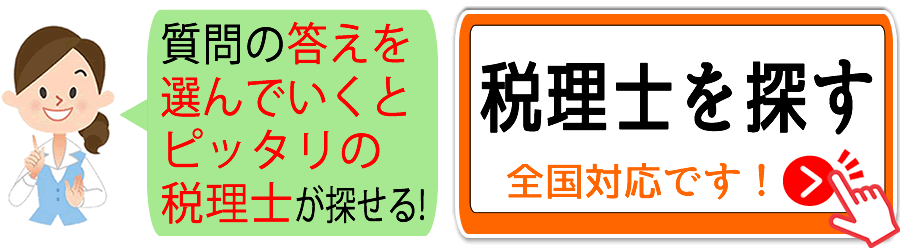PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説

- 年金受給者でも確定申告が必要になることがある
- 【ケース別】年金受給者で確定申告が必要になる主なパターン
- 年金受給者のための申告不要制度とその注意点
- 年金受給者が申告を忘れるとどうなる?
- 年金受給者の確定申告でよくある質問と誤解
- 年金受給者が確定申告の前に準備しておくべきもの
- まとめ|年金生活者も申告が必要になる可能性を忘れずに
- よくある質問(FAQ)
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
年金受給者でも確定申告が必要になることがある

「年金だけで生活しているから確定申告は必要ない」と思っている方も少なくありません。
しかし、年金受給者であっても、一定の条件に該当する場合は確定申告が必要になります。
特に、複数の年金を受け取っていたり、年金以外にも収入がある場合などは、申告が必要になる可能性が高く、無申告でいるとペナルティの対象になることもあります。
確定申告が「不要になる」条件とその誤解
年金受給者の中には、「確定申告不要制度」という仕組みに該当する方もいます。
この制度により、年金の収入のみで条件を満たしていれば確定申告をしなくてもよいとされています。
しかしこの制度は、あくまで「一定の条件下に限って申告が不要になる」ものであり、すべての年金受給者に当てはまるわけではありません。
誤解して申告しなかった場合、後から延滞税や加算税が発生するリスクもあるため、注意が必要です。
公的年金等控除と確定申告の関係
年金収入には「公的年金等控除」という制度があり、一定額までは所得として課税されない仕組みになっています。
たとえば65歳以上であれば、年金収入が年間約158万円以下であれば課税対象にならないため、申告は不要とされることもあります。
ただし、この「約158万円」という金額はあくまで基準の一例であり、他の所得の有無や年齢、扶養控除の有無などによって判定が変わるため、自分が対象になるかどうかは毎年確認する必要があります。
所得税と住民税の申告要否の違い
意外と見落とされやすいのが、所得税と住民税で確定申告の必要性が異なる点です。
たとえば所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が必要になるケースもあります。
これは、自治体が住民税の課税計算に必要な情報を把握するために、申告不要制度に該当していても申告書の提出を求める場合があるためです。
高齢者の医療費負担や介護保険料にも影響することがあるため、軽視できません。
【ケース別】年金受給者で確定申告が必要になる主なパターン

では、具体的にどのようなケースで年金受給者が確定申告をしなければならないのでしょうか。
ここでは代表的な5つのケースをご紹介します。
1. 公的年金が年間400万円を超える場合
まず明確な基準のひとつとして、公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要になります。
この金額には、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金がすべて含まれます。
高収入の年金受給者や企業で長く勤務していた方は該当するケースも多いため、自分の受給額をしっかり確認しておきましょう。
2. 複数の年金を受け取っている場合(例:厚生年金+企業年金)
公的年金と企業年金(私的年金)を同時に受給している場合も、確定申告が必要になる可能性があります。
企業年金や退職年金は「雑所得」に分類され、公的年金控除の対象にはなりません。
そのため、申告不要制度の対象外になることが多く、合算した金額が一定額を超える場合には申告義務が生じます。
3. 年金以外に収入がある場合(パート・不動産所得・利子など)
たとえ年金だけなら申告不要であっても、年金以外の収入がある場合は話が変わります。
- パート収入や内職収入
- 不動産収入(賃貸など)
- 配当・利子収入
- 雑所得(原稿料・講演料など)
これらの収入が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
申告しないと、税務署からの指摘を受けて追徴課税の対象となる可能性もあります。
4. 医療費控除や寄附金控除などで還付を受けたい場合
医療費が高額になった年や、ふるさと納税をした年には、確定申告をすることで税金の還付が受けられる可能性があります。
これは「申告しなければ戻ってこないお金」でもあるため、義務ではなくても「申告すべき」状況といえるでしょう。
年金生活者でも、控除を活用すれば節税や還付につながることを知っておくことが重要です。
5. 源泉徴収漏れ・年末調整未実施など特別な事情がある場合
年金からは通常、源泉徴収が行われていますが、何らかの手続き漏れやミスによって、正しく源泉徴収されていない場合もあります。
また、途中から年金を受け取り始めた場合や、勤務先からの給与と年金が重なっている年などは、年末調整がうまく反映されないことも。
そのようなときは、正しい税額を申告・納付するために確定申告が必要です。
年金受給者のための申告不要制度とその注意点

年金生活者の負担を軽減する目的で設けられているのが、「確定申告不要制度」です。
これは、一定の条件を満たしている年金受給者に対して、所得税の確定申告を不要とする仕組みです。
ただしこの制度は万能ではなく、条件から外れれば当然ながら申告義務が発生します。
誤解や思い込みで無申告状態になると、あとから大きな負担となりかねません。
申告不要制度の対象になる人とは?
制度の対象となるのは、以下のような条件をすべて満たす年金受給者です:
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- その他の所得が20万円以下
- 年金を支払う側(日本年金機構など)から源泉徴収票が発行されている
この条件を満たすと、税務署への申告は原則不要となります。
源泉徴収票を確認するだけで安心してはいけない理由
「源泉徴収票があるから確定申告は必要ない」と思ってしまうのは早計です。
源泉徴収票は年金額や控除内容などを記載した資料であり、申告不要を証明するものではありません。
実際には、年金以外の収入や控除の有無、扶養状況などによって確定申告の要否が変わるため、必ず確認が必要です。
「申告しないと損する」こともあるケース
年金受給者であっても、確定申告を行うことで税金が戻ってくるケースがあります。
たとえば以下のような場合です:
- 医療費控除
- 生命保険料控除の過不足
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 配偶者控除・扶養控除の追加申請
こうした場合、申告不要だからと放置してしまうと、受けられるはずの還付を逃してしまうことになります。
住民税の申告が必要になる場合もある
所得税の確定申告は不要でも、住民税の課税のために市区町村に申告が必要なことがあります。
住民税は所得の金額によって介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料にも影響を与えます。
自治体が正しい課税計算を行うために「所得の申告」を求めてくるケースがあるため、放置せず確認しましょう。
年金受給者が申告を忘れるとどうなる?

「自分には関係ないと思っていた」「何となく申告しなくても問題ないと思っていた」として、確定申告をせずに過ごしてしまうと、あとで深刻な事態に発展することもあります。
無申告による追徴課税や延滞税のリスク
確定申告が必要な人が期限内に申告をしなかった場合、無申告加算税が課せられます。
さらに納付が遅れると、延滞税が加算され、本来の税額以上の負担になることもあります。
とくに年金受給者にとって、突発的な出費は生活を大きく圧迫する要因となりますので、注意が必要です。
年金生活に影響する支給停止や過徴収の可能性
確定申告が正しく行われていないと、住民税や介護保険料が誤って高額に算定されることがあります。
また、公営住宅の家賃減免、医療費助成、福祉サービスの利用料など、多くの公的支援制度が所得を基準に判定されているため、本来受けられるはずの支援を逃すことにもつながりかねません。
税務署から通知が来るタイミングと対応方法
税務署は、年金機構などの支払調書や金融機関からの情報をもとに、個人の所得を把握しています。
そのため、申告を怠っていた場合でも、数年後に通知や問い合わせが来る可能性があります。
その時点で修正申告や期限後申告を求められると、本来よりも多くの税金と加算税を支払わなければならない事態もあり得ます。
そうなる前に、早めに対処することが重要です。
年金受給者の確定申告でよくある質問と誤解

確定申告の必要性については、多くの年金受給者が悩みや疑問を抱えています。
ここでは、年金生活者から寄せられることの多い質問や、よくある誤解について、わかりやすく整理しておきましょう。
「年金だけなら申告しなくていい」とは限らない?
「年金のみで暮らしているから確定申告は不要」と信じている方が多いですが、これは一部のケースに限った話です。
年金の収入額やその他の所得、扶養控除や医療費控除の有無などにより、申告の必要性が変わります。
特に以下のような場合は、年金だけでも確定申告が必要になる可能性があります:
- 年金収入が400万円を超える
- 年金が2箇所以上から支給されている
- 年の途中で受給を開始した
配偶者の年金はどう扱う?扶養控除との関係は?
配偶者も年金を受給している場合、それぞれが独立した納税義務者となるため、別々に所得や控除を計算する必要があります。
なお、配偶者の収入が一定以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象となりますが、年金額が増えて基準を超えると扶養にできないケースもあるため注意が必要です。
年の途中で年金をもらい始めた場合はどうする?
退職後に年金の支給が開始される場合、その年は給与所得と年金所得が混在する形になります。
このようなケースでは、年末調整がされていない所得がある可能性が高く、確定申告が必要となることが一般的です。
また、公的年金等控除は1年分を前提とした金額で計算されるため、年の途中開始分は控除額が調整される点にも注意が必要です。
亡くなった人の年金と確定申告(準確定申告)の関係
年金受給者が亡くなった場合、その年の所得については、遺族が代わりに確定申告を行う必要があります。
これを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告の提出期限は、死亡を知った日の翌日から4か月以内と定められており、通常の確定申告より早いため注意が必要です。
年金の未支給分を受け取る場合や、医療費控除の申請をする場合にも、準確定申告が必要になることがあるため、相続人がしっかりと手続きを確認しておくことが大切です。
年金受給者が確定申告の前に準備しておくべきもの

年金生活者が確定申告をスムーズに進めるためには、事前準備が鍵となります。
必要な書類や確認すべき情報をあらかじめ揃えておけば、ミスや手戻りを防ぐことができます。
必要書類(源泉徴収票・保険料控除証明書など)
年金受給者が確定申告をする際に用意すべき代表的な書類は以下の通りです:
- 公的年金等の源泉徴収票(毎年1月頃に送付されます)
- 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
- 国民健康保険料・介護保険料などの支払証明書
- 医療費の領収書(医療費控除を受ける場合)
- 寄附金の受領証明書(ふるさと納税など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや通知カード+身分証)
書類が1枚でも足りないと、申告がやり直しになることもあるため、チェックリストなどを使って丁寧に確認しましょう。
申告書類はどこで入手する?e-Taxと紙申告の違い
申告書類は、税務署窓口・市区町村の出張相談所・国税庁のホームページなどで入手できます。
特に近年は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の利用が広がっており、自宅からインターネット経由で申告できる便利な方法として注目されています。
e-Taxでは、源泉徴収票や保険料控除証明書などのデータを自動入力できる仕組みがあるため、手書きよりもミスが少なく、還付も早いというメリットがあります。
ただし、マイナンバーカードやICカードリーダー、マイナポータル連携などの初期設定に不安がある方は、窓口申告や郵送申告を選んでも問題ありません。
税理士に相談する際のチェックポイント
操作や書類の準備に不安がある場合は、税理士に依頼することも検討しましょう。
その際は以下の点を事前に共有しておくと、スムーズに進みます:
- 受給している年金の種類と金額
- 控除を受けたい支出(医療費・寄附金など)の有無
- 源泉徴収票や証明書類の所在
- 家族の扶養状況や配偶者控除の可否
まとめ|年金生活者も申告が必要になる可能性を忘れずに

「年金生活だから確定申告は不要」と決めつけてしまうのは、リスクや損失を招く原因になります。
実際には:
- 公的年金の収入額
- 年金以外の収入の有無
- 控除を使って還付を受けるべきか
- 住民税への影響
などの要素により、確定申告が必要かどうかは人によって異なります。
確定申告の目的は、「税金を納めるため」だけではありません。
正しく申告することで、払いすぎた税金を取り戻せたり、福祉制度や医療制度の適用において有利になることもあります。
不安がある場合は、早めに準備を始めることが安心への第一歩です。
よくある質問(FAQ)
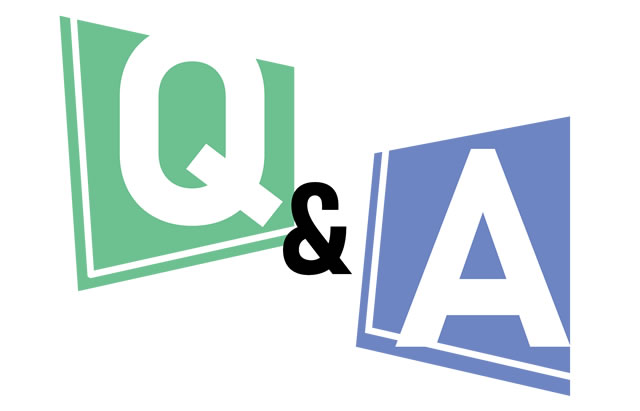
Q. 年金だけでも確定申告が必要な場合はありますか?
はい、あります。
たとえば年金収入が400万円を超える場合や、複数の年金を受け取っている場合、医療費控除などで還付を受けたい場合などは、確定申告が必要です。
Q. 確定申告しないとどうなりますか?
申告義務があるのに提出しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
また、医療費助成や介護保険料などの算定に不利になるケースもあるため注意が必要です。
Q. 配偶者も年金を受け取っている場合はどう申告すればいいですか?
それぞれが個別に申告する必要があります。
配偶者控除や扶養控除が適用されるかは、お互いの年金額や収入状況によって異なるため、確認が必要です。
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
全国の確定申告は税理士?アプリ?自分でやる?税務調査や失敗しない選び方
▼地域ごとの確定申告の手続きの情報はこちらから