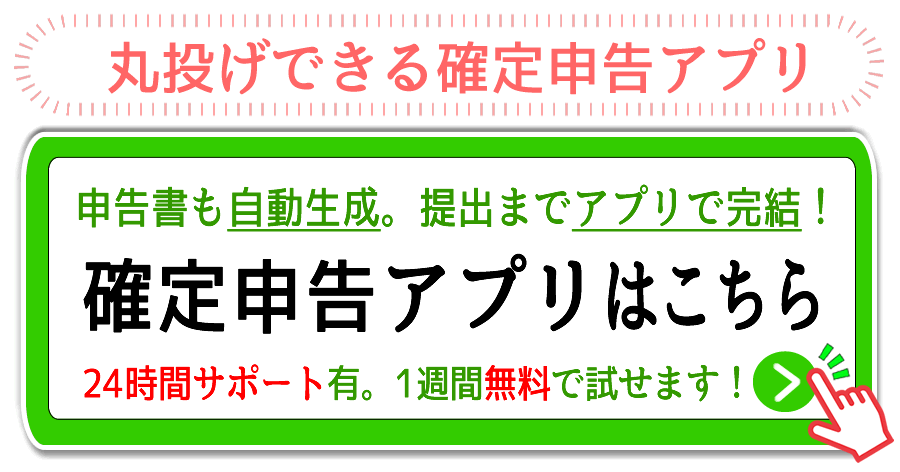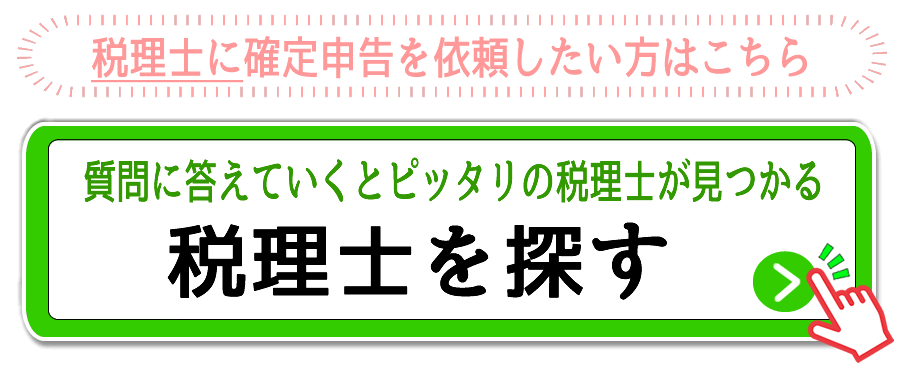PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説

- 不動産を売却したら確定申告が必要?まず知っておくべき基本
- 不動産売却の「利益」とは?課税対象になる金額の計算方法
- マイホームを売ったときの特例:3000万円の特別控除
- 住宅ローン控除を受けていた人が家を売った場合の注意点
- 住宅ローン控除を受けながら新居を購入したケース
- 確定申告の準備に必要な書類一覧(不動産売却・控除関連)
- こんな人は特に注意!申告漏れ・控除ミスの実例とリスク
- 確定申告の提出時期と提出方法について
- まとめ|不動産の売却時は確定申告と控除の両面から確認を
- よくある質問(FAQ)
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
不動産を売却したら確定申告が必要?まず知っておくべき基本

確定申告が「不要」なケースとは?
不動産を売却したすべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。
売却によって利益(譲渡所得)が発生していない場合、つまり売却価格が取得費や諸経費を下回った場合などは、税金がかからないため申告義務がないこともあります。
ただし、税金がかからない場合でも、あとで述べる「損益通算」や「繰越控除」などを利用したい人は確定申告をしておくと有利なケースもあります。
確定申告が「必要」なケースとは?(譲渡益が出た場合など)
不動産の売却で利益が出た場合には、その利益に対して譲渡所得税が課されるため、原則として確定申告が必要です。
とくに以下のような場合は注意が必要です。
- 相続で取得した不動産を売却し、大きな利益が出た
- 取得から5年以内の短期所有物件を売却した
- マンションや土地を高値で売却した
このような場合、売却益に対して所得税・住民税が課税されるため、正確に申告を行う必要があります。
赤字(譲渡損)でも確定申告すべきケースがある理由
実は、不動産の売却で赤字が出た場合にも、確定申告が「有利になる」ことがあります。
たとえば、マイホームを売却して損失が出た場合、「損益通算」や「繰越控除」といった制度により、他の所得(給与所得など)と相殺できることがあります。
つまり、売却損が出たことを確定申告することで、税金が戻ってくる(還付される)可能性があるのです。
これらの特例を使うためには、確定申告が必須となります。
不動産売却の「利益」とは?課税対象になる金額の計算方法

譲渡所得の計算式とは?
不動産売却における課税対象は「譲渡所得」と呼ばれるものです。
これは、単純な売却価格とは異なり、次のような計算式で算出されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額
つまり、売却によって得た金額から、物件を買ったときの費用(取得費)や売却時にかかった経費、さらに特別控除額を差し引いて、残った金額が課税対象になります。
取得費・譲渡費用・特別控除などを差し引く考え方
- 取得費:土地・建物の購入代金や仲介手数料、登記費用、リフォーム代金などが含まれます。相続や贈与で取得した場合は「取得時点の時価」を基準に計算します。
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、解体費用、登記手数料などが該当します。
- 特別控除:居住用財産の特別控除(最大3000万円)や、買い替え特例などがあります。
これらの費用をしっかりと差し引くことで、課税額を大きく下げることができるのです。
所有期間で変わる税率(短期譲渡所得/長期譲渡所得)
譲渡所得にかかる税率は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30%+住民税9%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15%+住民税5%
このように、長く所有していた不動産の方が、税率が低く抑えられるため、有利になります。
なお、所有期間の起算日は「取得した年の1月1日」とされるため、たとえば2019年12月に取得した場合でも、2025年中に売却すると「5年未満」とみなされる点には注意が必要です。
マイホームを売ったときの特例:3000万円の特別控除

3000万円特別控除の概要と適用条件
マイホームを売却した場合、最大で3000万円までの譲渡所得を非課税にできる特別控除があります。
これは居住用財産を売却する際に適用されるもので、適用されれば大きな節税効果が期待できます。
ただし、以下のような条件をすべて満たす必要があります。
- 自分が実際に住んでいた家であること(居住用)
- 売却後も住んでいたことを証明できること
- 売却の相手が親族などの「特別関係者」でないこと
- 売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていないこと
どんな物件が対象になる?居住用の要件とは
ここで言う「居住用」とは、実際に生活の拠点として住んでいたかどうかが問われます。
単に登記上の住所であるだけでは足りません。
電気・水道などの使用状況や、住民票の移動記録などをもとに判断されることになります。
また、転勤などで空き家になっていた物件でも、1年以内に売却するなどの条件を満たせば、特例の対象になることがあります。
申告しないと控除されない?確定申告での手続き方法
この3000万円の特別控除は、自動的に適用されるわけではなく、確定申告を行ってはじめて適用されるものです。
たとえ売却益が3000万円以下であっても、確定申告をしなければ税金が課されてしまうため、必ず申告しましょう。
また、必要書類(売買契約書・登記簿謄本・居住実態を示す資料など)を揃えて提出することが求められます。
住宅ローン控除を受けていた人が家を売った場合の注意点

住宅ローン控除は途中で終わる可能性がある
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、毎年の住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
最長で10〜13年の適用期間があるため、長期的な節税効果が見込まれます。
しかし、控除を受けている家を売却すると、その時点で住宅ローン控除は終了となります。
控除期間の途中であっても、売却した年以降は適用されなくなるため注意が必要です。
売却して利益が出たら控除はどうなる?
売却益が出た場合には、譲渡所得に対して課税が発生し、同時に住宅ローン控除の恩恵は消滅します。
つまり、
- 売却により利益 → 確定申告で譲渡所得税が課税
- 売却により控除 → 翌年以降の住宅ローン控除は打ち切り
となります。
ただし、売却益に対する税金と住宅ローン控除の関係は別物として扱われるため、過年度の控除分が取り消されることは通常ありません。
あくまで「今後の控除が使えなくなる」だけです。
売却損でも控除に影響がある?
不動産を売却して損失が出た場合も、住宅ローン控除は売却時点で終了します。
「損失が出た=控除が続けられる」という誤解が生じやすいのですが、制度の仕組み上、その住宅に住んでいない、もしくは所有していない時点で適用不可となるため、損失の有無に関係なく控除はストップします。
一方で、前述の「譲渡損失の損益通算」や「繰越控除」といった制度を使えば、他の所得と相殺することで節税効果が見込める場合もあります。
控除との併用NGなケース(買い替え特例など)
住宅ローン控除は、他の特例制度と併用できないことがあるため、注意が必要です。
たとえば以下の制度とは原則併用不可とされています。
- マイホーム買い替え特例(譲渡所得の課税を将来に繰り延べる制度)
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除(損失を3年間繰り越す制度)
どちらも有利な制度ではありますが、住宅ローン控除との併用はできず、いずれかを選ぶ必要があります。
そのため、買い替えを前提とした売却の場合は、どの制度が自分にとって有利かを事前にシミュレーションしておくことが重要です。
住宅ローン控除を受けながら新居を購入したケース

新居で住宅ローン控除を受けるには?旧居売却のタイミングが重要
転勤や住み替えなどで、旧居を売らずに新居を先に購入するケースも少なくありません。
この場合、新居の住宅ローン控除を受けたい場合には、旧居の売却タイミングに注意が必要です。
具体的には、新居で住宅ローン控除を受けるためには、
- 新居の取得から6カ月以内に居住を開始すること
- 旧居を一定期間内に売却していること
といった条件が求められます。
旧居を売却せず賃貸に出したり長期間保有し続けた場合、新居の住宅ローン控除が認められないリスクがあるため、売却時期は慎重に検討しましょう。
「マイホームの買い替え」と控除・確定申告の関係
買い替えを検討している場合には、旧居の譲渡所得と新居の住宅ローン控除の関係性にも気を配る必要があります。
たとえば、以下のような点がポイントとなります:
- 旧居の譲渡に3000万円特別控除を使った場合、新居の控除には影響しない
- 旧居で「買い替え特例」を使った場合、新居の住宅ローン控除は使えない可能性がある
このように、制度間の「重複利用の制限」があるため、売却と新築・購入を並行する場合は税務の専門家に確認するのが安心です。
重複適用ができない制度もあるので要注意
繰り返しになりますが、住宅ローン控除と他の譲渡所得特例との併用には制限があるため、自己判断で確定申告をしてしまうと損をする可能性があります。
特に以下のような誤解がよく見られます:
「住宅ローン控除は自動的に引き継がれる」
→ 新たな住宅に対しては、別途要件を満たし、再度確定申告が必要です。
「譲渡損を出せば税金が戻ってくる」
→ 繰越控除には控除対象所得の要件があり、使えない年もあることに注意が必要です。
新旧住宅で得られる控除や特例の適用には、それぞれ細かい条件がありますので、事前の確認が欠かせません。
確定申告の準備に必要な書類一覧(不動産売却・控除関連)

不動産の売却に伴う確定申告では、収支計算だけでなく、正確な証明書類の提出が不可欠です。
以下に、申告時に準備しておきたい書類を整理してご紹介します。
売却時に必要な書類
不動産の売却に関する証拠となる書類は以下のとおりです:
- 売買契約書(コピー可)
- 登記簿謄本(法務局で取得)
- 仲介手数料などの領収書(譲渡費用に含められる)
- 取得費に関する資料(購入時の契約書やリフォーム費用の領収書など)
- 固定資産税納税通知書(一部を取得費に含められる場合あり)
これらの書類は、譲渡所得を正確に計算し、課税額を適切に抑えるために不可欠です。
特に取得費関連の書類は失われやすいため、早めに準備しましょう。
住宅ローン控除関連で必要な書類
すでに住宅ローン控除を受けていた場合、または新居で再び住宅ローン控除を受ける場合には、以下のような書類も求められます。
- 住宅取得資金に関する借入金の年末残高証明書(金融機関から届く)
- 新居の登記事項証明書・売買契約書
- 住民票の写し(居住実態を証明)
- 認定長期優良住宅証明書や耐震基準適合証明書(対象物件の場合)
これらは新たに住宅ローン控除を適用するために必須となります。
最初の1回目の申告時には全て必要ですが、2年目以降は省略可となるケースが多いです。
税務署で確認できること・事前相談の活用
わからないことが多い場合は、税務署の確定申告相談コーナーを活用するのも有効です。
自分では判断が難しい特例の適用可否や書類の有無など、専門家のアドバイスを無料で受けられます。
なお、相談時には売却物件の詳細や書類一式を持参しておくと、よりスムーズに進みます。
こんな人は特に注意!申告漏れ・控除ミスの実例とリスク

不動産売却の確定申告では、以下のような「うっかりミス」や「認識のズレ」がよく見られます。
油断していると、税務署から指摘を受けることもあるため要注意です。
うっかり忘れがちな「住まなくなった後の売却」
たとえば、転勤で引っ越したあと空き家になった自宅を数年後に売却するケース。
本人は「マイホームだから3000万円控除が使える」と思っていても、空き家の期間が長すぎると適用対象外になる可能性があります。
居住実態のある期間や、売却時点との期間の関係によっては、控除が使えず、多額の税金が発生するリスクがあるため注意しましょう。
親族との売買・贈与のような取引
親子・兄弟など特別関係者との取引は特例の対象外となる場合があります。
売却価格が不自然に安いなど、市場価格とかけ離れたケースでは、贈与とみなされ課税されるリスクもあるため、適正な価格での売却と申告が必要です。
売却後の税務調査リスクとペナルティ
不動産の売却は額が大きいため、税務署側もチェックを強化している分野です。
申告を怠ったり、明らかな申告ミスがあった場合、税務調査が入り、延滞税や過少申告加算税が加算されることがあります。
たとえ悪意がなくても、ペナルティの対象となることがあるため、少しでも不明点がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
確定申告の提出時期と提出方法について

不動産の売却にともなう確定申告も、通常の確定申告と同じスケジュールで行います。
申告期間:毎年2月16日〜3月15日(※土日祝により変動あり)
提出方法:以下のいずれかで提出可能
- 税務署へ持参(控えに印をもらえる)
- 郵送(提出日=消印日)
- e-Tax(電子申告/マイナンバーカード対応)
なお、確定申告の具体的な手続き方法やe-Taxの使い方については、こちらのページで詳しく解説しております。
そちらもあわせてご確認ください。
まとめ|不動産の売却時は確定申告と控除の両面から確認を

不動産を売却したときの確定申告は、「利益が出たとき」だけでなく、「損失が出たとき」や「住宅ローン控除を受けていたとき」にも重要な意味を持ちます。
特に以下のようなポイントは見落とされがちです:
- 3000万円の特別控除は申告しないと適用されない
- 住宅ローン控除は売却した時点で終了
- 売却損でも他の所得と損益通算できる場合がある
- 特例制度は併用できないことがある
申告内容を間違えると、余計な税金を払ってしまったり、あとから追徴課税を受けることにもなりかねません。
不安な方は、税理士や税務署への相談も積極的に活用し、正確な手続きを心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
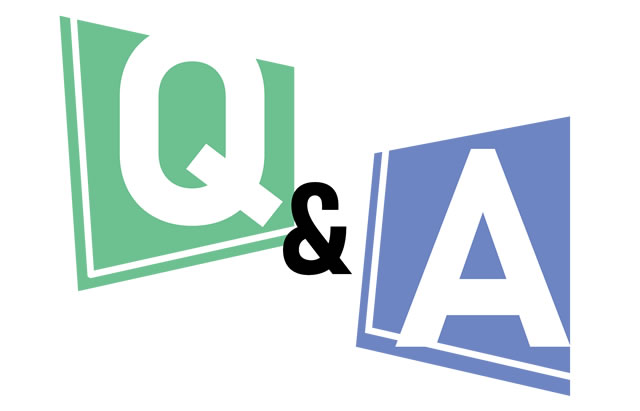
Q. 不動産を売って損が出た場合も申告が必要ですか?
A. はい、損が出た場合でも確定申告を行うことで税制上のメリットを受けられる可能性があります。
たとえば「損益通算」や「繰越控除」を利用すれば、給与所得などと相殺して節税につながることがあります。
Q. 住宅ローン控除は売却後にどうなりますか?
A. 住宅を売却した時点で住宅ローン控除は打ち切りとなります。
控除期間中でも、所有権を手放した場合には翌年以降の控除は受けられなくなります。
Q. 複数の特例を同時に使うことはできますか?
A. 原則としてできません。
たとえば、住宅ローン控除と「マイホームの買い替え特例」は併用できません。
どの特例が最も有利かを事前に検討し、申告時に選択する必要があります。
Q. マイホーム以外(別荘・投資物件)でも控除は使えますか?
A. 3000万円特別控除や住宅ローン控除は、居住用財産に限定されています。
別荘や賃貸物件など、居住の実態がない場合はこれらの控除は適用されません。
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
全国の税理士を探す
▼地域ごとの税理士の情報はこちらから