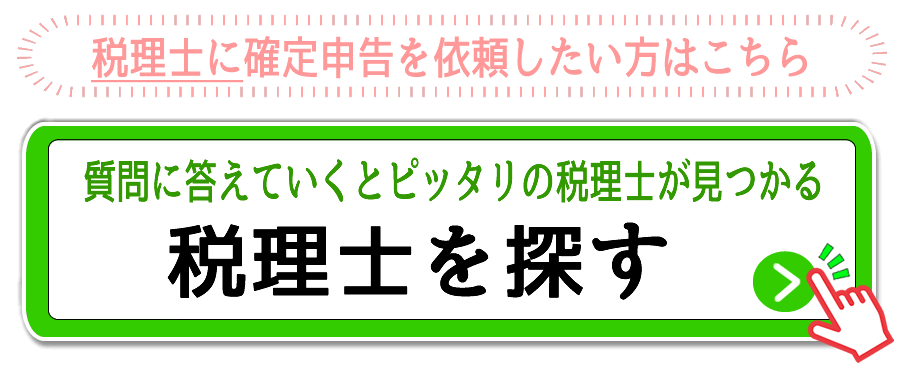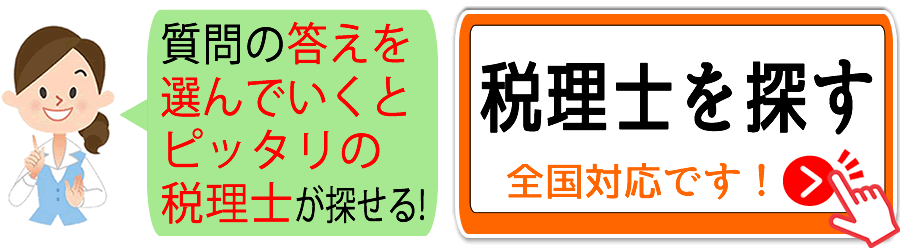PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説

- 投資で確定申告が必要になるケースとは?
- 株式投資で確定申告が必要になる場合
- FX(外国為替証拠金取引)の確定申告
- 仮想通貨(暗号資産)の確定申告
- 投資ごとの確定申告の違いを比較しよう
- 投資の確定申告でよくある失敗と注意点
- 確定申告が不安なときの相談先
- まとめ|投資の種類ごとに申告ルールは異なる
- よくあるQ&A(FAQ)
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
投資で確定申告が必要になるケースとは?

投資によって得られた利益が一定の金額を超えると、確定申告が必要になるケースがあります。
特に株式投資・FX・仮想通貨といった資産運用に取り組む方にとって、申告漏れは思わぬペナルティにつながることもあるため、正しい知識を持つことが大切です。
確定申告が必要になる条件とは
まず基本として、投資による利益は「所得」とみなされるため、税法上の一定条件を超えると確定申告の義務が生じます。
たとえば、サラリーマンなど給与所得者の場合、「給与以外の所得(副収入)が20万円を超えたら申告が必要」とされています。
この「20万円ルール」は多くの方に知られていますが、全ての人に一律で適用されるわけではありません。
具体的には、以下のようなケースでは確定申告が必要になります。
- 年間の投資収益が20万円を超える給与所得者(源泉徴収あり)
- 専業主婦や無職の方で、基礎控除(48万円)を超える所得がある
- 複数の収入源があり、住民税の申告が必要なケース
- 損失の繰越控除を使いたい場合(前年の損失と相殺したい)
このように、投資による利益が少額でも「条件次第」で確定申告が必要となるため、自分の状況に照らして判断することが重要です。
確定申告が不要なケースもある?
一方で、必ずしもすべての投資家が確定申告をしなければならないわけではありません。
たとえば、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合、証券会社が自動的に税金を計算・納付してくれるため、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、以下のようなケースでは、申告を行うことで有利になることもあります。
- 他の証券口座と損益通算をしたい
- 配当控除を活用したい(総合課税での申告)
- 医療費控除やふるさと納税などの他の控除と組み合わせたい
「申告不要だと思っていたら実は必要だった」という事態を避けるためにも、毎年の取引内容をしっかり把握しておくことが大切です。
確定申告の基本的な流れについて
投資に関する確定申告の方法自体は、一般的な確定申告と大きく変わりません。
確定申告の手順(書類の準備〜提出方法〜期限)については、確定申告のやり方と流れをわかりやすく解説で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
株式投資で確定申告が必要になる場合

株式投資に関しては、口座の種類(特定口座・一般口座)や源泉徴収の有無によって、確定申告が必要かどうかが変わります。
また、配当金の扱いや損益通算・繰越控除といった特有のポイントも押さえておく必要があります。
特定口座と一般口座の違い
証券会社で株式投資を始める際には、「特定口座」または「一般口座」のいずれかを選ぶことになります。
- 特定口座(源泉徴収あり):税金の計算・納付を証券会社が代行。確定申告不要。
- 特定口座(源泉徴収なし):税金の計算は証券会社が行うが、納税は自己責任。確定申告が必要。
- 一般口座:計算・納税のすべてを自分で行う。年間取引報告書の発行もなし。
初心者の方や確定申告をなるべく避けたい方には、「特定口座(源泉徴収あり)」がもっとも手間が少なく、おすすめされる選択肢です。
ただし、「源泉徴収あり」でも、複数口座の損益通算をする場合や、控除を適用したい場合には、あえて確定申告を選ぶこともあります。
配当所得の課税と申告方法
株式の配当金についても、受け取った金額に対して税金が課されます。
一般的には、証券会社を通じて受け取る場合、「源泉分離課税」が自動で適用されますが、選択によっては「総合課税」または「申告分離課税」として申告することも可能です。
- 総合課税:他の所得(給与など)と合算して課税。配当控除が適用可能。
- 申告分離課税:譲渡益と合算して、20.315%の税率で課税。
たとえば、年収が低めで配当金の割合が大きい方は、「総合課税」によって配当控除の恩恵を受けられるケースもあります。
逆に、所得が高い方は「申告分離課税」を選んだ方が節税になることもあります。
損失が出た場合の繰越控除とは
株式投資で年間トータルの収支がマイナス(損失)になった場合も、確定申告を行っておくことで、翌年以降の利益と相殺できる「繰越控除」を利用できます。
これは、最大3年間まで繰り越しが可能です。
例:
2024年:マイナス20万円(申告しておく)
2025年:プラス30万円
→ 2025年分の課税対象は、30万円 - 20万円 = 10万円となる
この制度を活用することで、損をしても税負担を抑えるチャンスが生まれるため、忘れずに申告しておくことが重要です。
FX(外国為替証拠金取引)の確定申告

FX(外国為替証拠金取引)で得た利益も、税法上は課税対象となります。
特に、年間の利益が一定額を超える場合や、専業で取引している場合は確定申告が必要です。
株式とは異なり、FXには独自の所得区分や課税方式があるため、正しく理解しておくことが重要です。
FXの利益は「雑所得」になる
国内FXの利益は、原則として「雑所得(申告分離課税)」として扱われます。
これは、給与所得や事業所得などとは区別され、他の所得と合算せずに税率が一定(20.315%)で課税されるという特徴があります。
つまり、年間利益が大きくても、所得税率が高くなることはありません。
これはサラリーマンなどにとっては有利な制度といえるでしょう。
ただし、海外FXの場合は異なり、「総合課税(累進課税)」として扱われます。
税率は所得額に応じて最大55%にも達するため、国内FXと海外FXでは税制が大きく異なる点に注意してください。
20万円以下でも申告が必要なケース
一般的に、給与所得者が得る副収入(雑所得)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要とされています(いわゆる「20万円ルール」)。
しかし、次のような場合には、20万円以下でも申告義務が発生します。
- 年金受給者で公的年金が400万円を超える
- 副収入が住民税の課税対象になる
- 住民税のみの申告が必要な自治体もある
また、損益通算や繰越控除を行う場合には、金額に関わらず申告が必須となります。
損失を翌年以降に繰り越すには
FX取引で損失が出た年も、確定申告をしておくことで、翌年以降の利益と相殺する「損失の繰越控除」を受けることができます。
この制度を利用するには、損失が出た年に確定申告を済ませていることが条件です。
例えば以下のような場合です。
2024年:FX取引で-30万円の損失 → 確定申告を行う
2025年:FXで50万円の利益 → 税金は50万円に-30万円を割り当てて、20万円分の利益に対して課税
このように、損失の年に確定申告をしておくことが、翌年以降の節税につながるということを覚えておきましょう。
仮想通貨(暗号資産)の確定申告
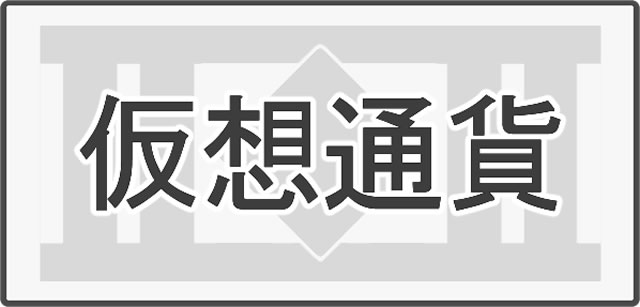
ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨(暗号資産)で得た利益も、課税対象として確定申告が必要です。
仮想通貨には株やFXとは異なる特殊なルールがあるため、より慎重な記録・管理・計算が求められます。
仮想通貨の所得区分は「雑所得」
日本国内において、仮想通貨で得た利益は「雑所得(総合課税)」に分類されます。
これは、FX(国内)と異なり、給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される方式です。
たとえば、会社員が仮想通貨で50万円の利益を得た場合、その50万円が給与所得と合算されて税率が決まるため、年収が高いほど税率も上がる点に注意が必要です。
売却・交換・決済で利益が出たら課税対象
仮想通貨は「売却して日本円に戻したとき」だけでなく、次のようなケースでも利益が確定したと見なされて課税対象になります。
- 仮想通貨を他の仮想通貨に交換したとき(例:BTC→ETH)
- 仮想通貨で商品を購入・決済したとき
- マイニングで得た報酬(法人化していない場合も所得扱い)
つまり、「現金化しなければ税金がかからない」と誤解している方は要注意です。
実態として利益が確定していれば、課税されることを認識しておく必要があります。
損益計算の方法と注意点
仮想通貨の確定申告における最大の難所は、正確な損益計算です。
仮想通貨は価格の変動が激しく、取引回数も多いため、1件ずつの記録と計算が非常に煩雑になります。
損益計算に用いられる主な方式は以下の2つです。
- 総平均法:購入価格の平均を使って原価を計算する
- 移動平均法:購入日ごとに価格を追って原価を計算する
個人投資家の場合は「総平均法」が推奨されるケースが多いですが、一度選択した方法は原則として変更できないため、初回申告時の選択が重要です。
複数取引所のデータ整理が必要
仮想通貨は複数の取引所を使って売買することも珍しくありません。
しかし、税務上はすべての取引所での損益を合算して申告する必要があります。
そのため、以下のような作業が求められます。
- 各取引所の取引履歴をCSVでダウンロード
- 通貨ペアごとの取引価格を記録
- 日本円換算で利益を算出
このような処理を正確に行うために、損益計算ソフト(Cryptact・Gtax・クリプタクトなど)の利用も検討するとよいでしょう。
投資ごとの確定申告の違いを比較しよう

株式・FX・仮想通貨といった投資には、それぞれ課税の仕組みや申告のルールが異なるため、しっかりと違いを把握しておくことが重要です。
ここでは主な違いをわかりやすく整理します。
課税方式の違い
- 株式投資:申告分離課税(20.315%)。特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要。
- FX(国内):申告分離課税(20.315%)。雑所得として別枠課税。
- 仮想通貨:総合課税(5%〜45%+住民税10%)。給与等と合算され累進課税。
株やFXは比較的税率が一定ですが、仮想通貨は所得が多くなるほど高額な税金がかかる点が大きな違いです。
損益通算の可否と繰越控除のルール
- 株式:他の株式や投資信託と通算可。3年間の繰越控除も可能。
- FX:他の国内FX取引と通算可。3年間繰越控除あり。
- 仮想通貨:原則、他の所得や投資との通算不可。繰越控除も不可。
仮想通貨は税制面で不利な点が多く、損失を翌年に活かせないことから、投資判断にも影響を与える要素といえるでしょう。
税率・控除・手続きの比較(表形式)
| 投資種類 | 所得区分 | 税率 | 確定申告の要否 | 損益通算 | 繰越控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | 申告分離課税 | 20.315% | 特定口座(源泉徴収あり)なら不要 | 可能 | 可能(3年) |
| FX(国内) | 雑所得(分離) | 20.315% | 必要(年間20万円超) | 可能 | 可能(3年) |
| 仮想通貨 | 雑所得(総合) | 5〜55% | 必要(利益確定時) | 不可 | 不可 |
投資の確定申告でよくある失敗と注意点

初めて投資で確定申告を行う方が陥りやすいミスには、いくつか共通点があります。
ミスはペナルティや追徴課税につながることもあるため、事前に確認しておきましょう。
申告漏れによるペナルティ
確定申告を忘れたり、金額を少なく申告したりすると、加算税(無申告加算税・過少申告加算税)や延滞税が発生します。
税務署は証券会社や取引所からのデータ提供を受けているため、「バレない」と考えるのは非常に危険です。
申告義務があるか微妙な場合でも、一度税務署や専門家に相談するのが安全です。
複数口座・取引所の損益を合算していない
証券口座や取引所が複数あると、それぞれの損益を合算する必要があります。
とくに仮想通貨では、「A取引所で利益」「B取引所で損失」などがある場合、トータルではプラスかマイナスかを判断しなければなりません。
これを怠ると、利益だけを申告して損失分を見落とすというミスにつながります。
経費の扱いを誤っている
投資にかかる費用(手数料や取引ツールの利用料など)は、必要経費として計上できる可能性があります。
たとえば、
- 株式取引の売買手数料
- 仮想通貨取引の入出金手数料
- 有料取引ツールの月額費
これらは適切に領収書や履歴を残しておけば、所得から控除できる場合があります。
逆に、経費と認められないもの(書籍購入・セミナー代など)もあるため、判断に迷う場合は専門家へ確認を。
確定申告が不安なときの相談先

投資の確定申告は、口座の種類・取引履歴・税法の知識が求められるため、不安を感じる方も多いでしょう。
そんなときは、以下のような相談先を活用しましょう。
税務署・自治体の無料相談会を活用する
確定申告シーズンになると、税務署や市区町村で無料の税務相談会が開かれます。
予約制の場合もあるので、事前に日程を確認しておくと安心です。
- 国税庁「税務相談窓口」
- 地方自治体の「確定申告相談会」
- 商工会議所・税理士会による出張相談ブース
いずれも、申告書類・取引履歴を持参すれば、その場でアドバイスが受けられるケースもあります。
投資に強い税理士に依頼する
仮想通貨やFXなど、取引が複雑で自分では対応しきれないと感じる場合は、投資に詳しい税理士に相談・依頼するのが得策です。
最近では、以下のようなサービスを提供している税理士も増えています。
- 仮想通貨に特化した損益計算代行
- FX収支のチェックと節税アドバイス
- 税務署とのやりとりの代理対応
料金の相場は3万円〜10万円前後が目安ですが、申告ミスによる追徴リスクを考えると安い投資といえるかもしれません。
まとめ|投資の種類ごとに申告ルールは異なる

投資によって得た利益は、原則として課税対象となり、一定条件を満たすと確定申告が必要です。
- 株式投資は特定口座を選べば申告不要も可能。ただし損益通算や配当控除を活用するなら申告を。
- FXは「雑所得(分離課税)」として毎年申告。損益通算や繰越控除の制度が活用できる。
- 仮想通貨は「雑所得(総合課税)」で累進税率。ルールが複雑で損失の繰越もできない。
こうした違いを正しく理解しておくことで、余計な税負担を避け、トラブルの予防にもつながります。
不安や疑問がある場合は、税務署や投資に強い税理士への相談も積極的に検討しましょう。
よくあるQ&A(FAQ)
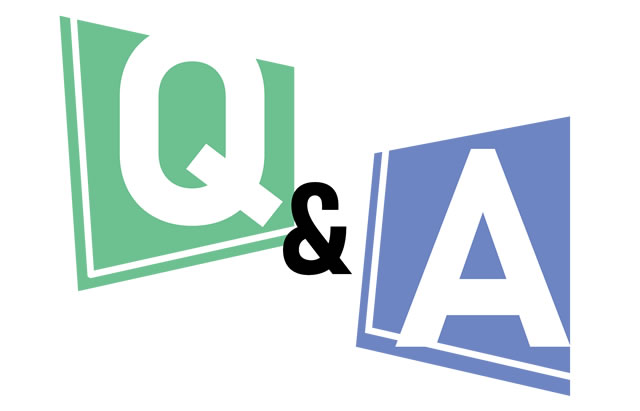
Q. 株の特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要な場合はありますか?
A. はい、あります。
損失を他の口座と通算したい場合や、配当控除を受けたい場合は確定申告が必要です。
源泉徴収で納税が完了していても、節税のために申告を選ぶ人もいます。
Q. FXの利益が20万円未満でも申告する必要はありますか?
A. ケースによります。
専業主婦や年金受給者などは、20万円未満でも住民税の申告が必要になることがあります。
また、損失の繰越控除を受けたい場合は金額に関わらず申告が必要です。
Q. 仮想通貨の利益が出たのに円に換金していない場合も申告が必要ですか?
A. はい、必要です。
仮想通貨を他のコインに交換した時点や、商品・サービスの決済に使った場合も課税対象になります。
Q. 投資の損失を翌年以降に活かす方法はありますか?
A. 株式やFXでは、確定申告をすることで「損失の繰越控除」が可能です(最大3年間)。
ただし、仮想通貨の損失は繰越控除の対象外なので注意が必要です。
Q. 確定申告が難しくて不安です。
どこに相談すればよいですか?
A. 税務署の無料相談や自治体の相談会を活用できます。
また、投資に詳しい税理士に依頼することで、ミスや申告漏れを防ぐことができます。
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
全国の確定申告は税理士?アプリ?自分でやる?税務調査や失敗しない選び方
▼地域ごとの確定申告の手続きの情報はこちらから