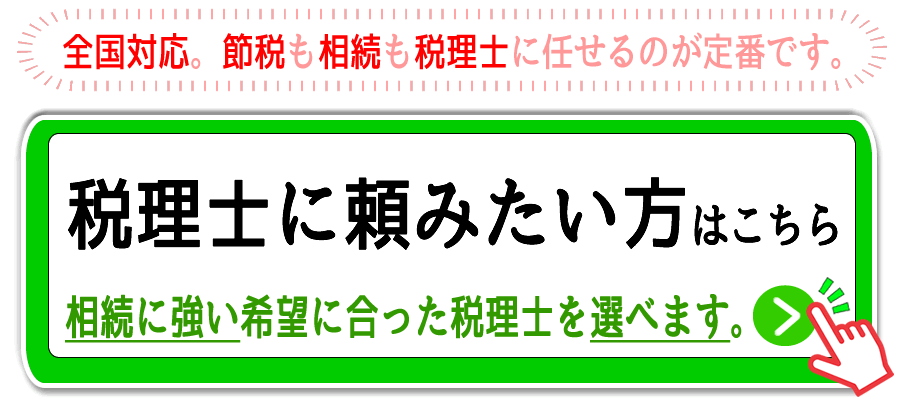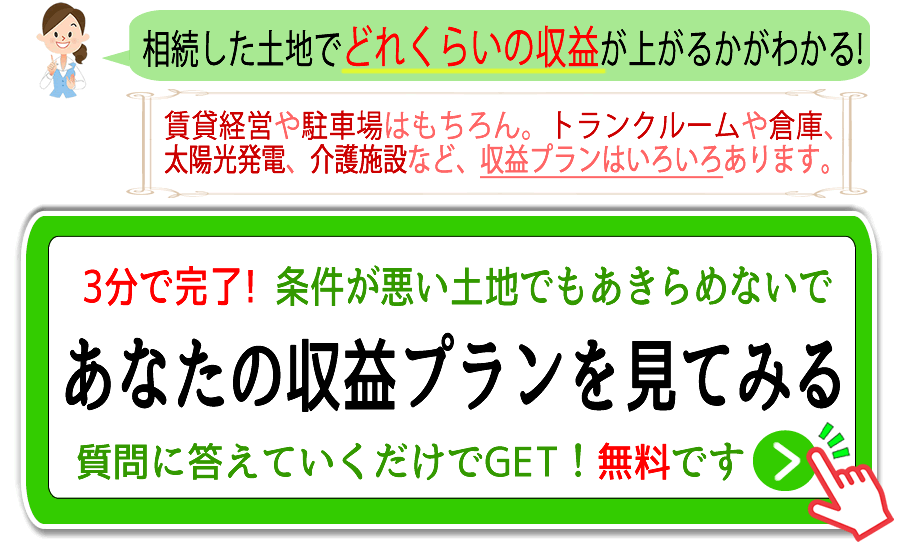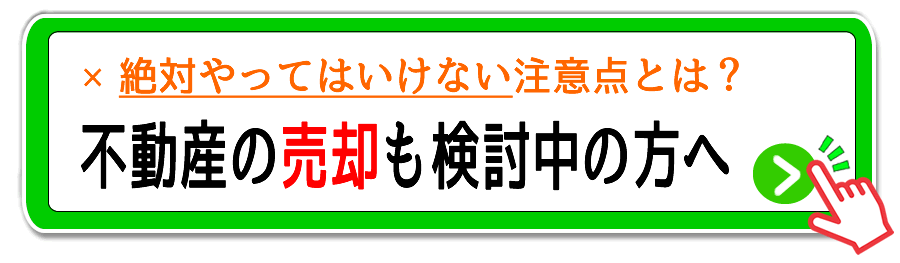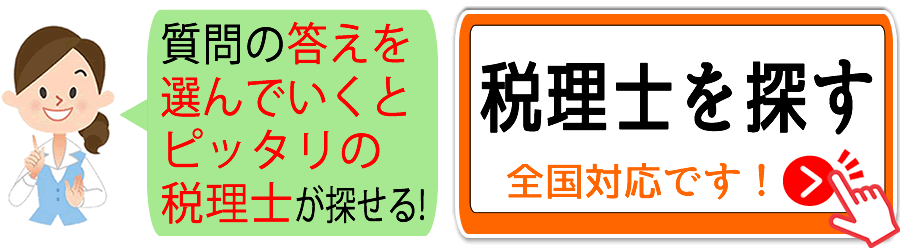PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは

- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
なぜ相続で「司法書士か税理士か」で迷うのか

相続は登記・税務・手続きの複合業務
誰かが亡くなった後に発生する「相続」は、単に財産を受け継ぐだけではありません。
相続人の確定、遺産分割協議、名義変更、そして相続税の申告や納税など、さまざまな手続きが複雑に絡み合う作業です。
その中でも特に「登記(不動産の名義変更)」と「税務(相続税の申告)」は、専門的な知識と正確な手続きが求められるため、司法書士または税理士のいずれか、もしくは両方への依頼が必要になる場面が少なくありません。
「手続きは司法書士?」「税金は税理士?」と悩む背景
実際に相続が始まったとき、多くの方が「何を誰に相談すればよいか分からない」という不安に直面します。
- 不動産の名義を変更したいけど自分でできる?
- 相続税がかかるかどうかがわからない
- 銀行の手続きも司法書士に頼めるの?
こうした疑問が次々に浮かび、「司法書士に頼むべきか?それとも税理士?」という迷いにつながっていくのです。
登記だけで済まない相続が増えている
以前は「相続=不動産の名義変更」という認識が強く、司法書士への依頼が中心でした。
しかし現在は、相続税の課税対象者が増加傾向にあり、税務申告や節税対策の必要性が高まっています。
また、相続登記が義務化されたことで「名義変更だけすればいい」という考え方では不十分になりつつあり、登記と税務の両方を意識した相続対策が必要な時代になっています。
司法書士と税理士、それぞれの役割と専門分野

司法書士の役割は「登記と書類作成の専門家」
司法書士は、法務局などへの登記申請手続きの代理を中心とする国家資格者です。
相続においては、主に以下の業務を担います。
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 金融機関・証券会社などの手続き代行
登記に必要な戸籍や住民票などの書類の収集、遺産分割に基づいた名義変更、金融機関とのやり取りなど、煩雑な書類対応をスムーズに代行してくれる点が最大の強みです。
ただし、相続税の申告や評価、税務調査対応などは司法書士の業務範囲外となります。
税理士の役割は「相続税の申告と節税対策」
一方、税理士は税務に関する唯一の国家資格者であり、相続税の申告書作成・提出、相続財産の評価、節税対策の提案など、税金面の専門家として相続をサポートします。
特に以下のような対応は、税理士でなければ行えません。
- 相続税の計算・申告
- 不動産や非上場株式の評価
- 小規模宅地の特例や配偶者控除の適用判断
- 二次相続まで見据えた節税提案
税理士はあくまで「税のプロ」であるため、登記申請や不動産の名義変更といった法務局での手続きは対応できません。
どちらも国家資格だが、対応できる内容が異なる
司法書士と税理士はどちらも国家資格者ですが、業務範囲はまったく異なります。
登記は司法書士、税務は税理士というふうに、得意分野がはっきりと分かれているのです。
| 業務内容 | 司法書士 | 税理士 |
|---|---|---|
| 相続登記(名義変更) | ◯ | × |
| 相続税の申告 | × | ◯ |
| 金融機関の名義変更 | ◯(一部対応) | △(補助的) |
| 財産評価・節税対策 | × | ◯ |
「どちらに相談すべきか」と迷ったときは、まずは自分の相続で必要な手続きがどれかを把握することが重要です。
税理士は登記できない/司法書士は税申告できない
中には「どちらか一方に全部まとめてお願いできないの?」と思われる方もいらっしゃいますが、法律上、それぞれが対応できる業務には明確な線引きがあります。
たとえば、
- 税理士は不動産の名義変更を代理申請できない
- 司法書士は相続税の申告を行うことができない
というように、それぞれの専門分野に専念することで、制度的な信頼性と専門性が担保されているのです。
司法書士に依頼すべき相続のケース

不動産の名義変更が必要なとき
相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合、名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野です。
法務局に提出する登記申請書類の作成や、戸籍・住民票など必要書類の収集、遺産分割協議書の整備など、複雑な手続きを代行してもらえます。
とくに2024年4月からは、相続登記が義務化され、3年以内の申請が必要となったため、放置していた相続不動産の登記を進める動きが活発化しています。
相続登記の義務化に伴う手続き
義務化された背景には、名義変更されないまま放置された土地が増えたことがあります。
これにより、
- 不動産の売却や活用ができない
- 固定資産税の納税義務者が曖昧になる
- 空き家問題が深刻化する
などの社会的課題が生じていたため、相続登記の申請が法的義務となりました。
司法書士はこのような背景も踏まえて、ミスなく期限内に登記を完了するための実務対応を担っています。
遺言書の検認や法定相続情報一覧図の作成
相続登記に先立って、遺言書の検認(自筆証書遺言がある場合)や、法定相続情報一覧図の作成を行うこともあります。
これらの作業は、
- 戸籍謄本の収集・確認
- 相続人の確定
- 家庭裁判所とのやり取り
など、時間も手間もかかるため、司法書士に任せることで大幅に手続きを簡素化できます。
預貯金や株式の名義変更サポート
相続財産には不動産以外にも、銀行口座、株式、投資信託、保険金などさまざまな資産が含まれます。
これらの名義変更についても、金融機関や証券会社への提出書類の確認・整備などを、司法書士がサポートすることができます。
ただし、金融機関によっては対応範囲に制限があるため、あらかじめ確認が必要です。
税理士に依頼すべき相続のケース

相続税の申告・納税が必要な場合
相続財産の総額が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。
この手続きは税務署への対応が必要であり、税理士にしか対応できません。
申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」と決まっており、時間との勝負になります。
相続財産の評価や特例の活用
相続税の課税額を決定するには、財産の正確な評価が欠かせません。
特に以下のような財産は、評価が複雑で専門的な知識を要します。
- 宅地や貸家建付地などの不動産
- 非上場会社の株式
- 借地権・借家権
- 生前贈与財産との関係整理
税理士はこうした財産の評価を行うだけでなく、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった制度の適用可否を判断し、適正な申告を通じて節税にも貢献してくれます。
税務署対応や二次相続を見据えた節税
相続税の申告後、税務署から内容に対する質問や税務調査が行われる場合もあります。
こうした際、税理士が代理人として対応してくれることで、依頼者の精神的負担は大きく軽減されます。
また、一次相続だけでなく、将来発生する二次相続(配偶者の死亡による相続)を見据えた税務戦略も重要です。
税理士はその視点から、長期的な節税プランの提案も行います。
遺産分割協議後の税務アドバイス
相続人間の話し合いで遺産分割が決まったとしても、それによって税負担がどう変わるかは素人では判断しきれません。
- 誰が不動産を相続するか
- 現金で受け取るか、物納を検討するか
- 特例を適用するための要件を満たしているか
など、遺産分割の内容と税務の整合性を事前にチェックし、アドバイスできるのは税理士だけです。
税理士だけで対応できるケースと注意点

争いがなく、相続登記が済んでいる場合
相続人同士の関係が良好で、すでに司法書士などによって相続登記が完了している、あるいは不動産が含まれていない場合は、税理士だけで対応可能なケースが多くあります。
このような場合、相続税申告と納税対応がメインとなるため、専門的な登記知識は不要です。
税申告がメインで、登記は不要な場合
現金・預貯金・金融商品が財産の中心で、不動産がまったくないケースでは、登記そのものが発生しないため、税理士のみで完結できます。
ただし、証券会社や銀行での名義変更手続きに関しては、相続人自身が対応する必要があります。
すでに司法書士に依頼済みの登記があるケース
司法書士に登記だけを先に依頼し、その後税務処理を税理士に依頼するという流れも一般的です。
この場合、各専門家が自分の得意分野に集中できるため、結果として効率的な対応が可能です。
ただし、登記未了の不動産があるとトラブルに
名義変更が終わっていない不動産があると、申告に不備が出たり、評価方法に誤りが生じたりする恐れがあります。
また、名義人不明のまま売却・運用ができないため、トラブルの元にもなりかねません。
こうしたケースでは、税理士だけで進めようとせず、司法書士との連携が不可欠です。
司法書士と税理士、両方に依頼すべきケースとは

不動産を含む相続で税申告も必要な場合
相続財産に不動産が含まれており、さらに基礎控除を超える資産がある場合は、登記と税務の両方の手続きが必要になります。
たとえば、
- 土地や建物の相続登記
- 不動産評価額に基づく相続税の計算
- 小規模宅地等の特例の適用判断
などは、それぞれ司法書士と税理士の専門領域に分かれます。
このようなケースでは、片方だけに依頼することは不十分で、両者の連携があってこそ適正な手続きが可能となります。
名義変更と税申告を並行して進める必要があるとき
相続税の申告には、不動産の評価資料や名義人の情報が必要になるため、登記が完了しているかどうかが重要になります。
一方で、登記を進めるうえでも、遺産分割協議の内容や税務上の影響を把握しておく必要があります。
このような場合は、司法書士と税理士が情報を共有しながら手続きを進めることで、ミスや重複を防ぎ、スムーズな完了につながります。
ワンストップ対応の事務所を活用する方法も
最近では、司法書士・税理士が在籍または連携している相続特化型の事務所も増えており、こうした事務所では「登記も税務も一括して相談できる」体制が整っています。
ワンストップサービスには以下のようなメリットがあります:
- スケジュール調整や書類提出が一元化される
- 手続きごとに別々の説明をする手間が省ける
- 分野をまたいだ助言が受けられる
特に、高齢の相続人が複雑な手続きを1人で抱えるような場合には、このような事務所の利用が安心材料となります。
費用や手続き面での比較ポイント

費用だけで選ばない方がいい理由
司法書士と税理士、どちらに依頼するかを費用面だけで決めてしまうと、かえって手続きが二度手間になったり、追加で依頼が必要になったりするケースがあります。
たとえば、登記が終わっていないまま相続税申告を進めてしまうと、評価額の根拠が弱くなる可能性があります。
また、節税の可能性があるのに税理士に相談していなかったため、納税額が余分に膨らんでしまうこともあります。
司法書士と税理士の報酬の違い
一般的に、報酬体系は以下のようになります:
| 業務内容 | 報酬の目安(相場) |
|---|---|
| 相続登記(司法書士) | 約7万円〜15万円前後(不動産の数により変動) |
| 相続税申告(税理士) | 約20万円〜50万円前後(財産規模による) |
※事務所によっては、相談料・書類取得費用・郵送代などが別途発生する場合もあります。
費用感は大切ですが、それ以上に、「自分のケースに合った手続きを確実に進める」という視点で専門家を選ぶことが重要です。
手続きの流れとスケジュールの違い
司法書士と税理士では、手続きの完了までに必要な期間や流れにも違いがあります。
| 項目 | 司法書士(登記) | 税理士(税務) |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 相続人の確定後 | 遺産の概要把握後 |
| 所要期間の目安 | 1〜2ヶ月 | 3〜6ヶ月 |
| 期限 | 義務化で3年以内 | 10ヶ月以内に申告・納税 |
これらのスケジュール感を意識し、どちらを先に動かすべきかを判断することも、円滑な相続手続きに欠かせません。
どちらを先に相談すべきか
相続税の有無が不明な場合は、まず税理士に財産の評価を依頼し、税務の必要性を判断するのが賢明です。
その上で、不動産がある・登記が必要であれば司法書士にも相談、という流れがおすすめです。
登記だけ済ませてしまってから「税務上不利な分割だった」と後悔するケースもあるため、最初に税理士→次に司法書士、という順序が合理的な場面は少なくありません。
まとめ|相続で司法書士か税理士か迷ったら

登記が必要なら司法書士、税務があるなら税理士
基本的には、
- 不動産や金融資産の名義変更 → 司法書士
- 相続税の申告や節税対策 → 税理士
と、役割を分けて考えることで、混乱を防ぐことができます。
複雑な相続は両者の連携がカギ
不動産が複数あったり、財産評価が難しかったり、相続人が多い場合には、登記と税務が密接に関係します。
そうした複雑な相続には、司法書士と税理士の両方の専門性が必要です。
判断に迷ったら、税額の有無と財産の中身を確認
自分のケースが「税申告が必要なのか?」「不動産の登記が必要なのか?」が分からない場合は、相続財産の総額と内容を把握することが第一歩です。
そのうえで、どちらの専門家に最初に相談すべきかを判断すると、手続きが円滑に進みます。
よくある質問(FAQ)
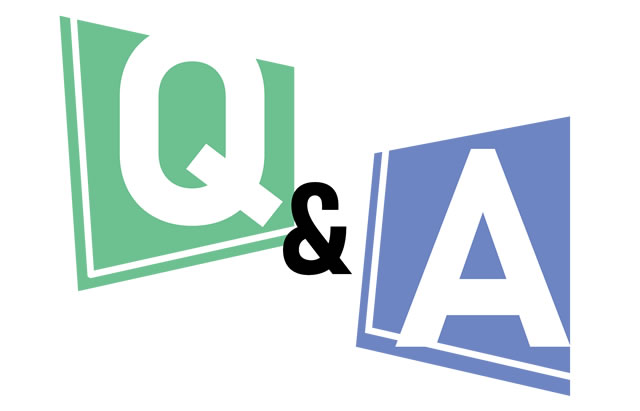
Q. 相続では司法書士と税理士のどちらに相談すればよいですか?
A. 不動産の名義変更が必要なら司法書士、相続税の申告や節税が必要なら税理士に相談するのが基本です。
相続内容によっては両方の専門家の協力が必要になることもあります。
Q. 登記だけなら税理士にお願いできますか?
A. 登記手続きは税理士の業務範囲外のため、司法書士に依頼する必要があります。
税理士は登記を代行できませんので、法務局への申請は司法書士に任せましょう。
Q. 相続税がかかるかわからない場合は誰に相談すればよいですか?
A. 相続税のかかる・かからないを判断するには、まず税理士に財産評価を依頼するのが適切です。
その結果、税申告が必要であれば税理士に継続して依頼できます。
Q. 両方に相談すると費用が倍になりますか?
A. それぞれの業務内容に応じた報酬は発生しますが、手続きの効率化やミスの防止につながるため、結果的に無駄を省けることが多いです。
ワンストップ対応の事務所であれば、費用調整が可能な場合もあります。
Q. 司法書士に先に依頼してしまいましたが、あとから税理士にも相談できますか?
A. もちろん可能です。
ただし、登記が税務的に不利にならないよう、できれば税理士と相談しながら進めることをおすすめします。
- 相続した不動産がいくらで売れるか無料で査定できます
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
全国の相続の手続き完全ガイド|まず何をすればいい?期限・流れ・必要書類を徹底解説
▼地域ごとの相続の手続きの情報はこちらから