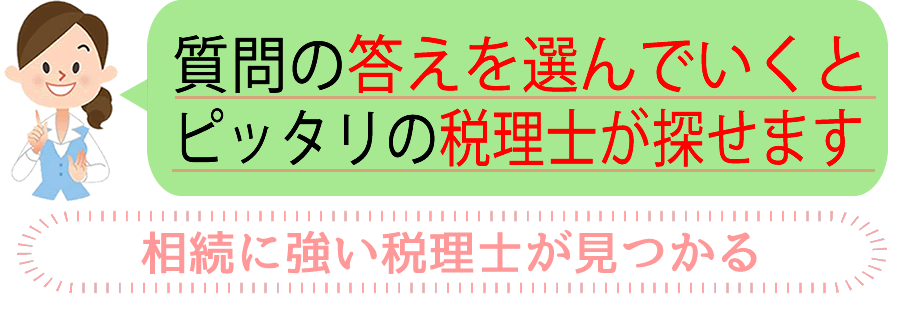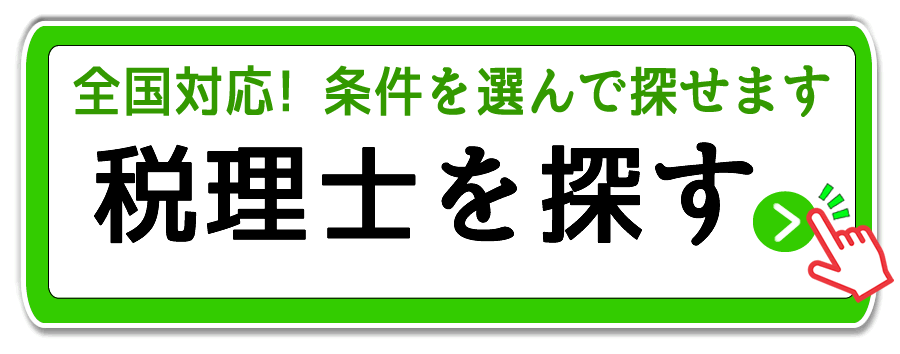生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
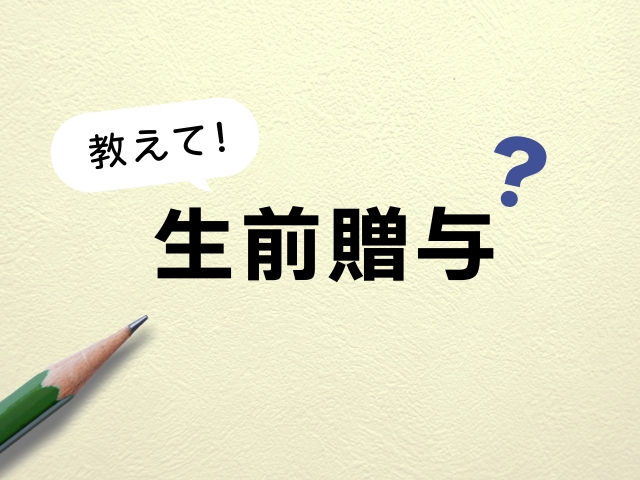
- 生前贈与とは?今あらためて注目される理由
- 生前贈与の具体的なやり方と選択肢
- 節税になる?ならない?生前贈与の損得勘定
- 生前贈与でありがちな失敗と落とし穴
- 生前贈与を成功させるために知っておきたい実務のポイント
- 贈与するタイミングはいつがいい?年齢・資産規模・家庭事情から考える
- 不動産や高額資産の生前贈与に特有の注意点
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
生前贈与とは?今あらためて注目される理由

「生前贈与」とは?相続との違いをざっくり理解
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を家族や親族などに譲り渡すことを指します。
つまり、相続のように「亡くなった後」に財産が引き継がれるのではなく、本人が意思を持って財産を移転させる点が大きな特徴です。
たとえば、親が子どもに現金や不動産を贈る場合、それを「生前贈与」と呼びます。
形式上は贈与契約が成立し、受け取った側には税金(贈与税)がかかることがあります。
一方で、相続は死後に発生する法定の手続きであり、誰にどれだけ渡すかは法定相続人や遺言の内容によって決まってきます。
これに対して生前贈与は、自分の意志で誰にいくら渡すかを自由に決められるのがメリットです。
なぜ今、生前贈与が注目されているのか
かつては「亡くなってから相続で分ければいい」と考える人が多くいました。
しかし最近では、生前のうちに財産を計画的に移しておくことで、家族間のトラブルを未然に防いだり、税金対策になったりするという考えが広まっています。
特に近年は「高齢の親を介護してきた人」と「疎遠な兄弟姉妹」の間で相続を巡るトラブルが急増しており、「自分の意思で、必要な人に確実に渡しておきたい」という需要が高まっています。
また、家族構成の変化や単身世帯の増加も背景にあります。
相続人が誰になるかわかりにくい状況では、あらかじめ贈与しておくことで、自分の思い通りの資産承継を実現できるという意味でも、生前贈与が再評価されています。
2024年税制改正で何が変わった?
令和6年度(2024年)の税制改正により、生前贈与を取り巻くルールが大きく変わりました。
具体的には、相続開始前7年以内の贈与は、一定条件のもとで相続財産に加算されるようになった点が注目されています。
これにより、従来のように「亡くなる直前に贈与して節税しよう」といった小手先の対策が通用しにくくなっています。
その一方で、早めに贈与計画を立てれば、依然として大きなメリットを得られる可能性もあります。
税制改正によって「贈与は慎重に行うべき」という空気が広がる一方、正しく使えば家族の資産形成や安心に繋がる制度であることに変わりはありません。
生前贈与の具体的なやり方と選択肢

1年110万円の非課税枠を活用する方法
生前贈与の中でもっともよく知られているのが、「暦年贈与」と呼ばれる方法です。
これは、1人あたり年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないという非課税枠を利用するものです。
この制度は非常にシンプルで、たとえば親が子どもに毎年100万円ずつ現金を贈ると、それだけで数年後には大きな財産移転が可能になります。
長期的に計画的な贈与をしたい場合に適している制度です。
ただし注意点もあります。
毎年同じ金額を同じ時期に振り込むと、「名ばかり贈与」とみなされるリスクもあるため、契約書を交わす・送金日をずらすなどの工夫が必要です。
不動産を贈与する場合の手続きと注意点
現金だけでなく、不動産を生前贈与することも可能です。
ただし、不動産贈与には次のような手続きが発生します。
- 贈与契約書の作成
- 登記名義変更
- 贈与税の申告・納税(評価額による)
- 登録免許税や不動産取得税の支払い
現金よりも費用と手間がかかるうえに、課税対象額が高くなりやすいため、慎重に進める必要があります。
また、贈与者が贈与後もその家に住み続けるケースでは「名義だけ移した」と判断されかねないため、実態も伴った贈与であることを明確に示す対策が必要です。
生命保険を活用した生前贈与のスキーム
意外に知られていないのが、生命保険を活用した贈与の方法です。
たとえば、契約者=親、被保険者=親、受取人=子どもという形で保険を設計し、保険料の支払いを贈与として行う方法があります。
これにより、毎年の保険料を非課税枠に収めつつ、将来の死亡保険金を非課税で子に渡すことが可能になることも。
ただし、契約内容や保険の種類により大きく扱いが異なるため、制度理解が欠かせません。
現金だけじゃない?預金口座・株式の贈与
生前贈与の対象は現金だけではありません。
たとえば、次のような資産も贈与の対象になります。
- 定期預金
- 株式・投資信託
- 車や宝石などの動産
とくに、証券口座を通じた株式の贈与は、時価による評価と税金の計算が複雑になることが多いため、正確な評価方法を押さえておくことが必要です。
また、通帳や印鑑を渡しただけでは「贈与が成立していない」と判断されるリスクもあります。
契約書と履歴が重要になる点は、現金と同様です。
節税になる?ならない?生前贈与の損得勘定

110万円の基礎控除だけで本当にお得?
生前贈与の定番である「年間110万円まで非課税」という制度(暦年贈与)ですが、これだけで本当に節税になるのかは状況によって異なります。
たとえば、相続財産が基礎控除内に収まるような小規模な家庭では、そもそも相続税がかからない可能性が高いため、生前に贈与しても節税効果が出にくいことがあります。
一方で、将来相続税がかかる見込みがある場合には、計画的に非課税枠を利用することで課税対象を減らせるため、有効な手段となり得ます。
暦年贈与 vs 相続時精算課税制度の比較
生前贈与の制度には、「暦年贈与」以外にも「相続時精算課税制度」という仕組みがあります。
これは、贈与時には非課税、もしくは2,500万円まで非課税になる一方で、将来の相続時にすべて合算して課税される制度です。
この制度のメリットは、一度に大きな金額を贈与できること。
たとえば、住宅購入資金や事業用不動産などを一括で渡したいときに重宝されます。
しかし、デメリットもあります。
一度この制度を選ぶと、暦年贈与に戻れないため、将来的な柔軟性が失われます。
制度の理解不足で「思っていたのと違った」と後悔する人も少なくありません。
失敗例に学ぶ「節税のつもりが逆効果」ケース
生前贈与でよくある失敗の一つは、制度を誤解したまま進めてしまい、結果的に税負担が増えてしまうケースです。
たとえば、
- 毎年110万円ずつ贈与していたが、贈与契約書を作っていなかった
- 贈与後も親が通帳を管理し続けていた
- 相続発生の直前にまとめて贈与してしまった
こうしたケースでは、税務署から「贈与と認められない」と判断され、相続税として課税されるリスクがあります。
「節税目的」が疑われるとどうなるのか?
税務署は「形式だけの贈与」や「相続税逃れのための不自然な動き」に非常に敏感です。
とくに近年は、マイナンバー制度や金融機関との連携が強化されたことで、調査の目が厳しくなっている傾向にあります。
そのため、贈与はあくまで「財産を渡したい」という実態と意思が伴っていることが大前提です。
節税だけを目的とした計画は、後々トラブルになる可能性が高くなります。
生前贈与でありがちな失敗と落とし穴

贈与契約書を作らなかった場合のリスク
意外と多いのが、贈与契約書を交わさずにお金だけ渡してしまうケースです。
贈与契約は口頭でも成立しますが、証拠が残らないと後で「それは贈与ではなかった」と主張される可能性があります。
とくに相続時に親族間で争いが起きたとき、「あれは貸し付けだった」「返済義務があるはず」と言われかねないため、書面による記録は必須といえます。
名義変更しても「贈与にならない」ケースとは
たとえば、不動産や預金口座の名義を子どもに変えただけでは、税務上の「贈与」が成立していないと見なされることがあります。
名義だけ変更しても、
- 実際の管理・使用は親のまま
- 通帳・印鑑が親の手元にある
- 利用履歴に変化がない
このような状態では、形式的な贈与と判断され、税務署から否認される可能性があるため、「誰が管理し、誰のために使われているのか」が重要です。
贈与者が生活資金として使い続けた場合のトラブル
親が「贈与した」と言いつつも、生活費の足しにするために、子名義の預金を自由に引き出している――こうした状態では、贈与の実態がないとされることが多いです。
特に高齢者が成年後見制度の対象となった場合、後見人によって贈与行為が無効とされるケースもあります。
「将来のために…」という善意であっても、ルールに則った形で贈与を行わないと、後に家族に不利益を及ぼすことになりかねません。
家族間でトラブルになりやすい3つのパターン
生前贈与は制度以上に、家族感情のバランスが重要です。
以下のようなケースでは、後に大きなトラブルに発展するリスクがあります。
1. 一部の子どもにだけ贈与し、他の兄弟には何もない
2. 同居している子だけが贈与を受けていた
3. 贈与の事実を隠していたことが後から発覚
生前贈与は本来、家族の絆を強める行為であるはずですが、不公平感や不信感が残る形になると逆効果です。
「贈与の内容をどう伝えるか」も大切な設計の一部といえるでしょう。
生前贈与を成功させるために知っておきたい実務のポイント

贈与契約書の書き方と注意点
贈与を行う際は、必ず「贈与契約書」を作成することが重要です。
口約束だけでは証拠が残らず、後々の相続争いや税務調査で不利になる可能性があります。
贈与契約書には、以下のような項目を記載するとよいでしょう。
- 贈与者と受贈者の氏名・住所
- 贈与の対象(例:金銭、土地、株式など)
- 贈与日と贈与額
- 「贈与する意思がある」「受け取る意思がある」とする文言
- 双方の署名・捺印
さらに、印紙の貼付(契約書が課税文書に該当する場合)や保管方法にも注意が必要です。
たとえば複数年にわたる贈与では、毎年契約書を作成し、都度記録に残しておくことが望ましいです。
登記・登録免許税・贈与税の関係とは?
不動産を贈与する場合、単に名義を変更するだけでは済まず、以下のような手続きと費用が発生します。
- 贈与による所有権移転登記(法務局への申請)
- 登録免許税(不動産評価額の2%)
- 贈与税(不動産評価額に応じた税率)
ここで注意したいのが、「評価額は時価ではなく固定資産評価額が基準になる」点です。
これにより、市場価格とは異なる額で税額が計算されることがあります。
また、不動産取得税の課税対象になる場合もあり、思わぬ出費となるケースもあるため、贈与前に全体の費用を試算しておくことが重要です。
生前贈与の記録は何を残せばいい?
贈与を行った証拠として、契約書だけでなく「贈与の履歴」も大切です。
たとえば以下のようなものが有効です。
- 贈与時の通帳の振込履歴(贈与者→受贈者の明細)
- 贈与金の使用目的がわかる領収書や記録
- 贈与契約書の控えと保管記録
これらの書類は、万が一の税務調査や相続時の紛争時に、贈与の正当性を証明する根拠となります。
複数年に分けた贈与計画の立て方
高額な財産を一度に贈与してしまうと、多額の贈与税が発生するリスクがあります。
そのため、毎年の非課税枠を利用して、数年かけて計画的に贈与するという方法がよく使われます。
ただし、注意点として、
- あらかじめ「毎年110万円ずつ贈与する」などの取り決めをしない
- 毎年、契約書や振込日を変えることで形式的贈与とならないようにする
こうした工夫により、税務署からの否認リスクを下げることができます。
贈与するタイミングはいつがいい?年齢・資産規模・家庭事情から考える

「早すぎても遅すぎてもダメ」な理由とは
生前贈与は「いつから始めるか」が非常に重要です。
早すぎると自分の老後資金が足りなくなるリスクがあり、遅すぎると相続開始前の贈与が税制上不利になることがあります。
特に2024年以降は、「相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になる」というルールがあるため、「余裕を持った贈与スケジュール」がより一層大切になりました。
年齢・健康・資産の種類によってベストタイミングは違う
- 健康状態がよく、経済的に余裕があるうちは「暦年贈与」でゆっくり進める
- 高齢になってからは「相続時精算課税制度」も検討する
- 不動産などの管理が難しくなってきたら、その資産だけ先に贈与する
このように、贈与する人のライフステージによって最適なタイミングと手法が異なるため、一律の答えはありません。
子や孫が成人しているかどうかも影響する?
贈与の受け手が未成年の場合、契約行為を行えないため親権者の同意が必要です。
さらに、実際に管理・使用していることを示す必要があり、形式的な贈与とみなされないよう注意が必要です。
一方で、成人した子や孫であれば自分名義の口座で管理できるため、贈与が成立していることを明確に示しやすいというメリットがあります。
不動産や高額資産の生前贈与に特有の注意点
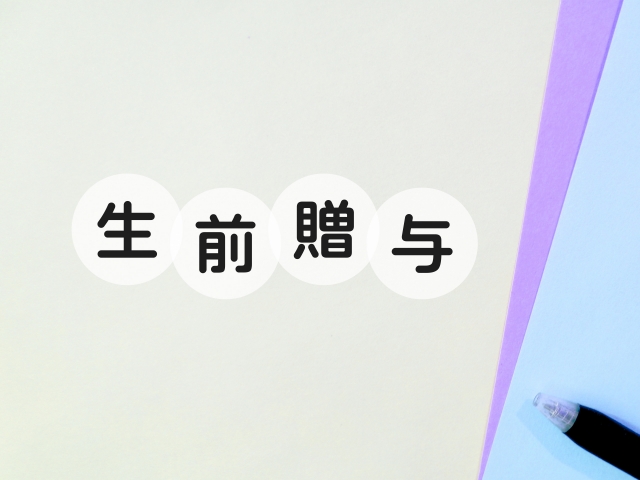
不動産の評価額と税負担の関係
不動産を贈与する際の贈与税額は、「固定資産評価額」や「路線価」に基づいて算出されます。
そのため、思っているより高額な税金が発生することも少なくありません。
さらに、評価額が高いと、登録免許税や不動産取得税なども連動して増加するため、事前の資産評価と費用シミュレーションが不可欠です。
共有名義にした場合のリスクと後悔
贈与時に「複数の子どもに平等に分けたい」との理由から、不動産を共有名義にするケースがあります。
しかしこれは、後にトラブルの火種になることも。
- 売却や賃貸で意見が分かれやすい
- 修繕や管理の責任が曖昧になる
- 相続のたびに権利関係が複雑化する
共有名義は、公平さを重視するあまり実務上の不便さや感情的なしこりを生みやすい選択肢であるため、慎重に検討する必要があります。
贈与後も住み続けたい場合はどうする?
親が住んでいる家を子に贈与したいが、自分は引き続きそこに住みたい――
そんなケースでは、「使用貸借契約」という形で住み続ける方法があります。
この契約を明文化しておけば、
- 税務署に対しても形式的贈与ではないと主張できる
- 他の相続人からの疑念も回避しやすい
つまり、実態と形式の整合性を取ることがトラブル回避の鍵になります。
生前贈与Q&A|よくある質問と答え
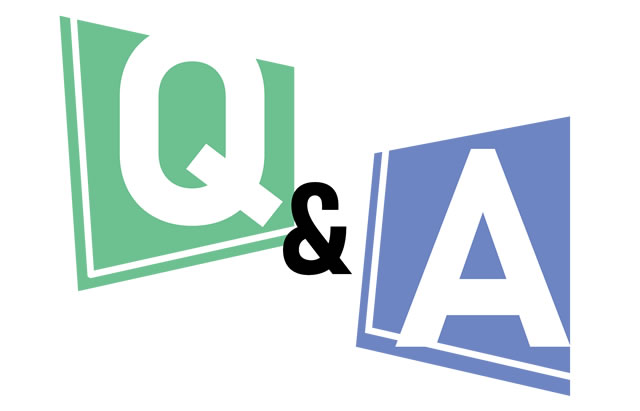
Q. 孫への生前贈与は可能ですか?
A. はい、可能です。
贈与は親子に限らず、孫や兄弟などにも行えます。
ただし、未成年の場合は親権者の同意が必要になる点に注意しましょう。
Q. 贈与を受けた側に知らせずに贈与はできますか?
A. 基本的にはできません。
贈与は「贈る側・受け取る側双方の合意」があって初めて成立します。
勝手に名義変更しただけでは、贈与とは認められません。
Q. 家を贈与する際に名義変更だけで済ませても問題ありませんか?
A. 名義変更だけでは不十分です。
登記、贈与契約書、贈与税の申告などが必要です。
とくに贈与税の申告漏れには注意が必要です。
Q. 毎年110万円ずつ贈与しても問題ありませんか?
A. 問題はありませんが、「最初から数年分をまとめて計画していた」と判断されると、課税される可能性があります。
毎年贈与契約書を作り、履歴を残すことが重要です。
Q. 夫婦共有の財産を妻から子へ贈与してもいいの?
A. 原則として、財産の名義人が贈与者となります。
共有名義の財産を贈与する場合は、各共有者がそれぞれの持分に応じて贈与することが必要です。
まとめ|「贈ること」がゴールではない。未来の家族の安心のために

生前贈与は、節税や相続対策としての側面だけでなく、「今のうちに思いを託したい」という家族へのメッセージでもあります。
制度やルールを知らずに進めてしまうと、税務上のトラブルや家族間の対立を招く恐れもあるため、正しい知識と丁寧な手続きが欠かせません。
- 贈与は「制度」であり「行為」であり「感情」でもある
- 節税のためだけに贈与するのではなく、家族との対話を大切にすることが成功のカギ
- 一度に進めなくても構いません。できるところから少しずつ進めていく姿勢が未来を守ります
生前贈与は、あなたの想いと財産を、安心して次の世代へ託すための「今できる選択」です。
- 相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説
- 税務調査に強い税理士の探し方|調査対応で損しないための選び方と依頼のタイミング
- オンライン税理士とは?|非対面でも安心して任せられる税務サポートの選び方と活用術
- 顧問税理士なしでも会社経営はできる?メリット・デメリットから考える賢い選択とは
- 税理士を変更したいと思ったら|乗り換えのタイミングと手順、よくある不安への対処法
- 飲食店経営に強い税理士を探すには?原価率・売上管理・助成金に精通した税理士の選び方
- 建設業に強い税理士とは?|経審・工事台帳・外注管理まで対応できる税理士の選び方と活用術
- ネットショップ・ECに強い税理士とは?複数チャネル・在庫管理・売上集計の悩みをプロがサポート
- 開業医・歯科医師のための税理士選び|医療経営を支える専門サポートとは
- 大家さんのための税理士活用ガイド|賃貸経営で差がつく節税・申告・相談のポイント
- 確定申告のやり方は?e-Taxを使った書類作成と申告方法をわかりやすく解説
- 投資で確定申告が必要なケースとは?株・FX・仮想通貨の違いや注意点を徹底解説
- 副業で確定申告が必要になるのはこんなとき|基準・注意点・よくある誤解を徹底解説
- 不動産の売却で確定申告が必要になるケースと住宅ローン控除の注意点を徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
全国の相続の手続き完全ガイド|まず何をすればいい?期限・流れ・必要書類を徹底解説
▼地域ごとの相続の手続きの情報はこちらから