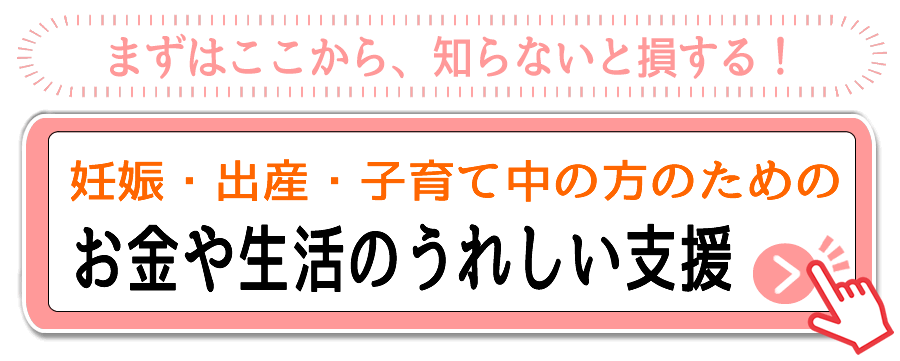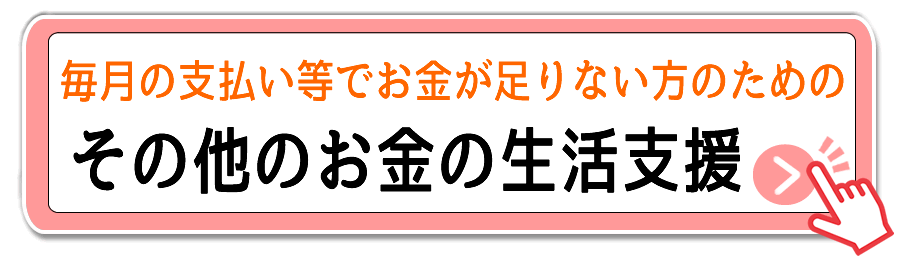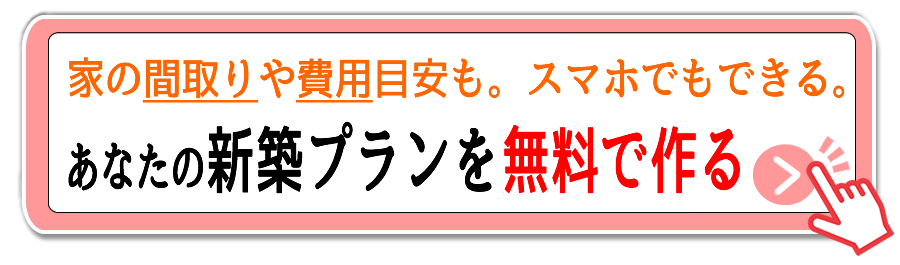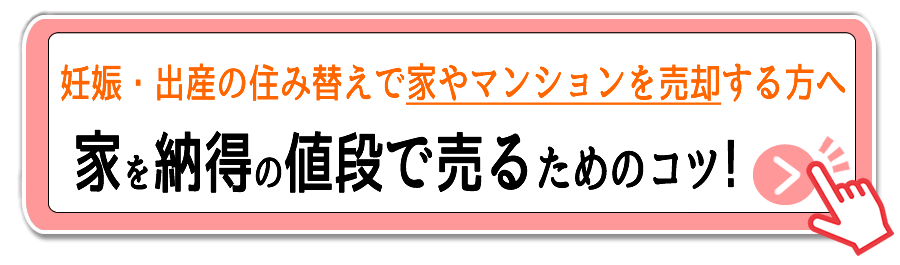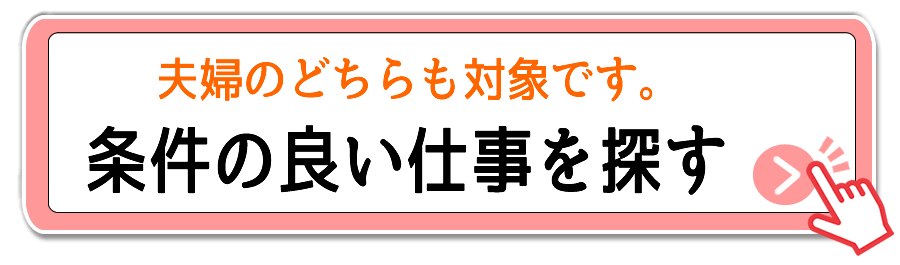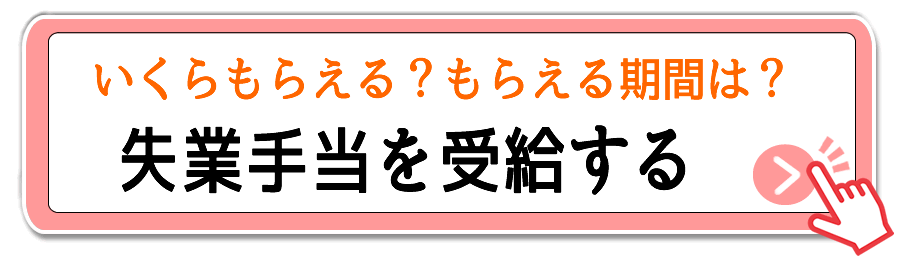妊娠から出産までにもらえるお金まとめ|手当・助成金・補助金をわかりやすく解説

- 【ケース別】もらえるお金の早見表
- 妊娠中にもらえる可能性のあるお金
妊婦健診の助成(妊婦健康診査費用補助),傷病手当金ほか - 出産時にもらえるお金
出産育児一時金,出産手当金など - 出産後にもらえるお金
育児休業給付金,児童手当など - 申請手続きの注意点とタイミング
- よくある質問(FAQ)
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
- 0歳から3歳におすすめの知育玩具・知育おもちゃ|年齢別・目的別にわかる選び方ガイド
妊娠・出産にはどんなお金がもらえるの?

妊娠・出産で受けられる経済的支援とは
妊娠や出産は、新しい命を迎えるかけがえのない時間であると同時に、精神的・身体的、そして経済的にも大きな負担がかかる時期です。
とくに経済面については「いくらくらいかかるの?」「どんなお金がもらえるの?」と不安を感じる方も少なくありません。
実は、妊娠中から出産後にかけて、条件を満たせば国や自治体からさまざまな経済的支援を受けることができます。
中には申請が必要なもの、加入している保険や雇用形態によってもらえる・もらえないが分かれるものもあるため、早めに把握しておくことが大切です。
このページでは、「妊娠から出産までにもらえるお金」だけに焦点を当て、制度の種類や金額、対象者、申請のタイミングなどをわかりやすくご紹介します。
全員がもらえる支援と条件がある支援の違い
妊娠・出産でもらえるお金には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 誰でも原則もらえるもの(全員対象)
→ 妊婦健診の助成、出産育児一時金、児童手当など - 雇用形態や保険加入状況によって変わるもの(条件付き)
→ 出産手当金、傷病手当金、育児休業給付金など
たとえば、会社員として健康保険に加入していれば「出産手当金」が支給されますが、国民健康保険のみの自営業の方には支給されません。
また、「育児休業給付金」は雇用保険の加入状況により、受け取れる人が限られます。
このように、支援制度はすべての人が対象とは限らないため、自分の状況に合わせて確認することが必要です。
「知らずに申請しなかった」で損しないために
支援制度の多くは、「申請しなければもらえない」という仕組みになっています。
とくに出産前後は心も身体も忙しく、情報を集める余裕がない方も多いでしょう。
しかし、制度の内容を知っていれば、事前に準備しておくことができ、必要なときに確実に受け取ることができます。
あとで「そんな制度があるなんて知らなかった…」と後悔しないように、妊娠中の今だからこそ、落ち着いて情報を整理しておきましょう。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
妊娠中にもらえる可能性のあるお金

妊娠中は身体的な変化が大きく、思うように働けなかったり、通院や安静が必要になったりすることも。
この期間にも受け取れる可能性のある支援を見ていきましょう。
妊婦健診の助成(妊婦健康診査費用補助)
妊婦さんの多くが最初に対象となるのが、「妊婦健診」に対する助成制度です。
妊娠が判明し、母子健康手帳を受け取ると、同時に「妊婦健康診査受診票(補助券)」が配布されます。
これは妊婦健診にかかる費用の一部または全額を自治体が負担する制度で、多くの市区町村で14回分以上の健診に適用されています。
ただし、助成内容や回数、金額は自治体によって異なります。
たとえば東京都23区と地方の町村とでは、助成上限に数万円単位の差があることも。
また、転居した場合は新しい自治体での再手続きが必要になるため注意が必要です。
傷病手当金(つわりや切迫流産などで休職した場合)
妊娠中の体調不良により、勤務が困難になった場合、「傷病手当金」が受け取れる可能性があります。
対象となるのは、健康保険(被用者保険)に加入しており、以下の条件を満たす方です。
- 医師の指示で仕事を休む必要がある
- 連続して3日間以上仕事を休んでいる
- 4日目以降も労務不能状態が続いている
たとえば、つわりがひどく出勤できない・医師から安静指示が出たなどの場合、医師の診断書があれば申請可能です。
支給額は、給与のおおよそ3分の2相当(細かい計算あり)。
出産手当金とは重複しないため、どの期間にどちらを優先すべきかも考える必要があります。
その他、自治体独自の妊娠支援制度(例:交通費・妊婦タクシー補助など)
一部の自治体では、妊娠中の通院や生活支援を目的とした独自の補助制度を設けています。
例としては:
- 妊婦タクシー利用補助(回数券の配布、1回500円助成など)
- マタニティバス定期券の割引
- 妊婦専用の相談窓口・給付金(例:都道府県単位での母子健康支援)
これらは全国一律ではなく、自治体ごとに大きな差があります。
「〇〇市 妊娠 助成」などで検索したり、母子手帳の交付時に窓口で直接聞くことで、地域の情報を確認できます。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
出産時にもらえるお金

出産のタイミングで受け取れる支援制度は、誰でももらえるものと就業状況によってもらえるものに分かれます。
出産費用は決して安くないため、これらの支援は非常に心強い存在です。
出産育児一時金(全国共通で原則もらえる)
「出産育児一時金」は、健康保険または国民健康保険に加入している方が対象で、原則として一児につき50万円が支給される制度です。
支給される条件は以下の通りです:
- 妊娠12週(85日)以上の出産であること(早産・流産・死産も含む)
- 健康保険または国民健康保険に加入している本人、またはその扶養者であること
この制度は、会社員・自営業・専業主婦などを問わず、基本的に全員が対象となります。
また、実際の出産費用が50万円に満たなかった場合でも、差額を自分で受け取ることができます(直接支払制度を利用している場合は病院を通じて精算)。
直接支払制度の利用について
ほとんどの医療機関では、「直接支払制度」を採用しており、本人が費用を立て替えることなく、出産育児一時金を医療機関に直接支払ってもらうことができます。
ただし、分娩施設によっては非対応のところもあるため、妊婦健診の段階で確認しておくと安心です。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
出産手当金(会社員・公務員の方が対象)
出産手当金とは、出産のために仕事を休んだ期間中に、給与の代わりとして支給されるお金です。
主に対象となるのは、会社員・公務員などで健康保険に加入している女性本人です(国民健康保険の方は対象外)。
支給対象期間は以下の通りです:
- 出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)
- 出産後56日
この間に仕事を休んだ場合、1日あたり【支給開始前1年間の標準報酬日額 × 2/3】が支給されます。
たとえば月収30万円の場合、1日あたり約6,600円前後が支給され、トータルで40万円〜50万円程度となるケースもあります。
育休と重なる場合の注意点
出産手当金と育児休業給付金は同時に受け取ることはできません。
基本的には、出産手当金の支給期間が終わってから育児休業給付金が開始される仕組みです。
出産後の復帰タイミングや職場との調整によって、受け取れる金額も変わってくるため、会社の人事や社会保険担当者に早めに相談しましょう。
国民健康保険加入者はどうなる?
自営業・フリーランス・専業主婦など、国民健康保険に加入している方も「出産育児一時金」は対象になりますが、「出産手当金」はもらえません。
ただし、自治体によっては独自に「出産祝金」や「助成制度」を設けていることもあります。
たとえば:
- 〇〇市:第1子に3万円の出産祝い金
- △△町:出産時の交通費補助(タクシー券支給)
このような制度は自治体ごとのホームページや母子手帳の配布時に案内されることが多いため、忘れずに確認しておきましょう。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
出産後にもらえるお金

無事に出産を終えたあとも、育児がスタートするまでの間、経済的支援が受けられる制度があります。
とくに育児休業を取得する方にとっては重要な給付制度が整っています。
育児休業給付金(雇用保険加入者向け)
育児休業給付金は、雇用保険に加入しており、一定の条件を満たした方が対象となる制度です。
支給対象の条件は以下の通りです:
- 育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育児休業を取得し、会社に復帰する予定がある
支給額の目安は以下の通りです:
- 育休開始〜180日まで:休業前賃金の67%
- 181日以降:休業前賃金の50%
つまり、最大で1年6ヶ月程度、一定額の給付を受けながら育児に専念することができるということになります。
なお、パートや派遣社員でも条件を満たせば対象となるため、雇用形態にかかわらず確認しておくと良いでしょう。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
児童手当(出産後に申請可能な継続支援)
児童手当は、0歳から中学卒業までの子どもを養育している保護者に支給される制度で、出生届の提出とともに申請します。
支給額は子どもの年齢・人数によって以下の通りです(2025年10月時点の情報):
| 年齢 | 月額(1人あたり) |
|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳〜小学校修了前 | 第1・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 |
| 中学生 | 10,000円 |
なお、所得制限により支給額が変わる場合があるため、詳細は自治体で確認しましょう。
自営業・フリーランスの場合はどうなる?
自営業やフリーランスの方は、「育児休業給付金」は対象外となるのが原則です。
ただし、児童手当や出産育児一時金は受け取ることができますし、自治体によっては独自の育児支援(例:産後ヘルパー派遣、育児応援金)を行っているケースもあります。
また、国民年金保険料の産前産後免除制度など、育児期間中の負担を軽減する制度もあるため、あわせて調べておくと良いでしょう。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
【ケース別】もらえるお金の早見表

妊娠・出産に関する経済的支援は、誰でも受け取れるものと雇用形態・保険の加入状況によって異なるものがあります。
ここでは主な立場別に、どのようなお金がもらえるかを一覧で整理します。
会社員・公務員の妊婦さんがもらえるお金
会社員や公務員など、健康保険(被用者保険)と雇用保険の両方に加入している方は、もっとも多くの制度を利用できる立場です。
| もらえるお金 | 条件 |
|---|---|
| 妊婦健診の助成 | 自治体により実施(受診券が配布される) |
| 出産育児一時金 | 健康保険加入者は全員対象(一児につき50万円)→詳細はこちら |
| 出産手当金 | 出産で休職した場合に支給(42日前〜56日後)→詳細はこちら |
| 傷病手当金 | つわり・切迫早産などで長期休業した場合→詳細はこちら |
| 育児休業給付金 | 雇用保険加入+一定の勤務実績がある場合→詳細はこちら |
| 児童手当 | 出産後に申請。0歳から中学卒業まで支給→詳細はこちら |
雇用保険に加入していることで、出産手当金と育児休業給付金の両方を受けられる点が大きなメリットです。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
フリーランス・自営業の妊婦さんがもらえるお金
フリーランスや個人事業主の場合、国民健康保険のみに加入している方が多く、被用者向けの制度は利用できません。
| もらえるお金 | 条件 |
|---|---|
| 妊婦健診の助成 | 自治体により実施(全国共通) |
| 出産育児一時金 | 国民健康保険加入者も対象(一児につき50万円)→詳細はこちら |
| 児童手当 | 出産後に申請。0歳から中学卒業まで支給→詳細はこちら |
| 傷病手当金 | ×(対象外) |
| 出産手当金 | ×(対象外) |
| 出産育児一時金 | ×(対象外) |
「会社員より不利」と感じるかもしれませんが、出産育児一時金と児童手当は受け取ることが可能です。
また、産後しばらく仕事を休む必要がある方は、自治体の産後ケア事業などを活用することで生活支援を得られる場合もあります。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
無職・専業主婦の場合にもらえるお金
専業主婦や現在無職の方は、自身の保険加入状況や扶養の有無によって支援内容が変わります。
| もらえるお金 | 条件 |
|---|---|
| 妊婦健診の助成 | 自治体により実施 |
| 出産育児一時金 | 夫の扶養に入っていれば健康保険経由で支給→詳細はこちら |
| 児童手当 | 出産後に申請(夫婦の所得合算で支給対象が決まる→詳細はこちら) |
| 出産手当金 | ×(自分で健康保険加入していない限り対象外) |
| 出産育児一時金 | ×(雇用保険加入していないため対象外) |
出産手当金や育休給付金は受け取れない場合が多いですが、出産育児一時金と児童手当は扶養関係を通じて受給可能です。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
ひとり親・生活が苦しい場合の追加支援
家庭の事情により生活が厳しい方には、生活保護とは別に一時的な経済支援を受けられる制度があります。
出産費貸付制度(健康保険組合や自治体)
出産育児一時金の支給までに時間がかかる場合、一時的に出産費用を立て替えてもらえる制度です。
保険組合や自治体を通じて、出産費用の貸付(無利子)が受けられます。
生活福祉資金貸付(緊急小口資金)
妊娠・出産による一時的な資金不足に対応するため、社会福祉協議会を通じて数万円〜数十万円の貸付を受けられる制度もあります。
審査はありますが、無利子・据置期間ありの支援が多く、困ったときのセーフティネットとして活用可能です。
児童扶養手当(出産後)
出産後は、母子家庭・父子家庭の方に対して児童扶養手当が支給される可能性もあります。
申請には所得制限や扶養状況の確認が必要ですが、経済的支援の柱となる制度です。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
申請手続きの注意点とタイミング
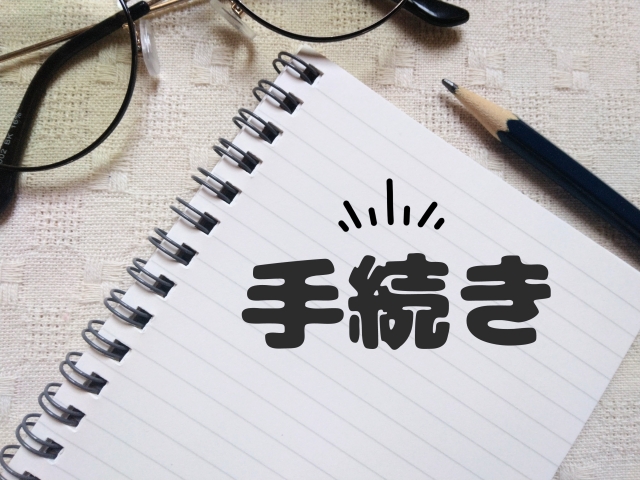
妊娠・出産に関する給付金や助成金は、「申請しなければもらえない」ものが大半です。
また、制度ごとに申請時期や必要書類、提出先が異なり、うっかりしていると受け取りのタイミングが遅れる、あるいは受け取れないことも。
この章では、申請に関する基本的な注意点と、事前に準備しておくべきポイントをご紹介します。
いつ・どこで申請すればよい?
支援制度によって、申請のタイミングは異なります。
以下に代表的な制度の申請時期と提出先を整理します。
| 制度名 | 申請時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 妊婦健診の助成 | 妊娠が判明したらすぐ | 市区町村の保健センター |
| 出産育児一時金 | 妊娠中〜出産後すぐ | 健康保険組合または国保の窓口 |
| 出産手当金 | 出産後にまとめて | 健康保険組合(会社経由が多い) |
| 傷病手当金 | 医師の診断後すぐ | 健康保険組合(会社経由が多い) |
| 育児休業給付金 | 育休開始後すぐ | ハローワーク(会社経由が多い) |
| 児童手当 | 出生届と同時に | 市区町村役所の子育て支援課 |
制度によっては「〇日以内に提出」といった期限があるため、出産後のバタバタの中で忘れないよう、事前に一覧でまとめておくのが効果的です。
産後すぐは大変!妊娠中から準備しておくことが大切
出産後は、体力も回復しきらない中での育児や通院などで手一杯になります。
そのため、出産前に申請書類をそろえたり、必要事項を家族と共有しておいたりすることが、スムーズな受給につながります。
準備しておきたいことの例:
- 各種申請書類のダウンロードや入手(自治体HP・会社経由)
- 医師の証明が必要な書類は、妊婦健診時に相談
- 保険証、印鑑、通帳コピー、身分証などのコピーを事前に用意
- 提出先の窓口の場所・担当者名をメモしておく
また、夫や両親などに代行してもらえる手続きもあるため、本人が難しいときの代替対応も視野に入れておきましょう。
証明書・診断書・書類の記載ミスに注意
支援金の申請に必要な「医師の診断書」や「出生証明書」「住民票」「就労証明書」などは、不備があると再提出になることがあります。
以下のような点に注意してください:
- 記載日・署名・押印の漏れがないか確認
- 医療機関名や担当医の氏名は明記されているか
- 書類によってはコピー不可(原本のみ)なものもある
- 会社の証明書類は総務・人事と連携して事前に準備
また、育児休業給付金などは支給までに数ヶ月かかることがあるため、手続きの進捗も定期的に確認しておくと安心です。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
妊娠中や出産前後の不安を軽くするために

妊娠や出産を迎える女性にとって、身体の変化や将来への不安は避けられないものです。
とくに経済面の不安は、出産を喜ぶ気持ちに影を落とすこともあるでしょう。
「いくらかかるのか想像がつかない」
「休職中に収入が減るけれど、やっていけるの?」
「申請って難しそう、忘れずにできるかな…」
そんな不安に、ひとつひとつ丁寧に向き合っていくことが、安心してお産を迎える第一歩になります。
お金の不安が心に与える影響
妊娠中はホルモンバランスの変化によって、気分の浮き沈みが激しくなることがあります。
加えて、「出産ってお金がかかるらしい…」「仕事を休むけど生活は大丈夫かな…」と不安が重なると、メンタル面にも大きな負担となり得ます。
お金のことは誰かに相談しにくく、インターネットで調べても情報が複雑だったり、専門用語が難しかったりして、かえって不安が強まってしまうことも。
だからこそ、「知ること」が最初の心のケアにつながります。
もらえるものを把握するだけで気持ちがラクになる
実際に申請する前であっても、「自分はこの制度の対象になりそう」「いくらくらいもらえそう」という見通しを立てられるだけで、不安は軽くなります。
たとえば──
「育児休業給付金があれば、半年間は収入が途切れない」
「出産育児一時金で入院費の負担が減る」
「児童手当を毎月もらえるなら、オムツ代くらいにはなるかも」
このように、制度を“知ること”は、未来に対する安心感を生み出す行動でもあります。
制度は変わることもあるので、自治体や保険窓口に確認を
妊娠・出産に関する制度は、国の法改正や自治体の方針変更により、年度ごとに内容が更新されることがあります。
実際に申請する際は、以下のような手段で最新情報を確認することをおすすめします:
- 住んでいる市区町村の公式サイト
- 健康保険組合の相談窓口
- ハローワークや会社の人事部門
- 病院のソーシャルワーカーや助産師への相談
「申請期限を過ぎてしまった」「制度が変わっていて受けられなかった」という事態を避けるためにも、“今の情報”を得る努力が大切です。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
よくある質問(FAQ)

Q. 無職の妊婦でももらえるお金はありますか?
A. はい。
出産育児一時金や児童手当は、就労の有無にかかわらず受給可能です。
健康保険の被扶養者であっても、配偶者の加入する保険から出産育児一時金が支給されるケースが多いため、扶養関係を確認しましょう。
ただし、出産手当金や育児休業給付金は、雇用保険や健康保険にご自身で加入していない場合は対象外となります。
Q. 出産手当金と育児休業給付金は同時にもらえますか?
A. いいえ、両方を同時に受給することはできません。
原則として、出産手当金(産前42日・産後56日)が終了したあとに、育児休業給付金の支給が開始されます。
受給時期が連続しているため、育児に集中しやすい制度設計にはなっていますが、育休の申請タイミングを会社と相談しておくことが大切です。
Q. 出産育児一時金はどうやって申請しますか?
A. 医療機関が「直接支払制度」に対応している場合は、病院側が保険組合とやり取りを行い、自己負担が減る仕組みになっています。
ご自身で申請する場合は、加入している健康保険組合または市区町村の国民健康保険窓口で手続きします。
出産前後でバタバタしないよう、出産前に確認・準備しておくのがおすすめです。
Q. フリーランスでももらえる手当はありますか?
A. フリーランスや自営業の方は、出産育児一時金や児童手当の対象にはなりますが、出産手当金・育児休業給付金・傷病手当金は基本的に対象外です。
ただし、産後のサポートとして自治体の訪問支援・産後ケア・助成金が活用できるケースもあります。
また、出産費用の一時貸付制度や、生活福祉資金貸付制度などの相談も検討できます。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 9割の妊婦さんがコリン不足!葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
まとめ|妊娠から出産まで、必要な支援は必ずあります

妊娠・出産に関する支援制度は、国や自治体によって多数用意されています。
「自分には関係ないかも」「どうせもらえないだろう」とあきらめず、まずは知ることから始めてください。
- 妊婦健診は、ほとんどの自治体で助成券が配布されます
- 出産には出産育児一時金が支給され、50万円の負担軽減になります
- 会社員や公務員は出産手当金・育児休業給付金の対象になる場合が多く、産休・育休中の収入を支える仕組みも整っています
- フリーランス・専業主婦・無職の方も、もらえる支援は必ずあります
- ひとり親家庭や生活に不安のある方には、自治体の独自支援も存在します
出産は人生の大きな節目であると同時に、心も身体も大きく揺れる時期です。
お金の不安を軽くし、少しでも安心してその日を迎えられるように、必要な情報を手に入れましょう。
そして何より、自分を責めたり、無理をしすぎたりせず、「頼れる制度は頼っていい」という気持ちでいてください。
あなたと、これから生まれてくる小さな命に、穏やかな時間が流れますように。
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 【コリンとは?】葉酸だけじゃない!妊娠・出産期に重要な栄養素「コリン」の摂り方ガイド
- 0歳から3歳におすすめの知育玩具・知育おもちゃ|年齢別・目的別にわかる選び方ガイド
- 妊娠から出産までにもらえるお金まとめ|手当・助成金・補助金をわかりやすく解説
全国の妊娠から出産後までの手続きガイド|母子手帳・出生届・保険や給付金の届け出まで完全解説
▼地域ごとの妊娠から出産後までの手続きの情報はこちらから