障害者年金をもらえる条件と対象者と金額

障害者年金とは、病気やけがによって障害を負い、生活や仕事に支障をきたすようになった方々に対して支給される公的年金制度です。
日本の年金制度は、国民年金と厚生年金の二本柱で構成されており、それぞれに対応した障害年金が存在します。
具体的には、国民年金に加入している方には「障害基礎年金」、厚生年金に加入している方には「障害厚生年金」が支給されます。
国民年金加入者がもらえる障害基礎年金を受給する条件と金額

障害基礎年金は、国民年金の被保険者が障害を負った際に支給される年金です。
受給のためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
第一に、障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であることが求められます。
具体的には、初診日が国民年金の被保険者であった期間、もしくは20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた期間であることが必要です。
第二に、初診日から1年6か月経過した日、またはその期間内に治った日(これを「障害認定日」といいます)において、障害等級表の1級または2級に該当する程度の障害状態であることが条件となります。
第三に、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であることが求められます。
ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合、直近1年間に保険料の未納がなければ受給資格を満たす特例も設けられています。
障害基礎年金の支給額は、定額で設定されています。
さらに、受給者に生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子どもがいる場合、または20歳未満で障害等級1級または2級の子どもがいる場合には金額が加算されます。
厚生年金加入者がもらえる障害厚生年金を受給する条件と金額
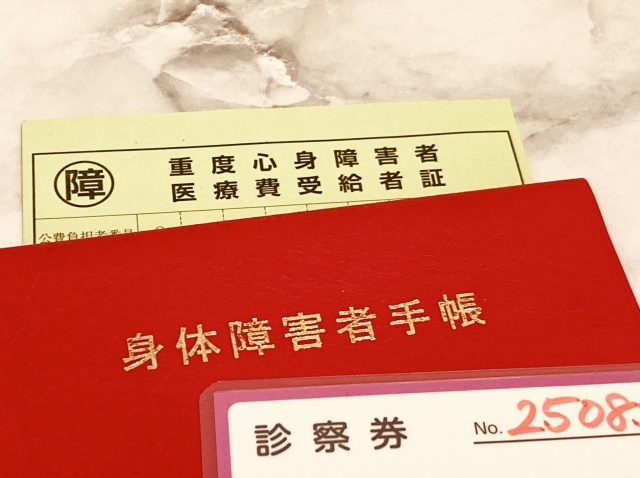
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがによって障害を負った場合に支給される年金です。
障害基礎年金と同様に、初診日が厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。
障害認定日において、障害等級表の1級から3級に該当する障害状態であることが条件となります。
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして支給されるため、1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。
3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。
また、3級に該当しない軽度の障害であっても、一定の要件を満たす場合には「障害手当金」が一時金として支給されることがあります。
障害厚生年金の支給額は、被保険者期間中の平均標準報酬額と加入期間に基づいて計算されます。
そのため、個々の加入状況によって金額は異なります。
1級の場合は、計算された年金額の1.25倍が支給され、2級の場合はそのままの金額が支給されます。
3級の場合は、最低保障額が設定されています。
厚生年金の障害手当金とは

障害手当金は、障害厚生年金の3級に該当するほど重度ではないものの、障害の程度が一定の基準を満たしている場合に支給されます。
これは、障害厚生年金とは異なり、継続的に支給される年金ではなく、一度限りの給付である点が特徴です。
障害手当金を受け取るためには、初診日から1年6か月後、またはその期間内に症状が固定した時点で障害認定を受け、その障害の程度が「障害手当金の対象」となる状態に該当することが求められます。
障害手当金の支給額は、受給資格者の加入期間中の平均標準報酬額を基に計算され、支給される額は基本的に「障害厚生年金の3級の年金額の2年分」に相当する金額となります。
これは、一時的な経済的支援を目的としており、障害状態が比較的軽い場合でも、生活の補助として一定の金銭を支給することで、生活再建を支援する制度となっています。
特別障害給付金とは

特別障害給付金とは、国民年金の任意加入対象であったにもかかわらず、未加入であったために障害基礎年金等を受給できない障害者の方々に対して支給される給付金です。
具体的には、昭和61年3月以前に学生であった方や、昭和36年4月から昭和61年3月までの間にサラリーマンの配偶者であった方で、任意加入していなかったために障害基礎年金を受給できない方が対象となります。
この給付金は、福祉的措置として平成17年4月に創設されました。
病気やケガでもらえる傷病手当金
- 北海道
- 青森県
- 秋田県
- 岩手県
- 山形県
- 宮城県
- 福島県
- 群馬県
- 栃木県
- 茨城県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 石川県
- 福井県
- 富山県
- 山梨県
- 長野県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 岐阜県
- 滋賀県
- 奈良県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 和歌山県
- 広島県
- 岡山県
- 鳥取県
- 島根県
- 山口県
- 香川県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 大分県
- 長崎県
- 佐賀県
- 熊本県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県












