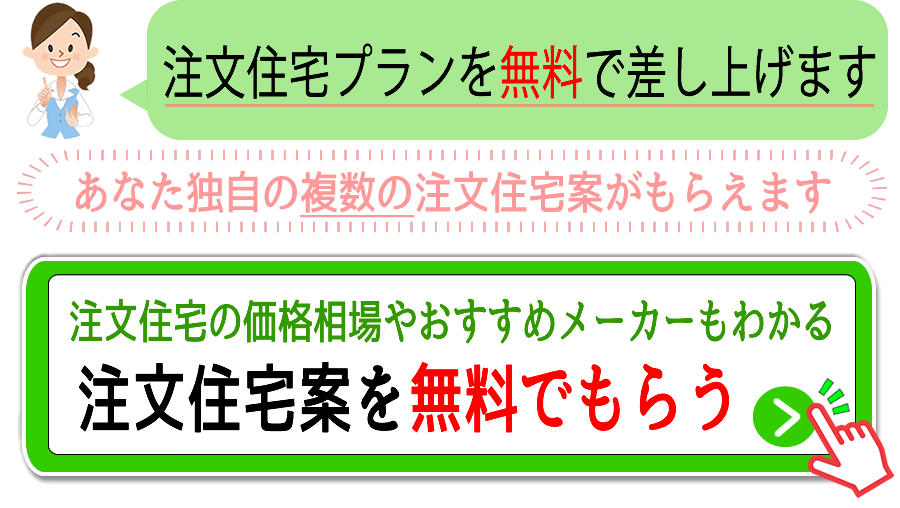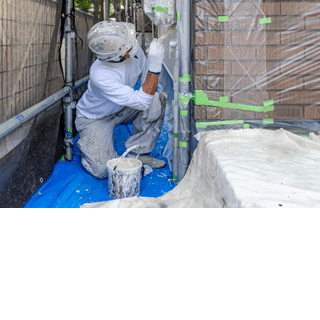PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説

- はじめて家を建てるなら知っておきたい住宅ローンの基本
- 住宅ローンの選び方で失敗しないために
- どの金融機関を選ぶ?住宅ローンの借入先比較
- 住宅ローンの審査で見られるポイント
- 住宅ローンを組むときに考えておきたい「保険」と「備え」
- よくある失敗例と後悔しないためのポイント
- これから住宅ローンを組む方に伝えたい大切なこと
- まとめ|住宅ローンは知識と準備で安心できる
- よくある質問(FAQ)
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ
はじめて家を建てるなら知っておきたい住宅ローンの基本

そもそも住宅ローンとは?
住宅ローンとは、マイホームの購入資金として金融機関から借りる長期の借入金のことです。
土地代や建物代のほか、場合によっては諸費用や税金、外構工事費用などにも使える場合があります。
家づくりの資金は大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 土地取得費(土地代金、登記費用など)
- 建物建築費(本体工事費、付帯工事費など)
- 諸費用(ローン手数料、火災保険料、引っ越し代など)
すべてを現金で支払える人は多くありません。
そのため、多くの方が住宅ローンを利用して、数千万円単位の資金を長期間にわたって返済していく仕組みを選んでいます。
注文住宅ならではのローンの特徴とは?
注文住宅を建てる場合、土地の購入と建物の建築が別工程になることがほとんどです。
建売住宅とは違い、「土地を買ってから設計・工事に入る」という流れのため、住宅ローンの使い方やタイミングも複雑になります。
とくに注意したいのは、工事が進むごとにお金が必要になるという点です。
たとえば、着工金・中間金・最終金といった支払いが発生するため、住宅ローンの融資実行時期と支払いタイミングがズレることもあります。
そのため、「つなぎ融資」や「土地先行融資」といった制度を利用するケースもあります。
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
住宅ローンの選び方で失敗しないために

金利タイプはどう選ぶ?固定金利・変動金利・ミックスの違い
住宅ローンを選ぶうえで最も重要なのが金利タイプです。
金利の種類には主に以下の3タイプがあります。
| 金利タイプ | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 固定金利型 | 借入時に決まった金利が返済終了まで変わらない | 将来の金利変動が不安な人、計画的に返済したい人 |
| 変動金利型 | 半年ごとに金利が見直される。
最初は金利が低い |
短期間で返済予定の人、リスクを理解できる人 |
| 固定期間選択型 | 最初の数年間は固定、その後は変動または再固定 | 中期的にライフプランが見えている人 |
固定金利は返済額が一定で安心感がある一方、変動金利よりも初期金利が高めです。
一方で、変動金利は低金利が魅力ですが、将来金利が上がるリスクも考慮する必要があります。
近年では、両者を組み合わせた「ミックス型(固定+変動)」を選ぶ方も増えています。
返済期間と借入額のバランスを考える
住宅ローンを組む際に、多くの方が「いくら借りられるか」に注目しがちですが、本当に大切なのは『いくらなら返せるか』という視点です。
例えば、借入可能額が5000万円でも、家計に無理が出るようであれば、その借入はリスクになります。
「毎月いくらなら無理なく払えるか」から逆算して借入額を決めるのが理想です。
また、返済期間も重要です。
返済期間が長ければ毎月の負担は軽くなりますが、総返済額は増える傾向にあります。
返済期間別のメリット・デメリット
| 返済期間 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 短め(15〜25年) | 総利息が少ない、老後前に完済できる | 毎月の返済額が高くなる |
| 長め(30〜35年) | 毎月の負担が少なく余裕をもてる | 総支払額が増える、完済が遅れる |
諸費用や手数料も忘れずに
住宅ローンを利用する際は、借入額とは別に発生する費用が多くあります。
- 事務手数料(数万円〜数十万円)
- ローン保証料(保証会社を利用する場合)
- 団体信用生命保険料(金利に含まれる場合が多い)
- 登記費用や印紙代
これらを合計すると、数十万円〜100万円以上になることもあります。
住宅購入費とは別に「諸費用の準備」も計画的に行うことが大切です。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
どの金融機関を選ぶ?住宅ローンの借入先比較

銀行系住宅ローンの特徴
住宅ローンの借入先として最も一般的なのが、メガバンクや地方銀行などの「銀行系ローン」です。
銀行系ローンは店舗があり、対面で相談できる安心感があります。
住宅ローンセンターなどで専門のアドバイザーに相談できるため、はじめての方にも向いている選択肢です。
ただし、審査はやや厳しめで、年収や勤続年数、信用情報などを重視する傾向があります。
また、保証料がかかる場合が多いため、諸費用も考慮する必要があります。
ネット銀行の住宅ローンは本当にお得?
ここ数年で人気が高まっているのが、ネット銀行の住宅ローンです。
主なメリットは以下の通りです。
- 金利が非常に低い(特に変動金利型)
- 事務手数料が一律で明確
- Web上で手続きが完結する
一方で、書類の提出ややり取りがすべて非対面で進むため、住宅ローンの仕組みに不安がある方や、柔軟な対応を望む方には向かない場合もあります。
また、団信の保障内容や金利優遇条件が複雑なケースもあるため、事前によく確認することが大切です。
フラット35とは?民間ローンとの違い
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する、長期固定金利型の住宅ローンです。
最大の特徴は、金利が借入時に固定され、完済まで変わらないという点です。
これにより、将来的な返済計画が立てやすいというメリットがあります。
また、自営業者や契約社員の方でも比較的利用しやすいといった柔軟な審査が魅力ですが、金利は変動型よりやや高めになる傾向があります。
住宅の性能(省エネ・耐震など)に応じて金利が優遇される「フラット35S」などの制度もあり、注文住宅にも適した選択肢の一つといえるでしょう。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
住宅ローンの審査で見られるポイント

住宅ローンを借りる際には、金融機関の審査を通過する必要があります。
この審査では、主に以下の点がチェックされます。
年収・年齢・勤続年数などの審査基準とは?
詳しくは別ページ「住宅ローンの審査基準」で解説予定ですが、ここではポイントを簡潔にご紹介します。
- 年収:年収に対して返済額が高すぎないか
- 年齢:完済時年齢が基準内か(多くは75〜80歳未満)
- 勤続年数:安定した勤務履歴(2〜3年以上が目安)
- 雇用形態:正社員が有利だが、近年はフリーランス向けローンも
- 信用情報:過去の借入や返済履歴に問題がないか
借入可能額は一般的に「年収の5〜7倍程度」が目安とされていますが、無理なく返せる金額での計画が重要です。
自己資金(頭金)の重要性
住宅ローンでは、頭金を用意できるかどうかが審査の大きなポイントとなります。
頭金が多いと、借入額が減り、毎月の返済額が軽くなるうえに金利優遇を受けやすいというメリットもあります。
一方で、フルローン(頭金なし)を組むことができる場合もありますが、審査はより慎重に行われ、金利や保証料が高くなるケースもあります。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
住宅ローンを組むときに考えておきたい「保険」と「備え」

団信(団体信用生命保険)とは?
住宅ローンを組むとき、多くの金融機関では団体信用生命保険(団信)への加入が条件となっています。
団信とは、ローンの契約者が死亡または高度障害となった場合に、ローン残債が保険で返済される制度です。
団信に加入しておくことで、家族に住宅ローンの返済負担を残すことなく、住まいを守ることができるため、万が一の備えとして非常に重要な役割を果たします。
最近では、がん保障特約付き団信や三大疾病保障付き団信など、保障内容が手厚くなっているものもあり、自分の健康リスクに応じて選ぶことができます。
火災保険・地震保険もセットで検討を
住宅ローンを組む際には、火災保険への加入が義務付けられているケースがほとんどです。
これは、ローンの担保である建物に万一のことが起きた場合に備えるためで、保険未加入だと融資を受けられないこともあります。
また、地震保険は任意ですが、日本は地震が多いため、加入しておくことでより安心です。
火災保険の内容も幅広く、家財の補償・水災・盗難などに対応するプランも選べるため、必要に応じてプランを比較しましょう。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
よくある失敗例と後悔しないためのポイント

「借りすぎて家計が苦しくなった」
はじめて家を建てる方が陥りやすいのが、「借りられる上限いっぱいに借りてしまう」という失敗です。
ローンの返済に追われてしまい、教育費・生活費・老後資金に回せないといった事態になりかねません。
「借りられる金額」ではなく、「返していける金額」から逆算して住宅ローンを組むことが、最も重要なポイントです。
「金利タイプを間違えた」
変動金利が低いからという理由だけで安易に選ぶと、将来の金利上昇に対応できなくなるリスクがあります。
固定金利で安心を取るか、変動金利で初期負担を抑えるかは、家計状況やライフプランによって異なります。
また、途中で金利タイプを変更できないローン商品もあるため、契約前にしっかり確認することが必要です。
「住宅ローン控除を受けられなかった」
住宅ローン控除は、ローンを利用して家を建てた場合に所得税が減額される制度ですが、要件を満たしていないと適用されません。
たとえば、床面積の基準や入居期限、借入先が対象金融機関であるかなどを確認しなかったために、制度が使えなかったというケースもあります。
こうした制度の活用についても、事前に税務署や住宅支援窓口などで確認しておくと安心です。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
これから住宅ローンを組む方に伝えたい大切なこと

「住宅ローンは組んで終わり」ではない
住宅ローンは契約時の金利や条件だけで判断しがちですが、借りたあとも継続的な見直しや管理が必要です。
たとえば、金利の変動や家計の変化によって、将来的に「借り換え」を検討することもあります。
また、教育費や老後資金など、住宅以外の出費も見越してライフプランを立てることが重要です。
「住宅ローンを返すために働き続けなければならない」と感じるような状況は避け、生活に余裕を持てる借入額と返済計画を心がけましょう。
夫婦でのローン(ペアローン・連帯債務)も検討を
共働き世帯では、夫婦それぞれが住宅ローンを負担する「ペアローン」や「連帯債務」という選択肢もあります。
ペアローンは夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約し、それぞれの収入に応じて返済していく方法です。
住宅ローン控除をそれぞれで受けられるメリットがありますが、事務手数料や団信の負担も2倍になる点には注意が必要です。
連帯債務型は一人が契約者で、もう一人が連帯して債務を負う方法。
こちらも収入合算が可能となり、より多くの借入ができる可能性があります。
どちらの方法も、万が一の離婚や転職などにも備えた話し合いを夫婦間で行っておくことが大切です。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
まとめ|住宅ローンは知識と準備で安心できる

はじめて家を建てるというのは、人生でも大きな節目です。
と同時に、数十年にわたる住宅ローンの返済が始まるタイミングでもあります。
「いくら借りられるか」だけではなく、「いくらなら返していけるか」をベースにした資金計画こそが、住宅ローンを成功させる鍵です。
金利タイプや金融機関の選び方、団信や火災保険といった備えの部分まで、トータルで自分に合った住宅ローンを組むことが大切です。
また、注文住宅の場合は、土地・建物の契約タイミングや中間金の支払いなども関係してきますので、つなぎ融資や土地先行融資などの制度についても理解しておくと安心です。
不安な点は、早めに住宅会社や金融機関、住宅ローンアドバイザーなどに相談することも忘れずに。
未来の自分と家族が安心して暮らせる住まいを手に入れるために、じっくりと準備して、後悔のない住宅ローン選びを進めてください。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
よくある質問(FAQ)

Q. 注文住宅の場合、どのタイミングで住宅ローンの返済が始まりますか?
住宅ローンの返済開始は、通常は融資が実行された翌月から始まります。
注文住宅では建物完成時に一括融資されるため、建物引き渡し後から返済開始となるケースが一般的です。
ただし、つなぎ融資を利用した場合は、工事中に利息のみ返済が発生します。
Q. ローンの支払いとは別に、家を建てたあとにもお金がかかりますか?
はい、固定資産税や都市計画税、火災保険・地震保険の更新費用、メンテナンス費用などがかかります。
家を建てたあとの維持費も踏まえて、毎月の支出をトータルで見積もっておくことが大切です。
Q. 住宅ローンの返済中に繰上返済はできますか?
はい、多くの住宅ローンでは、一部または全額の繰上返済が可能です。
繰上返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があり、利息を節約したい場合は期間短縮型がおすすめです。
繰上返済には手数料がかかる場合もあるので、金融機関の条件を事前に確認しましょう。
Q. 火災保険と地震保険には必ず入らなければいけませんか?
火災保険は、住宅ローンの契約条件として加入が義務付けられていることがほとんどです。
一方、地震保険は任意加入ですが、日本の地震リスクを考慮すると加入を検討する方が多く、火災保険とセットで申し込むと割引がある場合もあります。
- 住宅ローン審査の年収・年齢基準とは?落ちる原因と通過のコツを徹底解説
- 土地先行融資とは?住宅ローンで土地購入から始めるときの手続きと流れガイド
- 住宅ローンのつなぎ融資を完全ガイド|仕組み・流れ・金利・注意点まで網羅
- 家を建てる年齢はいつがベスト?30代・40代・50代・60代の判断基準とは
- はじめての家づくり完全ガイド|家を建てたいと思ったら読む7つのステップ
- 家を建てる時の土地探し完全ガイド|後悔しないための選び方・探し方のコツ
- 家を建てるハウスメーカーの坪単価を徹底比較|価格だけで選ばないポイントも解説
- 1000万円台・2000万円台・3000万円台で建てられる家とは?注文住宅の費用と価格帯別のイメージ
- 20坪・30坪・40坪・50坪の広さでどんな家が建てられる?|家づくりの坪数別イメージと暮らし方の違い
- 注文住宅はハウスメーカーと工務店どちらが正解?違いと選び方を徹底比較ガイド
- 地震に強い注文住宅を建てるには?耐震等級・構造・素材を徹底解説
- 実家の建て直しで叶える二世帯注文住宅|親との同居を前向きに考える人へ
- 注文住宅は本当に高い?実例で知る費用感と総額のリアル
- 住宅展示場・モデルハウスに行く前に!見学で失敗しないためのチェックリスト
- 狭小地でも理想の住まいは叶う|限られた敷地に夢を詰め込む注文住宅の魅力
- ペットと快適に暮らす注文住宅|後悔しないための設計アイデアと注意点を徹底解説
- おしゃれな注文住宅を建てたい!後悔しないためのデザイン・間取り・素材選び完全ガイド
- GX志向型住宅とは?持続可能な未来を築くスマートな家づくりガイド
- LCCM住宅とは?ゼロから学ぶ仕組み・認定基準・補助金の活用法まで徹底ガイド
- プレハブ住宅って実際どう?注文住宅と迷う方へ贈る特徴・誤解・向き不向き徹底ガイド
- ペットと快適に暮らす注文住宅|後悔しないための設計アイデアと注意点を徹底解説
- 全館空調のある注文住宅の魅力とは?後悔しないための選び方と注意点を徹底解説
- 注文住宅と建売住宅の違いとは?後悔しない選び方と費用・自由度・住み心地の比較ガイド
- 妊娠・出産をきっかけに「子供のための家を建てたい」と思ったら|後悔しない注文住宅の考え方と家づくりのヒント
- 老後の住み替えで家を建てたいと思ったら読むガイド|後悔しないための間取り・資金・暮らしの考え方
- 住宅ローン借り換えガイド|今の金利と残債でどれくらい返済額が減る?
- はじめて家を建てる人のための住宅ローン入門|基礎から失敗しない選び方まで徹底解説
全国の注文住宅の業者とメーカー探し
▼地域ごとの注文住宅の情報はこちらから
全国の住宅展示場とモデルハウス
▼地域ごとの住宅展示場とモデルハウスの情報はこちらから