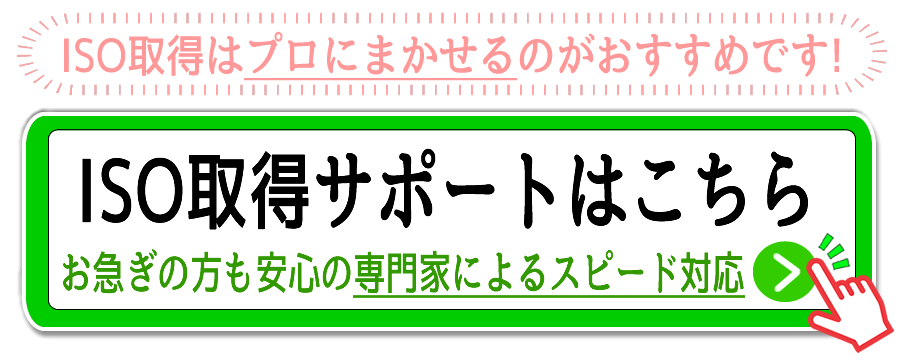PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
IT業界でのISO取得は競争力のカギ|ISMS・Pマーク・BCPの整備で信頼される企業へ

- なぜIT業界でISO取得が求められるのか?
- IT企業がよく取得している主要なISO規格
- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の重要性
- ISO取得によってIT企業が得られる具体的メリット
- スタートアップや中小IT企業でもISOは取得できる?
- IT業界向けISO支援サービスの選び方
- ISO取得の流れ(IT業界編)|取得後の運用ポイント
- よくある質問(FAQ)
- HACCPとISO22000の違いとは?食品業界の安全管理を徹底比較
- SDGsとISO14001・9001の関係とは?企業価値を高めるISO認証取得のススメ
- ISO27001とPマークの違いとは?|情報管理の目的別に選ぶ基準と取得コストのリアル
なぜIT業界でISO取得が求められるのか?

顧客情報・機密データを扱う業界ならではの責任
IT業界では、顧客から預かった個人情報や業務上の機密情報、あるいは自社が開発・運用するクラウドサービス上に蓄積された重要データを日常的に扱います。
そうした情報の漏えい、改ざん、紛失といったトラブルが起これば、企業の信頼は一瞬で失われ、顧客からの損害賠償請求や取引停止など深刻な事態につながりかねません。
そのため、情報セキュリティに関する国際的な管理体制(ISMS)を備えていることが、企業の信頼性を測る基準として年々重視されるようになっています。
取引先からの信頼性確保と受託リスクの可視化
SaaS・システム受託開発・保守運用など、IT企業のビジネスは多くの場合、クライアントの情報資産に直接関わるものです。
特に金融・医療・官公庁など情報管理が厳しい業種では、「ISO27001(ISMS)取得企業であること」が委託先の条件として明記されることも少なくありません。
第三者機関によるISO認証は、客観的に評価された安全管理体制の証明になるため、コンペや新規取引時に大きな武器となります。
システム障害・サイバー攻撃・災害への備え
サーバー障害や通信不良、マルウェア感染、DDoS攻撃、あるいは地震や火災などの災害は、情報システムに重大な影響を及ぼします。
こうしたリスクへの対策として、障害発生時の対応手順・業務継続計画(BCP)・バックアップ体制などを明文化し、運用体制に落とし込んでおくことは、IT企業にとって必須です。
ISO認証を取得することで、リスク管理と復旧能力が体系的に整備され、信頼性の高い事業基盤を構築できます。
IT企業がよく取得している主要なISO規格

ISO27001(ISMS)|情報セキュリティ管理の国際標準
IT企業で最も多く取得されているISO規格がISO27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)です。
この規格は、企業が保有・管理する情報資産に対して、リスク分析を行い、機密性・完全性・可用性を保つためのルールと体制を構築することを求めます。
クラウドサービスやEC、基幹システムなど、顧客の情報を預かるすべてのIT業種にとって信頼性の証明として有効です。
ISO27701(PIMS)|個人情報保護とGDPR対応
近年注目されているのが、ISO27701(PIMS:プライバシー情報管理システム)です。
これはISO27001を拡張する形で構築されるもので、個人情報(PII)の取得・保存・利用・破棄に関する体制整備を求めます。
日本の個人情報保護法だけでなく、GDPRやAPPIなど国際的な法令にも対応できるため、グローバルサービスや海外展開を視野に入れるIT企業には必須の認証となっています。
ISO22301(BCMS)|事業継続・災害対策を“仕組み化”
災害やサイバー攻撃などの非常事態に備える体制として、ISO22301(BCMS:事業継続マネジメントシステム)の認証を取得するIT企業も増えています。
これは、重要業務を止めないための準備・対応・復旧手順を体系化し、文書化・訓練・評価を繰り返して強化する仕組みです。
特にクラウド型サービスやSaaS、インフラ保守など、サービスの停止が多大な影響を及ぼす分野においては、BCP対策の信頼性を証明する手段として活用されています。
ISO9001(品質)|開発プロセス・サービス品質の標準化
IT企業の中でもシステム開発や受託開発を行っている企業では、ISO9001(品質マネジメントシステム)が有効です。
要件定義・設計・製造・納品・運用という一連のプロセスを「品質」として捉え、ミスやトラブルを未然に防ぐための仕組みを構築・文書化します。
IT業界特有の課題として、ヒューマンエラー・要件の取り違え・進捗管理ミスなどがありますが、ISO9001はそれらを繰り返さない組織づくりのベースとなります。
ISO20000(ITサービス)|クラウドや運用保守業務の品質管理
データセンター・クラウドサービス・MSP(マネージドサービスプロバイダ)など、ITサービス提供型のビジネスに適しているのがISO20000(ITSMS)です。
これは、ITILベースの運用管理・インシデント対応・変更管理・サービスレベル合意などの仕組みを整備する規格で、安定したサービス品質・顧客満足度の向上に寄与します。
特に運用保守を請け負う企業にとっては、業界標準に即した信頼性の証明となるでしょう。
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の重要性

クラウド・SaaS・Webサービスに欠かせない体制構築
ITビジネスがクラウド化・サービス化する中で、常時インターネット接続される環境での情報セキュリティ対策が企業の競争力を左右します。
クラウド上のアカウント管理・アクセス制御・ログ監視など、情報資産をどう守り、漏えいや不正アクセスを未然に防ぐかが問われます。
ISMSを導入すれば、リスク評価・保護策の明文化・教育・継続的な改善が仕組み化され、クライアントに安心してサービスを選んでもらえる状態をつくれます。
受託開発・委託契約時の“信用評価”として
システム開発や業務委託などでRFPや見積依頼を受けた際、「情報セキュリティ体制の有無」を問われる場面が増えています。
特に、ISO27001の有無が入札条件に含まれる案件も珍しくありません。
社内に情報セキュリティポリシーやルールが存在していても、それを客観的に評価する手段がなければ意味がありません。
ISMS認証は“対外的に認められた信頼性の証”として、営業活動や新規取引の場面で非常に有効です。
ISMSとPマークの違い・どちらを選ぶべきか?
IT業界では「ISMS(ISO27001)」と「プライバシーマーク(Pマーク)」のどちらを取得すべきか悩むケースも多いでしょう。
大まかにいえば、ISMSは情報資産全体(機密情報や業務データを含む)を守る国際規格、Pマークは日本国内の個人情報保護に特化した制度です。
クラウド・Webサービスなど不特定多数の情報を扱う企業や、海外との取引がある企業はISMSが適しています。
一方、BtoCで個人情報を多く扱う場合や、国内企業との取引が主な場合はPマークでも対応可能です。
ISO取得によってIT企業が得られる具体的メリット

入札・契約条件への対応力が高まる
官公庁・大手企業・医療機関などとの取引では、「ISO27001取得企業であること」「情報セキュリティ体制の証明書の提出」などが入札や契約の条件になることがあります。
ISOを取得していないだけで参入できない案件・商談から除外されてしまうこともあり得ます。
認証を取得することで、新たな市場への参入機会が広がるのは大きなメリットです。
顧客からの信頼性が向上し、商談がスムーズに
ISO取得企業であることをホームページ・提案書・会社案内に記載すれば、第三者機関から認証を受けた「信頼できる企業」であると伝わりやすくなります。
特に新規取引先との初期段階では、相手のセキュリティ体制を確認する手間が省け、商談の成立や契約締結までのスピードがアップすることも期待できます。
社内の業務プロセスが“見える化”される
ISO取得に向けた準備では、業務の流れを文書化し、ルールを明確に定義することが求められます。
その過程で、属人化・非効率・リスクの見落としなどが可視化され、業務改善のきっかけとなります。
認証取得後も継続的な見直しが必要なため、組織のPDCAサイクルが強化され、品質や対応力の向上へとつながっていきます。
採用活動にもプラスの影響がある
ISO認証取得は、「しっかりとした管理体制がある会社」「情報を大切に扱っている企業」という印象を求職者に与えるため、採用活動にも好影響を与えます。
特に情報系人材にとっては、セキュリティ意識や制度面が整っている環境が魅力的に映ることも多く、優秀なエンジニアの採用にも貢献します。
スタートアップや中小IT企業でもISOは取得できる?

「うちは小規模だから無理」ではない
ISO認証と聞くと、「大企業向け」「人員に余裕がないと無理」といったイメージを持たれがちですが、実際には従業員5名以下のIT企業でも取得事例は多数あります。
ISOはあくまで「自社の業務に即した管理体制」を構築するものであり、大企業と同じ仕組みを作る必要はありません。
むしろ、小規模だからこそ柔軟に整備しやすく、短期間・低コストでの取得が可能なケースもあります。
システム会社・SES・Web制作…形態に応じた導入
IT業界と一口に言っても、受託開発、SES、Web制作、SaaS提供、保守運用、インフラ構築など多岐にわたります。
それぞれの業態によって、必要な管理体制やISOの適用範囲も変わってきます。
経験豊富なISOコンサルを活用すれば、「現実的に回せる仕組み」を前提とした運用体制を設計してもらえるため、スタートアップでも無理なく取得が可能です。
資金面の不安も補助金や助成制度でカバー可能
自治体によっては、ISO取得にかかるコンサル費用や審査料の一部を補助する制度があります。
申請手続きや要件の確認など煩雑に感じるかもしれませんが、コンサル会社が代行やサポートを行ってくれることも多く、思っている以上にスムーズに進められる場合がほとんどです。
IT業界向けISO支援サービスの選び方

クラウド・SaaSビジネスに理解のある支援会社を選ぶ
IT業界の中でも、クラウドサービスやSaaS型ビジネスは、従来型のIT事業と異なる情報資産管理の視点が求められます。
例えば、マルチテナント構成での情報分離、クラウド事業者との責任分界、継続的デリバリーに伴うセキュリティ対策など、ISMS適用範囲の特性に対する深い理解が必要です。
支援会社を選ぶ際は、IT・情報セキュリティに精通しており、クラウドやSaaS特有の課題に柔軟に対応できる実績があるかを確認しましょう。
SaaS系スタートアップのISO導入事例を複数持つ会社であれば、現実的で効率的な体制づくりを支援してくれる可能性が高いです。
PマークとISOの同時取得・移行支援が可能か
BtoC向けサービスを展開しているIT企業では、個人情報保護法の観点からPマーク(プライバシーマーク)を取得済み、または取得を検討しているケースも少なくありません。
ただし、PマークとISO27001では要求事項の範囲や深さが異なり、運用負担が二重になるケースも見受けられます。
そのため、PマークとISMSをうまく統合運用できるような支援をしてくれる会社を選ぶことで、社内の混乱や業務過多を防ぐことができます。
また、すでにPマークを取得済みであれば、ISOへのスムーズな移行支援を行っている会社を選ぶことで、無駄な工数や費用を抑えられます。
社内工数を最小限にする「まるごと支援型」か「伴走支援型」か
ISOの取得にあたっては、「文書の作成」「社内教育」「リスクアセスメント」「内部監査」など、多くの作業が発生します。
そのため、社内担当者のリソースや知識レベルをふまえた支援スタイルの選択が重要です。
短期間で負荷を最小限に抑えたい企業には、書類作成や監査準備まで一括で任せられる「まるごと支援型」が向いています。
一方、内部の体制強化やノウハウ蓄積を重視したい場合は、自社のペースに合わせて丁寧に並走してくれる「伴走支援型」の方が長期的な効果が期待できます。
どちらの支援スタイルを採用するにせよ、IT業界特有の事情に配慮した柔軟な対応が可能な支援会社を選ぶことが、スムーズな取得と運用の鍵になります。
ISO取得の流れ(IT業界編)|取得後の運用ポイント

1. 情報資産の棚卸とリスク分析
まずは、自社が保有・管理している情報資産(システム、顧客データ、設計書、ソースコード、契約情報など)を洗い出し、どの資産にどのようなリスクがあるかを評価します。
IT企業の場合、クラウド上の資産、外注先との連携部分、エンジニアの端末管理、アクセス権限管理などが重要なポイントになります。
この段階で、リモート環境での情報管理や、DevOps環境下のコードのセキュリティといった特有のリスクにも注意を払う必要があります。
2. 情報管理ルール・文書の作成と展開
リスク分析に基づき、情報の取扱い方法やアクセス制御、変更管理、バックアップ、ログ管理などの具体的ルールを策定します。
これらは「情報セキュリティ方針」「手順書」「記録様式」など、文書化して明文化する必要があります。
IT企業では、エンジニアにとって実務に即した運用ルールが求められるため、理想論で終わらない“使える文書”の整備が重要です。
3. 教育・試験運用・内部監査
作成した文書をもとに、社員・エンジニア向けのセキュリティ教育を実施し、一定期間の試験運用を経てルールの実効性を確認します。
その後、社内で内部監査を実施し、ルールの運用状況と改善点を洗い出すことが求められます。
IT企業では、技術者が多く形式的な教育や監査に反発が出やすいため、実際のインシデントやヒヤリハットを題材にした教育コンテンツなどが効果的です。
4. 審査機関による認証審査と維持体制の構築
準備が整ったら、認証機関による初回審査を受けます。
審査では、文書の整合性・ルールの実施状況・社員の理解度などが確認されます。
無事に合格すれば認証が発行されますが、毎年のサーベイランス審査・3年ごとの更新審査もあるため、取得後の維持・見直し体制も重要になります。
IT企業にとっては、組織変更やシステムの更新が頻繁に発生するため、変化に応じて柔軟にルールを更新できる仕組みを整備しておく必要があります。
よくある質問(FAQ)

ISMSとPマークの違いは?
ISMS(ISO/IEC 27001)とPマーク(プライバシーマーク)は、どちらも情報セキュリティや個人情報保護を目的とした認証制度ですが、対象範囲や要求内容が異なります。
ISMSは、企業が保有する全ての情報資産を対象としたリスクベースの管理体系であり、組織的・技術的・人的・物理的な対策をバランス良く整備することを求められます。
一方、Pマークはあくまで「個人情報」を対象とした保護体制の整備を認証するもので、範囲も限定的です。
また、ISMSは国際規格であるため海外取引でも信頼性が高く、BtoB領域での要求が多いのに対し、Pマークは国内法に準拠した制度で、主にBtoCビジネスでの顧客信頼獲得が目的となります。
リモートワーク中心でも取得できますか?
はい、リモートワーク中心のIT企業でもISO取得は十分に可能です。
実際、クラウドインフラを活用したリモート業務体制を前提としたISMS運用に対応している支援会社も増えています。
ただし、自宅環境での端末管理やWi-Fiセキュリティ、画面覗き見防止、物理的盗難対策など、在宅勤務ならではのリスクを踏まえた管理策の整備が必要です。
さらに、オンラインでの教育・内部監査の仕組み、電子署名やクラウド文書管理の活用など、運用面での工夫も求められます。
最近では、完全リモート企業でのISMS取得実績も多数あるため、実態に即した支援を行っている会社を選べば問題ありません。
スタートアップでも取得する価値はある?
スタートアップ企業でも、ISOの取得は十分に価値があります。
むしろ、取引先企業やVC、官公庁、医療・教育などセキュリティ要件の高い業界と関係を築く際には、ISMSの有無が取引の可否を左右することさえあります。
また、少人数のうちにセキュリティ体制を整えることで、後の拡張時に混乱しにくいというメリットもあります。
取得にあたっては、初期費用・運用負担を抑えたスモールスタート支援を行う会社を選ぶことで、スピーディかつ柔軟に認証取得が可能です。
クラウドネイティブなスタートアップほど、文書類や手順をミニマムに設計するノウハウが支援会社に求められます。
顧客からISMSを要求されたが、短期間で取得できる?
ISMSの取得には、準備から審査合格まで通常3〜6か月ほどかかりますが、要件を明確化し、タスクを絞り込むことで2〜3か月で取得した事例もあります。
ただし、自社内に情報資産管理の意識やルールが全くない場合は、短期取得は現実的ではありません。
顧客からの要求に対応するためには、まず支援会社に現状を診断してもらい、取得スケジュールと可能性を確認するのが第一歩です。
「審査時に最低限必要なドキュメント」を効率的に整備できるようなテンプレートやサンプルが豊富な支援会社であれば、時間的な制約にも対応しやすくなります。
- HACCPとISO22000の違いとは?食品業界の安全管理を徹底比較
- SDGsとISO14001・9001の関係とは?企業価値を高めるISO認証取得のススメ
- ISO27001とPマークの違いとは?|情報管理の目的別に選ぶ基準と取得コストのリアル
- 製造業でのISO取得はなぜ重要?|現場で求められる規格と取得支援の進め方
- 建設・土木業でのISO取得は必要?公共工事・安全管理で差がつく規格と活用法とは
- 医療機器・精密機器メーカーのためのISO取得ガイド|ISO13485・ISO9001・ISO14001を徹底解説
- IT業界でのISO取得は競争力のカギ|ISMS・Pマーク・BCPの整備で信頼される企業へ
全国のISO規格取得支援サポート
▼地域ごとのISO規格取得支援サポートの情報はこちらから