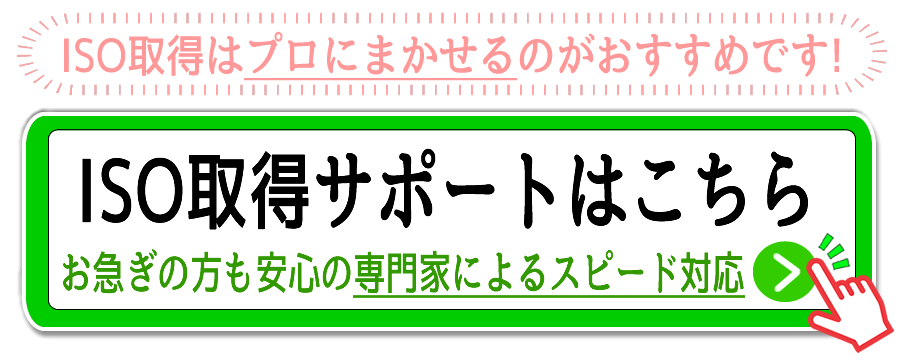PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
医療機器・精密機器メーカーのためのISO取得ガイド|ISO13485・ISO9001・ISO14001を徹底解説

- 医療機器・精密機器業界でISO取得が求められる理由
- 主な対象規格とその役割|ISO13485・ISO9001・ISO14001の違い
- ISO13485取得のポイント|GMPや薬機法との整合性をどう取るか
- 精密機器メーカーにおけるISO取得の課題と対策
- ISO支援サービスの選び方|医療・精密分野で実績のある会社を
- よくある質問(FAQ)
- HACCPとISO22000の違いとは?食品業界の安全管理を徹底比較
- SDGsとISO14001・9001の関係とは?企業価値を高めるISO認証取得のススメ
- ISO27001とPマークの違いとは?|情報管理の目的別に選ぶ基準と取得コストのリアル
医療機器・精密機器業界でISO取得が求められる理由
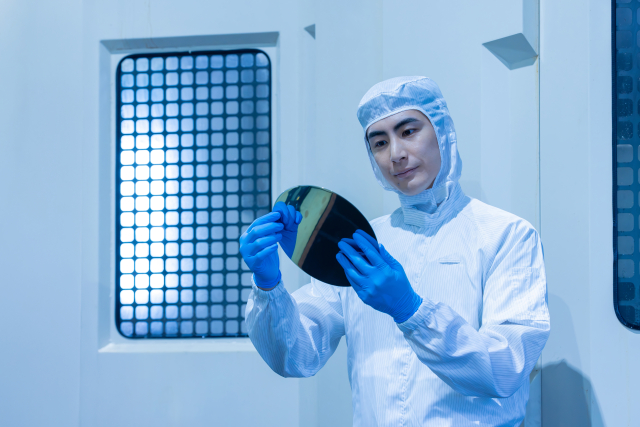
厳格な品質管理・安全性が要求される業界構造
医療機器や精密機器を製造・販売する企業にとって、高度な品質管理と安全性の確保は絶対条件です。
特に医療機器分野では、製品に欠陥があれば、人命に直接関わるリスクさえ伴います。
そのため、製造から出荷、販売後のフォローアップに至るまで、トレーサビリティや文書管理を含む品質保証体制の構築が不可欠です。
こうした背景から、国際的な認証であるISOを取得することが信頼の証明とされ、多くの企業が導入を進めています。
国内外の規制・調達要件への対応(薬機法・CEマーキング等)
日本国内では薬機法(旧薬事法)、海外ではCEマーキングやFDA基準など、医療機器には多岐にわたる法規制と認可要件があります。
これらに対応するためには、製品安全性・製造工程・管理体制における明確なルールと記録が求められます。
ISO認証、とりわけISO13485の取得は、薬機法のQMS省令と高い親和性があり、国内外の審査・輸出入時のスムーズな対応につながります。
特にCEマーキングでは、ISO13485の認証が前提条件とされるケースもあるため、グローバル展開を目指す企業にとっては必須ともいえる取り組みです。
サプライヤーとして信頼を得るための認証取得
医療機器や精密機器は、部品レベルでも厳しい品質要件が設定されます。
製造元だけでなく、部品・ユニットの供給元も一貫した品質体制が構築されていることを証明する必要があります。
そのため、サプライヤーやOEM企業にもISO取得が強く求められるようになってきました。
調達先の評価基準として、ISO13485やISO9001の取得有無が前提条件となるケースも多く、入札・契約時の信頼性確保にも直結する重要なファクターです。
主な対象規格とその役割|ISO13485・ISO9001・ISO14001の違い

ISO13485:医療機器品質マネジメントの国際基準
ISO13485は、医療機器の設計・製造・流通・保守に関わる事業者向けに定められた、国際的な品質マネジメントシステム規格です。
特徴的なのは、リスクマネジメントと製品の有効性を重視した構成である点です。
文書管理や設計開発プロセス、検証・妥当性確認、苦情処理や是正処置の仕組みまで、製品ライフサイクル全体をカバーしています。
また、日本の薬機法QMS省令との整合性が高いため、ISO13485の取得は法令順守にも直結します。
ISO9001:顧客満足と継続的改善にフォーカス
ISO9001は、業種を問わず幅広く採用されている品質マネジメント規格ですが、精密機器メーカーにとっても有効な指標です。
顧客要求事項の明確化、品質目標の設定、PDCAサイクルの運用など、継続的な改善を促す体制づくりがメインの目的です。
ISO13485との同時取得も多く、プロジェクト管理・工程内品質の可視化にも活用できます。
特に多品種小ロットで変動の多い現場において、標準化による効率化と不良削減が期待できます。
ISO14001:環境リスク対策とグリーン調達の観点
ISO14001は、環境マネジメントに関する国際規格であり、近年ではESG・SDGs対応やグリーン調達の観点から、医療機器・精密機器業界でも注目されています。
製造過程で発生する化学物質や廃棄物への対応、省エネ対策、環境負荷の測定と改善計画などが求められ、サステナビリティを重視する取引先や投資家へのアピールにもつながります。
ISO13485取得のポイント|GMPや薬機法との整合性をどう取るか

バリデーション・トレーサビリティ・リスクマネジメントの徹底
ISO13485では、製品の安全性・有効性の確保バリデーション(妥当性確認)やトレーサビリティ(追跡可能性)が重視されます。
特に、ソフトウェアや高度な部品を含む医療機器においては、設計・製造工程・最終検査までの一貫した記録が必要不可欠です。
さらに、リスクマネジメントも重要な要素です。
ISO14971に準拠したリスク分析を実施し、設計変更や製品回収の際の根拠として機能させる必要があります。
これにより、クレーム対応や法的リスクの低減にもつながります。
GMP(適正製造基準)やQMS省令との重複・整合性の整理
日本の薬機法におけるQMS省令(医療機器製造に関する品質管理基準)は、GMP(Good Manufacturing Practice)と呼ばれる適正製造基準に基づいています。
この省令はISO13485と共通部分が多く、ISO13485を取得していればGMPの要件の大部分をカバーできるとされています。
とはいえ、両者の間には一部で要求事項の違いがあるため、「ISO13485とQMS省令をどう並行運用するか」は重要なテーマです。
支援会社と協力しながら、文書体系や教育訓練の設計を共通化させることで、管理の手間と重複工数の削減が実現できます。
設計・開発段階のルール化が最大のハードル
医療機器分野において、ISO13485では「設計・開発プロセスの文書化とレビュー体制」が特に重視されます。
設計変更や試験結果、開発中のフィードバックなど、全プロセスに対して証跡を残す仕組みを構築しなければなりません。
とくに中小規模の精密機器メーカーでは、開発記録が個人依存・口頭ベースになっていることも多く、社内ルールの見直しや教育体制の整備が課題となります。
この設計プロセスのルール化を支援できるコンサルタントの有無は、支援会社選びの大きなポイントになるでしょう。
精密機器メーカーにおけるISO取得の課題と対策

少量多品種生産における手順標準化の難しさ
医療機器や精密部品の分野では、1品ごとの仕様が異なる少量多品種生産が一般的です。
この特性が、標準的な作業手順書(SOP)の整備や活用を困難にしています。
作業ごとに個別のノウハウが必要な場合、属人化が進みやすく、品質の一貫性を保つのが難しくなるのです。
この課題に対しては、「作業分類ごとのテンプレート化」や「動画や写真を使ったマニュアルの視覚化」が効果的です。
すべてを文書に落とし込むのではなく、要所を押さえた運用フローで、審査対応と現場の実態のバランスを取ることが重要です。
工程ごとの品質ばらつきと是正処置の記録対応
部品精度や加工誤差の問題は、ISO13485における「是正処置」や「予防処置」の記録義務に直結します。
製品検査のたびにバラつきが見つかるような場合、記録の蓄積と再発防止策の検証が求められます。
対応としては、日常的な品質記録をデジタルで簡易に残せる仕組みの導入が有効です。
スプレッドシートやアプリを活用し、現場負担を最小限にしながらエビデンスが残る体制を整えることが、ISO審査時にも信頼を得られるポイントになります。
協力会社・外注先を巻き込んだ品質管理体制
医療機器業界では、協力会社や部品サプライヤーも品質保証の一部として監査対象となります。
ISO13485では、外部供給者の選定・評価・監査のプロセスを定める必要がありますが、中小企業が単独で外注先をコントロールするのは容易ではありません。
そのため、外注先へのQMS教育や品質契約書の整備を、支援会社と連携して進めることが有効です。
また、年1回の評価記録や不具合連絡のルール化を進めておくことで、審査でも安心して説明できる体制が整います。
ISO支援サービスの選び方|医療・精密分野で実績のある会社を

ISO13485や薬機法を熟知した専門家が在籍しているか
医療機器や精密機器分野でのISO取得では、一般的な製造業と異なり、GMP・QMS省令・薬機法などの法令や規格とISO13485の関係性を理解していないと、かえって運用上の混乱を招くリスクがあります。
そのため、ISO13485の規格知識だけでなく、薬事法務やバリデーションの実務に精通した支援者がいるかは非常に重要です。
ISO認証だけを形式的に取得して終わるのではなく、現場での実効性ある品質マネジメント体制の構築を目指すためにも、専門性のあるパートナーを選びましょう。
現場とのギャップを埋める実践型支援ができるか
ISO13485の取得・運用では、文書の整備・記録の管理・内部監査の実施などが必須ですが、それらが現場の実態に合っていないと、単なる「形だけのルール」となって形骸化してしまいます。
支援会社が現場を理解し、オペレーターの業務負担や工程上の制約も踏まえたうえで、実務に即した手順や様式を提案できるかが大きな分かれ目となります。
形式的なISOコンサルではなく、ヒアリング・現場確認・フィードバックを重ねながら改善案を提示してくれる支援会社を選ぶことで、スムーズな定着と継続的な改善が期待できます。
審査機関との調整・指摘対応も任せられるか
ISO13485の審査では、審査機関との事前打ち合わせ・審査時の立ち合い・指摘事項への是正対応など、多くのやり取りが発生します。
特に、初めてISO認証を取得する企業にとっては、「何をどのように説明すべきか」「どの書類を提示すれば良いか」といった細かな対応が大きな負担になります。
こうした場面で、審査機関との折衝経験が豊富な支援会社がサポートしてくれれば、大きな安心感となるでしょう。
実際の指摘傾向を踏まえた事前対策や文書レビュー、説明のリハーサルまで行えるサービスを提供している支援会社であれば、審査の通過率も高まりやすくなります。
よくある質問(FAQ)

ISO13485とISO9001は併用すべき?一本化できる?
ISO13485は医療機器に特化した品質マネジメントシステムであり、ISO9001とは目的や要求事項に違いがあります。
ただし、共通する要素も多く、適切な構成であれば両規格を統合して運用することも可能です。
一方で、医療機器部門と一般製品部門を分けて運用する場合は、併用の方が合理的なケースもあります。
自社の事業構造や顧客要求に応じて、どちらの方式が適しているかを検討しましょう。
海外向けにCEマーキングを目指す場合、ISOは必要?
はい、CEマーキング取得の前提としてISO13485認証が求められることが多く、とくに欧州の医療機器規制(MDR)ではISO13485の体制がないと、技術文書の信頼性や製造管理体制が疑問視される可能性があります。
CEマーク取得を見据えている場合は、早い段階からISO13485を導入しておくことが、審査対応の負担軽減にもつながります。
研究開発中心の企業でも取得する意味はある?
あります。
試作開発段階であっても、ISO13485に基づいた文書化・記録管理の体制を持っておくことで、将来的な製造委託や量産化への移行がスムーズになります。
さらに、取引先からの信頼性確保や、公的補助金申請における加点要素としても有効です。
研究開発段階から品質管理体制を明確にしておくことは、製品ライフサイクル全体のリスク軽減にも直結します。
製造委託(OEM)企業でもISO取得は必要?
たとえ製造を外注している場合でも、製品の設計や仕様管理を自社が担っている場合、品質責任の一端を負う立場にあります。
ISO13485を取得することで、OEM先との品質契約や供給体制の管理を適切に行う土台が整い、顧客や規制当局からの信頼性向上にもつながります。
とくに欧米市場での展開を見据える場合、自社でもISO体制を整備しておくことがスタンダードとなっています。
- HACCPとISO22000の違いとは?食品業界の安全管理を徹底比較
- SDGsとISO14001・9001の関係とは?企業価値を高めるISO認証取得のススメ
- ISO27001とPマークの違いとは?|情報管理の目的別に選ぶ基準と取得コストのリアル
- 製造業でのISO取得はなぜ重要?|現場で求められる規格と取得支援の進め方
- 建設・土木業でのISO取得は必要?公共工事・安全管理で差がつく規格と活用法とは
- IT業界でのISO取得は競争力のカギ|ISMS・Pマーク・BCPの整備で信頼される企業へ
- 医療機器・精密機器メーカーのためのISO取得ガイド|ISO13485・ISO9001・ISO14001を徹底解説
全国のISO規格取得支援サポート
▼地域ごとのISO規格取得支援サポートの情報はこちらから