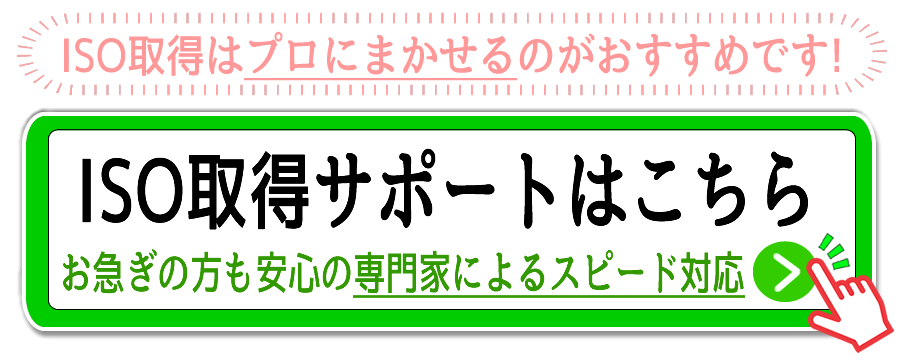- HACCPとISO22000は何が違う?|基本的な定義と役割
- 比較表でわかる!HACCPとISO22000の主な違い
- 食品工場が直面する衛生管理の課題とは?
- HACCPだけでは足りない?ISO22000が求められる理由
- HACCPとISO22000、どちらを選ぶべき?|認証比較のポイント
- ISO22000取得をスムーズに進めるには?|導入ステップと支援策
- HACCPとISO22000の併用はできる?両立運用の考え方
- よくある質問Q&A|食品衛生認証取得に関する疑問
- SDGsとISO14001・9001の関係とは?企業価値を高めるISO認証取得のススメ
- ISO27001とPマークの違いとは?|情報管理の目的別に選ぶ基準と取得コストのリアル
- 製造業でのISO取得はなぜ重要?|現場で求められる規格と取得支援の進め方
- 建設・土木業でのISO取得は必要?公共工事・安全管理で差がつく規格と活用法とは
- IT業界でのISO取得は競争力のカギ|ISMS・Pマーク・BCPの整備で信頼される企業へ
- 医療機器・精密機器メーカーのためのISO取得ガイド|ISO13485・ISO9001・ISO14001を徹底解説
HACCPとISO22000は何が違う?|基本的な定義と役割

HACCPとは?食品衛生法で義務化された管理手法
HACCPとは「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、日本語では「危害要因分析重要管理点」と訳されます。
これは、食品の製造工程におけるリスクを事前に分析し、危険を未然に防ぐための管理手法です。
従来の「最終製品の抜き取り検査」ではなく、製造工程の管理によって安全性を確保するという考え方に基づいています。
日本では2021年6月、改正食品衛生法によりHACCPに基づく衛生管理の導入がすべての食品等事業者に義務化されました。
ただし、業種や規模によっては「HACCPの考え方に基づく衛生管理」で代替することも認められており、小規模事業者には柔軟な運用が可能とされています。
ISO22000とは?国際基準に準拠した食品安全マネジメントシステム
一方、ISO22000は2005年に発行された国際標準規格であり、正式名称は「食品安全マネジメントシステム(FSMS)」です。
こちらはHACCPの考え方をベースにしつつ、経営全体として食品安全を確保する仕組みを求める規格となっています。
ISO22000の特徴は、単なる現場の衛生管理にとどまらず、経営者の関与、文書管理、継続的改善、内部監査、教育訓練といった要素を包括的に構築する点です。
つまり、組織全体で食品の安全を管理・保証するための体系的アプローチを実現するための枠組みといえます。
両者の立ち位置と対象範囲の違い
HACCPとISO22000は、いずれも食品の安全確保を目的とした手法ですが、その対象範囲や導入目的には明確な違いがあります。
- HACCPは、製造工程での危害要因分析と管理が中心であり、工程管理のルールと考えられます。
- ISO22000は、経営マネジメントを含む包括的な食品安全システムであり、組織全体の運用管理体制を求めます。
つまり、HACCPは「現場管理の道具」、ISO22000は「経営戦略の一環」として捉えると、その違いがより明確になります。
比較表でわかる!HACCPとISO22000の主な違い
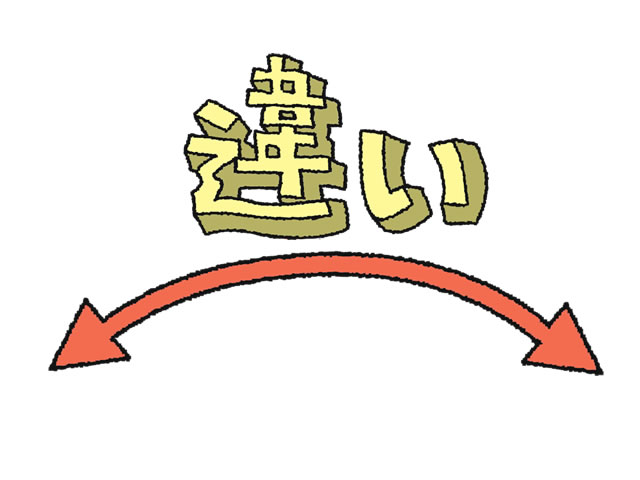
適用義務・業種別の対象範囲
HACCPは、日本国内ではすでに法律によって義務化されています。
一方で、ISO22000は義務ではなく任意の取得ですが、輸出入業務や大手取引先との契約条件として取得が求められるケースも増えています。
- HACCP:全食品等事業者が対象(例外あり)
- ISO22000:取得は任意。ただしグローバル展開や高品質要求の取引先に必要とされる
構築方法・必要書類・運用フローの違い
HACCPは、7原則12手順に基づいて危害要因を分析し、重要管理点(CCP)を設定して監視・記録する運用が基本です。
対して、ISO22000ではこれに加えて、組織方針・マネジメントレビュー・教育・是正措置といったPDCAサイクルの導入が必須です。
- HACCP:工程ごとの管理と記録が中心
- ISO22000:組織的PDCAによる継続的改善のマネジメント体系
認証取得の有無・第三者審査の有無
HACCPは自己運用も可能で、必ずしも第三者による認証審査を必要としません(ただし、HACCP認証制度を利用することも可能)。
一方、ISO22000は外部の第三者機関による審査を経て認証を受ける仕組みであり、対外的な信用性が高い点が特徴です。
内部監査・継続的改善の必要性
HACCPでは、業務が標準どおりに行われているかを点検する程度で済むケースが多いですが、ISO22000は年1回以上の内部監査や、不適合対応・是正処置・予防処置を含む「マネジメントレビュー」が必須です。
このように、HACCPは現場主導で回せる仕組み、ISO22000はマネジメントを含めて全社的な仕組みであるといえるでしょう。
食品工場が直面する衛生管理の課題とは?

HACCP義務化にともなう実務の変化
HACCPの義務化により、すべての食品等事業者は、リスクを事前に分析し、記録・監視を行う体制を整える必要が生じました。
これにより、従来の「経験と勘」に頼った管理から、数値と記録に基づいた衛生管理へと大きな変化が起きています。
特に、小規模の食品加工工場では、「日々の業務に追われながら帳票をつけるのは大変」「記録の保管や活用方法が分からない」といった現場の混乱も見られています。
「帳票はあるが活用されていない」現場の声
HACCP対応の一環として帳票を作成し、温度管理・衛生点検・清掃記録などを毎日記録している事業者は多いものの、そのデータが蓄積されるだけで分析・改善に活かされていないという課題も顕在化しています。
また、記録を提出する際に「書類は整っているが、管理責任者が内容を把握していない」など、形式的な運用になってしまっているケースも多く見られます。
ISO22000導入で業務フローはどう変わる?
こうした課題に対し、ISO22000では「記録の管理」だけでなく「改善活動」までが求められるため、帳票の形式的な作成では済みません。
むしろ、従業員全体でリスクを共有し、定期的に振り返り、是正・予防策を講じる文化を根付かせることが前提となります。
その結果、現場においても「なぜこの記録を取っているのか」「この管理がどのようなリスクを防ぐのか」を理解し、実効性のある衛生管理体制へと進化していくことが可能になります。
HACCPだけでは足りない?ISO22000が求められる理由

取引先・輸出入の審査要件としてのISO
近年では、HACCPの義務化だけでは十分とされず、ISO22000の取得を取引条件として求める企業が増えてきています。
特に、大手スーパーマーケットチェーンや外資系飲食ブランド、さらには輸出入を伴う取引においては、国際基準であるISO取得が信頼性の証として重視される傾向があります。
また、グローバルサプライチェーンへの参入を目指す企業にとって、HACCPのみでは評価されにくく、ISO22000が必要不可欠な条件となることも少なくありません。
HACCP導入後も事故が発生する背景とは
「HACCPを導入したのに食中毒事故が起きた」「回収騒ぎが発生した」といったニュースは後を絶ちません。
これは、HACCPが帳票や手順にとどまり、現場への意識改革が伴っていない場合に起こる典型例です。
HACCPは工程管理に重点を置くため、リスク対応が現場依存になりやすく、経営レベルでの改善サイクルが機能していない企業では、見落としや習慣化されたヒューマンエラーが残存しやすいのです。
「経営管理まで踏み込む」ISO22000の価値
ISO22000では、単に工程の衛生管理だけでなく、経営陣の関与が強く求められます。
たとえば、トップマネジメントは食品安全方針の策定やリスク評価に責任を持ち、全社的なリスクマネジメント体制の構築を主導する必要があります。
また、内部監査やマネジメントレビューといった仕組みを通じて、自社の弱点を定期的に発見し、改善を繰り返す文化が醸成されていきます。
これが「記録するだけの衛生管理」から「組織で守る食品安全」へと進化させる原動力になるのです。
HACCPとISO22000、どちらを選ぶべき?|認証比較のポイント

小規模事業者はHACCPで十分?ISO22000が必要な業種とは
HACCPは小規模事業者にも対応しやすく設計されており、日々の工程管理を基本にした実務中心の制度です。
したがって、地域密着型の飲食店や少量生産の食品加工業者などは、HACCPだけでも一定の水準の管理が実現できます。
一方で、以下のような企業にはISO22000の取得が強く推奨されます。
- 多拠点にまたがる食品工場を展開する企業
- OEM・業務用向けに供給している食品加工業者
- 海外輸出を検討している企業
- 大手企業と直接取引がある中堅企業
複数工場・海外取引ありならISO取得が有利
ISO22000の認証を取得すれば、取引先やバイヤーからの信頼性が高まり、新たな販路開拓や輸出ビジネスでの優位性を得ることができます。
特にEU、米国、ASEAN諸国などではISO準拠の食品安全マネジメントが前提とされることもあるため、ISOを取得しているか否かが商談の入口になることもあります。
コスト・導入期間・運用体制の違いを比較
HACCPは自社内で構築・運用することも可能で、導入コストが比較的低く、数週間〜1ヶ月でスタートできます。
ISO22000は、初期診断〜文書作成〜内部監査〜審査機関の審査という流れを踏むため、3ヶ月〜6ヶ月程度の期間と、コンサル・審査費用などのコストが必要になります。
したがって、短期的にはHACCP、長期的な企業価値向上を狙うならISOという選択が現実的です。
ISO22000取得をスムーズに進めるには?|導入ステップと支援策
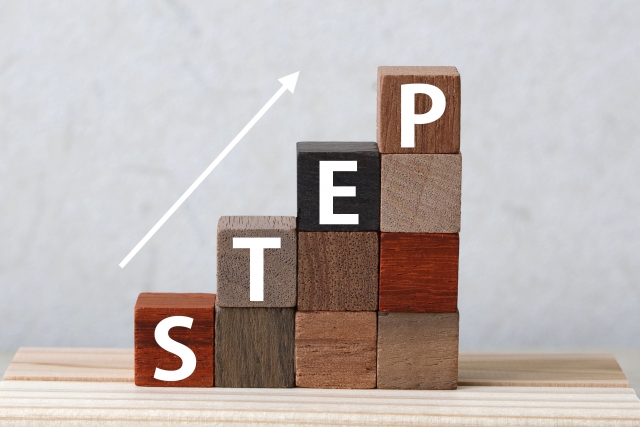
現場の不安を解消する「見える化」プロセス
ISO22000を導入する際、多くの現場から「文書作成が難しい」「監査が怖い」といった声が上がります。
こうした不安を解消するには、支援会社の活用による「ステップ設計の見える化」が効果的です。
各ステージで何をすべきかが明確になれば、従業員も納得して取り組みやすくなるため、形だけでなく実効性のあるマネジメントシステムを構築できます。
専門家によるコンサルの有無で導入難易度が激変
ISO22000の導入は、専門知識・審査基準への理解・監査対応のノウハウが求められるため、社内だけでの運用には限界があります。
多くの企業では、コンサルタントによる支援を受けることで、最短ルートでの取得やミスの回避を実現しています。
支援内容は、文書作成サポート、従業員教育、模擬審査、審査立ち会いなど多岐にわたり、費用対効果の高い支援サービスが選ばれています。
HACCPの実績がある企業こそISO移行がスムーズ
HACCPの運用経験がある企業であれば、危害要因分析や衛生管理のベースがすでに整っているため、ISO22000への移行が非常にスムーズです。
記録類・手順書・運用ルールが残っていれば、それをベースにマネジメントシステムのフレームに落とし込むことで、大幅に工数を削減できます。
HACCPとISO22000の併用はできる?両立運用の考え方

ISO22000の中にHACCPの考え方を組み込む
実は、ISO22000はHACCPの7原則を内包する設計となっており、併用ではなく統合的な運用が可能です。
つまり、ISO22000を取得すれば、HACCPの考え方も含めて認証されると考えて差し支えありません。
ダブルスタンダードではなく統合運用を目指す
HACCPとISOを分けて考えるのではなく、現場にとって理解しやすいように一体化した運用が理想です。
たとえば、HACCPで定義したCCPの監視記録を、ISOの内部監査資料に組み込むなど、業務負担を増やさず統合管理することが可能です。
多拠点・多業種展開企業での運用事例
実際に、全国に複数の食品工場を持つ企業では、HACCPとISO22000を融合させたシステムを構築し、現場・本部・経営層が連携して食品安全体制を運用しています。
こうした企業は、大手流通との契約獲得・海外展開といった事業拡大の大きな武器にISO認証を活かしています。
よくある質問Q&A|食品衛生認証取得に関する疑問

HACCPの義務化はいつから?誰が対象?
2021年6月から、すべての食品等事業者にHACCPによる衛生管理が義務化されました。
規模に応じて「基準B(簡易HACCP)」も活用可能です。
ISO22000は義務ですか?取得しないと不利になりますか?
ISO22000は義務ではありませんが、取引先や輸出先が取得を条件とするケースが増えており、商機を広げるうえで有利です。
HACCPとISO22000を両方取得する必要はありますか?
ISO22000はHACCPの考え方を包含しているため、ISOのみでもHACCP要件をカバー可能です。
ただし、HACCP認証を明示的に求める取引先がある場合は両方取得することもあります。
ISO22000は中小企業でも取得できますか?
はい。
支援サービスを活用すれば、中小・小規模事業者でも十分に取得可能です。
最近では、初期費用を抑えたプランも多く提供されています。
- SDGsとISO14001・9001の関係とは?企業価値を高めるISO認証取得のススメ
- ISO27001とPマークの違いとは?|情報管理の目的別に選ぶ基準と取得コストのリアル
- 製造業でのISO取得はなぜ重要?|現場で求められる規格と取得支援の進め方
- 建設・土木業でのISO取得は必要?公共工事・安全管理で差がつく規格と活用法とは
- IT業界でのISO取得は競争力のカギ|ISMS・Pマーク・BCPの整備で信頼される企業へ
- 医療機器・精密機器メーカーのためのISO取得ガイド|ISO13485・ISO9001・ISO14001を徹底解説
- HACCPとISO22000の違いとは?食品業界の安全管理を徹底比較
全国のISO規格取得支援サポート
▼地域ごとのISO規格取得支援サポートの情報はこちらから