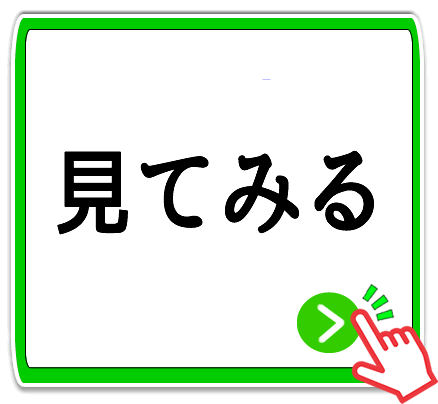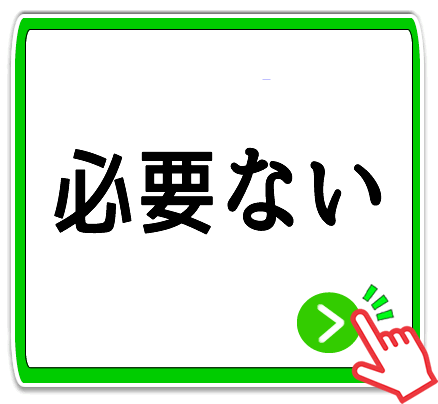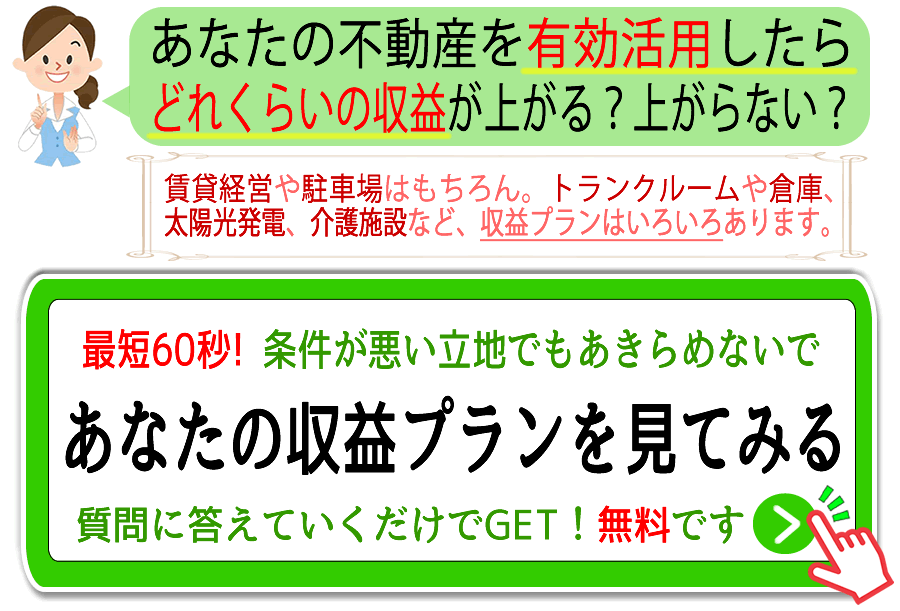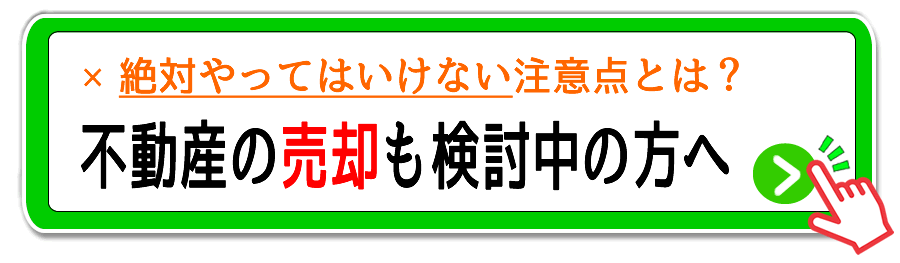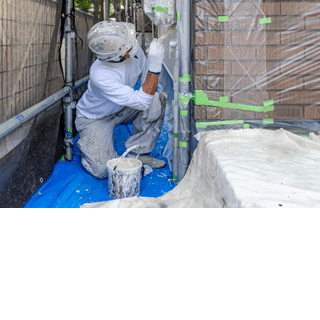PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
いらない土地をどうする?条件の悪い土地の手放し方と処分・収益化の選択肢をやさしく解説

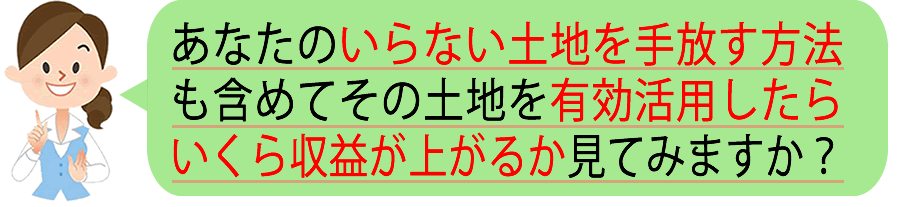

- 条件の悪い土地でも「収益化できる可能性」はある
- いらない土地の扱いに迷ったら、まずは相談から
- 「いらない土地」や「使えない土地」が増えている背景
- いらない土地を「手放したい」と思ったときにまず考えるべきこと
- いらない土地の「処分方法」とは?
- どうしても活用・処分できない土地はどうする?
- いらない土地の対処に役立つ公的・民間の支援制度
- まとめ|いらない土地の対処には「早めの行動」がカギ
- よくある質問(FAQ)
- 放置している空き家、ずっとこのままで大丈夫?──管理できない不安に今こそ向き合う
- 狭い土地でもできる土地活用とは?|3坪・5坪から考える狭小地の可能性
- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて
- 賃貸アパート・マンション経営という土地活用|収益性・始め方・失敗しないための実践ガイド
- 駐車場経営は土地活用の定番|リスク・収益性・始め方を徹底解説
- 太陽光発電で土地を活かす方法とは?初期費用・収益性・注意点まで徹底解説
- トランクルーム経営で土地活用|初期費用・収益性・失敗しない運営のコツ
- 老人ホーム・サ高住・介護施設経営という土地活用|収益性・リスク・始め方を徹底解説
条件の悪い土地でも「収益化できる可能性」はある

「売れない」「寄付もできない」「国にも引き取ってもらえない」――。
そうした土地でも、工夫次第でお金を生み出す方法は存在します。
もちろん万能な手段ではありませんが、諦める前に「収益化」の可能性を検討してみましょう。
収益化を検討するなら「初期費用」と「手間」を天秤に
土地の活用には、大きく分けて「初期投資が必要なもの」と「ほとんどお金をかけずに始められるもの」があります。
たとえば、建物を建てるような活用方法は初期費用が高く、固定資産税の負担も増える可能性があります。
逆に、設備を最小限にしてレンタルする形式であれば、収益性は小さいものの、リスクも低いという特徴があります。
収益化の成功は「その土地に適した方法を選べるかどうか」にかかっています。
建物不要の活用方法もある
条件が悪くても、「置く」だけ・「貸す」だけでできる活用方法を考えると可能性が広がります。
以下のような活用方法がその一例です。
資材置き場として貸す
建設会社や解体業者、造園業者などは、工事に使う一時的な資材置き場を必要としています。
都市部から離れていても、道路に接していて車両の出入りがしやすい土地であれば需要があります。
整地費用やフェンスの設置など多少の整備が必要な場合もありますが、建築不要で始められる活用法として注目されています。
貸し農園(市民農園)として活用
郊外の土地や農地転用可能な土地であれば、貸し農園として小区画に分けて貸すという方法もあります。
家庭菜園を楽しみたい人や自然と触れ合いたい人からのニーズがあります。
水道設備や簡易トイレの設置、草刈りの手間など管理面は必要ですが、都市近郊であれば収益化の実績も多い活用法です。
ドッグラン・アウトドアイベントスペースなど
平坦で広めの土地がある場合は、ペット用ドッグランやレンタルBBQスペースなどのアウトドア向け活用も検討できます。
許可や設備が必要なケースもあるため、初期投資とのバランスを見ながら判断することが重要です。
トランクルーム経営(外部リンク紹介)
狭小地や変形地でも、簡易なコンテナ型トランクルームを設置してレンタル運用する方法があります。
導入費はやや高めですが、狭い土地でも安定収益を目指せます。
月極駐車場よりも高単価が見込める点は大きな魅力です。
活用には向かない土地の特徴とは
一方で、以下のような土地は、収益化に適さない可能性が高いため注意が必要です。
- 傾斜が急で整地に費用がかかる土地
- 周辺に住民が少なくニーズがない場所
- 道路に接しておらず車両が進入できない土地
- 農地としての規制が強く転用できない土地
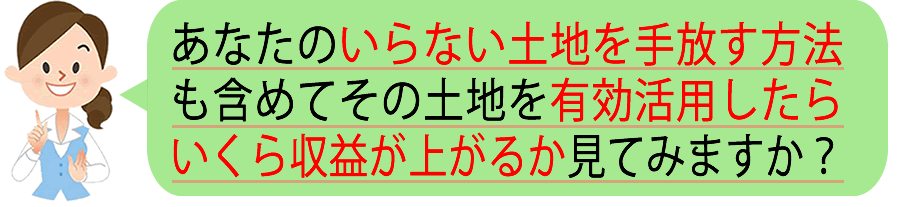

いらない土地の扱いに迷ったら、まずは相談から
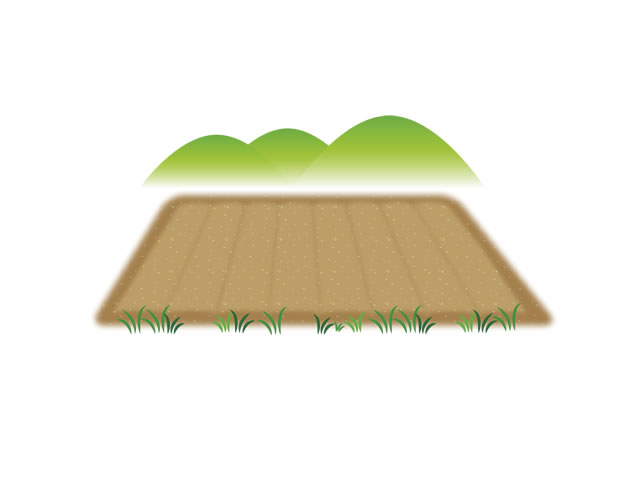
「いらない土地」に悩む人の多くが、情報不足によって判断を先送りにしています。
しかし、土地の問題は放置すればするほど、相続人や家族への負担が増える可能性があります。
無料査定サービスの活用
現在では、インターネット上で土地の無料査定を受けられるサービスも多くあります。
複数社に依頼することで、
- 自分の土地が市場でどの程度の価値があるのか
- 売れる可能性はあるのか
- どういった活用法が考えられるか
といった情報を知ることができます。
「売れるわけがない」と決めつけずに、まずは現状を正確に把握することが大切です。
専門家の意見を聞くことのメリット
司法書士、土地家屋調査士、不動産業者、税理士など、各分野の専門家に相談することで、思わぬ打開策が見つかることもあります。
たとえば、
- 境界が不明だった土地を測量して売却できた
- 活用法のアドバイスを受けて収益化できた
- 相続人との関係を整理して処分できた
など、自分だけでは気づけない可能性が見えてくることもあります。
「自分では活用できないけど価値がある」土地かもしれない
所有者本人にとっては「どうにもならない土地」と思っていても、地域によっては需要があるケースもあります。
とくに最近は、
- リモートワークの普及で地方移住が増えている
- キャンプ場や自給自足の拠点として使いたい人がいる
- 小規模事業のために空き地を探す起業家がいる
といった動きもあり、土地の価値の見方は時代とともに変化しています。
「どうせ価値がない」とあきらめる前に、ほんの少し情報収集をしてみるだけでも、新しい可能性が見えてくるかもしれません。
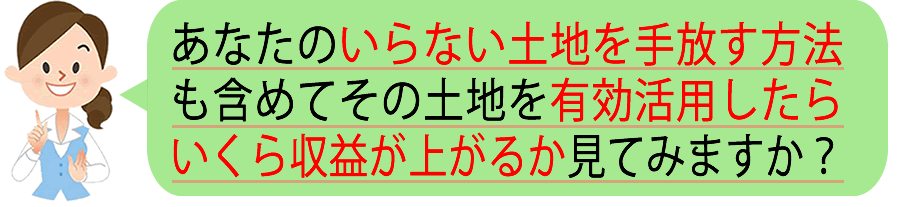

「いらない土地」や「使えない土地」が増えている背景

空き地・空き家の放置が増える理由
かつては「土地=資産」と信じられていました。
しかし現在、使い道がなく管理にコストばかりかかる土地を相続し、手をつけられずに放置してしまうケースが増えています。
とくに地方部では、人が住まなくなった土地や、耕作放棄地、山林などが増加。
都市部に住む相続人にとっては遠方で管理もできず、「負動産(負の不動産)」と呼ばれるほどの悩みの種になっています。
固定資産税が毎年かかります。
「土地は資産」とは限らない時代に
昭和の高度経済成長期では「土地を持っていれば資産になる」という考え方が常識でした。
けれども、人口減少や都市集中、地方の過疎化が進む中で、価値の低い土地や使いづらい土地は買い手がつかない現実が出てきています。
一方で、手放すにもお金がかかる、もしくは法律上の制約があるため、「簡単には処分できない」という状況に陥る人も少なくありません。
「いらない土地」とはどんな土地?具体例で紹介
ここで言う「いらない土地」とは、単に使っていないというだけでなく、以下のような特徴を持つ土地です。
- 山林・農地・原野:日常的に使うことがなく、管理に手間がかかる。
- 狭小地・変形地:建物が建てにくく、商業利用も難しい。
- 接道義務を満たさない土地:建築基準法上の「再建築不可」など、法的制限がある。
- 相続したけれど使い道がない土地:地方や山奥で、現地に行くのも難しい。
こうした土地を所有している人が、「どうにか手放したい」「お金にならなくてもいいから処分したい」と悩むのは自然なことです。
しかし、対処を誤ると後々まで負担が続く可能性があります。
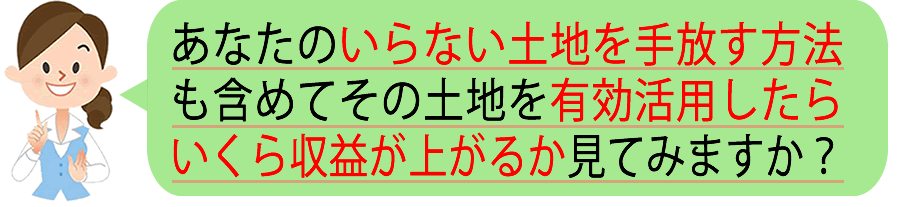

いらない土地を「手放したい」と思ったときにまず考えるべきこと

維持費がかかる土地は放置しないほうがいい理由
たとえ活用していなくても、土地を所有しているだけで毎年、固定資産税や都市計画税などが発生します。
さらに、草木の繁茂や不法投棄、近隣との境界問題など、管理の手間やリスクもあります。
特に高齢化により、自分で管理できなくなったり、遠方の土地で管理が困難な場合には、放置しておくことが将来的に家族の負担になることも十分に考えられます。
相続登記は済んでいるか?名義を確認しよう
土地を処分するにも、まず確認すべきは名義が誰のものかという点です。
相続後に登記をしていないままだと、「売却」「寄付」「譲渡」など、あらゆる手続きができません。
2024年4月からは、相続登記が義務化されました。
相続した土地の登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
近隣トラブルや固定資産税のリスクも放置の代償
草木が生い茂ったり、空き地にゴミが捨てられたりすると、近隣住民とのトラブルに発展することがあります。
行政から「管理不全土地」として勧告を受けることも。
また、土地の評価額が高くない場合でも、固定資産税の軽減措置が外れて増税される可能性があり、放置は結果的にコスト増を招くリスクもあります。
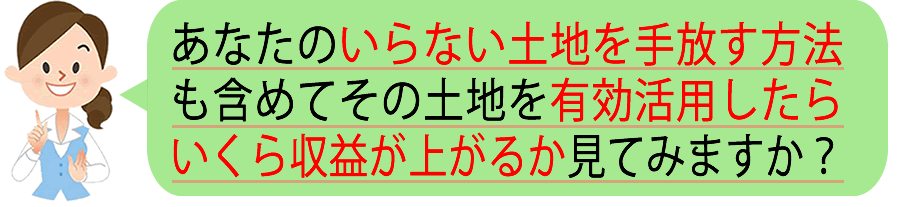

いらない土地の「処分方法」とは?

「いらない土地を手放したい」と思っても、簡単に引き取り手が見つかるわけではないのが現実です。
ここでは代表的な処分方法と、それぞれの特徴・注意点についてわかりやすく解説します。
1. 売却する
最もオーソドックスなのが「売却」です。
しかし、条件の悪い土地は売れにくいことを前提に、売却方法の選択肢を考える必要があります。
不動産会社による売却(仲介)
一般的には不動産会社に依頼して、土地を市場に出す方法です。
相場に近い価格で売れる可能性がありますが、売却までに時間がかかる、買い手が現れないことも。
また、広告費・測量費・登記費用などの諸経費がかかる点にも注意が必要です。
買取業者に売却する
「早く手放したい」という方は、不動産買取業者に直接買い取ってもらう方法もあります。
仲介よりも価格は安くなりますが、現金化が早いというメリットがあります。
とくに「訳あり不動産」「再建築不可」「狭小地」などを専門に扱う業者もあるため、条件の悪い土地でも買い取ってもらえる可能性があります。
隣地所有者に声をかける方法
土地を有効活用しやすいのは、隣接する土地の所有者です。
たとえば、隣地の人が「庭を広げたい」「建物の配置を変えたい」と考えている場合、その土地を買ってくれる可能性が高まります。
不動産会社に依頼して近隣住民にアプローチするケースもありますが、自分で声をかけることができる関係性であれば、仲介手数料が不要な分、スムーズに話が進むこともあります。
2. 寄付する
「売れなくてもいいから、引き取ってもらえればいい」と考える方が次に検討するのが「寄付」です。
しかし、思ったほど寄付先は多くありません。
自治体やNPO法人への寄付は可能?
まず思いつくのが「市町村に寄付する」ことですが、ほとんどの自治体では無条件で土地を引き取ってはくれません。
管理責任や費用が発生するため、原則として「公共利用できる土地」に限定されます。
一部のNPO法人や地域団体が「空き地再生事業」として引き受けてくれる場合もありますが、条件が厳しいのが現実です。
相手が受け取ってくれないケースが多い現実
たとえば「傾斜地」「崖地」「水はけが悪い土地」などは、受け取ってもらえる可能性が非常に低いです。
さらに、地中埋設物や境界不明な土地は管理上のトラブル要因となるため、寄付先がリスクを負いたがらないです。
3. 相続土地国庫帰属制度を使う
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、いらない土地を国に引き取ってもらう制度です。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件と費用がかかる点に注意が必要です。
どんな土地が対象?
以下のような土地は制度の対象外となります。
- 建物がある土地
- 境界が明らかでない土地
- 他人の権利が設定されている土地(地上権・賃借権など)
- 著しく管理が困難な土地(崖地、災害リスクが高い土地など)
つまり、「まったく使えない土地」ほど対象から外れやすいという逆説的な制度です。
手続きの流れと費用
制度の利用には以下の費用が必要です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 審査手数料 | 14,000円(1筆ごと) |
| 負担金(引き渡し時) | 20万円前後が目安 |
また、申請から完了までに半年〜1年以上かかることもあります。
4. 無償譲渡・個人間譲渡
「売れないけど、誰か使ってくれるなら譲りたい」という場合、無償譲渡という選択肢もあります。
SNSやマッチングサービスの活用
近年では、不要な土地の譲渡を希望する人と、活用したい人をつなぐマッチングサイトも登場しています。
SNSや地域掲示板などを活用して、譲り手・受け手が見つかることもあります。
ただし、相手が土地の管理に本当に対応できるかは慎重に見極める必要があります。
譲渡に伴う登記や税金に注意
無償で譲る場合でも、登録免許税・司法書士報酬などの費用がかかります。
また、贈与税や譲渡所得税が発生するケースもあるため、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
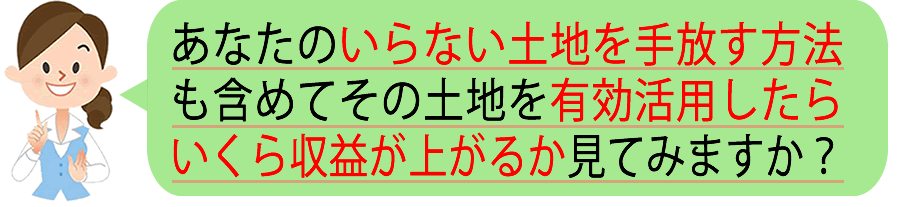

どうしても活用・処分できない土地はどうする?

「売れない」「譲れない」「使えない」――。
ここまでさまざまな方法を試してもなお、処分や収益化ができない土地も存在します。
そうした場合は、「最終手段」や専門的な支援を検討する段階に入ります。
土地を手放せないときの「最終手段」も検討
どうしても活用・処分ができない土地は、管理の手間や税負担をできる限り減らす工夫が必要です。
具体的には次のような方法があります。
- 登記上の整理(分筆・合筆)をして、扱いやすくする
- 一部だけ活用して収益や減税につなげる(例:一部を駐車場にする)
- 固定資産税の減額措置を自治体に相談する
「今すぐには解決しないけど、将来的に何らかの道が開けるかもしれない」と考え、あえて維持しながら機会をうかがうという選択もあります。
専門業者に相談してみる価値があるケース
最近では「訳あり物件専門」の不動産業者や、「土地処分代行」を行う業者も存在します。
売却できない土地や権利関係が複雑な土地も対象にしていることがあるため、諦める前に相談だけでもしてみる価値があります。
また、土地家屋調査士や司法書士、行政書士、税理士など専門家によるアドバイスを受けることで、思わぬ解決策が見つかることもあります。
売却や処分が難航する原因とその対策
以下のような原因が、土地処分を難しくしているケースは非常に多いです。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 境界が不明確 | 測量・境界確認を行い、トラブルのリスクを解消する |
| 所有者が複数人いる(共有) | 他の共有者と協議し、売却の同意を得る |
| 建築基準法の接道義務を満たしていない | 隣地と一体売却や特例の申請を検討する |
| 災害リスクが高い土地 | 用途制限や売却対象の見直しが必要 |
こうしたケースでは、「なぜ売れないのか」を明らかにして、個別に対策を講じることが成功の鍵になります。
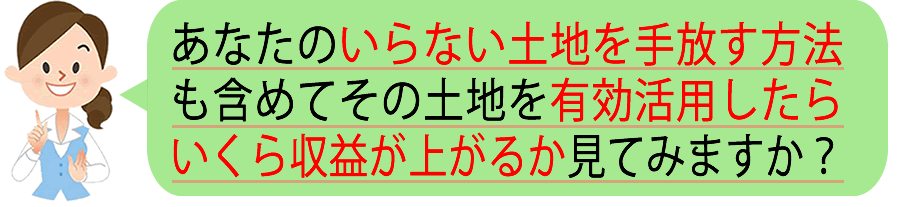

いらない土地の対処に役立つ公的・民間の支援制度

自治体の「空き地バンク」や空き家対策制度
多くの自治体では、地域内の空き地や空き家の有効活用を促進するため、「空き家・空き地バンク」制度を設けています。
登録しておくことで、地域に移住したい人や店舗用地を探している事業者などとマッチングされる可能性があります。
ただし、登録には条件や審査があり、必ずしもすぐに引き取り手が現れるわけではないことに注意が必要です。
民間マッチングサービスの活用
近年では、いらない土地・空き地の所有者と利用希望者をつなぐ民間マッチングサービスが増えています。
たとえば、
- 無償譲渡を希望する人向けのマッチング掲示板
- スモールビジネス向けの土地活用紹介サイト
- ソーラーシェアリングや家庭菜園希望者向けの検索サービス
などがあります。
インターネット検索やSNSでも、「土地 譲ります」「空き地 活用」などのワードで探してみるとよいでしょう。
税理士・司法書士・土地家屋調査士に相談すべき場合とは
以下のようなケースでは、専門家の力を借りることで早期解決につながることがあります。
- 登記が放置されていて、相続人が複数いる
- 境界が不明確で、測量トラブルの懸念がある
- 譲渡にともなう税金が発生する可能性がある
「よくわからないから放置する」のではなく、無料相談からでも一歩を踏み出すことが重要です。
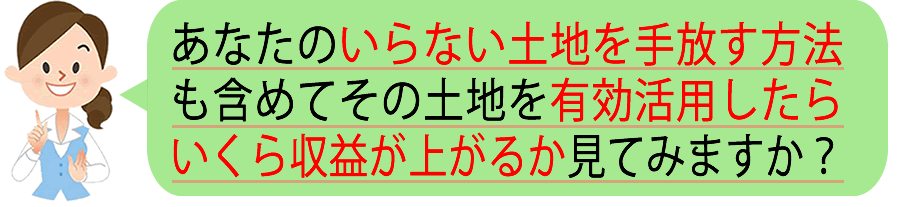

まとめ|いらない土地の対処には「早めの行動」がカギ

「いらない土地をどうすればいいのか?」という悩みは、多くの方にとって共通するものです。
相続や譲渡などで思いがけず所有者になってしまい、活用も処分もできずに放置してしまうことは、誰にでも起こりうる問題です。
しかしながら、放置すれば固定資産税・管理の手間・近隣トラブルのリスクが積み重なっていくばかりです。
活用や収益化が難しい土地であっても、売却・寄付・譲渡・国への引き渡しなどの選択肢があり、それぞれに向き不向きがあります。
重要なのは、「自分の土地の現状を把握し、どの方法が適しているかを知ること」です。
専門家への相談や無料査定、マッチングサービスなどを活用することで、思ってもみなかった道が開ける可能性もあります。
「いらない土地」に悩んでいるのは、あなただけではありません。
早めの行動が、負担を最小限にし、安心した生活へとつながっていきます。
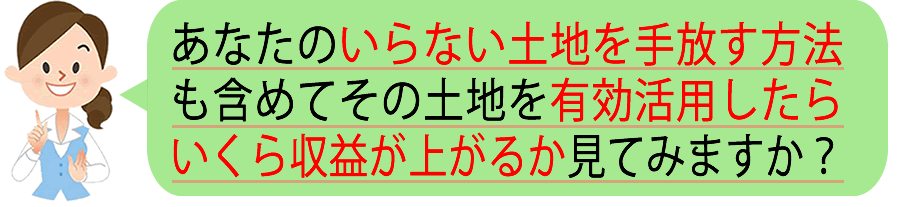

よくある質問(FAQ)
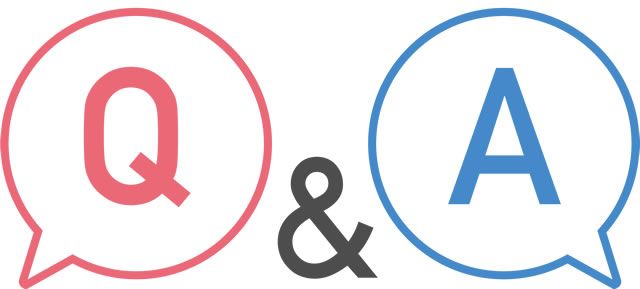
Q. 使っていない土地を放置しても問題ないですか?
固定資産税が毎年かかるほか、雑草や不法投棄による近隣トラブルのリスクがあります。
将来的には相続人に負担を残すことにもなるため、早めの対処をおすすめします。
Q. 相続した山林を処分したいけど、売れません。どうすれば?
山林は活用が難しく需要も少ないため、国庫帰属制度や無償譲渡の検討が有効です。
地域によっては資材置き場などとして使える可能性もあるため、一度専門家に相談してみましょう。
Q. 条件が悪くても活用できる土地の特徴は?
接道している・平坦・水道が使える・市街地に近いといった要素があれば、たとえ狭くても活用の可能性はあります。
小規模トランクルームや貸し農園、簡易駐車場などが検討できます。
Q. 土地を売らずに収益化できる方法はありますか?
トランクルーム経営、資材置き場、ドッグランなど建物を建てずに始められる活用があります。
初期投資とのバランスを見ながら検討するのがポイントです。
Q. 無償で土地を引き取ってもらうことは可能ですか?
自治体が無条件で引き取ることは稀ですが、NPO法人や個人への無償譲渡、国庫帰属制度などを活用することで、処分できる可能性があります。
名義や土地の状態を確認した上での手続きが必要です。
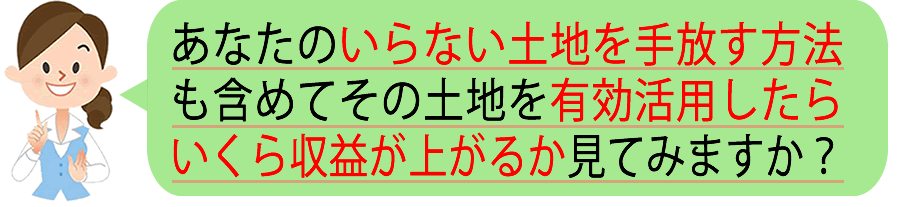

- 土地活用は広さで変わる!100坪・200坪・300坪で考える賢い選択肢と収益性の違いとは?
- 狭い土地でもできる土地活用とは?|3坪・5坪から考える狭小地の可能性
- 賃貸アパート・マンション経営という土地活用|収益性・始め方・失敗しないための実践ガイド
- 駐車場経営は土地活用の定番|リスク・収益性・始め方を徹底解説
- 太陽光発電で土地を活かす方法とは?初期費用・収益性・注意点まで徹底解説
- トランクルーム経営で土地活用|初期費用・収益性・失敗しない運営のコツ
- 老人ホーム・サ高住・介護施設経営という土地活用|収益性・リスク・始め方を徹底解説
- 土地を活用するよりも売却したほうが良いケースとは?
- いらない土地をどうする?条件の悪い土地の手放し方と処分・収益化の選択肢をやさしく解説
土地活用による駐車場や賃貸アパートやマンション経営やサ高住の無料資料請求
▼地域ごとの土地活用で駐車場や賃貸アパートやマンション経営やサ高住を検討する方の情報と無料資料請求はこちらから