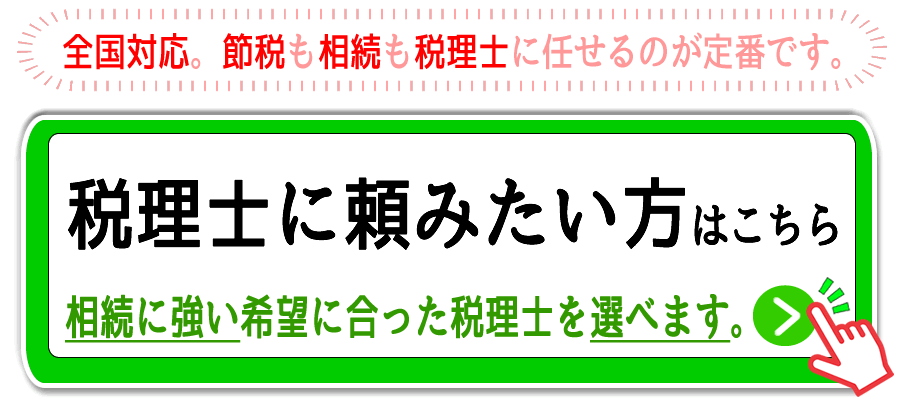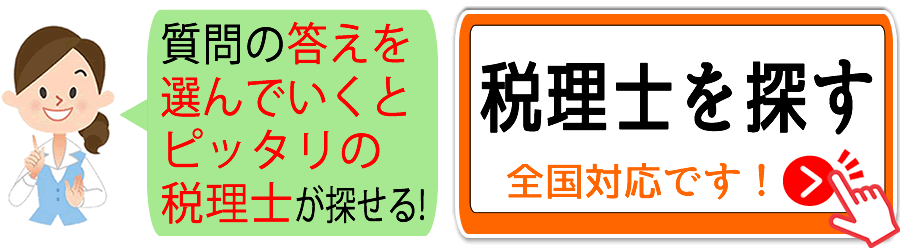PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
相続税に強い税理士を探している方へ|後悔しない依頼先と選び方のポイント

- 相続した不動産は売る?土地活用?家や土地の税金・手続き・トラブル回避のすべて
- 相続した不動産を売却したときの税金ガイド|譲渡所得税・3000万円控除・期限と注意点を徹底解説
- 相続の依頼は弁護士か税理士か?迷ったときの選び方と判断の目安を徹底解説
- 相続の依頼は司法書士か税理士か?登記と税務で迷ったときの判断ポイントとは
- 生前贈与を考えている方へ|損しないために知っておくべき制度・手続き・落とし穴
- 相続した不動産の名義変更手続き完全ガイド|必要書類・流れ・期限まで丁寧に解説
相続税の申告が必要なのはどんなとき?

基礎控除を超える相続が発生したとき
相続税はすべての相続で発生するわけではありません。
基本的には、遺産総額が一定の金額(基礎控除)を超える場合にのみ、相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の基礎控除は以下のように計算されます。
> 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。
遺産総額がこの金額を超える場合は、原則として申告義務が生じます。
都市部に不動産を所有している場合や、預金・有価証券を多く保有していたケースなどでは、相続税の対象となるケースが急増しています。
「うちは関係ない」と思っていた方も、実際に試算してみると申告義務があるケースが少なくないのです。
不動産・株式などの財産が含まれている場合
遺産に不動産や株式などが含まれている場合、その評価額の算出方法が複雑になります。
特に問題となるのは以下のような財産です。
- 相続人が自宅に住み続けるケース(小規模宅地等の特例)
- 収益物件・貸家・貸地
- 非上場株式(自営業・会社経営)
これらの財産は、評価額の違いによって税額が大きく変動するため、税理士の判断やスキルに左右されやすいのが現実です。
また、分割が難しい財産が含まれていると、相続人間のトラブルや税負担の不公平を招く恐れもあります。
そのため、相続に強い税理士に早めに相談し、評価・分割・税負担のバランスを考慮した申告を行うことが大切です。
税務調査が入りやすいケースとは
相続税申告は、提出すれば終わりではありません。
申告内容に不備がある場合や、申告漏れが疑われる場合には、税務署が調査(税務調査)に入ることがあります。
特に調査が入りやすいとされるケースは以下の通りです。
- 明らかに財産の多い家庭にもかかわらず申告額が少ない
- 過去の贈与履歴が複雑である
- 申告書の作成が不慣れな税理士や本人によるものである
- 銀行口座・保険・株式などの資産の記載漏れがある
こうした事態を避けるためにも、相続税申告に慣れた税理士に依頼することが、税務調査リスクを抑えるための有効な対策となります。
相続に強い税理士を選ぶべき理由

相続税申告の経験値がものを言う
相続税申告は、所得税や法人税と異なり、一生に一度あるかないかの手続きです。
だからこそ、経験のある税理士かどうかが成否を大きく分けるポイントになります。
税理士の中には、年間100件以上の申告実績を持つ専門特化型の事務所もあれば、年に数件程度しか相続業務を行わない事務所もあります。
経験値の違いは、節税提案の引き出しの数、調査対応力、スピード感に大きく影響します。
たとえば、小規模宅地の特例や配偶者控除、生命保険非課税枠の活用など、知っているか知らないかで納税額が数百万円単位で変わることもあります。
相続税に強い税理士であれば、こうした制度を的確に活用し、最適な申告を行ってくれます。
評価が難しい財産に対応できる
相続財産には、一律に金額を決められないものが多く存在します。
たとえば、
- 複数の路線に接する不整形地
- 相続人の共有持分となっている土地
- 貸宅地・借地権が絡む不動産
- 評価基準があいまいな非上場株式
こうした財産は、評価の仕方ひとつで税額が大きく変わることがあります。
相続に不慣れな税理士が無理に評価すると、税務署に否認されたり、不適切な申告となるリスクがあります。
相続専門の税理士であれば、不動産鑑定士や司法書士との連携も含めて、正確な評価と分割を提案してくれます。
税務署との交渉もスムーズに進む
税務調査は、提出された相続税申告書の内容が不自然な場合に実施されます。
もし税務署から「調査に伺います」と連絡があった場合、その後の対応によって追徴課税の有無や額が大きく変わってきます。
このとき、相続税に精通した税理士が立ち会えば、調査官との論点整理や資料説明がスムーズに行われ、結果として大きな修正なく終わる可能性が高くなります。
さらに、相続に強い税理士は、税務署の指摘を事前に予測し、調査されにくい申告書を作成するノウハウを持っています。
つまり、正確性と防御力の高い申告書を作ってくれるという点で、依頼者にとっては非常に心強い存在です。
相続に強い税理士の見分け方

相続専門チームや実績があるか
相続税申告の経験が豊富な税理士は、専門の相続チームや相続専門部署を設けていることが多くあります。
こうした事務所では、相続専任スタッフが申告から手続き、各士業との連携まで一貫して対応してくれるため、安心して任せられる体制が整っています。
特に確認しておきたいのが、
- 年間の相続税申告件数
- 土地評価や非上場株評価を含む案件の割合
- 実績として公開されている事例や口コミ
単に「相続にも対応できます」と書かれているだけでなく、相続専門ページが用意されているか、過去の実績が具体的に提示されているかも大きな判断材料となります。
節税提案が具体的か
相続税の負担は、税理士の節税提案の有無で大きく変わります。
たとえば、以下のような制度を的確に活用してくれるかどうかが重要です。
- 小規模宅地等の特例(最大80%の減額)
- 配偶者の税額軽減
- 生命保険の非課税枠
- 二次相続を見据えた財産配分
- 暦年贈与との組み合わせ提案
経験の浅い税理士の場合、「特例の適用漏れ」「余分な納税」「調査リスクの増大」といった問題が起こることもあります。
初回相談の段階で、財産概要に基づいた簡易試算や節税案を出してくれるか、具体例を挙げながら説明してくれるかを確認することで、信頼に値するかを見極めることができます。
不動産・非上場株の評価に詳しいか
相続財産において、不動産や非上場株式は最も評価が難しく、かつ税額への影響が大きい項目です。
そのため、これらに精通しているかどうかは、相続に強い税理士を見極めるうえで欠かせません。
以下のような知識・対応力がある税理士は、評価スキルが高い傾向にあります。
- 路線価・倍率方式・地積規模の大きな宅地の知識がある
- 貸家建付地・底地・借地など複雑な権利関係に対応可能
- 中小企業評価指針に基づく非上場株式評価の実績あり
- 必要に応じて不動産鑑定士や弁護士と連携を取っている
相続税は、評価が高すぎれば納税額が増え、低すぎれば税務署から否認されるリスクが伴います。
そのため、適正かつ合理的な評価を行える税理士を選ぶことが不可欠です。
相続税申告の料金相場は?

財産総額による費用の目安
相続税の申告にかかる税理士報酬は、遺産総額に応じて変動するのが一般的です。
以下はおおよその目安となる料金帯です。
| 遺産総額 | 申告報酬の目安(税抜) |
|---|---|
| 〜5,000万円未満 | 20万円〜40万円程度 |
| 〜1億円未満 | 30万円〜70万円程度 |
| 1億円〜2億円 | 60万円〜100万円超 |
| 2億円超 | 応相談(100万円〜200万円以上) |
これはあくまで目安であり、実際には財産の種類・数・評価の複雑さ・相続人の数などにより変動します。
土地が複数ある・非上場株式を含む・海外資産があるといったケースでは、追加報酬が発生することが一般的です。
「いくらかかるのか心配」という方は、初回相談時に概算の費用を提示してもらうのが安心です。
加算されることの多い業務とその費用
相続税申告においては、以下のような付加的業務が発生する場合、基本報酬とは別に加算料金が請求されることがあります。
| 加算業務内容 | 加算相場(税抜) |
|---|---|
| 土地1筆ごとの評価 | 3万円〜10万円/筆 |
| 非上場株式の評価 | 10万円〜30万円/社 |
| 申告期限まで2か月以内の特急対応 | 5万円〜10万円 |
| 税務調査立会い・書面添付 | 5万円〜15万円 |
| 二次相続を見越した分割設計 | 5万円〜15万円 |
土地や会社が絡む場合、価格設定が複雑になるため、個別見積もりが必要です。
「土地1筆あたり加算」「非上場株式は別料金」といった点は、契約前に明示してもらうようにしましょう。
また、銀行手続きや遺産分割協議書の作成支援など、税務外の業務が含まれる場合は、別途実費や手数料が発生することもあります。
見積もりは複数社で比較を
相続税申告の料金は、税理士ごとに設定基準が異なるため、複数の税理士から見積もりを取り比較検討することが非常に重要です。
比較の際には、単に価格だけでなく以下の点もチェックしましょう。
- 対応範囲の明確さ(どこまでが料金に含まれるか)
- 税理士本人が対応するのか、事務スタッフが中心か
- 料金体系が固定制か、成果報酬型か
- 修正申告や税務調査対応の有無
見積書には「土地評価●筆」「相続人●人」「財産総額●万円」など、条件が明記されているかを確認してください。
中には、初回面談や簡易見積もりを無料で対応してくれる事務所も多いため、安心して相談できる相手をじっくり選ぶことが、後悔しない税理士選びのコツです。
相続税に関するよくあるトラブルと防止策

遺産分割でもめた場合の注意点
相続に関するトラブルで最も多いのが、遺産分割をめぐる相続人同士の対立です。
被相続人が遺言書を残していなかった場合、法定相続人全員による協議で財産の分け方を決める必要があります。
この協議がまとまらないと、相続税申告に必要な「遺産分割協議書」や「名義変更手続き」ができず、結果的に特例や控除が使えなくなるリスクがあります。
例えば、小規模宅地の特例や配偶者控除は、分割が確定していない財産には適用されません。
つまり、もめて申告が間に合わないと、結果的に税額が高くなるのです。
税理士が関与していれば、法的アドバイスこそできないものの、節税上の観点から冷静な判断材料を提示することができ、相続人同士の橋渡し役としても機能します。
税務調査が入るとどうなる?
相続税の申告後、一定割合の申告に対して税務調査が行われます。
調査対象となるのは、申告内容に不自然な点があるケースや、過去の贈与歴・不動産評価に疑義があるケースが多く、調査時期は通常申告から1〜2年以内です。
調査では、以下のような点がチェックされます。
- 通帳の動きや贈与履歴の整合性
- 現金・宝飾品・タンス預金の記載漏れ
- 不動産の評価が適正かどうか
- 名義財産(実際の所有者と異なる名義)に関する判断
調査の結果、申告漏れや過少申告が認定されると、追徴課税や延滞税が発生するだけでなく、ペナルティ(過少申告加算税など)が課されることもあります。
相続に強い税理士であれば、税務署に指摘されやすいポイントをあらかじめ見抜き、正確で防御力のある申告書を作成することが可能です。
また、調査対応の実績がある税理士であれば、調査時にも適切に立ち会い、主張すべき点を代弁してくれます。
節税対策が認められないケース
相続税の節税対策にはさまざまな方法がありますが、すべてが適用されるとは限りません。
中には、無理に適用した結果、否認されたり、追加納税の対象となるケースもあります。
よくある「否認されがちな節税策」には以下のようなものがあります。
- 小規模宅地の特例を適用するも、居住実態が認められなかった
- 名義預金の存在を否定したが、通帳の出入りから被相続人の財産と判断された
- 生前贈与と主張したが、贈与契約書や証拠がなく形式的だった
- 評価減を目的に不自然な借地・借家契約を結んだが、実態がないと判断された
これらは「形式は整っていても、実態がない」と税務署に判断されると否認されるため、制度の内容を正しく理解したうえで活用することが不可欠です。
相続に精通した税理士であれば、「否認されないための準備・書類の整備・説明責任を見越した設計」が可能です。
トラブルを避けるためにも、安易な自己判断ではなく、必ず専門家の意見を仰ぐことが重要です。
相続税申告までの流れと準備すべきこと

申告までのスケジュール感
相続税の申告には期限があり、原則として相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内に手続きを完了させる必要があります。
以下は一般的なスケジュール例です:
| 時期 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 相続開始〜2か月 | 死亡届の提出・葬儀、遺言書の有無確認、相続人の調査 |
| 〜4か月 | 財産の調査・預金や不動産の評価・債務の洗い出し |
| 〜6か月 | 遺産分割協議の開始、相続税の試算、税理士への依頼 |
| 〜8か月 | 協議の取りまとめ、財産評価確定、必要書類の収集 |
| 〜10か月 | 相続税申告書の作成・提出、納税の実行 |
注意したいのは、思った以上に時間がかかる作業が多いという点です。
特に、遺産分割協議が長引いたり、不動産の評価が難航すると、ギリギリになってしまうリスクがあります。
早めに税理士に相談し、スケジュールを立てて進めることで、申告期限を守りつつ、節税にもつながる準備が可能となります。
必要書類と財産の一覧化
相続税申告に必要な書類は多岐にわたり、準備不足が申告遅延や特例不適用の原因となります。
以下は主な書類一覧です。
相続人関係の書類
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺言書(ある場合)
- 相続人の印鑑証明書
財産関係の書類
- 預貯金残高証明書(すべての金融機関)
- 有価証券・株式の明細書
- 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 生命保険金支払明細書
- 借入金残高証明書・未払い税金・未払金など
その他
- 葬儀費用の領収書
- 贈与履歴(生前贈与がある場合)
- 財産目録(相続税申告用)
税理士に相談する際には、可能な限りこれらの資料をそろえて持参することで、正確な申告試算・節税提案がスムーズに進みます。
早めの相談が重要な理由
相続は突然始まるものですが、申告には多くの準備が必要\
だからこそ、「税理士に相談するのは申告直前でいい」という考えは非常に危険です。 早期に相談することで得られるメリットは以下の通りです: また、税理士によっては「期限ギリギリの新規依頼は受け付けていない」ケースもあるため、余裕を持ったスケジュールで相談を始めることが、失敗しない相続税対策の第一歩となります。 相続税の申告を依頼したいと思ったとき、どこで税理士を探すかは大きな悩みどころです。 知人の紹介がない場合は、税理士紹介サイトや自治体・商工会議所の相談窓口を活用するのが一般的です。 ただし、紹介サイトや相談窓口を通じて出会ったからといって、すべての税理士が相性良好とは限りません。 次の項目でご紹介する「初回相談での確認事項」をしっかりチェックし、自分に合った専門家かどうかを見極めましょう。 初めて税理士と面談する際には、以下のような項目を確認することで、依頼後のトラブルを避けることができます。 過去の申告件数、土地・非上場株式の評価経験などを質問し、対応力を見極めましょう。 基本報酬・加算項目・納税サポート・税務調査対応の有無などを確認し、明細のある見積書を依頼するのが安心です。 こちらの質問に対して丁寧に答えてくれるか、専門用語を使わず平易な言葉で説明してくれるかも重要な判断基準です。 進行のペースを説明してくれる税理士は、計画的な進行を重視する信頼性の高い人物といえるでしょう。 特に、自分と家族に寄り添う姿勢があるかどうかは、実務以上に大切な要素です。 「話しやすい」「信頼できる」と感じられるかを大切にしてください。 「最初に依頼した税理士と合わなかった」「対応が遅い」「質問しても答えが曖昧」といった理由で、他の税理士への変更を検討する方も少なくありません。 税理士は契約上、申告前であれば変更することが可能です。 変更時には以下の点に留意してください。 「このまま任せて本当に大丈夫なのか」と感じたときは、セカンドオピニオンを得るための相談を他の税理士に持ちかけてみるのも有効です。 後悔しない相続税申告のためには、税理士との信頼関係と納得感がなにより大切です。 迷ったときは、遠慮せず専門家を変えるという選択肢も検討してみましょう。 相続税の申告には明確な期限があり、相続開始から10か月以内に手続きを完了させなければなりません。 この「10か月」という期限は、遺産の把握・評価・分割協議・申告・納税という数多くの作業を進めるには、意外と短いというのが実感です。 特に以下のような場合は、期限ギリギリの申告がリスクを伴うことがあります。 期限を過ぎると、特例の適用が受けられなかったり、延滞税・加算税が課されたりする可能性もあります。 だからこそ、できるだけ早く、経験豊富な税理士に相談することが不可欠です。 相続税は、一見して「自分たちだけで何とかできそう」と思う方もいるかもしれません。 しかし、実際には、 など、専門知識と実務経験が問われる場面が非常に多いのです。 相続に強い税理士であれば、こうした複雑な判断をすべて引き受け、依頼者が安心して本来の手続きやご家族との時間に集中できる環境を整えてくれます。 また、節税だけでなく、「後から揉めない申告」や「税務署に否認されにくい記録」を整えることで、長期的にも安心できる財産管理につながります。 相続税の申告は、法律上はご自身で行うことも可能です。 しかし、財産評価の難しさや節税制度の活用、申告ミスによるペナルティのリスクを考えると、税理士に依頼するのが現実的です。 特に、不動産や非上場株式を含む複雑な財産がある場合は、専門の税理士に任せることで大きな安心が得られます。 相続税の申告が期限(相続開始から10か月以内)に間に合わないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。 また、小規模宅地の特例や配偶者控除といった優遇措置が適用できなくなる恐れもあります。 早めの相談・準備が重要です。 実績と専門性を確認するのがポイントです。 年間の相続税申告件数や、土地や株式の評価経験の有無、相続専用ページや事例紹介の有無などをチェックしましょう。 初回相談で節税提案の具体性を見れば、実力の差が見えてきます。 相続が発生したら、できるだけ早く税理士に相談するのがベストです。 申告期限までの10か月は、財産調査や評価、協議、書類収集であっという間に過ぎてしまいます。 相続税申告の経験豊富な税理士であれば、スケジュール管理と節税提案を早期に進めてくれます。 ▼地域ごとの相続の手続きの情報はこちらから ▼地域ごとの税理士の情報はこちらから
相続税の申告を税理士に依頼する方法

紹介サイト・地域の相談窓口を使う
税理士紹介サイトのメリット
地域の窓口のメリット
初回相談で確認すべきポイント
相続税申告の実績や専門性
料金体系の明確さ
相談への対応姿勢と説明のわかりやすさ
申告期限までのスケジュール管理と納期感覚
税理士変更も可能|相性の合わないときは
まとめ|相続に強い税理士に早めに相談を

「申告期限10か月」の壁に注意
節税・トラブル防止はプロに任せるのが安心
よくある質問(FAQ)
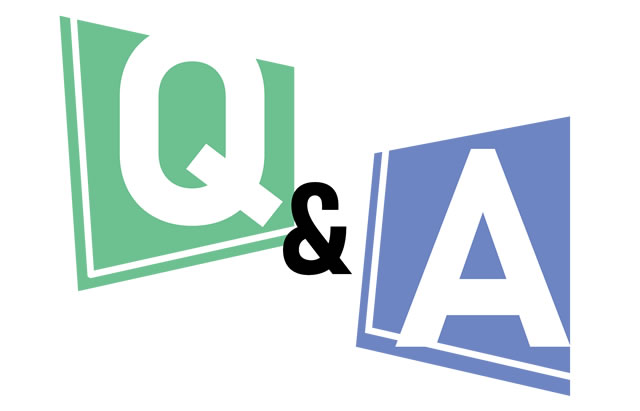
Q. 相続税の申告は必ず税理士に依頼しないといけませんか?
Q. 申告期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
Q. 相続に強い税理士かどうかは、どう見分ければよいですか?
Q. 税理士への相談はいつ頃から始めるのがベストですか?
全国の相続の手続き完全ガイド|まず何をすればいい?期限・流れ・必要書類を徹底解説
全国の税理士を探す