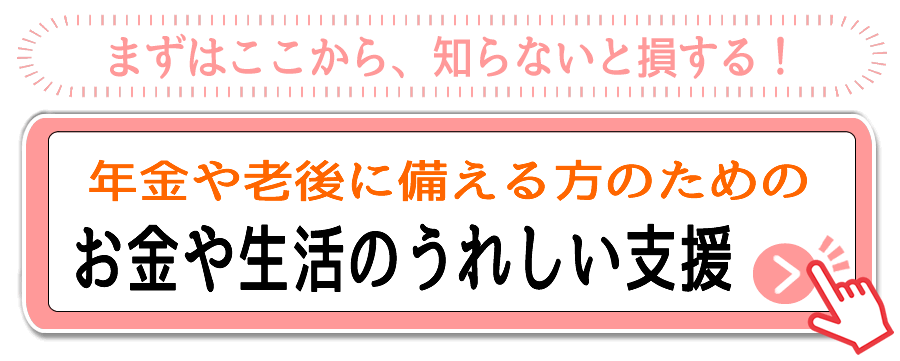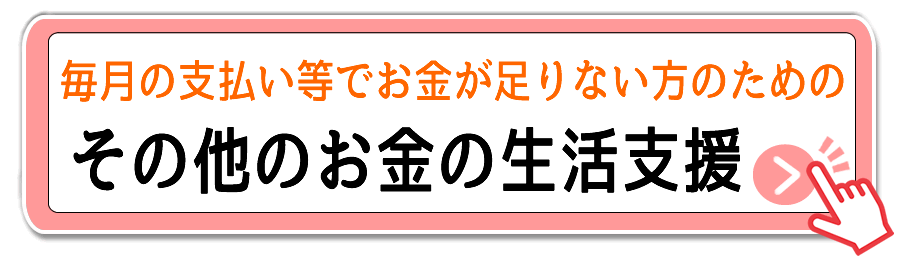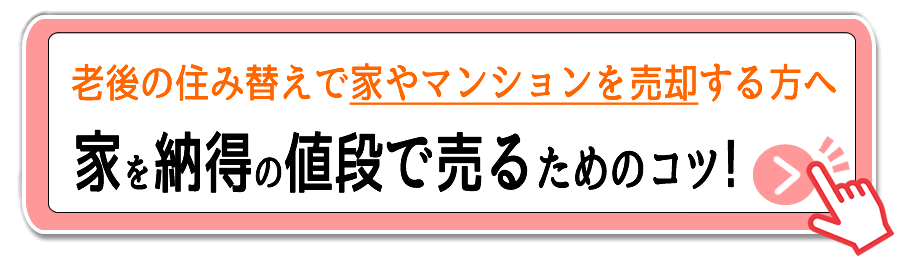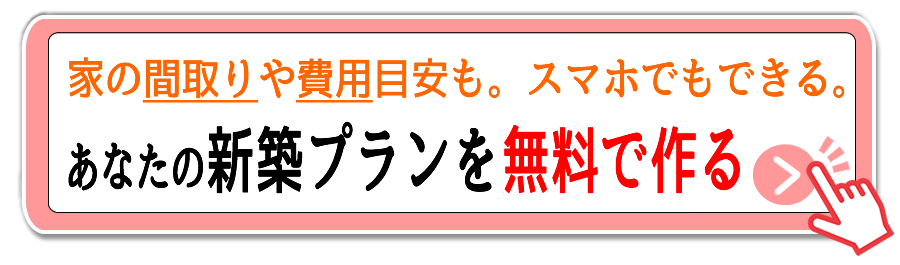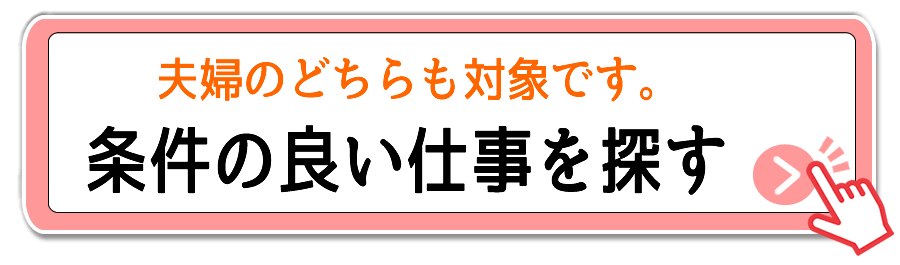年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説

- 年金から天引きされるお金とは?
- 天引き額の目安はいくら?年金額ごとのシミュレーション
- 「こんなに引かれるの?」と感じたときのチェックポイント
- 年金の天引きはやめられる?対処法と選択肢
- 年金生活を圧迫しないための工夫とは
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|天引きを理解して、安心の年金生活を
- 年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 遺族基礎年金とは?寡婦年金との違いと死亡後の年金手続き|亡くなった人の年金はどうなる?
- 障害年金でもらえる金額と条件とは?1級・2級・3級の等級別の受給額と認定基準の違いをやさしく解説
- 介護認定を受けるには?申請の流れと注意点をわかりやすく解説|初めてでも安心の手続きガイド
年金から天引きされるお金とは?

年金受給が始まると、意外な出費として驚く方が多いのが「年金からの天引き」です。
「毎月の年金が少ないな」と感じて明細を見てみると、いくつかの項目で天引きがされていることに気づきます。
実はこれは制度として当然の処理であり、多くの方に共通する部分と、個人差のある部分があります。
まずは「天引きとは何か」から見ていきましょう。
そもそも「天引き」とはどういう意味?
「天引き」とは、給付される金額からあらかじめ必要な費用を差し引いて支給することを指します。
年金に限らず、給与明細でもよく使われる言葉です。
たとえば、会社員の給料から税金や保険料が差し引かれて振り込まれるのと同じように、年金の支給額からも一定の金額が差し引かれて支給されます。
これが「年金の天引き」です。
国が自動で行う処理であるため、「勝手に引かれている」という印象を持たれることもありますが、その中身を理解すれば、公的制度の維持に必要な仕組みであることがわかります。
公的年金から天引きされる代表的な項目
天引きされる項目は人によって異なりますが、代表的なものは以下の3つです。
国民健康保険料(後期高齢者医療保険)
75歳以上になると、「後期高齢者医療制度」に加入することになり、医療保険料が発生します。
その保険料は、原則として年金から自動的に天引きされる仕組みになっています。
なお、75歳未満でも、65歳以上で一定の障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も、同様に年金から天引きされる場合があります。
介護保険料(65歳以上対象)
65歳以上になると第1号被保険者として介護保険料の支払いが必要になります。
これもまた、原則として年金から天引きされる仕組み(特別徴収)が採用されています。
ただし、年金額が年18万円未満の場合や、新たに65歳に到達したばかりの方などは、一時的に「口座振替(普通徴収)」で納めることがあります。
住民税(所得に応じて)
住民税も、年金から天引きされることがある項目です。
ただしこれは「所得が一定以上ある方」に限られ、すべての年金受給者が対象になるわけではありません。
たとえば、企業年金や個人年金の収入が多い場合、市区町村が住民税の特別徴収(天引き)を行うケースがあります。
その他:所得税・社会保険料等の可能性
上記以外にも、特定の年金(企業年金や私的年金)では、源泉徴収として所得税が差し引かれる場合があります。
また、過去に未納の保険料があると、滞納分の徴収が行われるケースも。
これは個別対応となるため、年金機構や市区町村からの通知をしっかり確認することが重要です。
特別徴収制度とは?天引きとの関係を知る
「特別徴収」という言葉は、給与や年金などから自治体が税や保険料を直接徴収する仕組みを指します。
これが「天引き」の制度的な裏付けです。
年金の場合、主に国民健康保険料(後期高齢者医療)、介護保険料、住民税などが特別徴収の対象となります。
対象者には市区町村から「特別徴収開始通知書」が送られます。
一定以上の年金支給額(年額18万円以上)がある場合に限り、特別徴収が自動的に適用されるのが原則です。
支給額が低い方は「普通徴収(自分で納付)」になります。
天引き額の目安はいくら?年金額ごとのシミュレーション

「天引きされる金額って実際いくらくらいなの?」という疑問を持つ方は少なくありません。
しかし実際には、天引き額は人によってかなり異なります。
ここでは、その違いが生まれる理由や、年金額別のケーススタディを通じて、平均的な目安を紹介します。
天引き額は人によって違う理由
天引きされる金額が一定でないのは、主に以下のような条件が関係しています。
住んでいる自治体の違い
介護保険料や後期高齢者医療保険料は、市区町村ごとに保険料率が異なります。
都市部と地方でも差があり、同じ年金受給額であっても天引きされる金額に違いが出ます。
たとえば、A市では介護保険料が月額7,000円でも、B町では月額5,000円というケースも。
住民税についても自治体ごとに若干の差があります。
所得や扶養状況による違い
天引きされる金額は、本人の所得や世帯の所得状況によっても変わります。
具体的には、住民税の課税・非課税判定や、保険料の「段階(所得段階別)」によるものです。
高所得の方は保険料の負担も高くなり、反対に所得の少ない方は軽減措置が適用される場合があります。
月額年金10万円/15万円/20万円の場合の天引き例
ここでは、月額年金が10万円、15万円、20万円のケースにおいて、天引きされる金額の一例をシミュレーション形式でご紹介します。
※数値は参考値であり、実際の金額は自治体や条件によって異なります。
年金月額10万円:手取りはどのくらい?
年金収入が月10万円(年120万円)の方の場合、所得も控えめなため、住民税が非課税になるケースが多く、保険料も軽減されやすい傾向があります。
- 後期高齢者医療保険料:3,000円程度
- 介護保険料:4,000円程度
- 住民税:非課税の可能性あり
合計の天引き額:月7,000円前後
手取り支給額は約93,000円ほどとなります。
年金月額15万円:意外に多い天引きの中身
年金月額15万円(年180万円)のケースでは、一定の所得があると見なされ、住民税が課税される可能性が出てきます。
- 後期高齢者医療保険料:4,000〜5,000円
- 介護保険料:5,000〜6,000円
- 住民税:3,000〜5,000円
合計の天引き額:月12,000〜16,000円程度
手取りは13万円台に落ち着くことが多いです。
年金月額20万円:住民税が高いと…
年金月額20万円(年240万円)になると、住民税の負担が大きくなるケースが増えます。
また、企業年金や個人年金の併給があれば、所得税の対象になる場合もあります。
- 後期高齢者医療保険料:5,000〜6,000円
- 介護保険料:6,000〜8,000円
- 住民税:6,000〜10,000円
合計の天引き額:月17,000〜24,000円程度
手取りは約17万〜18万円程度に落ち着きます。
平均的な天引き額の統計は?
厚生労働省や自治体の資料によると、後期高齢者医療保険料の全国平均は、年間約10万円前後となっています。
介護保険料も同程度が目安です。
つまり、年金からの天引きとしては、年間20万円前後、月あたり1.5〜2万円が一般的とされています。
これに住民税が加われば、さらに増えることもあります。
年金生活では「支給額」ではなく「手取り額」で生活設計をすることが重要です。
毎月の支出が不安定な方は、まず天引きの内訳を明細で確認する習慣を持ちましょう。
「こんなに引かれるの?」と感じたときのチェックポイント

年金受給が始まったばかりの方や、毎年の年金額の変動に戸惑っている方の中には、「こんなに天引きされるなんて思わなかった…」という驚きの声も多く聞かれます。
実際、思ったより手取りが少ないと感じる原因には、いくつかの共通パターンがあります。
ここではそのチェックポイントをご紹介します。
住民税が想定より多いケース
とくに注意が必要なのが住民税の特別徴収が始まった年です。
年金から住民税が天引きされるのは、「前年の所得に応じて計算された住民税」が市区町村によって差し引かれるため、昨年の収入状況が影響します。
たとえば、退職金や企業年金、一時的な副収入が前年にあった場合、それに基づいた住民税が翌年度に加算され、「思った以上の天引き額」になることがあるのです。
介護保険料が急に増えた理由
介護保険料は、本人の所得段階(所得割)に応じて7〜9段階程度に分けて決定されます。
前年に比べて医療費控除や扶養控除が減っていたり、年金額が上がっていたりすると、「所得が増えた」と判断されて段階が上がることがあります。
また、多くの自治体では保険料率が毎年度見直されるため、地域全体で保険料が値上がりした結果、天引き額が増えることもあります。
年金から天引きされる対象になったタイミング
65歳や75歳といった節目の年齢を迎えると、自動的に保険制度の加入区分が変わり、それに伴って天引きが始まる場合があります。
たとえば、65歳になると介護保険料の特別徴収が始まり、75歳になると後期高齢者医療保険料が発生します。
これらの制度は、自動的に適用されるため、本人の意思に関係なく開始されることが多く、通知を見落としていると驚くこともあります。
手取りが減ったと感じたら明細を確認
年金の支給明細は、偶数月の支給時に送付される書面や、「ねんきんネット」などで確認できます。
明細には、「支給額」「控除項目」「天引き額」「差引支給額」が記載されています。
とくに前年との比較をすると、どの項目が増えているのかが見えてきます。
「急に手取りが減った」「何が引かれているかわからない」といった不安がある方は、まず明細書を丁寧に見て、不明な点は年金事務所や自治体に問い合わせてみましょう。
年金の天引きはやめられる?対処法と選択肢

年金からの天引きに戸惑いや不安を感じたとき、真っ先に思い浮かぶのが「これはやめられないのか?」という疑問ではないでしょうか。
結論から言えば、一部の天引き項目については変更や猶予の可能性がありますが、すべてが自由にやめられるわけではありません。
ここでは、特別徴収(天引き)の対象となっている各制度について、普通徴収(自分で支払う方式)への切り替え可否や、その際の注意点を解説します。
「口座振替(普通徴収)」に変更できる?
原則として、年金から天引きされている保険料や税金は、市区町村に申請することで「口座振替」へ変更できる可能性があります。
これにより、支払いのタイミングや管理を自分で行えるようになり、「何にいくら払っているか」を可視化しやすくなるというメリットもあります。
ただし、制度上「特別徴収が優先」とされているため、希望すればすぐに普通徴収へ切り替えられるとは限りません。
個別に審査や制限があることを理解しておきましょう。
特別徴収から普通徴収への変更方法
変更を希望する場合は、各自治体の役所・市民課や保険年金課などへ申請します。
必要となるのは、次のような手続きです。
- 本人確認書類の提出
- 「徴収方法変更申請書」などの様式への記入
- 金融機関口座の登録(口座振替に切り替える場合)
ただし、申請タイミングによっては翌年度からの変更となることが多く、すぐに天引きが停止されるわけではない点にご注意ください。
自治体ごとに異なるルールと注意点
介護保険料や後期高齢者医療保険料については、自治体ごとに徴収方法や変更可否の運用が異なります。
ある市では「原則特別徴収のみ」として変更を認めていないケースもあり、また別の市では、生活上の事情があれば柔軟に対応してくれることもあります。
とくに「口座残高管理を自分でしたい」「家計のやりくりを明確にしたい」など、合理的な理由を添えて相談することが、変更を認めてもらう第一歩になります。
「やめられない項目」もあることに注意
すべての天引きが任意に切り替えられるわけではありません。
たとえば、住民税や所得税などの法定徴収分は、一定の条件下で自動的に特別徴収となり、変更不可とされる場合があります。
また、企業年金連合会などの支給する年金では、最初から税金が源泉徴収された状態で支給されるため、そもそも天引きではなく「差し引き済み」であることに注意が必要です。
つまり、天引きには「制度によって絶対に避けられないもの」と「個別事情で変更が可能なもの」が混在しているのです。
年金生活を圧迫しないための工夫とは

年金からの天引きは避けられない部分も多いため、手取り額が思ったより少なく、生活が苦しいと感じることもあるでしょう。
しかし、天引き制度を正しく理解しつつ、使える制度を上手に活用すれば、年金生活の不安を軽減し、安心感を持って過ごすことが可能です。
ここでは、年金生活を圧迫しないために今からできる工夫をご紹介します。
手取りを正しく把握して生活費を調整
まず第一に重要なのが、「支給額」ではなく「手取り額」を基準に家計を考えることです。
たとえば、月額15万円の年金を受給していても、介護保険料・後期高齢者医療保険料・住民税などで2万円前後が天引きされることもあります。
実際に使える金額は月13万円ほどであるにも関わらず、「15万円あるつもり」で生活設計をすると赤字に陥りやすくなります。
支出管理の際には、必ず「差引支給額(手取り)」をベースに計画を立てましょう。
節税・控除制度を活用する
少しでも手元に残るお金を増やすためには、税金や保険料の軽減につながる制度を賢く利用することがカギです。
社会保険料控除
年末調整や確定申告で、支払った介護保険料や国民健康保険料を「社会保険料控除」として申告することで、所得税や住民税の軽減が期待できます。
医療費控除
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、医療費控除の対象になります。
交通費や薬局での市販薬購入も含まれる場合があるため、レシートを保管しておくとよいでしょう。
障害者控除・寡婦(寡夫)控除など
身体に障害がある方や、一定の条件を満たす寡婦・寡夫の方は、自治体や国税庁に控除申請を行うことで、住民税や所得税の負担を軽くできることがあります。
申告しなければ適用されない控除も多いため、「年金受給者でも申告が必要なのか?」と疑問に思ったときは、市区町村の税務担当窓口へ相談してみましょう。
福祉・減免制度を確認する
生活が苦しいときには、福祉的な支援や保険料の減免制度を利用できる場合があります。
住民税の非課税世帯
所得が一定以下の場合、住民税が「非課税世帯」として扱われることがあり、これにより介護保険料や医療費負担の軽減、公共料金の減免などが受けられる場合があります。
保険料の減免申請
後期高齢者医療保険料や介護保険料は、本人や世帯の収入減少などを理由に「減免制度」の申請が可能です。
とくに、退職・病気・災害など突発的な収入減があった場合は、必ず早めに役所へ相談してください。
知らずに通常通りの保険料を払い続けるのではなく、相談しながら制度を活用することで、年金生活の負担を減らすことができます。
よくある質問(FAQ)

Q. 年金から天引きされるのは何歳からですか?
一般的に65歳から介護保険料、75歳から後期高齢者医療保険料が年金から天引きされるようになります。
住民税については所得や地域によって変わりますが、特別徴収の対象になったタイミングで天引きが始まります。
Q. 年金が少ない人も天引きされるのですか?
はい、年金の額に関わらず一定の年齢に達すると天引きが発生します。
ただし、年金額が年18万円未満の方は特別徴収ではなく、普通徴収(自分で支払う方式)となる場合もあります。
また、所得が少ない方には軽減措置が適用されることがあります。
Q. 天引き額を確認するにはどうすればいいですか?
支給明細書を見るか、「ねんきんネット」などのオンラインサービスで確認することができます。
不明点がある場合は、年金事務所や市区町村の担当課に問い合わせましょう。
Q. 過払い・誤徴収などのトラブルはありますか?
ごくまれに、自治体側の手続きミスや本人の情報更新漏れによって、誤って天引きされたり、金額が間違っていたりすることがあります。
支給明細を確認し、疑問がある場合は必ず問い合わせて確認しましょう。
Q. 年金天引きに関する相談窓口はどこですか?
日本年金機構(年金事務所)またはお住まいの市区町村の「保険年金課」や「高齢福祉課」などが窓口になります。
年金や保険料の種類によって相談先が異なるため、まずは役所に確認するのが安心です。
まとめ|天引きを理解して、安心の年金生活を

年金生活においては、毎月受け取る金額よりも、実際に使える「手取り額」が生活の軸になります。
天引きという仕組みは一見複雑に見えますが、制度に則った公的な徴収方法であり、必要不可欠な医療や介護の支えでもあります。
とはいえ、「何にいくら引かれているのか」を把握しないままにしておくと、知らぬ間に生活が圧迫されてしまうことも。
まずは明細書や「ねんきんネット」を活用し、定期的に確認する習慣をつけましょう。
また、減免制度や控除制度の活用、普通徴収への切り替え相談など、できる対処も多数存在します。
「制度を知って動くこと」が、ゆとりある老後の第一歩となります。
もし不明点や不安がある場合は、一人で抱え込まずに、年金事務所や市区町村の窓口に相談してみてください。
正しく知って、上手に備えることが、年金天引きとの賢い付き合い方です。
- 年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 遺族基礎年金とは?寡婦年金との違いと死亡後の年金手続き|亡くなった人の年金はどうなる?
- 障害年金でもらえる金額と条件とは?1級・2級・3級の等級別の受給額と認定基準の違いをやさしく解説
- 国民年金が払えないときは?保険料免除制度の条件・申請方法をわかりやすく解説
- 年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説
全国の年金受け取りの手続きのやり方は?申請と流れを徹底解説
▼地域ごとの年金受給の手続きの情報はこちらから