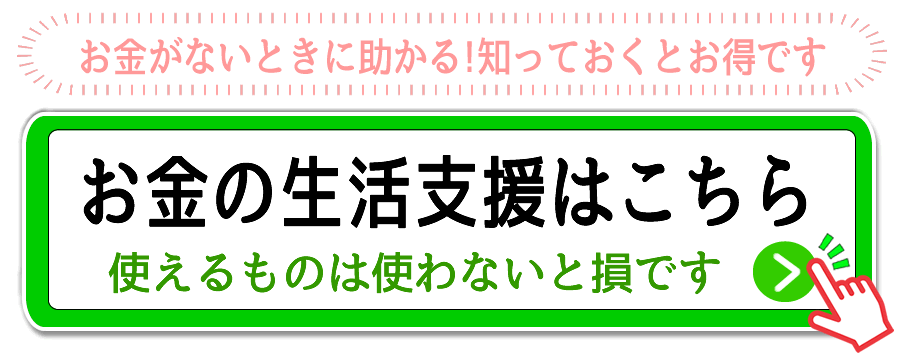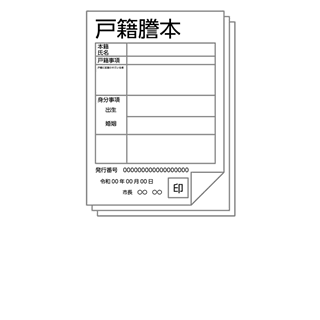国民年金が払えないときは?保険料免除制度の条件・申請方法をわかりやすく解説

- 国民年金の支払いがつらい…そんなときは免除制度を検討して
- 国民年金の保険料免除制度とは?
- 免除には種類がある|4つのパターンをわかりやすく解説
- 免除の対象になる条件とは?
- 免除申請のやり方と必要書類
- 免除期間の扱いと追納について
- 免除が認められなかった場合は?
- 免除を受けるときのよくある誤解と注意点
- まとめ|無理せず、正しく免除制度を活用しよう
- よくある質問(FAQ)
国民年金の支払いがつらい…そんなときは免除制度を検討して

払いたくても払えない人が増えている
毎月の支払いが厳しく感じられるものの一つが、国民年金の保険料です。
2025年度の国民年金保険料は月額16,980円。
収入が不安定な方や、仕事を失ってしまった方、フリーランスや自営業で生活が苦しい方にとっては、この金額は決して小さくありません。
「今月は払えなかった…」
「年金よりも今日の生活が優先」
「どうしたらいいか分からない」
そう感じるのは、あなただけではありません。
同じように悩む人は全国に多く、実際に何らかの形で保険料の支払いを免除されている人も少なくありません。
「滞納」より「免除」の申請を
保険料を払えないままにしてしまうと、それは「未納(滞納)」という扱いになります。
未納の期間は、将来年金を受け取る際に受給資格に影響したり、年金額が減ったりすることがあります。
しかし、「免除申請」を行えば、その期間は「免除期間」として認定され、一定の年金受給額が計算されるようになります。
つまり、まったくの未納よりも、きちんと手続きを踏んで免除を受けたほうが、将来のためになります。
免除制度は恥ずかしいことではありません
「免除制度を使うなんて、怠けているみたいで気が引ける」
「人に知られたらどうしよう」
といった不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、免除制度は、生活の困難さに寄り添うために設けられた公的制度です。
適切に利用することは、決して悪いことではありません。
税金や公共料金の減免制度と同じく、国民年金保険料の免除も、「一時的に支払いが困難な人」を支えるための仕組みです。
遠慮せず、まずは制度を知り、自分が対象になるかを確認してみましょう。
国民年金の保険料免除制度とは?

保険料免除の基本的な仕組み
国民年金の保険料免除制度とは、経済的に困難な状況にある方が、申請を行うことで保険料の一部または全額の納付が免除される制度です。
この制度の目的は、生活が苦しい状況でも、将来の年金受給資格を失わずにすむようにすることです。
免除制度には、「全額免除」だけでなく、「一部免除(4分の1・半額・4分の3)」といった複数の区分があり、本人や世帯の所得状況などに応じて判定されます。
自治体を通じて申請を行い、日本年金機構が審査します。
免除されても将来の年金はもらえる?
「保険料を免除されたら、将来年金がもらえなくなるのでは?」と心配される方もいますが、それは誤解です。
免除された期間も、原則として年金受給資格期間に含まれます。
たとえば、全額免除された場合でも、その期間中における将来の年金額は満額の2分の1(=50%)が計算されます。
また、一部免除の場合は、支払った割合に応じて年金額が決まるため、完全にゼロにはなりません。
免除期間と年金額の関係(例)
以下は、保険料免除の種類と、その期間中に加算される年金額の目安です。
| 免除の種類 | 将来加算される年金額の割合(目安) |
|---|---|
| 全額免除 | 50% |
| 4分の3免除 | 62.5% |
| 半額免除 | 75% |
| 4分の1免除 | 87.5% |
ただし、制度改正によって割合は変動する可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトや年金事務所で確認するのが安心です。
「免除」と「猶予」の違い
国民年金の保険料に関する制度としては、「免除」のほかに「納付猶予制度」や「学生納付特例制度」もあります。
免除
保険料の支払いが免除される。
将来の年金額に影響するが、受給資格にはカウントされる。
猶予
支払いを一定期間先延ばしにできる制度。
原則として、将来の年金額には反映されない(追納すれば加算可能)。
学生納付特例
学生を対象に、在学中の保険料納付を猶予する制度。
こちらも追納可能。
つまり、「免除」は支払いを不要にする制度、「猶予」は支払いの時期を先送りにする制度という違いがあります。
今の経済状況や今後の収入見通しに応じて、どの制度を選ぶか検討することが大切です。
免除には種類がある|4つのパターンをわかりやすく解説

国民年金の保険料免除制度には、4つの区分があります。
これは、申請者の所得状況や世帯の構成などに応じて、保険料の全額または一部が免除される仕組みです。
ここでは、それぞれの免除区分について、どのくらい負担が軽くなるのか、将来の年金額にどう影響するのかをわかりやすくご紹介します。
全額免除
最も負担が軽くなるのがこの「全額免除」です。
申請が認められると、その月の保険料は一切支払わなくてもよくなります。
ただし、保険料を払っていないからといって、将来の年金がゼロになるわけではありません。
先述の通り、将来の年金額には50%が反映される仕組みになっています。
所得要件は最も厳しく、本人および世帯主・配偶者の所得が一定額以下でなければなりません。
4分の3免除
この免除区分では、月額保険料の4分の3が免除され、残り4分の1のみを支払うことになります。
たとえば保険料が16,980円であれば、月額4,245円だけ納付すればよいことになります。
年金額への反映は、免除された分も含めて62.5%相当になります。
全額免除よりも所得要件は緩やかで、ある程度の収入がある方でも認められる可能性があります。
半額免除
こちらは月額保険料の半額を支払うタイプの免除です。
16,980円の半額=8,490円を毎月納付することで、将来の年金額には75%が反映される形になります。
この制度のよいところは、少しでも払える状況にある方が、無理なく年金制度に参加し続けられるという点です。
「全額は払えないけれど、まったくの免除は気が引ける…」という方に適しています。
4分の1免除
もっとも軽度の免除が、この4分の1免除です。
4分の1だけが免除され、残りの4分の3を支払うことになります。
具体的には、月額16,980円のうち、4分の1(4,245円)が免除され、12,735円を毎月支払う形です。
将来の年金額には、87.5%が反映されることになります。
「完全に全額払うのは難しいけれど、大部分は払える」という方にとって、最も現実的な選択肢となることもあります。
免除区分ごとの比較表
| 免除の種類 | 支払う保険料(月額・目安) | 将来反映される年金額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 50%が年金額に反映 |
| 4分の3免除 | 約4,245円 | 62.5%が年金額に反映 |
| 半額免除 | 約8,490円 | 75%が年金額に反映 |
| 4分の1免除 | 約12,735円 | 87.5%が年金額に反映 |
※金額は2025年度の国民年金保険料(16,980円)をもとにした概算です。
免除の対象になる条件とは?

所得による判定の仕組み
国民年金の免除制度を受けるためには、本人や世帯主、配偶者などの所得が一定の基準を下回っていることが必要です。
審査は前年(1月〜12月)の所得をもとに行われ、次のような計算式が使われます。
所得判定の目安
| 免除区分 | 所得基準(扶養親族等がいない場合の目安) |
|---|---|
| 全額免除 | 57万円以下 |
| 4分の3免除 | 78万円以下 |
| 半額免除 | 99万円以下 |
| 4分の1免除 | 120万円以下 |
※上記は扶養親族がいない単身者の場合の概算です。
扶養親族がいる場合や控除額が増える場合は、基準はより緩和されます。
また、給与所得者の場合は、給与所得控除後の金額(課税所得)で判定されるため、年収ベースではもう少し高くても対象になる場合があります。
扶養家族や配偶者の所得も関係する
免除申請をする際は、本人の所得だけでなく、配偶者や世帯主の所得も審査の対象になります。
たとえば、実家に住んでいて世帯主が高所得者である場合や、夫(または妻)が扶養者であり安定した収入がある場合には、本人に収入がなくても免除が認められない可能性があります。
このように、「誰と同居しているか」「世帯の収入全体はどうか」が重要になります。
収入のある親や配偶者と住民票上同じ世帯になっている場合には、住民票を分けることで条件が変わるケースもあります。
学生の場合は「学生納付特例制度」
20歳以上の学生で、所得が一定以下である場合は、「学生納付特例制度」の利用が可能です。
これは、「免除」ではなく「猶予」に分類される制度ですが、実質的には在学中の支払いが不要になる仕組みです。
この制度を利用すれば、在学中は保険料の納付が猶予され、将来年金受給資格としてカウントされるため、卒業後にまとめて追納することも可能です。
ただし、申請は毎年必要で、学校の在学証明書や学生証のコピーなどの提出が求められます。
失業中でも申請できる?
はい、失業している場合でも免除の申請は可能です。
むしろ、仕事を失ったばかりで収入がなくなるタイミングこそ、積極的に免除制度を利用すべきです。
失業による申請の場合、「失業の特例」が適用され、前年の所得が高くても、失業証明書などを提出すれば審査に考慮されることがあります。
必要書類としては、以下のようなものが一般的です。
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 離職票の写し(1・2)
- 解雇通知書や退職証明書
特に、自営業の廃業やフリーランスの廃業の場合は、確定申告書や廃業届などで証明することが求められます。
免除申請のやり方と必要書類
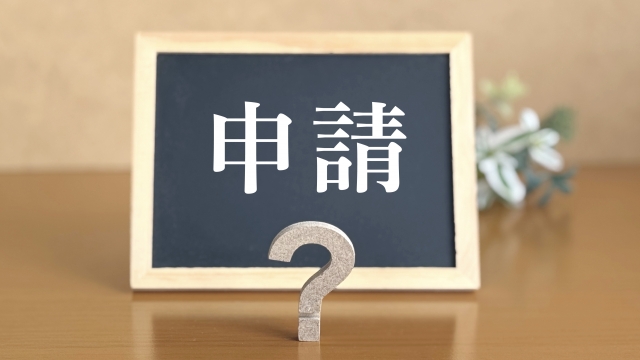
国民年金の保険料免除制度は、申請しなければ適用されません。
たとえ支払いが困難な状況でも、放置してしまうと「未納扱い」となり、将来の年金額に不利益が生じるおそれがあります。
ここでは、免除の申請方法や必要書類、申請のタイミングについて詳しく解説します。
どこで申請する?窓口とオンライン申請
免除申請の窓口は、お住まいの市区町村役場(国民年金担当窓口)です。
また、年金事務所でも相談や書類の提出が可能です。
【主な申請先】
- 市区町村の国民年金窓口
- 年金事務所(地域の日本年金機構)
- 郵送による申請も可
- 一部はマイナポータル経由の電子申請(スマホ・PC)も対応
※電子申請はマイナンバーカードと対応スマートフォンなどが必要です。
仕事や体調の都合で役所に出向けない方は、郵送での提出やオンライン申請も活用しましょう。
必要な書類とその入手方法
免除申請には、以下の書類が必要です。
| 書類名 | 内容・補足 |
|---|---|
| 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 | 役所や年金事務所で入手可。日本年金機構の公式サイトからダウンロードも可 |
| マイナンバー確認書類 | マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証など) |
| 失業や廃業などの証明書 | 雇用保険受給資格者証・離職票・退職証明書など(該当者のみ) |
| 学生証または在学証明書 | 学生納付特例を申請する場合に必要 |
これらの書類を揃えて、対象年度の申請期間内に提出することが大切です。
申請のタイミングと注意点
申請は、毎年度ごとに必要であり、自動更新ではありません。
保険料の年度は4月から翌年3月までなので、原則としてその年の7月から翌年の6月末までが申請受付期間となります。
また、失業や災害などやむを得ない事情があれば、遡って申請できる場合もあります。
しかし、原則として申請が遅れると未納扱いとなり、将来の年金受給資格に響く可能性もあります。
申請の注意点
- 年度ごとの更新が必要
- 提出後に「承認」「却下」の通知が届く
- 免除が認められるまでは、支払い義務は残っている
- 結果通知までに数週間かかる場合がある
「迷ったらまず申請する」という意識を持つことが、年金制度との良い付き合い方の第一歩です。
免除期間の扱いと追納について

免除を受けたからといって、将来の年金がゼロになるわけではありません。
免除期間も「受給資格期間」としてカウントされ、一定の年金額が反映されます。
また、経済的に余裕が出てから支払う「追納制度」も用意されています。
ここでは、免除期間の具体的な扱いや追納の仕組みについて解説します。
免除期間でも年金額はゼロではない
前の章でも触れたとおり、免除期間中であっても、保険料を「一部支払った」とみなして年金額に反映されます。
たとえば、全額免除を受けた場合は、その期間に相当する年金のうち50%が加算対象となります。
一部免除の場合は支払額と免除額に応じて、62.5%・75%・87.5%の割合で年金額に反映されます。
つまり、「未納」のままにしておくと将来の年金額に全く反映されませんが、免除を受けておけば一部は受け取れるという重要な違いがあります。
あとから払える「追納制度」とは
「当時は免除を受けるしかなかったけれど、今なら少し余裕がある」
そんなときに役立つのが、「追納制度」です。
追納制度とは、過去に免除や猶予を受けた保険料を、あとから納めることで将来の年金額を満額に近づけることができる仕組みです。
追納制度のポイント
- 原則として、10年以内であれば追納可能(※改正により過去は2年だったが、現在は延長されている)
- 免除区分に応じて、不足分のみを支払う
- 追納すれば、その分が将来の年金に上乗せされる
注意点:加算金がかかることも
追納には「加算金(利子のようなもの)」が付く場合があります。
免除を受けた年度から時間が経つほど、加算金が大きくなる傾向があります。
たとえば、免除から2年以内であれば加算金が免除されることもありますが、3年目以降は追納額に加えて加算金を支払う必要が出てくるため、なるべく早めに検討するのが望ましいです。
追納しないとどうなる?損する?
追納しない場合、その期間については免除された分の年金額しか加算されません。
つまり、本来もらえるはずの満額の年金よりも少ない額しか受け取れないということになります。
たとえば、20歳から60歳まで40年間すべて納付すれば、満額の老齢基礎年金(2025年度見込み:約80万円/年)を受け取れますが、免除期間が10年あり、そのまま追納しなかった場合は、50%〜87.5%に減額された年金額が加算され、結果的に年間で数万円以上差が出ることもあります。
追納する・しないの判断基準
追納すべきかどうかは、以下のような観点から判断するのが現実的です。
- 将来の生活設計にゆとりがあるか
- 加算金がどれだけかかるか
- 健康状態・平均余命・働ける年数
- 障害年金や遺族年金の必要性
年金事務所では、追納することで年金額がどれだけ増えるかを試算してもらうことも可能ですので、迷った場合は相談してみると良いでしょう。
免除が認められなかった場合は?

申請をしたからといって、必ずしもすべての方が免除を受けられるわけではありません。
所得基準をわずかに上回っていたり、提出書類に不備があるといった理由で、「不承認(却下)」となるケースもあります。
しかし、そこで諦める必要はありません。
不承認後でもできることはあります。
不承認通知が来たときの対処法
免除申請の審査結果は、申請から1か月〜2か月程度で届きます。
不承認だった場合は、「国民年金保険料免除申請 不承認通知書」という形で通知されます。
まずは、なぜ不承認となったのか理由を確認しましょう。
多いのは以下のようなパターンです。
- 所得が基準を超えていた(前年所得や配偶者・世帯主の所得)
- 提出書類が不足・不備があった
- 証明書の内容に不備がある(離職証明など)
- 世帯構成が誤っていた(扶養関係の誤認)
もし書類不備が原因であれば、追って正しい書類を提出することで再審査してもらえる場合もあります。
再申請・審査請求という選択肢
不承認に納得がいかない場合や、状況が変わった場合は、再度の申請(再申請)や、「審査請求」という不服申し立てを行うこともできます。
再申請できるケース
- 所得が下がった、世帯を分けたなど状況の変化があった
- 書類不備を修正できた
- 時期をずらして再提出する
再申請は同一年度内であれば可能です。
たとえば、7月に申請して不承認だった場合、翌年6月までに条件が変われば再度申請できます。
審査請求とは?
審査請求とは、日本年金機構の判断に不服がある場合に、第三者機関に再評価を求める正式な手続きです。
- 不承認通知を受け取ってから60日以内に請求
- 書面での申し立てが必要
- 結果が出るまで数か月かかることもある
所得の計算方法や世帯認定に誤りがある場合などは、審査請求が通る可能性もあります。
他の支援制度を検討する
どうしても免除が認められなかった場合でも、生活の困難さに応じた他の公的支援を検討することが重要です。
たとえば:
- 生活困窮者自立支援制度(各市区町村の福祉課)
- 住民税非課税世帯向けの給付金制度
- 就労支援や職業訓練による収入回復策
- 医療費の減免制度(国保・高額療養費制度など)
免除を受けるときのよくある誤解と注意点

国民年金の免除制度は、正しく理解して使えば心強い制度ですが、誤ったイメージを持っている方も少なくありません。
ここでは、よくある誤解や注意すべき点を取り上げ、安心して制度を活用できるよう解説します。
「免除=年金がゼロになる」は誤解
もっとも多い誤解のひとつが、「免除された期間は将来の年金がもらえない」というものです。
実際には、免除された期間でも将来の年金額に一部が反映される仕組みになっています。
たとえば全額免除でも、その期間の50%は年金に加算されます。
一部免除なら、支払った分と免除分をあわせて62.5%〜87.5%の範囲で年金額が加算されます。
つまり、「払えないから仕方なく未納にする」のではなく、免除制度を利用すれば損を最小限に抑えることができます。
「一度免除を受けると戻せない」は間違い
「一度免除を受けたら、今後ずっと免除扱いになるのでは?」という不安を抱く方もいますが、免除はあくまで「その年度に限っての一時的措置」です。
毎年度、収入や世帯状況などに応じて申請・審査されるため、翌年以降に状況が改善すれば、通常通りの納付に戻すこともできます。
また、収入が上がれば免除が打ち切られ、通常納付の対象になるのが一般的です。
必要なのは、今の生活を守るために、制度を柔軟に使っていく姿勢です。
「未納」と「免除」は全く違う
見逃されがちですが、「未納」と「免除」は根本的に異なります。
| 状態 | 年金の受給資格期間に カウントされるか |
将来の年金額に 反映されるか |
督促・差押えのリスク |
|---|---|---|---|
| 免除 | される | 一部が反映される(50〜87.5%) | なし |
| 未納 | されない | 反映されない | あり(長期間未納時) |
まとめ|無理せず、正しく免除制度を活用しよう

国民年金の保険料免除制度は、生活が苦しいときにこそ利用してほしい公的な支援制度です。
年金と聞くと将来の話に思えるかもしれませんが、「今」困っているあなたの生活を守る制度でもあります。
自分の生活を守るための制度
国民年金は、老後の生活の支えになるだけでなく、障害年金や遺族年金の受給資格にもつながる重要な制度です。
もし未納が続くと、将来年金が受け取れないだけでなく、万が一のときに障害年金や遺族年金がもらえないという深刻な事態にもなりかねません。
そうした事態を避けるためにも、払えないときは「放置する」のではなく、「申請する」という行動が大切です。
苦しいときは申請をためらわないで
「免除なんて使っていいのかな」
「役所に行くのが気が重い」
「知られたくない」
と感じる方も多いかもしれません。
でも、誰にでも経済的に厳しい時期はあります。
免除制度は、そうした一時的な困難を支えるために存在する正式な制度です。
利用することは、国に頼ることでも甘えることでもなく、制度の利用者としての正当な権利です。
申請すること自体に勇気がいるかもしれませんが、その一歩が、あなたの将来の年金や生活を守る大きな安心につながります。
年金事務所での相談も活用しよう
「自分が対象になるのか分からない」「どの書類を出せばいいか不安」という場合は、最寄りの年金事務所や市区町村の窓口で相談するのが一番確実です。
年金事務所では、以下のようなサポートを受けることができます。
- 所得条件に合致するかの目安確認
- 申請に必要な書類の案内・準備
- 追納の可否や年金見込み額の試算
事前予約をすれば、待ち時間を減らしてスムーズに相談できることもあります。
不安なときほど、専門の窓口に頼ることが安心への近道です。
よくある質問(FAQ)

Q. 国民年金の免除を受けても将来の年金はもらえますか?
A. はい、免除された期間も将来の年金額に一部反映されます。
たとえば全額免除なら50%、一部免除なら支払った割合に応じて62.5%〜87.5%が加算されます。
Q. 免除を受けるには毎年申請しなければいけませんか?
A. はい、国民年金の免除は1年ごとの制度です。
前年の所得や世帯状況によって判断されるため、毎年申請が必要です。
Q. 免除が認められなかったときはどうすればよいですか?
A. まずは不承認の理由を確認し、再申請や審査請求を検討できます。
失業や世帯分離などの事情を証明できれば再度認められる可能性があります。
Q. 学生でも免除を申請できますか?
A. 学生の場合は「学生納付特例制度」が利用できます。
在学中は保険料の納付が猶予され、将来の受給資格期間にもカウントされます。
申請は毎年度必要です。
Q. 免除された保険料はあとから払うことができますか?
A. はい、「追納制度」により、過去10年以内の免除分はあとから納めることができます。
その分、将来の年金額が増えるメリットがあります。
- 年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説
- 遺族基礎年金とは?寡婦年金との違いと死亡後の年金手続き|亡くなった人の年金はどうなる?
- 障害年金でもらえる金額と条件とは?1級・2級・3級の等級別の受給額と認定基準の違いをやさしく解説
- 国民年金が払えないときは?保険料免除制度の条件・申請方法をわかりやすく解説
全国の年金受け取りの手続きのやり方は?申請と流れを徹底解説
▼地域ごとの年金受給の手続きの情報はこちらから