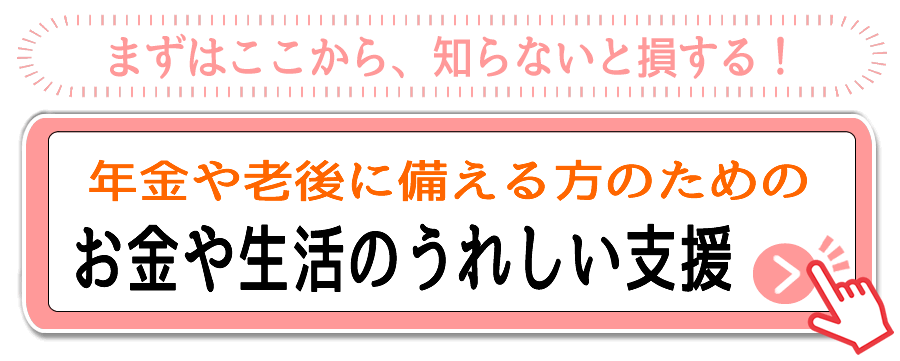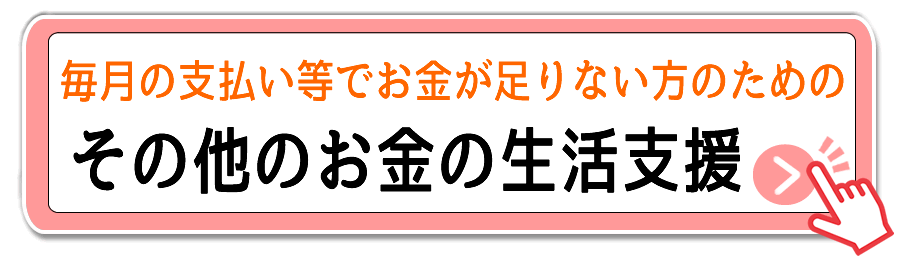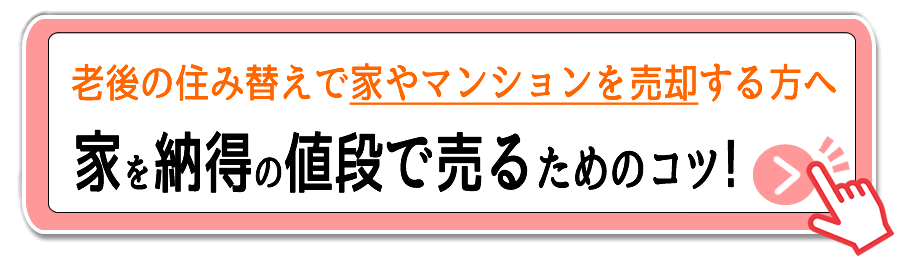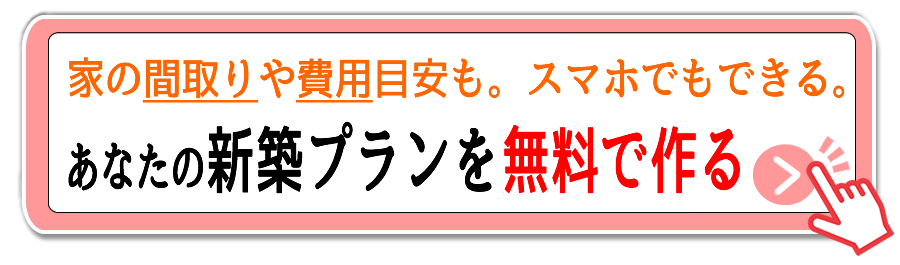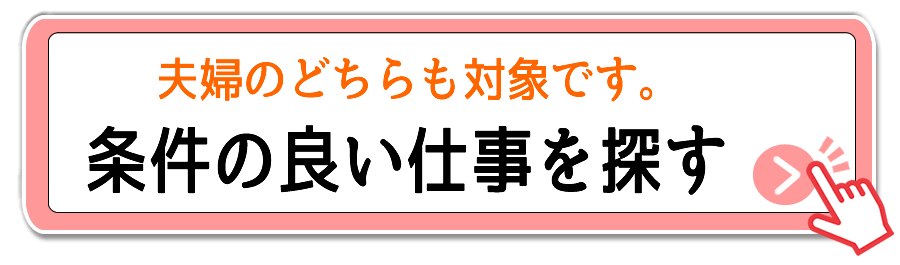遺族基礎年金とは?寡婦年金との違いと死亡後の年金手続き|亡くなった人の年金はどうなる?
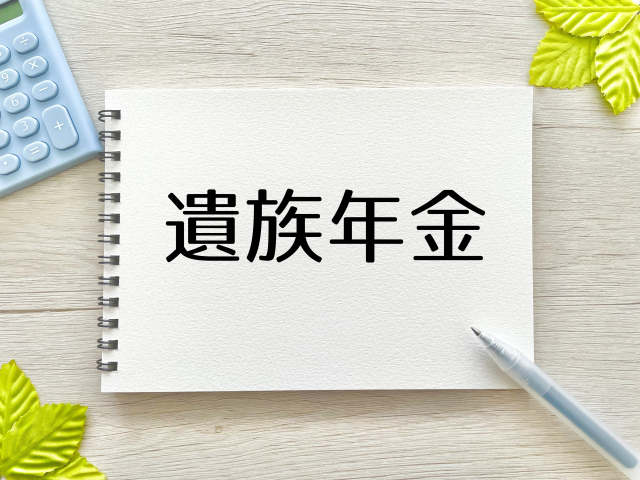
- 遺族の年金制度はどうなっている?
- 遺族基礎年金とは?
- 寡婦年金とは?遺族基礎年金との違い
- 亡くなった人の年金はどうなる?
- 遺族年金の受給手続きの流れ
- 遺族年金がもらえない場合はどうしたらいい?
- 遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る方へ
- よくある質問(FAQ)
遺族の年金制度はどうなっている?
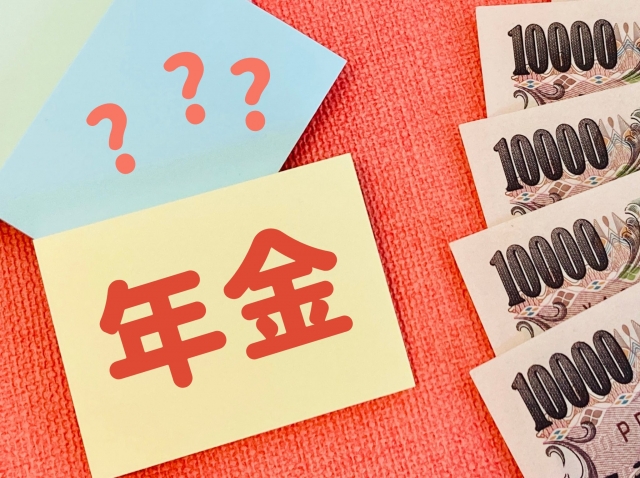
遺族年金には2種類ある:遺族基礎年金と遺族厚生年金
大切な家族を亡くした直後というのは、心身ともに大きなショックの中にあり、今後の生活への不安が押し寄せます。
そんな中で、手続きを進めなければならない制度のひとつが「遺族年金」です。
遺族年金とは、亡くなった方が国民年金や厚生年金に加入していたことを前提に、遺された家族が一定の条件を満たせば受け取れる年金です。
遺族年金には大きく分けて次の2種類があります。
- 遺族基礎年金(国民年金に基づく)
- 遺族厚生年金(厚生年金保険に基づく)
たとえば、自営業の方や専業主婦などが加入している「国民年金」の場合、亡くなった方が保険料を一定期間納めていたことが条件になります。
そして、18歳以下の子どもがいる配偶者、または子ども本人がいる場合に限って、遺族基礎年金を受け取ることができます。
一方、厚生年金に加入していた方が亡くなった場合には、配偶者や子ども、または父母や孫、祖父母なども一定の条件下で遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
遺族年金の制度は、加入していた年金の種類によって内容が異なるため、「どの年金に加入していたか」を確認することが最初のステップになります。
寡婦年金や死亡一時金など、その他の給付制度も
遺族年金と並行して、制度として知っておきたいのが「寡婦年金」と「死亡一時金」です。
これらは、遺族基礎年金の受給要件を満たさない方に対する補完的な制度といえます。
まず、寡婦年金とは、亡くなった夫が国民年金の保険料を一定期間納めていたにもかかわらず、遺族基礎年金の対象にならない妻(子のいない配偶者)に支給される年金です。
また、死亡一時金は、年金を受給する前に死亡した方に代わり、遺族が一度きりで受け取れる給付金です。
こちらも、遺族基礎年金や寡婦年金のいずれも受け取れない場合に限られるため、要件はやや限定的です。
表にまとめると以下のようになります。
| 制度名 | 対象者 | 主な要件 | 支給形式 |
|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のいる配偶者または子 | 亡くなった人が保険料を一定期間納付 | 年金(継続的) |
| 寡婦年金 | 子のいない妻 | 婚姻10年以上+保険料納付要件 | 年金(継続的) |
| 死亡一時金 | 主に配偶者 | 年金を受けずに死亡した場合 | 一時金(一度限り) |
亡くなった人がもらっていた年金はどうなる?
すでに年金を受給していた方が亡くなった場合、その年金の取り扱いについても大切な手続きが発生します。
まず最初に必要なのは「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出です。
この届出をしないまま年金が振り込まれ続けた場合、「過払い金」として返金義務が発生する可能性があります。
たとえ使ってしまっていたとしても、返金を求められるのが原則です。
また、亡くなった月の年金がまだ振り込まれていない場合、「未支給年金」として、配偶者や子などが請求できます。
これは死亡月までの受給権があった年金のうち、まだ支払われていない分を、所定の順位にある家族が受け取るという仕組みです。
未支給年金の請求順位は以下のようになります。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
ただし、「生計を同じくしていたこと」が要件となります。
遠方で別世帯になっていた親族では、受け取れないこともあるため注意が必要です。
遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金の対象者:18歳以下の子がいる配偶者や子ども
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。
対象となるのは、以下のいずれかに該当する遺族です。
- 18歳到達年度の3月末までの子どもがいる配偶者
- 18歳到達年度の3月末までの子ども本人
つまり、子どもがいない配偶者だけでは受け取ることができません。
この点が、後述する「寡婦年金」との大きな違いとなります。
また、障害がある子どもの場合、20歳未満まで受給の対象になることもあります(障害等級1級または2級に該当する場合)。
亡くなった方が比較的若く、子育て世代であることが多いため、生活の立て直しが難しい時期に支えとなる制度です。
亡くなった人の納付状況によって支給されない場合も
ただし、遺族基礎年金は誰でももらえるわけではありません。
亡くなった方が年金保険料を一定期間納めていたことが条件となります。
現在のルールでは、次のいずれかを満たしている必要があります。
- 死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付済期間が3分の2以上あること
- 令和8年3月31日までに死亡した場合に限り、死亡日の直近1年間に保険料の未納がないこと
たとえば、保険料を長期間滞納していた場合や、国民年金の任意加入中に未納だった場合などには、遺族が年金を受け取れないことがあります。
これは非常に重要なポイントであり、受給者側にとってはどうしようもないことですが、「なぜもらえないのか?」という疑問や悔しさにつながりやすい部分です。
納付要件に関する判断がつかない場合には、迷わず年金事務所へ相談し、被保険者記録の確認を行うことが推奨されます。
いくらもらえる?金額と計算方法
遺族基礎年金の金額は、定額部分+子の加算額で構成されています。
2025年度時点での支給額は以下の通りです。
| 内容 | 金額(年額) |
|---|---|
| 基本額(子ども1人含む) | 約78万3,100円 |
| 第2子の加算 | 約22万4,900円 |
| 第3子以降の加算(1人あたり) | 約7万4,900円 |
例えば、子どもが2人いる場合は、基本額+第2子の加算で年額約100万8,000円程度となります。
支給は原則として年6回(偶数月に2ヶ月分ずつ)行われるため、毎月安定した収入源として生活を支えてくれます。
ただし、支給開始のタイミングや、申請の遅れによってはさかのぼって受給できない月もあるため、早めの手続きが重要です。
遺族基礎年金がもらえないケースとは
以下のような場合には、遺族基礎年金を受け取ることができません。
- 亡くなった方の保険料納付要件を満たしていない
- 子どもがいない、またはすでに成人している
- 再婚して新たに配偶者ができた(受給資格喪失)
- 実際には同居していなかった、または生計維持関係がなかったと判断された
このようなケースでは、「寡婦年金」や「死亡一時金」などの他の制度でカバーできるかどうかを検討する必要があります。
また、遺族基礎年金は受給資格を満たしていても、自動的に支給されるわけではありません。
申請手続きを行わなければ一切受け取ることができないため、注意が必要です。
寡婦年金とは?遺族基礎年金との違い

寡婦年金の対象:子のいない配偶者に支給される年金
遺族基礎年金が「子どもがいる配偶者」に限られる一方で、子どもがいない配偶者を支える制度が「寡婦年金」です。
亡くなった配偶者が国民年金に加入していた場合で、以下の条件を満たすと、妻(または夫)に支給されます。
寡婦年金の主な受給要件は以下の通りです。
- 亡くなった夫が国民年金の保険料を10年以上納付していたこと
- 死亡当時、夫が老齢基礎年金を受け取っていなかったこと
- 婚姻関係が10年以上継続していたこと(事実婚含む)
- 妻が遺族基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていないこと
なお、寡婦年金は原則として妻に対する制度です。
夫が受け取ることは基本的に想定されておらず、男女平等の観点からも見直しが議論されていますが、2025年時点ではこの仕組みが維持されています。
遺族基礎年金との主な違いを表で比較
制度名は似ていますが、遺族基礎年金と寡婦年金は「支給対象」「金額」「支給期間」など多くの点で異なります。
以下の表に主な違いをまとめました。
| 比較項目 | 遺族基礎年金 | 寡婦年金 |
|---|---|---|
| 支給対象 | 18歳未満の子がいる配偶者または子 | 子のいない妻 |
| 受給できる年齢 | 年齢要件なし(ただし子どもの年齢制限あり) | 60歳から65歳未満 |
| 年金額 | 定額+子の加算(年100万円前後) | 夫が受給予定だった老齢基礎年金の4分の3 |
| 支給期間 | 子が18歳になるまで | 60歳から65歳までの5年間 |
| 併給可否 | 他の年金との併給可能性あり(条件あり) | 死亡一時金との併給不可 |
寡婦年金の特徴は、「65歳までの限定支給」であることと、「金額が老齢基礎年金の4分の3相当」となる点です。
定額ではないため、夫の納付年数や加入期間によって年金額は変動します。
支給対象
前述の通り、遺族基礎年金は「子どもがいる配偶者」、寡婦年金は「子のいない妻」が対象です。
したがって、子どもが成人した後や、子がいなかった場合に備える制度として、寡婦年金は機能しています。
受給できる年齢
寡婦年金の支給開始は60歳からで、65歳になると老齢基礎年金に切り替わるため、それまでの5年間が受給期間となります。
60歳になるまでの間は、遺族としての支給がない点には注意が必要です。
年金額
夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3という計算式になるため、人によって支給額に差が出るのが特徴です。
特に、保険料納付年数が短いと、想像以上に低額になることもあるため注意しましょう。
支給期間
支給されるのは60歳から65歳の5年間限定です。
65歳以降は、自分自身の老齢基礎年金を受け取ることになります。
寡婦年金と老齢基礎年金の同時受給はできないため、年齢と年金の切り替わり時期を意識する必要があります。
寡婦年金と死亡一時金の併給はできない
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当しそうな場合でも、この2つは併給(同時に受け取ること)ができません。
どちらか一方を選択する必要があります。
寡婦年金のほうが金額としては高くなる傾向がありますが、受給できるのは60歳以降であるため、「すぐに現金が必要」という状況であれば死亡一時金を選ぶこともあります。
また、寡婦年金は申請しない限り支給されません。
自分にとってどちらが有利かを冷静に判断する必要があり、年金事務所への相談をおすすめします。
亡くなった人の年金はどうなる?

年金受給者が死亡した場合の停止手続き
もし亡くなった方がすでに年金を受給していた場合、年金の支給は自動的には止まりません。
家族側で正式な手続きを行わなければ、年金がそのまま振り込まれ続ける可能性があります。
このような誤支給を防ぐために、必要なのが「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出です。
これは、亡くなった方が年金を受け取っていたことを日本年金機構に伝える重要な手続きで、以下のような場面で必要になります。
- 老齢年金(基礎・厚生)を受給していた
- 障害年金を受給していた
- 遺族年金を受給していた
提出先は、年金事務所または市区町村役場です。
葬儀後の慌ただしい時期ではありますが、できるだけ早く届け出ることでトラブルを防げます。
また、提出が遅れて過払いとなった場合は、返還を求められる可能性があります。
たとえすでに使ってしまっていても、返金が原則です。
亡くなった月までの年金はどうなる?返金が必要?
年金の支給は「後払い」で行われています。
たとえば4月分と5月分の年金は、6月に振り込まれる仕組みです。
そのため、亡くなった月の翌月以降の支給分は返金が必要になるケースがあります。
たとえば、5月10日に亡くなった方の年金が6月15日に振り込まれた場合、5月分までは受給資格がありますが、6月分からは受け取る権利がないため、過払いとなります。
一方で、亡くなった月分までの年金がまだ支払われていない場合には、それを「未支給年金」として受け取ることができます。
未支給年金とは?請求できる人と手続き方法
未支給年金とは、亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ支払われていない分のことです。
これを受け取るには、所定の手続きが必要です。
未支給年金を請求できるのは、次のような条件を満たした人です。
- 亡くなった方と生計を同じくしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など)
- 他の相続人が辞退した場合は、次順位の人が受け取れる
請求に必要な書類には、次のようなものがあります。
- 年金受給権者死亡届
- 未支給年金・未支払給付請求書
- 亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことを証明する書類(住民票など)
- 戸籍謄本
- 請求者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 振込先金融機関の通帳コピー
なお、請求の時効は5年です。
期限を過ぎると請求できなくなってしまうため、できるだけ早く申請しましょう。
遺族年金の受給手続きの流れ

年金事務所への届出と必要書類
遺族年金の受給は、「申請しないと受け取れない制度」です。
つまり、亡くなった方が条件を満たしていても、家族が自ら請求しなければ支給されないという仕組みになっています。
手続きは、お住まいの地域の年金事務所で行います。
まずは電話などで予約を取り、必要書類をそろえて相談・申請に行く流れとなります。
特に気をつけたいのは、「どの年金制度に該当するか」で手続き先が異なる場合がある点です。
- 国民年金のみ加入:市区町村役場または年金事務所
- 厚生年金に加入:日本年金機構(年金事務所)
また、年金手続きは一度で完了しないこともあるため、余裕を持った日程で進めることが大切です。
実際に必要な書類一覧
遺族年金を請求する際には、以下のような書類が必要です。
書類の内容は申請者の状況や年金の種類によって若干異なりますが、代表的なものを以下にまとめます。
| 必要書類 | 内容/備考 |
|---|---|
| 遺族年金裁定請求書 | 年金事務所またはWebで入手可能 |
| 死亡診断書のコピー | 医師による発行(原本不要) |
| 戸籍謄本 | 家族関係・婚姻関係を確認するため |
| 世帯全員の住民票 | 生計維持関係を証明する資料 |
| 所得証明書 | 一部の年金制度では収入制限がある |
| 保険料納付確認書類 | 納付状況の確認に必要な場合がある |
| 振込先通帳のコピー | 受給者本人名義のもの |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
年金事務所では、書類に不備があると申請を受け付けてもらえない場合もあります。
事前に電話で確認し、必要に応じてチェックリストを使って準備しましょう。
いつまでに手続きすればよいか
遺族年金には、明確な「申請期限」が設けられているわけではありませんが、原則として時効は5年です。
つまり、亡くなった日の翌日から5年以内に請求しなければ、遡って支給を受けることができなくなります。
ただし、例えば子どもが18歳になる直前に申請しても、その時点ですでに対象外になっている場合は受給できないこともあります。
そのため、できるだけ早く申請することが非常に重要です。
申請後、いつから支給されるのか
申請が受理され、審査が通ると、おおむね2〜3か月後から初回の支給が行われます。
支給月は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、その月に2か月分ずつ支給される仕組みになっています。
たとえば、2月には12月分と1月分が支払われます。
申請が遅れると、支給開始も遅くなるため、できるだけ速やかに書類を整えて手続きを進めることが、家計の安定につながります。
遺族年金がもらえない場合はどうしたらいい?

対象外の場合に検討できる他の公的支援
遺族年金は、遺された遺族を経済的に支えるための制度ですが、誰もが必ず受け取れるとは限りません。
保険料の未納や、年齢・家族構成の条件を満たさない場合など、残念ながら受給資格がないケースも少なくありません。
そんなときに頼れるのが、他の公的支援制度の活用です。
国や自治体では、ひとり親世帯や低所得世帯に対して、生活を支えるための制度を用意しています。
具体的には、以下のような支援制度があります。
- 児童扶養手当(18歳以下の子どもを扶養している場合)
- ひとり親家庭等医療費助成(医療費の自己負担分が軽減される制度)
- 就学援助制度(子どもの学用品や給食費の支援)
- 母子・父子寡婦福祉資金貸付金(教育・生活資金などを無利子または低利で貸し付け)
こうした支援制度は、各自治体によって名称や内容が異なることも多く、詳細は市区町村の福祉課で案内してもらえます。
生活保護・児童扶養手当などの併用も視野に
もし遺族年金がもらえず、収入が大幅に減って生活に困窮している場合は、生活保護の検討も視野に入れる必要があります。
生活保護は、「すべての支援を使い切ったあとの最後のセーフティネット」ともいわれていますが、本当に困ったときは迷わず申請すべき制度です。
申請の際には、収入・資産状況の確認が行われます。
また、児童扶養手当は、ひとり親世帯が一定の所得要件を満たす場合に、子ども1人あたり月額最大44,140円(2025年度)が支給されます。
遺族基礎年金とは併給調整があるため、金額は調整されることがありますが、全く支給されないというわけではありません。
さらに、教育費の支援や住居支援、就労支援など、状況に応じた支援メニューが多岐にわたって存在しています。
心身ともに不安定な時期に複雑な制度を調べるのは大変ですが、「困っている」と伝えることでつながる支援は確実にあります。
可能であれば、社会福祉協議会、民生委員、学校の相談員などにも早めに相談し、孤立せずに手を差し伸べてもらえる体制を整えることが大切です。
遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る方へ

心の整理がつかないまま手続きに追われる現実
配偶者や親を亡くした直後というのは、想像を超える悲しみと混乱の中にいます。
遺された家族の心が追いつかないうちに、次々と押し寄せるのが現実的な手続きです。
火葬や埋葬、各種届け出、保険や銀行の対応に追われる中で、遺族年金や寡婦年金の申請も「やらなければいけないこと」のひとつになります。
しかし、焦って処理しようとして大切な書類をなくしたり、精神的に消耗してしまう方も少なくありません。
そんなときは、まず「全部を一人で抱えなくていい」ということを思い出してください。
無理をせず、誰かに頼ることも選択肢に
年金の手続きは煩雑に見えますが、年金事務所の職員は、こうした相談に日常的に対応しています。
決して特殊なことではありません。
「制度のことがまったく分からない」「どこに行けばいいか分からない」と感じていても、少しずつ情報を集め、信頼できる人に話すことで道が見えてきます。
たとえば以下のようなサポートを受けることができます。
- 年金事務所での窓口対応や予約制の個別相談
- 市区町村役場での無料相談(年金・福祉・法律)
- 社会保険労務士(社労士)への相談や代行依頼
また、感情の整理がつかないままでは、判断力も鈍りがちです。
行政書士や社労士、福祉の専門家と話すことで、「もう少し肩の力を抜いていいんだ」と感じられることもあります。
年金事務所・専門家(社労士)への相談をためらわないで
実際に「申請に必要な書類をどこでもらえばよいか分からない」「手続きが不安でずっと先延ばしにしていた」という声は非常に多くあります。
年金事務所では、事前予約をしておけば、丁寧に個別対応してくれる窓口があります。
時間が確保された相談であれば、制度の内容や提出書類をひとつひとつ説明してもらえるため、安心です。
また、社労士(社会保険労務士)に代行を依頼することで、申請書の作成や提出まで任せることも可能です。
費用は発生しますが、「安心を買う」という意味でも、有効な選択肢になるでしょう。
誰かを亡くしたあとに、経済的な心配まで抱えることは、あまりに過酷です。
せめて制度が整っている部分については、しっかりと受け取ってほしいと願っています。
よくある質問(FAQ)

Q. 子どもがいない場合は遺族基礎年金はもらえませんか?
A. はい、遺族基礎年金は18歳到達年度の末日までの子どもがいる配偶者または子ども本人が対象です。
子どもがいない場合は、寡婦年金や死亡一時金の対象になるかをご確認ください。
Q. 寡婦年金と遺族基礎年金の両方を受け取ることはできますか?
A. いいえ、寡婦年金と遺族基礎年金の併給はできません。
どちらか一方の要件を満たしていれば、そちらを選択する形になります。
Q. 遺族年金の申請はいつまでにすればいいですか?
A. 原則として時効は5年です。
5年を過ぎると、さかのぼっての受給ができなくなるため、早めの申請をおすすめします。
Q. 年金を受け取っていた人が亡くなった場合、手続きは必要ですか?
A. はい、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出して、年金の支給停止を行う必要があります。
未支給年金がある場合は、別途請求が可能です。
Q. 年金の手続きはどこで相談できますか?
A. お住まいの地域の年金事務所、または市区町村役場で相談できます。
事前予約をしておくと、個別対応してもらえるため安心です。
- 年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説
- 国民年金が払えないときは?保険料免除制度の条件・申請方法をわかりやすく解説
- 障害年金でもらえる金額と条件とは?1級・2級・3級の等級別の受給額と認定基準の違いをやさしく解説
- 遺族基礎年金とは?寡婦年金との違いと死亡後の年金手続き|亡くなった人の年金はどうなる?
全国の年金受け取りの手続きのやり方は?申請と流れを徹底解説
▼地域ごとの年金受給の手続きの情報はこちらから