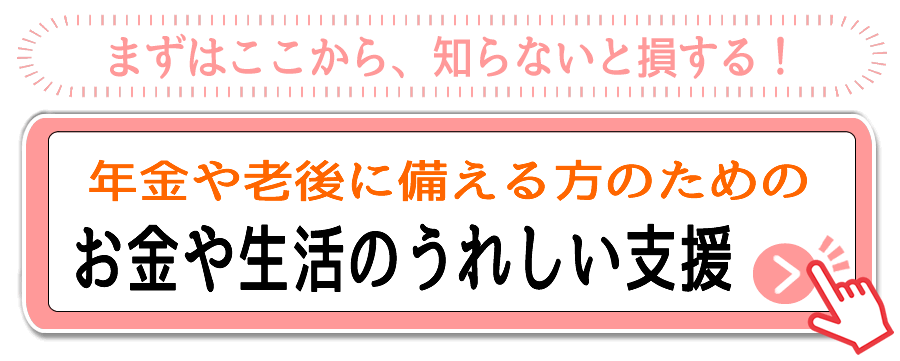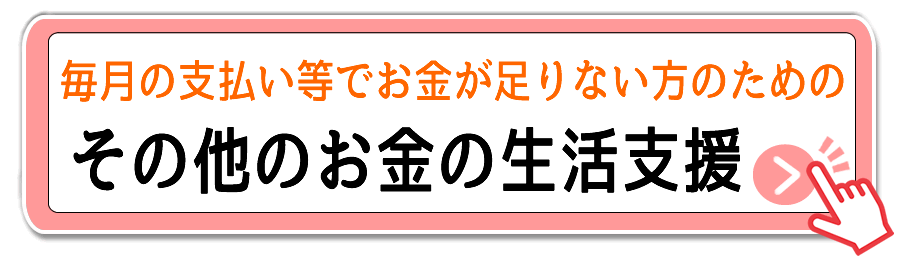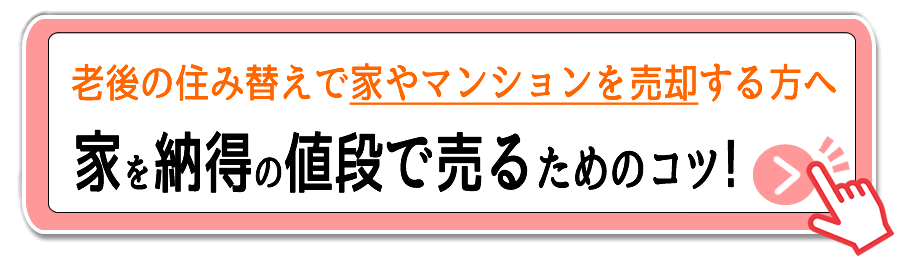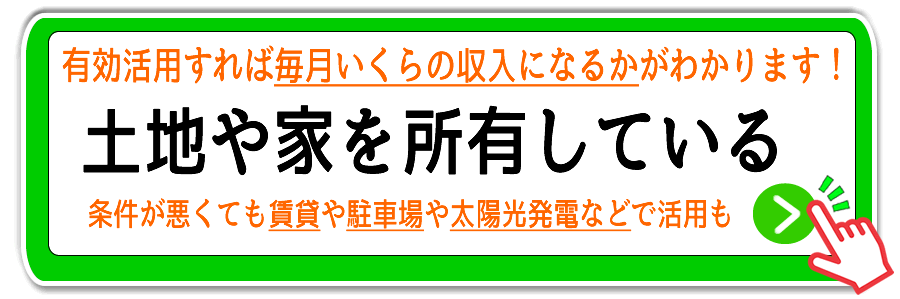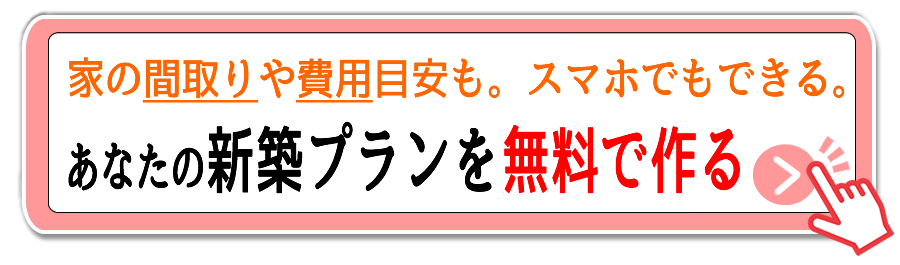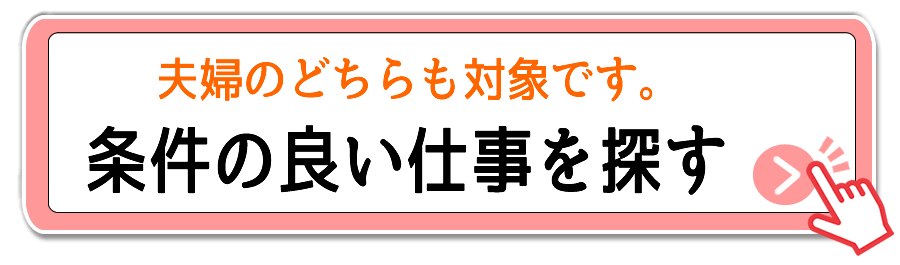年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説

- 年金の繰り上げ・繰り下げ受給とは?
- 年金を「繰り上げ受給」するメリットとデメリット
- 年金を「繰り下げ受給」するメリットとデメリット
- 繰り上げ・繰り下げの具体的な計算例
- 「いつからもらうべきか?」判断のポイント
- 年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 介護認定を受けるには?申請の流れと注意点をわかりやすく解説|初めてでも安心の手続きガイド
年金の繰り上げ・繰り下げ受給とは?

年金を「いつから受け取るか」は、老後の生活設計において非常に重要な選択です。
原則として公的年金は65歳から支給開始となりますが、受給開始年齢を変更する制度として「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」が用意されています。
繰り上げ受給とは?
繰り上げ受給とは、本来65歳から受け取る老齢年金を60歳から繰り上げて受け取ることができる制度です。
申請をすれば、60歳以降であれば1か月単位で前倒しが可能です。
ただし、繰り上げた分だけ受給額は減額され、その減額率は生涯にわたって固定されます(詳細は後述)。
「今すぐ年金が必要」という方にとっては選択肢となり得る制度です。
繰り下げ受給とは?
一方で繰り下げ受給とは、年金の受給開始を65歳以降に遅らせることで、1か月ごとに年金額を増やすことができる制度です。
70歳までが一般的ですが、2022年4月の制度改正により、最大で75歳まで繰り下げることが可能になりました。
月単位で繰り下げるほど年金額は増加し、75歳まで繰り下げた場合、年金額はおよそ84%増加します。
長生きを前提とした老後設計をするなら、検討に値する選択肢といえるでしょう。
65歳から受給を基準にした考え方
65歳は「基準年齢」であり、ここから前にずらせば減額、後ろにずらせば増額という仕組みになっています。
受給開始年齢の変更は一度決めると原則として変更できません。
慎重な判断が必要です。
年金を「繰り上げ受給」するメリットとデメリット

早くもらえる安心感と生活設計の柔軟性
繰り上げ受給の最大のメリットは、何といっても早くお金が受け取れるという点です。
60歳から受け取れるため、収入が減るタイミングをカバーする手段として非常に有効です。
たとえば、定年退職後に十分な貯蓄がない方や、再雇用・パート収入だけでは生活が不安な方にとって、年金という定期収入があることは大きな安心材料となります。
受給額が永久に減額される点に注意
繰り上げ受給の最大の注意点は、受給額が一生涯にわたって減額されたままになることです。
2022年4月以降の繰り上げでは、1か月繰り上げるごとに0.4%減額され、たとえば60歳で受給を開始した場合、最大24%も減額されます。
年金は終身でもらえるため、長生きすればするほど損をする可能性が高まります。
単純に早くもらえるから得とは限らないです。
繰り上げによって受けられない制度・控除とは
繰り上げ受給をすると、以下の制度や控除が受けられなくなることもあるため注意が必要です。
- 振替加算の対象外になる可能性
- 加給年金が受けられない
- 高齢者控除などの税制優遇が影響を受ける可能性
つまり、単に「金額が少なくなる」だけでなく、付随する権利や制度を失うことにもつながります。
繰り上げ受給が向いているのはどんな人?
以下のような方は、繰り上げ受給のメリットが大きいといえます。
- 早期退職して無収入期間がある方
- 貯蓄が少なく、生活資金に不安がある方
ただし、本当に必要な資金かどうかを見極めてから決めることが重要です。
年金を「繰り下げ受給」するメリットとデメリット

年8.4%増える受給額の魅力
繰り下げ受給最大のメリットは、受給額が増えることです。
2022年の制度改正以降、繰り下げによる増額率は1か月あたり0.7%。
1年繰り下げるごとに約8.4%、5年間(70歳)繰り下げれば42%、75歳まで繰り下げると最大84%増額となります。
たとえば、65歳から受け取るはずの年金額が月10万円だった場合、75歳から受け取れば月18.4万円にまで増える計算になります。
この差は一生涯にわたり続くため、長生きすればするほど有利になる制度といえるでしょう。
繰り下げ中に死亡した場合は一円も受け取れないリスク
繰り下げ受給の最大のリスクは、「繰り下げ期間中に亡くなってしまうと年金を1円も受け取れない」という点です。
これは大きな心理的ハードルになります。
たとえば、70歳から受け取るつもりでいたのに、68歳で亡くなった場合、それまで支払ってきた保険料に対して一切の受給がないまま終わってしまいます。
このため、健康状態や家族歴などをふまえた長寿の見通しが、繰り下げ受給を判断する大きな鍵になります。
受け取りが遅くなることでの生活資金の問題
もう1つのデメリットは、年金の開始が遅れることにより、それまでの生活費をどこから捻出するかという問題です。
退職金や貯金、再雇用による収入などがなければ、生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。
繰り下げで増える金額を目当てにしていても、生活費を切り崩して苦しい思いをするようでは本末転倒です。
選ぶ前に資金計画をしっかり立てておく必要があります。
繰り下げ受給が向いているのはどんな人?
次のような方は、繰り下げ受給のメリットを活かせる可能性があります。
- 健康状態が良好で、長寿家系の方
- 退職後も継続的な収入があり、65歳以降の生活に困らない方
- 老後の生活費にゆとりを持たせたい方
- 一人暮らしや独身で、遺族年金などを気にしなくて良い方
一方で、持病がある方や生活資金がギリギリの方にはあまり向きません。
長期的な人生設計の中で慎重に選択すべき制度です。
繰り上げ・繰り下げの具体的な計算例

65歳受給を基準とした繰り上げ時の減額率
繰り上げ受給では、1か月あたり0.4%ずつ年金額が減額されます。
| 開始年齢 | 減額率 | 支給額(例:65歳基準で月10万円) |
|---|---|---|
| 64歳 | -4.8% | 95,200円 |
| 63歳 | -9.6% | 90,400円 |
| 62歳 | -14.4% | 85,600円 |
| 61歳 | -19.2% | 80,800円 |
| 60歳 | -24.0% | 76,000円 |
※2022年4月以降の基準に基づく。減額は生涯続きます。
70歳受給を選んだ場合の増額率
一方、繰り下げ受給は1か月あたり0.7%ずつ増額されます。
| 開始年齢 | 増額率 | 支給額(例:65歳基準で月10万円) |
|---|---|---|
| 66歳 | +8.4% | 108,400円 |
| 67歳 | +16.8% | 116,800円 |
| 68歳 | +25.2% | 125,200円 |
| 69歳 | +33.6% | 133,600円 |
| 70歳 | +42.0% | 142,000円 |
※最大75歳まで繰り下げれば+84%、月184,000円となります。長生きすればするほど増額の恩恵が大きくなります。
平均寿命との比較で得か損かを考える
では、どちらが「得」なのでしょうか?
簡単な目安としては、以下のように言われています。
- 男性の平均寿命:約81歳
- 女性の平均寿命:約87歳
仮に「繰り上げ受給(60歳開始)」と「繰り下げ受給(70歳開始)」を比べた場合、受給総額が逆転するのは80歳前後です。
つまり「80歳以上生きる」と思うなら、繰り下げの方がトータルでもらえる金額は多くなる傾向にあります。
年金生活に入る前にシミュレーションを
ご自身の状況に合った受給時期を決めるためには、年金額の試算やライフプランシミュレーションを活用することが非常に重要です。
「ねんきんネット」では、自分の加入実績に基づいた将来の年金額や、繰り上げ・繰り下げをした場合の変化を具体的に確認できます。
感覚ではなく、数値で確認することが失敗を防ぐカギになります。
「いつからもらうべきか?」判断のポイント

年金の繰り上げ・繰り下げは、将来の暮らしを左右する大きな選択です。
損得だけで判断するのではなく、ご自身の状況・健康状態・家族構成・資産背景を冷静に見つめることが重要です。
健康状態と余命の見通し
「自分は何歳まで生きるのだろう?」という問いは、簡単には答えられません。
しかし、繰り下げ受給で得をするには長生きする可能性が高いことが前提となります。
たとえば、親族に長寿の方が多い、本人に持病がないなど、健康寿命に自信がある方は繰り下げが有利となりやすい傾向にあります。
逆に、早めに年金を確保したいと考える方は繰り上げのほうが安心です。
配偶者や遺族年金との関係
配偶者の存在も重要な判断材料です。
たとえば、妻が専業主婦であった場合、夫が受給を繰り上げてしまうと加給年金(一定の条件で支給される加算)を受けられなくなる可能性があります。
また、繰り下げ受給を選択した場合でも、遺族年金には繰り下げの増額分が反映されないという仕組みもあります。
これらを知らずに繰り下げを選ぶと、思ったよりも将来の家計が厳しくなることも。
貯金・退職金・再雇用などの他の収入とのバランス
「年金がなくても生活できる期間」がどれだけあるかを確認しましょう。
貯金や退職金、パート収入などで65歳以降も生活が安定しているなら、繰り下げ受給により将来の安心を得るという選択も現実的です。
逆に、定年後すぐに現金収入が必要である場合は、繰り上げてすぐに受給することが合理的です。
生活費の見通しと必要な月額
老後の生活費の目安は人それぞれですが、総務省の家計調査では、高齢夫婦無職世帯の平均支出は月およそ22万円前後とされています。
これに対し、年金だけで足りるのか、不足分はどう補うのかを考えておくことが重要です。
「受給額」だけを見て決めるのではなく、家計収支のシミュレーションをすることで、自分にとって最適な受給開始年齢が見えてきます。
迷ったときの選び方のヒント

年金受給のタイミングに正解はありません。
「こうすれば必ず得をする」という単純な話ではなく、それぞれの人生と資産背景に合わせた選択が求められます。
60歳からの繰り上げと65歳基準の比較
早期退職などで60歳から年金を受け取りたいと考える方もいるでしょう。
しかし、繰り上げによる減額は生涯に渡って続くため、慎重な判断が必要です。
繰り上げを選ぶ場合は、「何歳まで生きると損になるのか?」という視点も忘れずに。
たとえば、65歳受給に対して60歳受給が元を取れるのは76〜77歳ごろと言われています。
つまり、その年齢まで生きれば、65歳受給の方が得になるということです。
「一部繰り下げ」や「途中変更」はできる?
年金の受給開始は原則として一度決めると変更不可です。
ただし、60歳以降に請求しなければ繰り下げになりますので、「請求しないまま待つ」=繰り下げになるという形です。
部分的に繰り下げたり、あとでやっぱり早めるといった調整は基本的にできません。
受給開始年齢の選択は一度きりの重大な決断となるため、よく検討する必要があります。
ライフプランに合わせた柔軟な選択が大切
受給開始年齢は、収入・支出・資産・寿命予測といった複数の視点から検討することが求められます。
将来の不安に備えるために、「早くもらっておきたい」という気持ちも、「長く安定して受け取りたい」という考えも、どちらも正解です。
「これからの人生、どんな風に暮らしていきたいか」
それを軸に、年金受給のタイミングを選ぶことが、もっとも後悔のない判断につながります。
よくある誤解と注意点

年金の繰り上げ・繰り下げ受給は制度として明確に整備されていますが、意外と誤解されやすいポイントも多く存在します。
思い込みで判断してしまうと、将来の受給に大きな影響が出るおそれがあります。
繰り上げたら元に戻せる? という誤解
「とりあえず60歳で繰り上げても、65歳で戻せばいい」──そんな誤解を抱いている方もいますが、繰り上げ受給は一度決めると原則として取り消しできません。
例外的に、受給開始後1年以内であれば受給を取り消す特例(年金の返納+再申請)がありますが、すでに受け取った年金をすべて返還する必要があり、実行のハードルは非常に高いといえます。
増額を狙った繰り下げが裏目になるケースも
「年金が増えるなら、できるだけ遅らせたほうが得だろう」と考える方もいます。
しかし、繰り下げている間に受給せずに亡くなってしまえば、1円も受け取れません。
さらに、65歳から70歳まで働いて収入があるうちはよくても、70歳以降に病気になったり介護が必要になったりすると、せっかく増額された年金を活かす前に出費がかさむリスクもあります。
「増やすために我慢する」ことで将来の安心を失ってしまう可能性があることを、忘れてはいけません。
年金制度改正の影響が出ることも
年金制度は、今後も人口動態や社会情勢に合わせて見直しが行われる可能性があります。
現時点では「75歳まで繰り下げ可能」「1か月ごとの増減率」といったルールが適用されていますが、制度は変わるものと考えておくべきです。
そのため、「繰り下げで84%増えるから70歳まで待とう」と思っていても、制度が変わればその前提が崩れることもあり得えます。
社会全体の動向も含めて、柔軟に判断する姿勢が求められます。
繰り上げ・繰り下げを検討する前に相談したい窓口

年金の受給開始年齢は、人生を左右する重大な選択です。
個人だけで判断するのが難しいと感じたときには、専門機関の相談窓口を活用することが有効です。
ねんきんネットでの確認方法
「ねんきんネット」は、厚生労働省が提供する年金記録の確認・試算サービスです。
自分の納付記録に基づいて、65歳で受給した場合の見込み額や、繰り上げ・繰り下げした場合の金額の変化を数値で確認できます。
インターネット上で24時間利用でき、年金の見える化に最適なツールといえるでしょう。
年金事務所やFPへの相談
お住まいの地域の「年金事務所」では、無料で年金相談が可能です。
予約制での個別対応もあり、手続きや制度の詳細を正確に把握することができます。
また、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すれば、年金だけでなく資産・保険・ライフプラン全体から受給タイミングをアドバイスしてくれます。
特に有資格の独立系FP(CFPやAFP)を選ぶと安心です。
市区町村の年金相談窓口を活用しよう
市区町村によっては、定期的に社会保険労務士(社労士)などによる年金相談会を開催しているところもあります。
地域密着型の支援が受けられる点で、年金事務所とは異なる利点があります。
「年金のこと、誰に聞けばいいかわからない」という方も、まずは市役所や区役所の年金担当窓口で情報収集を始めてみましょう。
まとめ|「いつからもらうか」は一人ひとりの事情で最適解が違う

年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給は、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。
- 繰り上げ受給:早く受け取れる反面、生涯の受給額は減る
- 繰り下げ受給:受給開始が遅れる分、月額は大きく増える
どちらが「得か損か」ではなく、自分のライフスタイル、健康状態、資産状況に合っているかどうかで判断することが大切です。
人生100年時代を生き抜くには、「何歳まで生きるか」を正確に予測することはできません。
しかし、自分らしく、安心して暮らせる選択をすることは可能です。
そのためにも、制度を正しく理解し、専門家の力を借りながら、納得のいく判断をしていきましょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 繰り上げ受給後に働いたらどうなりますか?
繰り上げ受給後に60歳以上の厚生年金加入の仕事をすると、在職老齢年金の制度が適用され、一部の年金が減額される可能性があります。
特に賃金が高い場合は、支給停止の対象になることもあるため、就労と年金の関係について事前に確認しておくことが大切です。
Q. 繰り下げ受給にすると配偶者の遺族年金も増えますか?
繰り下げによって受け取る本人の年金額は増えますが、遺族年金にはその増額分は反映されません。
遺族年金はあくまで被保険者が死亡時点での基準に基づいて計算されるため、繰り下げのメリットは引き継がれないことに注意が必要です。
Q. 一度繰り上げた年金はやっぱり取りやめできますか?
繰り上げ受給を開始してから1年以内であれば、受給を取りやめて再申請する特例(年金返還)が可能です。
ただし、すでに受け取った年金は全額返金しなければならず、条件も厳しいため、慎重な判断が求められます。
- 年金から天引きされるお金はいくら?健康保険・介護保険・住民税の仕組みと対処法を解説
- 年金受給者で確定申告が必要なケースとは?課税対象・申告不要制度・注意点を徹底解説
- 遺族基礎年金とは?寡婦年金との違いと死亡後の年金手続き|亡くなった人の年金はどうなる?
- 障害年金でもらえる金額と条件とは?1級・2級・3級の等級別の受給額と認定基準の違いをやさしく解説
- 国民年金が払えないときは?保険料免除制度の条件・申請方法をわかりやすく解説
- 年金はいつからもらうのが得?|繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットを徹底解説
全国の年金受け取りの手続きのやり方は?申請と流れを徹底解説
▼地域ごとの年金受給の手続きの情報はこちらから