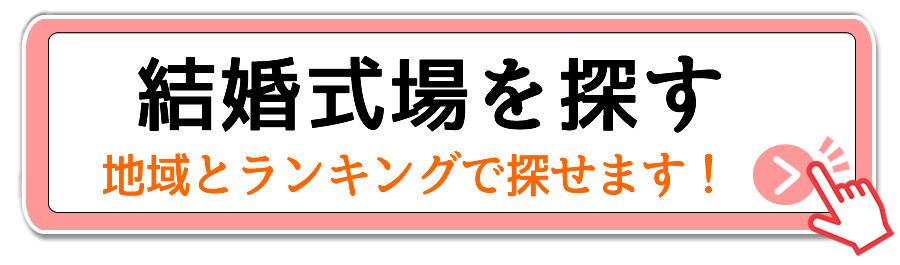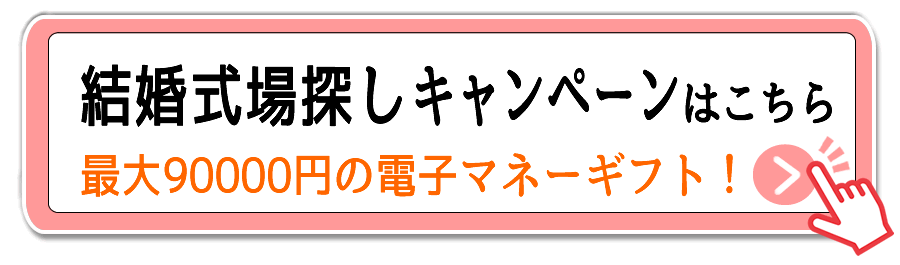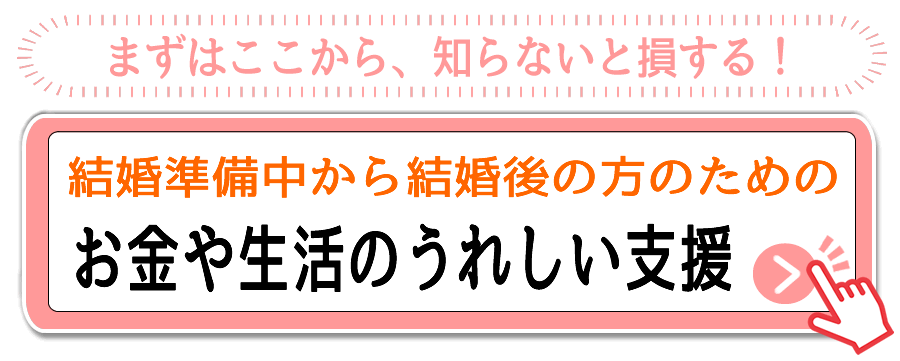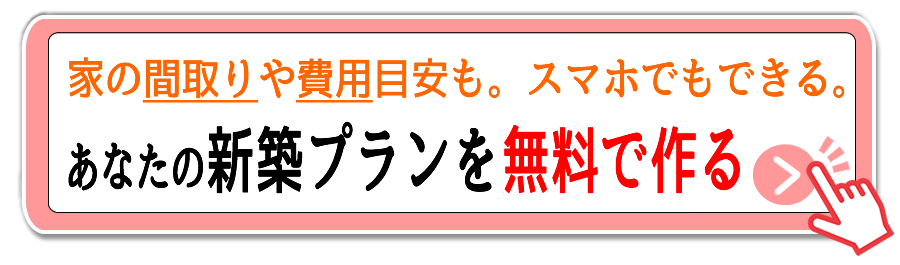PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
結納とは?顔合わせとの違いと今どきの選び方|迷ったときの判断ポイントも解説

- 結納とは?昔と今でどう違う?
- 顔合わせとは?カジュアルだけど大切な場
- 結納と顔合わせ、どう違う?どちらを選ぶべき?
- 結納と顔合わせ、両方やるのはあり?
- 結納や顔合わせをするときの不安とその解消法
- ケース別:結納・顔合わせの選び方ガイド
- 結納・顔合わせの準備チェックリスト
- よくある質問(FAQ)
結納とは?昔と今でどう違う?

結納の基本的な意味と目的
「結納(ゆいのう)」とは、結婚の約束を正式に交わすための伝統的な儀式です。
かつては結婚の前提として必ず行われていたもので、両家の結びつきを確認し、親同士の合意を形にするための大切な場でした。
由来をたどると、結納は「結いの物(ゆいのもの)」とされる品々を交換する儀式に端を発し、現在では「結婚を認め合う証」としての位置づけを持っています。
昔は仲人が間に立ち、結納品や結納金の受け渡し、受書のやり取りなどが行われるのが一般的でしたが、現代ではスタイルも目的も多様化しています。
「伝統を守りたい」親世代の気持ちと、「カジュアルに済ませたい」若いカップルの意向の間で悩む方も多いかもしれません。
結納の本質は「形式そのもの」ではなく、両家がこれからの関係を円滑に築くための第一歩を踏み出すことにあります。
結納の主な流れとマナー
正式な結納では、あらかじめ日取りを調整し、結納品・結納金・受書(結納を受け取った証明)を準備しておきます。
通常は男性側が女性側へ贈り物を届ける形で行われ、仲人を通じて両家の親が集う場となります。
一般的な流れは以下の通りです。
- 結納の日取りを決定(吉日を選ぶことが多い)
- 結納品や結納金、受書の準備
- 当日の服装・会場を整える(和室の料亭や自宅など)
- 仲人または家族による進行のもと結納品の贈呈
- 受書を交わし、結びの会食
ただし現在は、仲人を立てずに両家のみで行う略式結納が主流になっています。
進行も堅苦しいものではなく、事前に内容をすり合わせておけば柔軟なスタイルで進められるでしょう。
服装については、正式結納では男性はスーツまたは礼服、女性は訪問着やワンピースが一般的です。
ただし格式よりも両家のバランスが大切で、どちらかが浮いてしまわないように事前相談が欠かせません。
現代の結納事情:略式・簡略化が進む理由
現在では、伝統的な結納を省略するカップルも増えています。
その背景には以下のような事情があります。
- 「形式にこだわりたくない」という若い世代の価値観
- 費用や準備にかかる負担
- 親同士がすでに顔見知りで、改めて儀式の必要を感じない
その代わりに行われているのが「略式結納」や「結納を兼ねた顔合わせ食事会」です。
たとえば、以下のようなスタイルが見られます。
- 結納金のみを渡す略式結納
- 結納品なしで手紙や口頭で気持ちを伝える
- レストランなどで会食しながら結婚報告
このように、昔ながらの形式にこだわらず、自分たちらしいやり方を選ぶ傾向が強まっています。
ただ、どれほど簡略化しても、「両家の意思を尊重する」ことが一番大切なのは変わりません。
顔合わせとは?カジュアルだけど大切な場
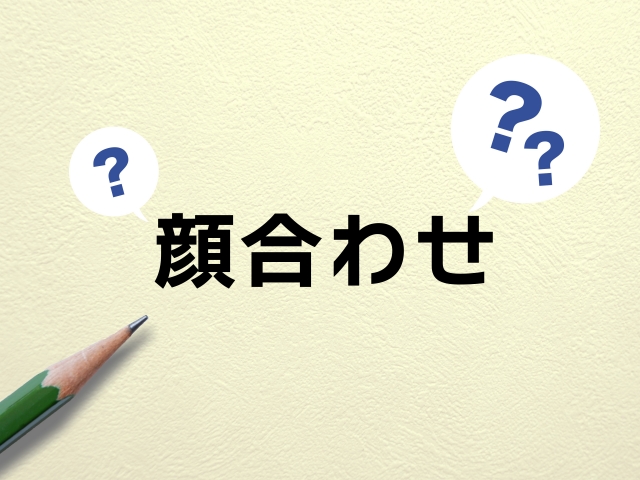
顔合わせ食事会の目的と位置づけ
「顔合わせ」は、結婚を控えたふたりが両家の親を紹介し合うための食事会です。
結納の代わりとして選ばれることも多く、よりカジュアルかつ自由なスタイルで行えるのが特長です。
目的は「結婚の報告」と「今後の両家の関係構築」であり、形式的な儀式ではありません。
しかしながら、初対面となる場合は緊張も大きく、配慮や準備が必要な場面です。
特に地方によっては、「結納なしで顔合わせだけ?」と親世代が不安に感じることもあるため、両親との事前相談やすり合わせがカギになります。
顔合わせの一般的な流れと会場選び
顔合わせの会場は、ホテルの個室、和食料亭、落ち着いたレストラン、自宅などさまざまです。
選ぶ際のポイントは、両家の移動距離・人数・雰囲気に合わせることです。
一般的な顔合わせ食事会の流れは次のようになります。
- 会場に集合・着席
- ふたりから結婚の報告
- 家族紹介(両親・兄弟姉妹など)
- 乾杯・会食
- 今後についての軽い話し合い(式・入籍など)
- 記念撮影・解散
進行役は男性本人、あるいは両家どちらかの父親が務めるケースが多いですが、あらかじめ簡単な進行メモを作っておくと安心です。
顔合わせでもやっておきたい準備とは?
カジュアルとはいえ、顔合わせは人生の節目を彩る大切な場です。
以下のような点に気を配ると、よりスムーズな会になります。
- 手土産:地元のお菓子など、気を遣わせない程度のものが理想
- 服装:男性はジャケット、女性はワンピースなどが一般的
- 費用:両家折半か、本人たちが負担するケースも多い
- 話題:自己紹介や趣味、出身地など無難な話題を想定
また、席順や乾杯のタイミングなど細かい点も事前確認しておくと、当日の緊張も和らぎます。
結納と顔合わせ、どう違う?どちらを選ぶべき?

形式・費用・負担・印象の違い
「結納と顔合わせ、どちらを選ぶべきか」と悩まれる方は少なくありません。
まずは両者の違いを把握しておきましょう。
| 項目 | 結納 | 顔合わせ |
|---|---|---|
| 目的 | 正式な婚約を両家で確認する儀式 | 親睦を深めるカジュアルな食事会 |
| 形式 | 儀式の進行や結納品の交換などがある | 進行役は本人が担い、自由な構成が可能 |
| 費用 | 10万〜50万円前後(結納金・会場費など) | 3万〜15万円前後(会食費用のみ) |
| 服装 | スーツや礼服、訪問着などフォーマル | セミフォーマル〜カジュアルまで可 |
| 両家の印象 | 「きちんとした家」という印象を与える | 気軽だが「略式」と受け取られる場合も |
このように、結納は「伝統や正式さ」を重視したスタイルであり、顔合わせは「実用性や気軽さ」を優先する場と言えます。
それぞれのメリット・デメリット
結納と顔合わせ、それぞれに良さがあります。
両方を比較することで、ふたりと両家にとってより適した形を選びやすくなります。
- 結納のメリット:正式な場として区切りがつけられる/親世代の安心感が強い/地域によっては常識として根付いている
- 結納のデメリット:費用・準備・形式の負担が大きい/若い世代にはやや堅苦しく感じられることも
- 顔合わせのメリット:柔軟な形式で行いやすい/費用も比較的抑えられる/リラックスした雰囲気で話しやすい
- 顔合わせのデメリット:伝統を重視する両親には物足りなく感じられる可能性/婚約の証としての「形式」に欠ける印象
両家の考え方が違うときの対処法
「新郎側は結納を希望」「新婦側は顔合わせだけでよい」といったように、両家で意見が分かれるケースもよくあります。
そんなときは、次のようなステップで対話を進めましょう。
- ふたりが事前に意見をすり合わせ、仲介役となる
- どちらかの意向に完全に合わせるのではなく、双方の希望を取り入れた形を探る
- 略式結納や顔合わせ兼結納など、中間案を提案する
「うちはこうだった」「今どきはこう」といった意見がぶつかる場面でも、大切なのは“両家の関係を良好に保つこと”です。
形式にこだわりすぎず、「気持ちが通じ合う場」をどう作るかに焦点を当てましょう。
結納と顔合わせ、両方やるのはあり?

両方行うカップルの割合と理由
実は、「結納も顔合わせも両方行った」というカップルも少なくありません。
調査によっては、約1〜2割程度が両方のイベントを実施しているとも言われています。
その理由には、次のような背景があります。
- 結納で正式に婚約を交わし、顔合わせで親睦を深めたい
- 親世代への配慮として形式を大切にしたい
- 結納は親が主導、顔合わせは自分たちのペースで進めたい
つまり、結納は「儀式」、顔合わせは「交流の場」として目的を分けて考えることで、両方行う価値が見いだされています。
順番や日程の組み方の注意点
結納と顔合わせを両方行う場合、どちらを先にするべきか迷うかもしれません。
基本的には、結納を先に行い、後日に顔合わせを兼ねた会食を行う流れが自然です。
ただし、以下のような調整が必要になることもあります。
- 日程が近すぎると準備や出費が重なる
- 遠方の両親が複数回移動するのが難しい
このような場合は、1日に結納→顔合わせを兼ねた会食というスケジュールを組むのも一案です。
その際には、会場の選定や時間配分に余裕を持つことがポイントになります。
両方する場合の費用や準備の工夫
当然ながら、結納と顔合わせをそれぞれ行う場合、費用や準備も二重になります。
そこで、簡略化や共通化を意識すると、負担を減らすことができます。
たとえば:
- 結納品は最低限にして費用を抑える
- 顔合わせの会場と結納の会場を同じにする
- 当日の服装を共通にし、写真撮影も兼ねる
- 1冊の進行表で両方の式次第をまとめる
このように、伝統を重んじつつも現代的な工夫を取り入れることで、両家にとって心地よいイベントが実現できます。
結納や顔合わせをするときの不安とその解消法

よくある悩み:準備の負担・服装・費用・言葉遣い
結納や顔合わせは、人生の節目ともいえる大切な行事。
だからこそ、「失敗したくない」「不快な思いをさせたくない」と緊張してしまう方も多いです。
特に多い悩みは以下のようなものです。
- 「何を準備すればよいのかわからない」
- 「服装や手土産のマナーに自信がない」
- 「進行がうまくできるか不安」
- 「費用の負担は誰がすべき?」
これらはすべて「正解が一つではない」からこその不安です。
地域差や両家の考え方によって異なるため、自分たちだけで判断するのが難しいです。
どこまで準備すればいい?親とすり合わせるべきこと
不安を減らすためにまず重要なのが、両親との情報共有です。
とくに結納を行う場合や、格式にこだわる親御さんがいる場合には、次の点を事前にすり合わせておくことが大切です。
- 結納の有無(正式/略式/顔合わせのみ)
- 費用の負担(どちらの家が何を負担するか)
- 服装のレベル(フォーマル/セミフォーマル)
- 手土産の有無と内容
- 当日の進行役とスケジュール
「サプライズは禁物」と心得て、事前に双方の意向を確認し、ふたりが“橋渡し役”となってまとめるのが円滑な進行のカギです。
結納も顔合わせもやらないという選択肢は?
近年では、結納も顔合わせも行わず、ふたりだけで結婚に進むカップルも少なくありません。
背景には以下のような理由があります。
- 親が高齢または遠方に住んでいて負担になる
- 経済的に準備が難しい
- 再婚や年齢的な事情であまり形式を重視していない
こうした選択が「間違い」「非常識」というわけではありません。
大切なのは、お互いと両家の気持ちを理解し合い、納得のいく形を選ぶことです。
「やらない」場合でも、親御さんに感謝の気持ちを伝える場や報告の場を設けると、誠意は十分に伝わります。
ケース別:結納・顔合わせの選び方ガイド

ケース1:両家が遠方同士
両家の距離が遠い場合は、移動の負担と費用が大きなネックになります。
このようなケースでは、以下のような方法が有効です。
- 中間地点で結納または顔合わせを行う
- 片方の家に合わせ、もう一方は交通費・宿泊費を負担する
- 顔合わせのみで済ませ、結納はしない
物理的な負担を考慮して、シンプルで感謝の気持ちが伝わるスタイルが好まれます。
ケース2:親世代にこだわりがある
どちらかの親が「結納は当然」と考えている場合、無理に否定するのではなく、気持ちを尊重する姿勢が大切です。
- 正式な結納を行う(できれば費用を親が一部負担)
- 略式結納や、顔合わせの中で簡易的な結納風の演出を取り入れる
- 「やってもらった感」だけでも大きな満足につながる
親が納得して祝ってくれることが、今後の関係にも良い影響を与えるでしょう。
ケース3:再婚や年齢的な事情がある
再婚や年齢的に結納がそぐわないと感じる場合は、形式よりも当人同士と両家の納得感を重視するのがベストです。
- 顔合わせのみで十分
- 手土産と簡単な挨拶だけの会食スタイル
- 「改めての出発を祝う会」として柔らかな演出にする
形式に縛られない、新しい形の結びつきとして前向きにとらえるのがおすすめです。
ケース4:予算が限られている
結納品や会食費など、金銭的な負担が気になる方は少なくありません。
無理せず、感謝の気持ちが伝わる範囲で計画することが重要です。
- 略式結納や簡易的な儀式にする
- 顔合わせ食事会を少人数で行う
- 会場は個室のあるカフェや和食店などリーズナブルに抑える
費用を抑えつつも、「大切な時間を過ごす」という本質を忘れないことがポイントです。
ケース5:親を交えずふたりで判断したい
近年では、「結婚はふたりのもの」として、親を巻き込まずに進めたいというカップルも増えています。
とはいえ、完全に省略することで親との関係にしこりが残るケースもあるため注意が必要です。
- 親には事前に簡単な報告を入れておく
- ふたりだけの会食後、別途それぞれの家で挨拶の場を設ける
- 「式はしないけど、ありがとうの気持ちは伝えたい」という姿勢があれば充分
ふたりの意思と、親への配慮のバランスをとることが、後悔のない選択につながります。
結納・顔合わせの準備チェックリスト

準備すべきこと一覧表(内容+時期)
結納や顔合わせをスムーズに進めるためには、事前準備が何よりも大切です。
以下に、一般的なスケジュールと準備項目を一覧表にまとめました。
| 時期 | 準備すること |
|---|---|
| 1〜2か月前 |
・両家で希望スタイルの確認(結納 or 顔合わせ) |
| 3〜4週間前 |
・結納品・結納金の準備(必要な場合) |
| 1週間前 |
・会場の最終確認と人数連絡 |
| 当日 |
・時間に余裕をもって出発 |
費用の目安と支払いの考え方
費用はスタイルによって大きく変わります。
以下はあくまで目安です。
| 項目 | 結納 | 顔合わせ |
|---|---|---|
| 会場費 | 1万〜5万円 | 0円〜2万円 |
| 食事代(1人あたり) | 5,000円〜15,000円 | 3,000円〜10,000円 |
| 結納品・結納金 | 5万〜50万円(地域により変動) | なし |
| 服装・準備品 | 1万〜数万円 | 5千円〜2万円程度 |
誰が費用を負担するかについては、両家で事前に話し合って決めるのが基本です。
最近では、新郎新婦が全額負担または両家で折半するケースも増えています。
事前に話し合っておくべき5つのこと
準備を進めるうえで、両家で必ず話し合っておくべき重要なポイントをまとめました。
- 結納をするか、顔合わせにするか
- 開催場所と日程の調整
- 服装の格を合わせるかどうか
- 費用の分担方法
- 当日の流れと挨拶の順番
これらのポイントを曖昧にしたままだと、当日のトラブルや気まずい雰囲気の原因になってしまいます。
準備段階から「ふたりが調整役になる」意識が大切です。
よくある質問(FAQ)

Q. 結納金は必ず渡すものですか?
結納金は地域や家ごとの慣習によって異なりますが、現代では「渡すかどうか」を両家で自由に決めるスタイルが主流です。
略式結納では金額も抑えめにするなど、柔軟な対応が可能です。
Q. 結納品はどこで手配する?略式でも必要?
正式結納では専門店で用意することが多く、地域の風習に合わせて選ばれます。
略式や顔合わせのみの場合は、結納品を省略してもマナー違反ではありません。
Q. 顔合わせの服装はスーツとワンピースでよい?
問題ありません。
大切なのは「両家の服装の格を合わせること」です。
どちらかだけがフォーマル過ぎる/カジュアル過ぎるとバランスが崩れるため、事前に相談しましょう。
Q. 結納や顔合わせの進行役は誰がする?
正式結納では仲人や父親が務めることが多いですが、顔合わせでは新郎本人やふたりで進行するケースが一般的です。
挨拶の順番や話す内容をメモしておくと安心です。
Q. 結納・顔合わせをしないと失礼になりますか?
必ずしも失礼ということではありません。
ただし、親御さんの気持ちを無視すると、あとからしこりが残る可能性があります。
省略する場合でも、感謝や誠意をしっかり伝えることが大切です。
- 結婚式場の選び方とブライダルフェア徹底ガイド|理想の式を叶えるためのステップと注意点
- 妊娠中でも結婚式はできる?マタニティ婚・授かり婚の準備と注意点ガイド|何ヶ月までOK?演出は?ドレスは?
- 結婚にかかるお金はいくら?結婚式・新生活・新婚旅行までのリアルな費用と資金準備ガイド
- 結婚助成金(結婚新生活支援事業)とは?対象・金額・申請の流れを徹底解説
- 婚約とは?結婚・入籍までの流れとやり方|後悔しないために必要な心構えと進め方ガイド
- 結納とは?顔合わせとの違いと今どきの選び方|迷ったときの判断ポイントも解説