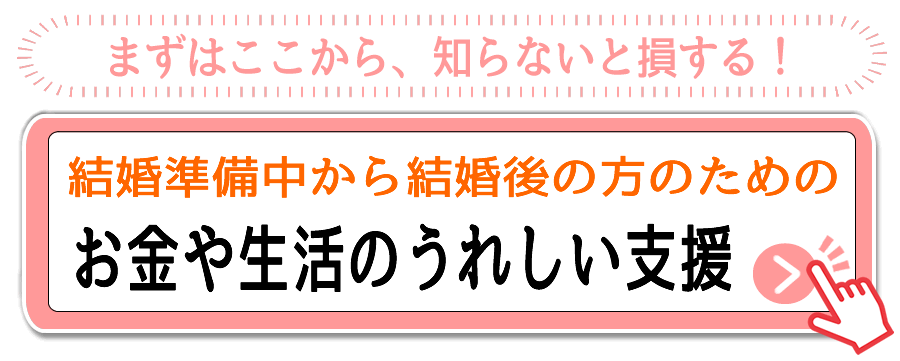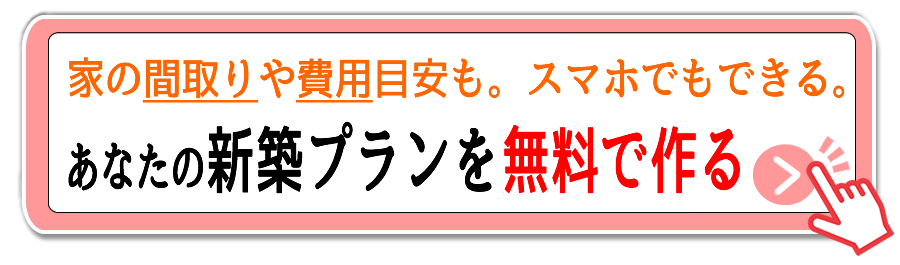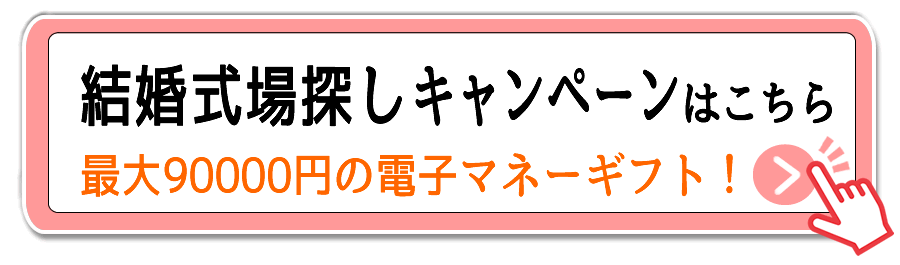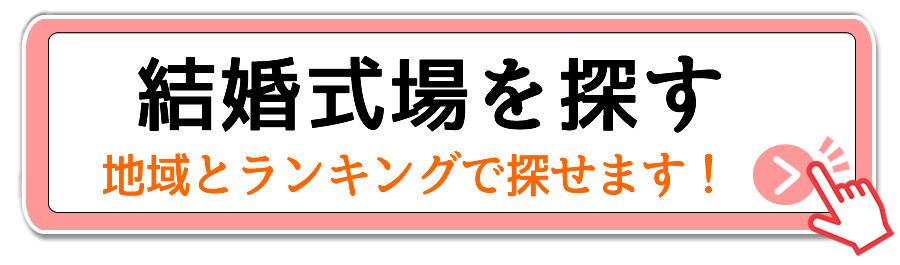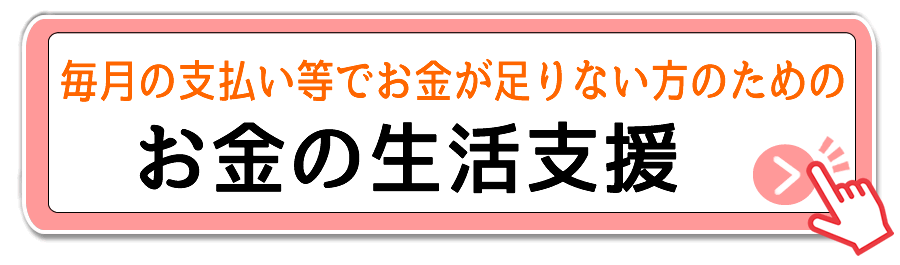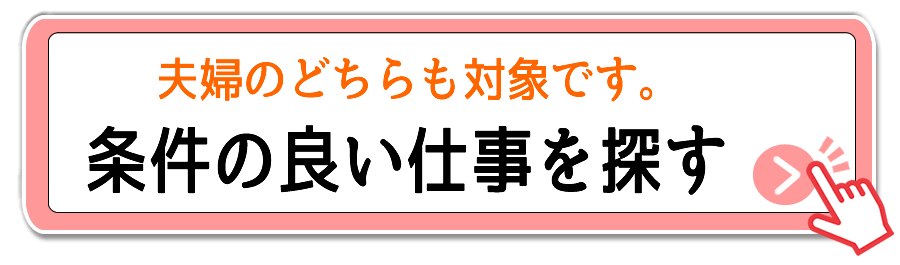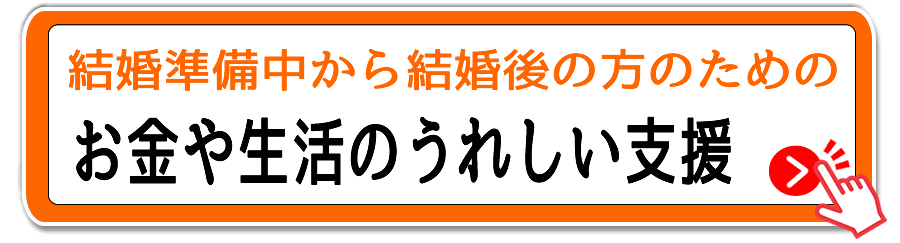PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
結婚助成金(結婚新生活支援事業)とは?対象・金額・申請の流れを徹底解説

- 結婚助成金(結婚新生活支援事業)とは?
- もらえる金額はいくら?補助対象と支援上限額
- 結婚助成金の対象となる条件とは
- 結婚新生活支援事業の申請の流れと必要書類
- どこでももらえる?自治体による対応の違い
- 助成金をもらうときの注意点
- こんな人にこそ活用してほしい制度
- 制度の活用事例|もらえた人・もらえなかった人の違い
- 他の支援制度との併用はできる?
- まとめ|結婚助成金で新生活の不安を軽減しよう
- よくある質問(FAQ)
結婚助成金(結婚新生活支援事業)とは?

若い世代の結婚・新生活を支援する制度
近年、経済的な理由から結婚や新生活のスタートをためらう若者が増えています。
そんな中、国と自治体が連携して実施しているのが、「結婚新生活支援事業」、いわゆる結婚助成金です。
この制度は、一定の条件を満たす新婚世帯に対し、住宅取得や賃貸、引越し費用などの一部を補助するもので、結婚後の経済的な負担を軽減することを目的としています。
結婚という人生の大きな転機を、経済的な不安で諦めてほしくない。
そうした想いから生まれた制度であり、全国の自治体で積極的に活用が進められています。
補助される内容は?住宅取得・引っ越し費用など
「結婚助成金」と聞くと、どこか曖昧なイメージを持たれるかもしれませんが、実際には使途が明確に定められています。
たとえば以下のような費用が補助の対象です。
- 賃貸住宅の敷金・礼金・共益費
- 不動産仲介手数料
- 引っ越し費用
- 新居購入のための頭金
- リフォーム・リノベーション費用(新生活に必要なもの)
これらの費用を合算し、上限金額内であれば自治体から助成金が支給されます。
国の制度?自治体の制度?仕組みをわかりやすく解説
この制度は、正式には国(内閣府地域活性化推進事務局)による交付金を活用し、各市区町村が主体となって運用する形です。
つまり、全国一律の制度というわけではなく、実施しているかどうかは自治体ごとに異なります。
また、実施している自治体の中でも、支援の上限額や対象条件、申請方法には差があるため、自分の住んでいる(または引越し先となる)自治体の制度内容を事前に確認することが非常に重要です。
もらえる金額はいくら?補助対象と支援上限額

支援上限額は最大60万円(※条件あり)
制度を利用した際に実際にもらえる助成金の額は、最大で60万円が基本です。
ただし、これはすべての夫婦に対して自動的に支給されるわけではなく、年齢や年収などの条件によって異なります。
内閣府の基本枠では以下のように設定されています。
- 通常の対象世帯:最大30万円
- 特に支援が必要とされる世帯(世帯年収が一定以下など):最大60万円
たとえば、夫婦ともに39歳以下で世帯収入が500万円未満という条件に該当すれば、上限60万円の補助を受けられる可能性があります。
自治体によっては、さらに独自に「上乗せ支援」をしているケースもあり、実質的に70万円以上の支給を受けた例も存在します。
補助対象となる費用の具体例
申請時には、補助の対象となる支出について「領収書や契約書」などの証明が必要です。
以下に補助対象となる具体的な費用例を紹介します。
【住宅費用】
- 賃貸住宅の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)
- 新築・中古住宅の購入費用の一部(頭金・登記費用など)
- 持ち家のリフォーム費用(生活環境整備として)
【引越し費用】
- 引越し業者への費用
- 家具・家電など新生活に必要な購入費(※自治体によっては対象外)
【その他】
- 自治体が指定するその他の費用(例:自治体独自の支援プログラム費など)
ただし、すでに契約・支払い済みの費用は対象外となるケースが多いため、必ず申請前に確認・相談しておくことが大切です。
結婚助成金の対象となる条件とは

年齢条件(夫婦ともに39歳以下)
結婚助成金を受けるためには、まず年齢条件があります。
制度上の基本ルールとしては、夫婦の双方が申請年度の4月1日時点で39歳以下であることが求められています。
たとえば、申請年度が2025年度であれば、2025年4月1日時点で39歳以下でなければ対象外となる可能性があります。
また、一部の自治体では「いずれか一方が39歳以下であれば対象」など、独自の緩和基準を設けている場合もあります。
該当年齢に近い方は、自治体の細かい条件をしっかり確認しておくと良いでしょう。
世帯収入の上限(世帯年収約500万円未満など)
もう一つの大きな条件が、世帯年収に関するものです。
助成金は「経済的に支援が必要な夫婦」を対象とした制度であるため、世帯収入の上限が設けられているのが特徴です。
基本的には、夫婦の合計年収が500万円未満であることが目安とされており、自治体によっては600万円以下など、多少の幅が設けられていることもあります。
なお、収入の判定には「源泉徴収票」や「所得証明書」が使われることが多く、年収計算の基準(所得ベースか給与ベースか)も自治体によって異なります。
対象地域に住むこと・住民票の移動が必要
助成金を受け取るには、その制度を実施している自治体内に新生活の住居があることが必要です。
すなわち、結婚を機に新たな生活を始める場所が、制度対象エリアでなければなりません。
さらに多くの自治体では、住民票の移動が完了していることを申請の条件としています。
そのため「将来的に引越し予定」だけでは対象とならず、既に新居に住んでいる or 入居が確定していることが必要となります。
婚姻日からの期間制限に注意
助成金申請には、婚姻届提出日から一定期間以内という条件が設けられている場合があります。
一般的には、婚姻から1年以内の申請が求められますが、中には「半年以内」「申請年度内であること」など、より厳しい条件の自治体も存在します。
このように、「年齢・年収・居住地・婚姻時期」など多面的な条件があり、すべてをクリアして初めて申請可能となります。
結婚新生活支援事業の申請の流れと必要書類
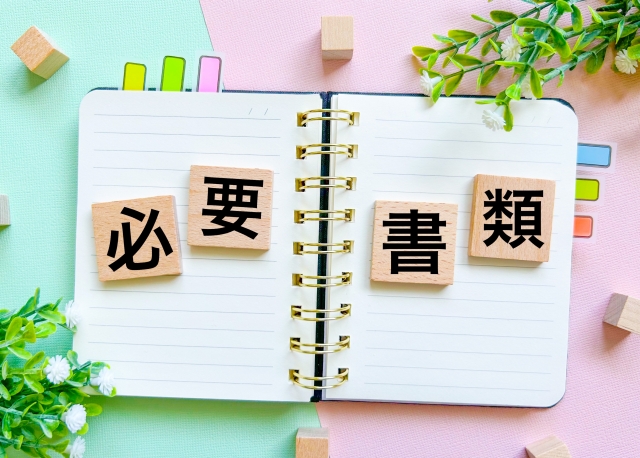
1. 自治体への申請が基本
結婚助成金の申請は、夫婦が住んでいる(あるいは住む予定の)自治体に対して行います。
この制度は国からの交付金をベースにしてはいますが、運用はあくまで各自治体が担っているため、申請書類やスケジュールも自治体ごとに異なるのが現状です。
多くの場合は、役所の「企画課」「地域振興課」「定住促進課」などが窓口となります。
2. 必要書類一覧(住民票・婚姻届受理証明・領収書など)
主に必要となる書類は以下の通りです(自治体により若干異なる):
- 申請書(指定様式)
- 夫婦それぞれの住民票
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 所得証明書または源泉徴収票
- 住宅の契約書や領収書(家賃・引越し代・リフォーム費など)
- 金融機関の口座情報
これらを揃えて提出することで、審査・交付決定が行われ、後日助成金が指定口座に振り込まれるという流れになります。
3. 手続き時期・スケジュール感の目安
助成金には自治体ごとの予算上限があるため、早めの申請が重要です。
たとえば、4月に予算が組まれ、7月〜9月頃から受付が始まり、秋には予算が尽きて終了するケースも珍しくありません。
また、申請から支給までには1ヶ月〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。
新生活の資金計画に組み込む場合は、余裕を持ったスケジューリングが必要となります。
どこでももらえる?自治体による対応の違い

制度を実施していない自治体もある
ここで注意が必要なのは、すべての自治体がこの制度を実施しているわけではないという点です。
国の交付金を活用してはいますが、導入するかどうかは各自治体の判断に委ねられています。
たとえば、ある県内の市町村のうち、半分は制度を導入しているが、もう半分は実施していないという地域もあります。
そのため、「もらえる前提」で進めてしまい、実は対象外だったと後から知って後悔するケースも。
事前確認は必須です。
独自に上乗せ支援している地域も
一方で、制度を活用しながらも、独自の上乗せ支援を行っている自治体も存在します。
たとえば、
- 支援額:国基準の30万円→自治体独自に60万円
- 対象年齢:国基準の39歳→自治体で45歳までに緩和
- 支援対象:家賃だけでなく、家具・家電購入もOK
など、地元への定住促進や少子化対策の一環として柔軟な制度設計をしている例も増えています。
事前確認のポイント:自治体HPの確認と問い合わせ
こうした違いがあるため、申請前に自治体の公式サイトで要項を確認することが極めて重要です。
多くの自治体では「結婚新生活支援事業について」といったページが設けられており、
- 実施の有無
- 対象条件の詳細
- 必要書類のダウンロード
- 問い合わせ先
などが掲載されています。
それでも不明点がある場合は、電話で問い合わせるのが確実です。
制度の運用は年度ごとに更新されることが多く、古い情報を見て判断してしまうリスクもあるため、最新年度の情報かどうかをチェックしましょう。
助成金をもらうときの注意点

予算枠に限りがある=早い者勝ち
結婚助成金はすべての希望者に自動的に支給されるわけではありません。
自治体によっては予算枠が設定されており、年度内でも予算が上限に達し次第、受付を終了するケースが多くあります。
「引越ししてから申請すれば大丈夫」と思っていたら、すでに受付が締め切られていたという事例もあります。
特に人気エリアでは、早い段階で予算消化となる可能性があるため、計画段階で問い合わせておくことが大切です。
購入済・契約済では申請不可のケースも
申請時点で、すでに住宅の契約や引っ越しが完了していると、助成金の対象外になる可能性があります。
なぜなら多くの自治体では、「交付決定通知」が届いた後の支出に限って補助対象としているからです。
つまり、「契約→申請」ではなく、「申請→交付決定→契約・支出」の順序を守ることが必要です。
領収書を出せばもらえる、という考えで動いてしまうと、せっかくの支援を受けられなくなってしまいます。
申請前に必ず「交付決定通知」を受け取ること
上述の通り、支出が助成対象になるかどうかは「交付決定通知」以降の費用かどうかで判断されます。
これは自治体によって運用ルールが異なるものの、多くの地域で共通している重要なポイントです。
したがって、新居探しや引越し日程、契約時期の調整などは「交付決定通知」を見越して計画的に進める必要があります。
こんな人にこそ活用してほしい制度

これから同居・入籍予定のカップル
結婚助成金は、これから新生活を始める予定のカップルにとって大きな味方です。
結婚や同棲を検討している段階であっても、制度を活用できる可能性は十分あります。
特に住宅費用や引越しに不安を抱えている方にとって、最大60万円の支援は非常に心強いもの。
早めに情報収集を始めることで、制度の恩恵を最大限に受けることができます。
貯金が少ない状態で結婚生活を始める夫婦
結婚式、新居、家具、家電……結婚を機に必要となる支出は予想以上に多く、貯金が十分でない状態での新生活は、大きなプレッシャーや不安の原因にもなりかねません。
そのような場合、この助成金制度を活用すれば、初期費用の一部が軽減され、ゆとりをもって生活をスタートできるでしょう。
Uターン・Iターン移住と併用を考えている人
地方自治体によっては、結婚助成金に加えて移住支援金や就職支援金などをセットで提供している地域もあります。
たとえばUターン(地元への帰郷)やIターン(新天地への移住)を考えている方は、複数の支援制度を組み合わせることで、より有利にスタートを切ることが可能です。
制度の活用事例|もらえた人・もらえなかった人の違い

もらえたケース:事前に自治体確認していた夫婦
ある30代のカップルは、結婚を決めた段階で自治体のホームページを確認し、事前に要項をチェックしてから引越しと入籍のスケジュールを組みました。
自治体にも直接問い合わせて、「交付決定通知」後に契約を行ったことで、スムーズに申請→支給まで進行しました。
このように、制度の仕組みを理解した上で、逆算して行動できたことが成功の鍵となっています。
もらえなかったケース:引越や入籍の順番ミス
一方で、「すでに結婚していたし、引越しも終えていたから申請したら断られた」という声もあります。
この夫婦は、制度の存在を後から知ったものの、すでに婚姻日から1年以上経過していたうえに、引越しも自己手配で完了していたため、申請の対象外とされてしまいました。
このようなケースでは、条件を一つでも満たしていないだけで支給不可となるため、制度を知るタイミングが極めて重要です。
体験談から学ぶ「成功のコツ」
成功事例に共通しているのは、以下の3点です。
- 早めに制度の存在を知り、計画に組み込んでいた
- 自治体に問い合わせて不明点を解消していた
- 交付決定通知を受け取ってから支出を行っていた
この流れを意識するだけで、助成金をスムーズに受け取れる確率が大きく上がるといえるでしょう。
他の支援制度との併用はできる?
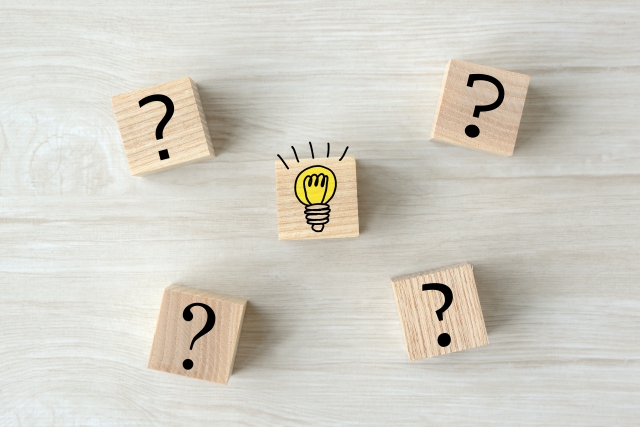
住宅支援・移住支援・子育て支援との組み合わせ
結婚新生活支援事業は、他の行政支援制度と併用できる場合があります。
たとえば、
- 移住支援金(東京圏からの転出など)
- 定住促進住宅の家賃補助
- 若年世帯向け住宅取得補助
- 妊娠・出産に関する助成
などと一緒に活用すれば、新生活の経済的負担をさらに軽くできます。
同一の費用に対して複数の補助は受けられない場合もありますので、併用可能かどうかは必ず確認しましょう。
補助金と助成金の違いと注意点
似たような言葉として「補助金」「助成金」「支援金」がありますが、制度によって条件や手続きが異なります。
特に、
- 補助金:予算に達し次第終了、事前申請が必要
- 助成金:条件を満たせば支給されやすい
- 支援金:用途が広いが、自治体独自ルールが強い
といった違いがあるため、名称に惑わされず中身を見て判断することが大切です。
まとめ|結婚助成金で新生活の不安を軽減しよう

結婚助成金(結婚新生活支援事業)は、若い夫婦が安心して新生活を始められるようサポートする制度です。
年齢や年収などの条件をクリアすれば、最大60万円の補助を受けることが可能で、引越し費用や住宅取得費など、負担が大きい部分に充てられます。
ただし、
- 自治体によって制度の有無・内容が異なる
- 「交付決定通知」前の契約は対象外になることも
- 年度途中で予算終了するケースも多い
といった注意点があるため、制度を早めに知り、計画的に活用することが成功のカギになります。
結婚をきっかけに、新しい土地で生活をスタートする方や、将来の家族形成に向けて基盤を整えたいと考える方にとって、この制度は心強い一歩となるはずです。
よくある質問(FAQ)

Q. 結婚助成金は誰でももらえますか?
A. いいえ、年齢や世帯年収、新居の所在地など一定の条件を満たす夫婦に限られます。
とくに夫婦ともに39歳以下、世帯収入が500万円未満であることが一般的な基準です。
また、助成制度を実施している自治体に住むことが条件となります。
Q. 引っ越し後に申請しても間に合いますか?
A. 自治体によって異なりますが、多くの場合、引越し前に「交付決定通知」を受けていることが補助対象の条件となります。
すでに引越しを済ませたあとでは申請できないケースがあるため、必ず事前に確認・申請するようにしてください。
Q. 妊娠・出産後にももらえますか?
A. 婚姻届の提出日からの経過期間や、申請年度の対象条件を満たしていれば、妊娠・出産の有無にかかわらず申請可能です。
ただし、婚姻から一定期間(1年以内など)という制限があるため、出産後に申請を検討する場合は注意が必要です。
Q. 申請から支給まではどれくらい時間がかかりますか?
A. 自治体や時期によって異なりますが、申請から支給までは1ヶ月〜3ヶ月程度が一般的です。
必要書類に不備があるとさらに時間がかかることもあるため、早めに準備し、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
- 結婚式場の選び方とブライダルフェア徹底ガイド|理想の式を叶えるためのステップと注意点
- 結婚にかかるお金はいくら?結婚式・新生活・新婚旅行までのリアルな費用と資金準備ガイド
- 婚約とは?結婚・入籍までの流れとやり方|後悔しないために必要な心構えと進め方ガイド
- 結納とは?顔合わせとの違いと今どきの選び方|迷ったときの判断ポイントも解説
- 結婚助成金(結婚新生活支援事業)とは?対象・金額・申請の流れを徹底解説