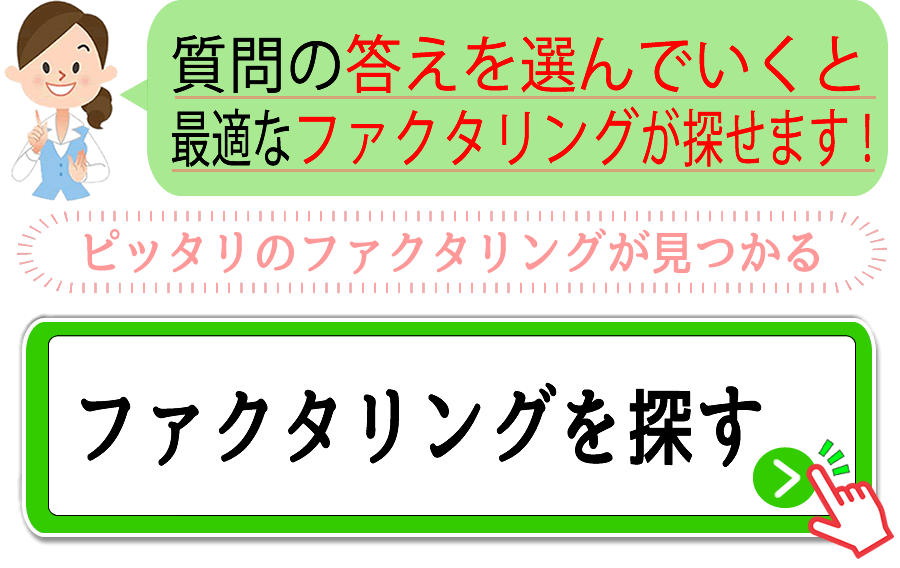- 介護施設における資金繰りの現実
- ファクタリングとは?介護施設が活用できる理由
- 介護施設がファクタリングを利用する3つのメリット
- どんなときにファクタリングを検討すべきか
- 介護事業者におすすめのファクタリングの種類
- ファクタリング利用の流れ|介護施設の場合
- 導入事例に見るファクタリング活用の効果
- ファクタリングで介護事業を守るために
- よくある質問(FAQ)
介護施設における資金繰りの現実

介護業界では、現場で働くスタッフの献身的な努力によって高齢者の生活が支えられています。
しかし、経営という視点で見たとき、介護施設が直面する課題は少なくありません。
とくに資金繰りの問題は慢性的かつ深刻であり、運転資金が不足することで施設運営そのものが危ぶまれることもあります。
その最大の原因のひとつが、介護報酬の入金サイクルです。
一般的に、介護保険サービスを提供した際の報酬(=介護報酬)は、月末締めで翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)に請求を行い、その入金があるのはさらにその月の月末という流れになります。
つまり、実際のサービス提供から現金が施設に入るまでに最大で2カ月近くのタイムラグが生じます。
たとえば、4月にサービスを提供した分の報酬が施設に入金されるのは6月の月末近く。
にもかかわらず、職員の給与や施設の家賃、仕入代金などは先に支払わなければならず、「立て替え払い」の状態が常態化してしまいます。
こうした構造は、他の業界と比べても特殊なものであり、特に新規開設したばかりの介護事業所や、小規模な施設では深刻な影響を及ぼします。
経営者の中には、融資に頼る形でこのキャッシュフローのギャップを埋めようとする方も少なくありません。
しかし、金融機関の融資は審査に時間がかかり、そもそも審査が通らないケースもあるため、すぐに現金が必要な局面では役に立たないこともあります。
こうした状況が続くと、いくら帳簿上は黒字でも、資金ショートが起きれば「黒字倒産」に陥る可能性も否定できません。
実際に、近年では介護報酬請求の遅れや、入金待ちによるキャッシュ不足をきっかけに事業を縮小せざるを得なくなった施設も存在します。
ファクタリングとは?介護施設が活用できる理由

このような資金繰りの課題を抱える介護施設にとって、有効な解決策となるのがファクタリングという資金調達方法です。
ファクタリングとは、未回収の売掛金(=将来得られる報酬)をファクタリング会社が買い取ることで、早期に現金化する仕組みのことを指します。
介護業界においては、「介護報酬請求債権」もファクタリングの対象になります。
つまり、国保連に請求した介護報酬が入金される前に、その債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、通常よりも1〜2カ月早く資金を得ることができます。
この方法は銀行からの融資と違い、担保や保証人が不要で、審査期間も短く、早ければ即日〜数日以内に資金化できる点が特徴です。
さらに、利用用途が自由であるため、従業員の給与支払いや備品の仕入れ、突発的な修繕費の支払いなど、急な出費に柔軟に対応できます。
介護施設がファクタリングを活用できる理由はもうひとつあります。
それは、介護報酬という「確実性の高い債権」を保有していることです。
国から支払われる介護保険報酬は回収リスクが極めて低いため、ファクタリング会社側にとってもリスクが小さく、スムーズな審査が行いやすいという利点があります。
また、ファクタリングの中でも「2社間ファクタリング」を選べば、国保連に通知する必要がなく、施設とファクタリング会社だけで契約が完結するため、外部に知られずに利用できる点も安心材料です。
信用への影響を気にする介護事業者にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
介護施設がファクタリングを利用する3つのメリット

介護施設がファクタリングを導入することには、単なる資金調達以上の効果があります。
経営の安定性を高め、職員や利用者へのサービスの質を維持・向上させるためにも、ファクタリングは「守り」と「攻め」の両面で活用できる手段といえるでしょう。
ここでは特に重要な3つのメリットを紹介します。
1. 給与・家賃などの固定費を安定して支払える
介護施設では毎月決まって発生する支出が多くあります。
たとえば人件費、家賃、光熱費、消耗品費などがそれにあたります。
こうした支出は、施設の運営規模にかかわらず、入金の有無に関係なく支払わなければならないものです。
しかし、介護報酬が2カ月近く遅れて入金されるという構造のなかでは、資金が足りずに従業員への給与が遅れてしまう、あるいは、オーナーの個人資金を使って穴埋めせざるを得ないといった事態に陥ることもあります。
ファクタリングを活用することで、請求した報酬分を前倒しで資金化できるため、こうした固定費を安定して支払う体制が整います。
給与の支払い遅延や、家賃滞納によるトラブルを防ぎ、職員の信頼や施設の信用を守ることができます。
2. 利用者増にともなう先行投資に対応できる
介護施設では、利用者数が増えることは売上アップのチャンスでもありますが、それに先立って人材確保や設備導入、ベッド数の増設など先行投資が求められます。
しかし、実際に報酬として反映されるのは数カ月後であるため、「増加分のコスト」をカバーできず、せっかくの需要を断らざるを得ないことも起こります。
こうしたときに、ファクタリングで資金を得ておけば、採用活動や備品購入など必要な支出にタイムリーに対応できます。
結果として、機会損失を防ぎ、スピーディーな事業拡大につながります。
3. 新規事業や設備更新の資金として活用できる
介護施設の中には、新しいサービスの導入や地域密着型事業の展開を目指すところも多くあります。
たとえば、デイサービス併設や訪問介護の新規開設、小規模多機能型施設への転換などです。
こうした前向きな取り組みにも、初期投資が必要不可欠です。
自己資金だけでは不十分で、金融機関の融資も時間がかかる場合、ファクタリングによって迅速に資金を確保するという選択が有効になります。
一度きりの利用でも目的に応じて柔軟に対応できるため、過剰な借入を避けたい事業者にとってもリスクが低い資金調達方法といえるでしょう。
どんなときにファクタリングを検討すべきか
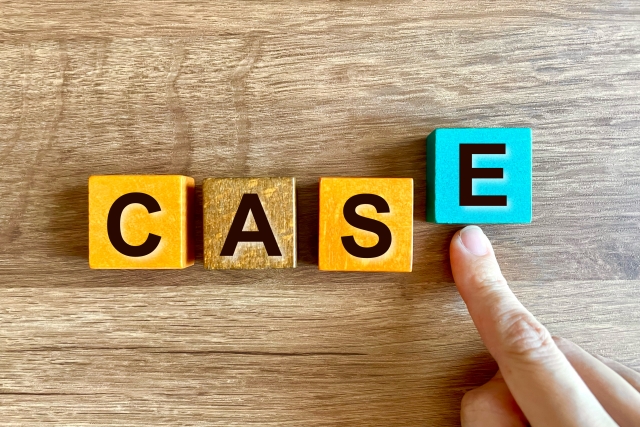
すべての介護施設が常時ファクタリングを利用すべきというわけではありません。
むしろ、計画的に、必要なときにだけ使うことで、最大限の効果を得られる資金調達手段です。
では、どのようなタイミングで検討すべきなのでしょうか。
入金サイクルが重く、資金繰りがひっ迫しているとき
最も典型的な利用タイミングは、「月末の支払いが目前に迫っているのに、現金が足りない」というケースです。
こうした状態で金融機関に駆け込んでも、審査に時間がかかるうえ、断られる可能性も否定できません。
ファクタリングであれば、請求済の介護報酬分を迅速に現金化できるため、給与や仕入れの支払いに間に合わせることができます。
金融機関からの融資が間に合わないとき
融資は低金利で資金調達できるという点でメリットもありますが、審査日数が長く、事業計画書や担保などの準備が必要です。
そのため、緊急性の高い資金ニーズには対応しにくいのが現実です。
一方、ファクタリングは、審査も比較的スピーディーで、書類も最小限で済むことが多いため、「融資までのつなぎ」としても非常に有効な手段です。
新規施設の開設・増床・職員増加にともなう先行支出
介護業界では、サービス提供量が増えても、それに応じた介護報酬が支払われるまでには時間差があります。
とくに、新規開設や増床時には、大きな支出が先に発生します。
新しい施設の設備投資、人員配置、各種申請手続きなど、資金が先に必要になる場面ではファクタリングが心強い選択肢になります。
介護事業者におすすめのファクタリングの種類

ひとくちにファクタリングといっても、実際にはさまざまな方式があります。
介護施設の事情や希望に応じて、最適な形態を選ぶことが重要です。
以下では、主なファクタリングの種類とその特徴について紹介します。
2社間ファクタリング:施設と業者の間で完結
2社間ファクタリングとは、介護施設とファクタリング会社の2者だけで契約を行う方式です。
国保連や自治体などの第三者に通知する必要がなく、現金化のスピードが早いのが特徴です。
「ファクタリングを使っていることを外部に知られたくない」という事業者にとっては、特に安心できる方法です。
ただし、債権回収のリスクがファクタリング会社側にあるため、手数料はやや高めになる傾向があります。
3社間ファクタリング:国保連への通知が必要だが手数料は安い
3社間ファクタリングは、介護施設・ファクタリング会社・国保連の3者間で契約を行う方法です。
国保連に対して「報酬はファクタリング会社に支払ってください」と通知を出すため、債権の確実性が高まり、手数料が安くなる傾向にあります。
ただし、通知の手間や事務作業が増えるうえに、「他人に知られたくない」という施設には不向きな場合もあります。
即日対応・小口対応が可能な業者の選び方
介護事業者のニーズに合ったファクタリング会社を選ぶには、業界対応の実績、スピード、柔軟性を重視する必要があります。
特に、100万円以下の小口債権にも対応しているか、即日入金に対応しているかなどは、緊急性の高い場面では重要な判断基準になります。
ファクタリング利用の流れ|介護施設の場合

ファクタリングの利用は、銀行融資に比べてはるかに簡単かつスピーディーです。
特に介護報酬債権は確実性が高いため、審査通過率も比較的高く、スムーズに資金調達できる傾向にあります。
以下に、一般的な利用の流れを紹介します。
ステップ1:介護報酬の請求書を準備
まずは、介護報酬の請求に関する書類(国保連への請求明細書など)を手元に準備します。
ファクタリング会社は「この請求が確実に支払われるかどうか」を見極めるため、証拠としての請求書類が重要になります。
あわせて、法人登記簿謄本や身分証明書、通帳のコピーなど、一般的な事業者情報の提出も求められますが、銀行融資に比べると必要書類はかなり少ないと言えます。
ステップ2:ファクタリング会社による審査
書類を提出したあとは、ファクタリング会社による簡易的な審査が行われます。
審査といっても、融資とは異なり、信用情報や赤字の有無よりも「債権の確実性」が重視されるため、赤字経営であっても通ることがあります。
ここで特に重視されるのが、過去の介護報酬の入金実績です。
安定して入金されている履歴がある場合、審査はスムーズに進みます。
早ければ数時間〜翌営業日中に結果が出ることもあります。
ステップ3:契約と資金の受け取り
審査通過後は、ファクタリング契約書を締結します。
内容をよく確認し、不明点があれば契約前にクリアにしておくことが大切です。
特に手数料の割合や入金スケジュール、債権譲渡通知の要否などはチェックポイントになります。
契約が完了すると、指定口座に資金が振り込まれ、現金を即座に使うことが可能になります。
これにより、数週間〜数カ月後の入金を待つことなく、現在の支払いに充当することができます。
導入事例に見るファクタリング活用の効果

実際にファクタリングを導入した介護施設の声を聞くと、その効果は想像以上に大きいことがわかります。
ここでは、具体的な導入シーンを3つ紹介します。
人件費未払いの危機を回避できた事例
ある中規模の特別養護老人ホームでは、国保連からの報酬入金が予定より遅れたことにより、給与資金が確保できず、職員の支払いに頭を抱える状況に陥りました。
銀行融資は間に合わず、最終的にファクタリングを利用。
わずか2日で500万円を資金化し、従業員への給与支払いを滞りなく終えることができました。
赤字脱却と新規施設の立ち上げに成功したケース
地方で複数の通所介護事業所を展開していた法人は、一時的な稼働率低下によって赤字状態に。
しかし、新規開設のチャンスが舞い込み、初期費用をファクタリングで調達することにより、資金不足を克服。
数カ月後には稼働率回復により黒字転換を実現しました。
税理士との連携で安全に導入した例
ある介護付き有料老人ホームでは、税理士からのアドバイスでスポットファクタリングを活用。
契約前に契約内容を精査し、一度きりの利用でキャッシュフローの改善に成功しました。
その後は定期的な財務チェックと併用しながら、必要時にのみ利用するスタンスを維持し、無理のない経営体制を整えています。
ファクタリングで介護事業を守るために

介護施設を取り巻く経営環境は、年々厳しさを増しています。
人材不足、物価高騰、報酬単価の見直し、制度変更への対応など、経営者が考えるべきリスクは多岐にわたります。
こうしたなか、資金繰りの不安を少しでも軽減する手段として、ファクタリングは非常に有効です。
繰り返しになりますが、ファクタリングは借金ではありません。
将来的に得られる確定的な報酬債権を前倒しで現金化する仕組みです。
無理のない範囲で活用することで、経営の流動性を高め、健全な施設運営を続けることができます。
また、一度利用したからといって、継続利用が義務付けられるわけではありません。
たとえば、「今月だけ資金が足りない」「設備投資の初期費用だけをカバーしたい」といったスポット利用にも柔軟に対応できるのが、ファクタリングの大きな魅力です。
加えて、税理士や行政書士など、専門家との連携も重要です。
契約内容の精査や財務計画の見直しを通じて、適切なタイミングでファクタリングを取り入れることで、過度な依存や手数料負担のリスクを最小限に抑えることができます。
最後に、介護は人を支える仕事です。
そして、その現場を支えるのが経営です。
安心して働ける職場環境、そして安定したサービス提供を継続するためにも、資金繰り対策は軽視できません。
ファクタリングを正しく理解し、必要に応じて上手に活用することで、今ある介護事業を守り、未来の成長へとつなげることができます。
よくある質問(FAQ)
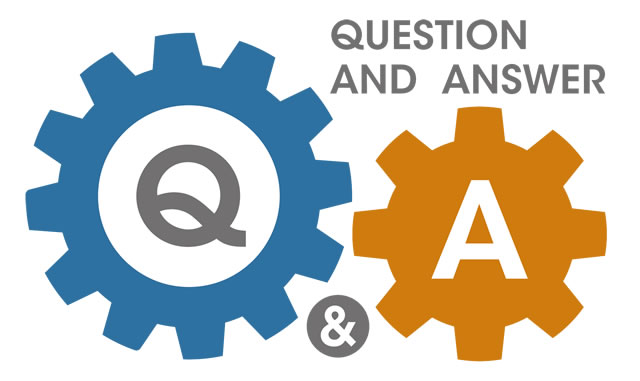
Q. 介護報酬もファクタリングの対象になりますか?
はい、介護報酬請求債権もファクタリングの対象となります。
国保連への請求分や自治体への請求が含まれることが一般的です。
確定性が高いため、審査も比較的スムーズです。
Q. 国保連や自治体に知られずに利用できますか?
2社間ファクタリングを選べば、国保連に通知せずに利用できます。
そのため、外部に知られたくない場合でも安心して利用可能です。
ただし、3社間方式では通知が必要です。
Q. 一度だけの利用でも問題ありませんか?
はい、スポット利用(単発利用)も可能です。
継続契約の義務はなく、「今月だけ資金が必要」というケースでも利用できます。
Q. 手数料はどのくらいかかりますか?
2社間ファクタリングで10〜20%、3社間で2〜5%程度が相場です。
契約内容により異なるため、事前に見積もりを取り、総額で比較することが大切です。
Q. 審査が不安ですが、赤字経営でも使えますか?
はい、ファクタリングは借入ではなく売掛債権の買取なので、赤字や債務超過でも審査に通る可能性があります。
債権の確実性が重視される点が融資とは異なります。
Q. 小規模な施設でも利用できますか?
もちろん可能です。
100万円未満の債権でも対応しているファクタリング会社は複数存在します。
実績のある会社を選ぶことで、小規模事業者でも安心して導入できます。
Q. 税務上の扱いはどうなりますか?
ファクタリングは資産の譲渡にあたるため、原則として売掛債権が減り、手数料は経費として計上されます。
- 運送業にこそ必要な資金繰り対策|ファクタリングで燃料費・人件費を即時確保
- 建設業の資金繰りにファクタリングという選択肢|工期遅延・外注費の支払いに悩む前に
- 医療機関・病院でもファクタリング活用が進む理由とは?資金繰りの課題をスピード解決する方法
- 介護報酬の入金待ちに困っていませんか?ファクタリングで安定運営を支える介護施設の資金繰り対策とは
全国のファクタリング業者
▼地域ごとのファクタリングの情報はこちらから